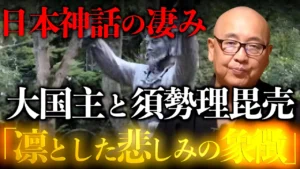古事記に描かれた大国主命の物語には、現代にも通じるリーダーの二つの条件が示されています。
それは「神々からの承認」と「人を支える垂木(たるき)の精神」。
日本型リーダーの原点を探ります。
Ⅰ.「リーダーとは何か」──古事記に見る原点
日本で「リーダー」と聞いて思い浮かぶ像は、大きく二つあります。
ひとつは織田信長のように強く牽引するカリスマ型、
もうひとつは温厚で控えめ、調和を重んじる型です。
では、日本人にとっての理想はどちらか。答えは、古事記の中に語られています。
主人公は大国主命(おおくにぬしのみこと)。
若い頃は「大穴牟遅(おおなむち)」と呼ばれ、兄弟神たちとともに姫を娶ろうと旅に出ます。
途中の「稲羽の白兎」をきっかけに兄たちは姫に振られ、末弟の大穴牟遅のみが選ばれました。
これが兄たちの嫉妬と怒りを招き、命さえ狙われる受難へと続きます。
それでも大穴牟遅は、恨まず、逃げず、誠実に歩みます。
苦難の果てに出会ったのが、須佐之男命(すさのおのみこと)の娘・須勢理姫(すせりひめ)。
二人は愛によって結ばれ、幾多の試練をともに乗り越え、やがて須佐之男命の許しを得て結婚に至ります。
ここにすでに、日本のリーダーに求められる「愛」と「忍耐」の原型が示されています。
Ⅱ.「垂木(たるき)の教え」──支える者こそ真のリーダー
須佐之男命は大国主命に命じます。
「高天原まで届く立派な垂木(たるき)を立てよ。」
一見すると不思議な言葉ですが、垂木とは屋根面を支える斜材のこと。
天へと聳える“柱”ではなく、下から面全体を支える部材です。
この比喩は、リーダーの本質が「上から命じること」ではなく、「下から支えること」にあると教えてくれています。
人々が安心して暮らし、笑って働けるようにする。
屋根がたわまぬよう、見えない場所で確かに支える。
その姿が「高天原まで届く統治」、すなわち神に恥じない政治です。
現代の政治家や経営者にも、この「垂木の精神」が問われています。
権力で見下ろすのではなく、生活を支える力へ。
豊かで穏やかな暮らしの実現に向け、まず自らが支えの木となること――それがリーダーの使命です。
Ⅲ.「門弟」という関係性──正当性はどこから来るか
古事記が示すもう一つの鍵は「神々からの承認」です。
大国主命は、須佐之男命から正式に「大いなる国の主」と認められて、はじめて統治の正当性を得ました。
日本におけるリーダーは、個人の能力やカリスマだけでは選ばれません。
「正当性」という「認証」が求められ、その背景には「誰のもとで薫陶を受け、どの系譜につらなるのか」という「門弟」の観念が横たわります。
肩書きだけでは信頼は得られず、拠って立つ「徳と系譜」が問われてきたのです。
【結び】
垂木となって人々を支える。
門弟として正統の系譜に学び、誠実にふるまう。
この二つが、日本型リーダーの条件です。
筆者は、親分なしの子分なし(笑)。
誰の門弟にもならず、子分も持たない立場での研究の自由を大切にしてきました。
なぜなら筆者にとっての師匠は、亡き父だからです。
親父は高名な宗匠ではありません。
けれど筆者にとっては、最上の師です。
世の中で認められるためには、師匠の存在があることが大切だということは、よくわかります。
けれど、悪いけれど「偽物」ばかりのような気がするのです。
親父は、いろいろ教えてくれたわけではありません。
子どもの頃の自分は不詳の息子で、顔を見れば怒られてばかり。だから怖かった。
社会人になってからは助言もしてくれましたが、振り返ってみれば闘争的で、あまり役に立ったとも言えません(笑)。
それでも、親父のことがいまも大好きです。
だから「尊敬する人は?」と聞かれたら、迷わずこう答えます。
「死んだ親父です」と。
結局その思いが、「小名木家の恥を晒さないこと」という自己制御の根幹になりました。
そしてその心が、いまの自分を形づくっているのだと思います。