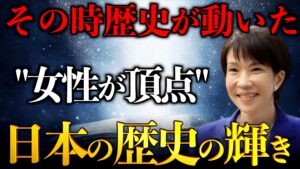10月30日は、明治23年(1890)に教育勅語が発布された日です。発布の背景には、神仏観の揺れや近代国家としての学校制度整備、そして「日本らしい教育原理」を言語化しようとした明治人の試みがありました。戦後には教育基本法の制定と、1948年の衆参両院決議による教育勅語の排除・失効確認が続きます。占領下という政治状況の中で下された判断をどう受けとめ、主権回復後の今日に何を学びとして引き継ぐのか。制度(ルール)、物語(共有記憶)、日常運用(困りごと解決)の三点から、歴史の要所を確かめていきます。
■ 教育勅語が求められた理由――「日本の学び」を言語化する試み
10月30日は、教育勅語が公布された日。
明治の近代化で学校制度は整備されたものの、現場では江戸以来の寺子屋文化や地域の相互扶助の知恵が生きていました。
近代国家として体系的な学制を築くなら、その根にある「日本の学びの型」を言葉にしなければならない。
そこで「孝・友・和・信・勤勉・公益・遵法」など、人間として当たり前に大切な徳目を、天皇から国民への呼びかけのかたちでまとめたのが教育勅語でした。
同時代の背景として見逃せないのが、維新直後に過熱した廃仏毀釈です。
推古天皇以来の神仏習合という長い歴史をもつ日本で、急進的な宗教整理は大きな摩擦を生みました。
西洋由来の一神教理解をそのまま日本に当てはめると、かえって社会の安心が揺らぐ。
だからこそ「制度(ルール)」だけでなく、「物語(共有記憶)」としての歴史観、そして地域の「日常運用(困りごと解決)」を支える徳目が必要でした。
教育勅語は、その三点を束ねる“学びの軸”として受けとめられていきます。
■ 1947–48年の転換――教育基本法と国会決議、占領下という条件
戦後、1947年3月31日に教育基本法が公布・施行され、教育の新しい理念が示されました。
この時点では教育勅語は存置されていましたが、
1948年6月19日、衆議院は教育勅語などの諸詔勅を「日本国憲法の理念に反する」として排除決議。
同日、参議院は失効確認決議を行いました。
ここで重要なのは、当時の日本が占領下にあったという事実です。
GHQの意向が政治・行政・教育の広い領域に及ぶ中で、国会は「新法体系への整理」を急ぎ、教育の拠り所を教育基本法に一本化していきました。
この決定に対しては、評価も疑問も共存します。
戦後復興を急ぐ局面で、混乱を避けるための判断だったという見方がある一方、
主権回復後に何を回復し、何を更新すべきだったのかという問いは残されました。
とくに、教育勅語が説いた「人としての当たり前(孝・友・和・信・勤勉・公益・遵法)」の価値そのものまで否定するのか――この点は、制度論と切り分けて考えるべきテーマです。
制度(ルール)は時代で変わる。
しかし、物語(共有記憶)と日常運用(困りごと解決)の知恵は、
社会の安心を支えるインフラとして再評価しなければならないものです。
ここに、いまへの宿題があります。
■ いまへの問いかけ――「制度・物語・日常運用」を再接続する
今回の配信では、教育勅語を“賛否の対象”としてだけではなく、「社会の重心を『力』から『安心』へ移すための道具立て」として捉え直しました。
推古天皇の神仏習合、持統天皇の『日本書紀』と『万葉集』、北条政子の現場統率――歴史の要所で、リーダーは必ず「制度(ルール)」「物語(共有記憶)」「日常運用(困りごと解決)」の三点セットをそろえています。
対立が長引くほど、人々が求は勝敗よりも、「和の手続き」や「文化の共有」を求めます。
教育勅語の徳目は、まさにその基礎体力でした。
占領下の国会決議という歴史的条件を踏まえつつ、主権回復後の今日に問われるのは、徳目を現代語で再接続し、地域と学校と家庭のあいだで日常運用できる形に落とし込むことです。
たとえば、
学校では「公益と遵法」を“地域の困りごとを調べて企画・実行する総合学習”に翻訳し、
家庭では「孝・友・和・信」を“ケアと言葉の交換、記憶の継承”として積み重ねる。
地域では「勤勉」を“世代横断の継続プロジェクト”に育てる。
こうした実装例は、思想ではなく習慣として“安心”をつくります。
結びに、学びの姿勢について。
配信の締めくくりで触れた「3分に一度、笑顔になる」は、単なる気分の話ではありません。
笑顔は“和の手続き”の最小単位であり、緊張をほぐし、言葉を届きやすくします。
制度を整え、物語を分かち合い、日常運用を続ける――そのすべての土台に、笑顔という微細な実践があります。
歴史の転換点にある今こそ、「制度・物語・日常運用」の三点を結び直し、学びを楽しく、そして誇りあるものへと育てたいと思います。
【所感】
昭和23年の国会で、教育勅語の排除に異を唱える議員が一人もいなかったという事実は、やはり残念なことです。
占領下という特殊な状況にあったとはいえ、その沈黙の裏には「自らの国の精神を自らの手で手放した」という痛みが残ります。
当時唱えられた「民主国家」「主権在民」という言葉が、戦後八十年を経てなお金科玉条のように繰り返されてきたことも、同じ痛みの延長線上にあります。
しかし、その時代の人々を責めるよりも、今を生きる私たちが「昭和天皇の大御心」をどう受け継ぐかが問われているのだと思います。
「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」という終戦の御詔勅の昭和天皇のお言葉は、屈服ではなく“文明の再建”への覚悟でした。
そのお心を、戦後八十年を経た今こそ謙虚に受け止める必要があります。
先人たちが耐え、忍び、築いてくださった礎の上に、いまの日本があり、私たちの命がある。
そこにあるのは感謝以外の何ものでもありません。
「教育勅語に戻れ」「復活させよ」という声もありますが、単なる復古では未来は開けません。
本当に求められているのは、江戸の寺子屋で教えられた『童子教』や『実語教』の精神、さらに『古事記』『日本書紀』の根源的な日本精神に立ち返りながら、古き良きものと現代の叡智を結び合わせ、より良い未来を創造していく姿勢です。
教育勅語の本質は、形式にではなく「共に生きるための心」にあります。
それを今の時代にふさわしい言葉と形で生かしていくこと――それこそが、戦後を生き抜いた先輩たちへの最大の恩返しではないでしょうか。