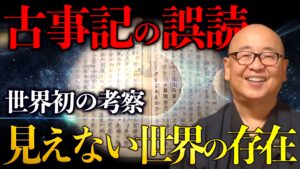11月10日は「トイレの日」。世界では今も多くの子どもが不衛生が原因で命を落とし、日本では「トイレを見ればその家がわかる」と言い伝えられてきました。掃除は単なる家事ではなく、心を整え、共同体の秩序をつくる実践です。奇しくも同日は、日教組の初大会、ベルリンの壁崩壊、文化大革命の序幕という“歴史の同日”でもあります。衛生と教育、秩序と革命──対照を手がかりに、いま何を選び直すべきかをお話しします。
清潔な一室は、心の一角を磨く。
たった一拭きが、人の品位と街の空気を変えていく。
Ⅰ. 11月10日「トイレの日」──衛生は命と品位を守るインフラ
日本トイレ協会は語呂合わせから11月10日を「トイレの日」と定め、各地でシンポジウムや「グッドトイレ賞」を行っています。
国連も2013年に11月19日を「世界トイレの日」としています。
ユニセフ/WHOの2019年報告では、
世界人口の約4分の1がトイレのない生活、
約半数が安全に管理されたトイレを使えないとされ、
5歳未満の子どもが不衛生と水因性下痢で年間約30万人亡くなる現実が示されています。
衛生は、まさに“生命線”です。
日本の生活文化には、トイレ掃除を日々の躾・道徳修養と結ぶ感性が息づきます。
風水の文脈でも「邪気を溜めない場所」とされ、清潔は運気全般に通じるとも語られてきました。
学校現場でも、生徒が自ら掃除を担う学校ほど荒れにくいという実感が共有されています。
印象的な逸話として、旧ソ連崩壊後のロシアで成功した“新興経済人”の会合で、年齢・業種・価値観が全く異なる彼らに唯一共通していたのが「自分でトイレ掃除をしている」ことでした。
衛生は“人任せ”では続きません。自分の場を自分で清める節度が、仕事の質と信頼を底から支えます。
番組では世界のトイレサインのバラエティや、日本で話題になった透明→施錠で不透明化する公園トイレも紹介。
安心・防犯と快適さの両立という設計思想は、日本の「配慮を形にする技術」が衛生を文化の次元に高めてきた証でもあります。
- 日本のトイレ史に学ぶ──自立と循環の発想
日本は水が豊富で、奈良時代には流し(流水)式の設備が実装されていました。
時代は遡りますが、武田信玄が水洗式を好んだ逸話も伝わります。
一方で、肥を資源として循環利用できたためボットン式が長く主流となり、生活の現場で「衛生」と「資源循環」の折り合いをつけてきました。戦後の極限状況のエピソード(抑留地の粗末な便所や紙不足)は、衛生が文明の土台であることを逆照射します。
今日、学生マンションや公共施設のトイレに換気・清掃・バリアフリーが当たり前に設計される背景には、長い時間をかけて培われた他者への配慮と場を清める価値が横たわっています。
大切なのは最新機器の有無ではなく、“場を保つ心”。
トイレ掃除は見えない場所にも手を伸ばす稽古です。
足元を整え続ける習慣は、家族・職場・地域の信頼を静かに積み上げていきます。
- 同日の歴史から読み解く──左翼革命の教訓と「学び直す共同体」
11月10日には、いくつかの象徴的出来事があります。
1951年に日本教職員組合が第1回全国教育研究大会を開催。
1989年にはベルリンの壁が崩れ、東西分断の終焉と共産圏の神話が剝がれ落ちました。
さらに1965年、姚文元の論文が上海紙に掲載され、文化大革命の口火となります。
紅衛兵が教育や文化を破壊し、教師が暴力の標的になった惨劇は、「革命」の名で教育と道徳が踏みにじられた例として忘れてはなりません。
ここからの教訓は明快です。
社会を良くするのは断罪の言葉ではなく、日々の実践。
犯人探しと糾弾は容易ですが、場は清まりません。
汚れを丁寧に清めるところに、秩序の再生が生まれます。
政治への過度な依存ではなく、教育の国・日本の再生へ。
勉強会や読書会、朝の挨拶や小さな掃除から、地域の自立は始まります。
支援と利権で縛る政治ではなく、協力と清潔と学びでつながる市民。
文化を壊す“革命”ではなく、文化を耕す“教育”。
ベルリンの壁が倒れた日に、こちら側の選択を新たにする意味は大きいはずです。
最後に実践の合言葉をひとつ。
「3分に1回、にっこりと」
完璧にはいきません。
それでも意識が表情をつくり、表情が空気を変え、空気が人を変えます。
笑顔と掃除—この二つの小さな習慣が、社会の基礎代謝を高めます。
結びとして、
トイレ掃除は文明の基礎体力。
衛生を整えることは、場を清め、人の心を整え、学び合う用意を整えること。
断罪より実践へ。
依存より自立へ。
今日の一拭きと一笑いが、明日の日本を明るくします。
今日も“響き合う場”を、それぞれの場所で。