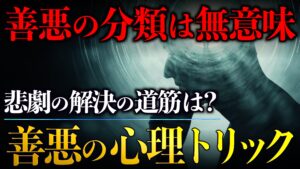11月13日は茨城県民の日です。今回の配信では、この日をきっかけに「日立国」という古い国の歴史と、茨城という地名に込められた神話的由来をたどりました。同時に、食料自給や農業の問題、国分寺・風土記の成立などを通して、「日本人の魂とは何か」「誇りと自立とは何か」を改めて見つめ直しています。自分たちの足元にある物語を知ることが、これからの日本を立て直すための第一歩になるという思いで、お話ししました。
1.日本人の魂は「自立」と「誇り」から見えてくる
今回の配信では、まずチャンネル名や倭塾LINEの名称を「日本人の魂を呼び覚ます」というテーマに合わせて整理し直したお話から始めています。
歴史や古典を語る目的は、単に知識を増やすことではなく、日本人としての「魂」を取り戻していくことにあります。その核にあるのが「自立」と「誇り」だという視点です。
夫婦の関係を例にとると、恋愛時代のような「あなたがいないと生きていけない」という依存関係ではなく、夫も妻も一人の人間としてきちんと自立し、そのうえで深く支え合う姿が、成熟したかたちだと言えます。
国も同じで、日本が本当に誇りある国であろうとするなら、軍事や外交だけでなく、食料やエネルギーの面でも自立していなければなりません。
ところが現状では、日本の食料は肥料・種子・飼料まで含めると海外依存が非常に高く、輸入が途絶えた場合には、1億2,000万人のうちごく一部しか生き残れない水準だと指摘されています。
数字上の自給率よりも、実際に「完全国産だけでどこまで食べられるのか」を見たとき、日本の脆弱さが浮き彫りになります。
そのため、倭塾農園やアノアス財団など、仲間たちとの農業の取り組みを通して、まずは「関係者だけでも食べていける基盤をつくる」という試みが始まっています。
食料の自立は、単にお腹を満たすためだけではなく、「自分たちのいのちを自分たちで支える」という誇りの問題でもあります。
歴史チャンネルや倭塾サロンの活動もまた、そうした自立と誇りを取り戻すための学びの場として位置づけています。
2.常陸国と「茨城」という名前に込められた物語
11月13日は「茨城県民の日」です。
この日を入り口に、かつての常陸国と「茨城」という地名の由来をたどりました。
まず押さえておきたいのは、現在の日本には「いばら(ぎ)」という地名は存在せず、茨城県も大阪府茨木市も、正式には「いばらき」と読むという点です。
今の茨城県北部は、古くは「常陸国(ひたちのくに)」と呼ばれていました。
この常陸の地には、常陸国風土記の神話に、「茨(いばら)の茂みで城を築き、賊を退治した英雄」の話が遺されています。
ここから「茨の城=いばらき」という地名が生まれました。
『古事記』『日本書紀』には書かれていないものの、各地の歴史と伝承をまとめた『風土記』の世界観の中に位置づけられる物語です。
奈良時代、日本を一つの統一国家としてまとめるために『日本書紀』が編まれましたが、各地にはそれぞれ固有の神話があり、「うちの国の神様が抜けている」「伝承と違う」という声がたくさん上がりました。
中央政府は、その声を抑えつけるのではなく、「それぞれの国は自分たちの歴史書をつくりなさい」と促し、その成果として生まれたのが各地の『風土記』です。
ここで重要なのは、「文句を言うだけでなく、自分たちの手で歴史書を書き上げるだけの誇りと力を持つ国」が、実はそう多くなかったという事実です。
その中で、常陸国はきちんと自前の『常陸国風土記』を残しました。
これは、地元の人々が自分たちの国に対して強い「誇り」を持っていたことの証です。
その「誇り」が、平安時代には、常陸国は親王任国とされ、天皇の皇子が名目上の国司に任じられる「大国」として扱いとなりました。
国府が置かれた現在の石岡市には、今も国分寺跡や国府跡が残り、かつてここが政治と文化の中心地であったことを物語っています。
江戸時代には多数の藩や旗本領・幕府直轄地が入り組み、明治維新の廃藩置県を経て、常陸や下総の一部が組み合わされて現在の茨城県が誕生しました。
幕末に幕府側に付いた土地柄であったため、明治新政府からは冷たく扱われた側面もありますが、それでも「茨城」という新しい県名に、古い神話的由来を踏まえた意味を込めたことは、地元の人々の「誇り」が形になったものして、特記すべきことだと感じています。
3.「日が立つ国」と高天原──歴史を知ることで生まれる誇り
常陸国には、「茨城」だけでなく「日立(ひたち)」というもう一つの重要な名前があります。
現在は「常陸」と表記しますが、もともとは「日が立つ」と書き、これは「天照大御神が立たれた地」という意味を持つ地名と伝えられています。
高天原(たかまがはら)は、現在では「神々の世界」という抽象的なイメージで語られることが多いのですが、江戸時代中期までは「日本列島のどこかに実在した土地」と伝承されていました。
気候変動に合わせて人々が移動していた時代には、「こここそ高天原だ」と名乗る土地が各地にあっても不思議ではありません。
常陸の地もまた、その一つとして「日が立つ国」としての誇りを抱いてきたのだと思います。
こうして見ていくと、地名とは単なる住所表示ではなく、「自分たちはどの神々と共に生きてきたのか」「どんな物語を誇りとして受け継いできたのか」という、魂の記録のようなものだと分かります。
聖武天皇が国分寺と国分尼寺を全国に置き、寺を学びの拠点としたこと、のちに唐から戒律が伝わり女性の受戒が認められなくなって国分尼寺が姿を消していったことなども含め、日本の各地には、それぞれの歴史とドラマが折り重なっています。
常陸国が「大国」として扱われるようになった背景には、「いばらの城で賊を退治した英雄神の物語」や、「天照大御神がお立ちになった地である」という神話を、地元の人々が誇りとして抱き続けてきたことがありました。
その誇りが『常陸国風土記』という形になり、やがて茨城県という名前の中にも受け継がれています。
お伝えしたかったのは、
「誇りは、知ることによって生まれる」
ということです。
自分が住む地域の名前の由来や、そこに込められた神話や歴史を知ることで、自分自身の立ち位置や、日本という国の意味が少しずつ見えてきます。
日本は「知らす国」、すなわち、上から押さえつけるのではなく、互いに知り合い、理解し合うことで成り立つ国だと語り継がれてきました。
だからこそ、日々の暮らしの中で、足元の歴史を学び直すことが、新しい時代の「自立」と「誇り」を育てる出発点になります。
今回の茨城・常陸のお話も、その一助になれば嬉しく思います。