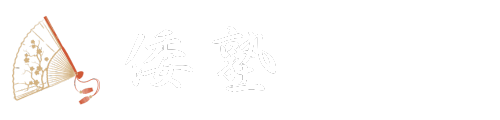米国人のラルフ・タウンゼント(Ralph Townsend)は、1900年(明治33年)生まれで、戦前のChinaに外交官として赴任した人です。
この人が書いた本の日本語訳が出版されています。
たいへん興味深い内容です。
『暗黒大陸 中国の真実』ラルフ・タウンゼント著
以前、義和団事件(1900年)を題材にしたチャールトン・ヘストン主演の映画『北京の55日』のご紹介をしたことがあるのですが、この映画を見たあるご年配の方が、
「当時のChineseには、あんなに太っている奴なんていなかったよ。」
とおっしゃられていました。
清朝末期、国が荒廃する中で、誰もが餓え、貧困のどん底にいた時代です。
とりわけ圧倒的多数を占める低所得者層の生活は悲惨を極めていました。
そんな時代の、Chinaの光景が、このタウンゼントの著書には詳しく述べられています。
そしていまではChinaは豊かになったとはいえ、その精神構造は、当時と何も変わっていない。
そのことを、この本は私達に教えてくれます。
すこし刺激が強いですが、たいへんな良書です。
以前にもご紹介しましたが、そのなかの一部を抜粋してお届けしてみたいと思います。
******
屎尿(しにょう)はどう処理をするのか。
家の中に大きな石のカメがあり、これに用をたす。
これをとっておき、農家や仲介業者に売る。
華北では、営業許可を得た農家や業者が毎日のように、呼び声高らかに、手押し車や荷馬車を引いて、華南では、天秤棒に桶を二つぶらさげて買いに来るから良いが、内陸部の田舎はひどい。
客室と同じ棟に巨大なカメがデンと座っている。
なかなか処理しないから、慣れない客はたいへんだ。
脱臭剤など見たことも聞いたこともない。
都市部から田舎へ向かう屎尿買い付けの長い列が続く。
写真で見ると実に素晴らしい。
見渡すかぎりの田舎道、山道を、桶を二つぶらさげた天秤棒を担いで、何千という人間がのろのろ歩いていく。
古くなって中程がへこんだ屋根の家や、灰色の竹と日干レンガのあばら屋などがごちゃごちゃした中に、高くそびえる塔がひとつ、ふたつ見える街から集めた屎尿を畑に撒きに行くのである。
伝統的な畑造りである。
華南では、担ぎ手は大抵が女で、痩せてはいるが足腰は強く辛抱強い。
年嵩の女連中は、荷物で重くなってキーキーいう竿(さお)にあわせて掛け声をかける。
決まったようにくるぶしと膝の中ほどまでの黒い木綿のズボンをはき、よほど暑くない限り何もかぶらない。
上着は何度も洗うから、色落ちしている。
足は裸足である。
若い娘の中には目もと明るい美人もいる。
また、赤いヘアバンドをしている者もいる。
これは人妻の印である。
ぽっちゃり型で元気であるが、歳をとるのが早いから、すぐに歯が欠け、おばあちゃんになる。
街の市場で買い物をする者がいる。
魚一匹、田舎では買えない野菜一束等である。
これを桶の側にぶらさげるから、糞尿がかかる。
手押し車や荷車で市場に野菜を運ぶ者がいる。
前日、糞尿を入れた同じ桶に入れてなんとも思わない。
まして糞尿がかからないように包もうなどとは、まったく考えない。
彼らは伝染病が流行るときは大変だ。
流行に一役買うことになる。
屎尿を桶にめいっぱい汲んで蓋をしない。
毎日通る道をヌルヌルに汚して、全く気にしない。
そこで遊んだ子供や犬や豚が、バイ菌を家に持ち込むのである。
写真で見たらきれいな田舎の風景ではあるが、現実はきれいごとでは済まされない。
街から集めた屎尿を水で薄め、作物に撒き、家族総出で一日中、土になじむように裸足でこねまわすのである。
真夏の強烈な日差しに照らされると、美しい田園風景どころではない。
一面、悪臭で息もできなくなり、一度足を踏み入れたら、必ず具合が悪くなる。
(『暗黒大陸 中国の真実』82ページ)
*******
タウンゼントは米国人で、米国務省に入省し、昭和6(1931)年に上海副領事としてChinaに赴任しています。
満州事変に伴う第一次上海事変を体験し、その後福建省に副領事として赴任したあとに、昭和8(1933)年に米国に帰国してこの本を出版しました。
タウンゼントは親日派の言論を展開したために、大東亜戦争開戦後にまる1年間投獄されてしまいました。
もし当時の米国がChinaの買収による宣伝工作に乗らず、冷静かつ客観的にタウンゼントの言をいれて東亜政策を推進していたのなら、おそらく日華事変も大東亜戦争も起きなかったといわれています。
またその後のChina国民党とChina共産党の争いもなく、China共産党による1億人規模の虐殺も起こらなかったことでしょう。
辛亥革命は、清朝の王都である紫禁城内にあった清王朝の所有する財宝類を、まるごと奪い去りました。
清の最期の皇帝である愛新覚羅溥儀に残されたのは、古くなった自転車1台と着ている服一着だったそうです。
それ以外は、すべて略奪されました。
その略奪された財宝は、値段のつけれないような高価な品々ばかりでした。
当然のことですが、貧しい当時のChinaでは品物の捌きようがありません。
そこで蒋介石は弟をヨーロッパに、妻の宋美麗を米国に派遣して、これらの財宝類をメディアや政治家たちにばらまきました。
また国民党が日本に勝利した暁にはと、China国土の欧米への切り売りの空手形を大量に発行していました。
蒋介石および妻の宋美齢の三姉妹は、いずれもChinaのある家族集団の出身です。
その集団は、古代の周から春秋戦国時代の王族の末裔といわれています。
不思議なことに、この集団の数詞は、北京語の「イーアルサンスー」ではなく、どういうわけか「いちにさんし」です。
そして語順もまた日本語と同じ「主語、目的語、述語」の順です。
この集団は、長い歳月、中原を追われてジャングルなどの僻地に家族集団でドーナッツ状の巨大家屋を造って、その内側だけで生活をしてきました。
欧米列強が清国の植民地化にやってきたとき、彼らの植民地支配には特徴があって、欧米人にはChina語はわかりませんから、現地にある迫害された(とされる)少数民族に特権を与えて、彼らを手先として利用して、その国の簒奪を行いました。
このとき、英国の手先となって、英国の東インド社のアヘン売買を一手に担ったのがその家族集団でした。
英国のアヘンは人気が高く、当時は麻薬としての扱いは受けておらず、民間の治療薬として、一時的に戦闘によって得た痛みも消す効果があって混迷が続いて暴力が支配したChina国内でたいへんな人気となりました。
またアヘンは性交に用いると男女ともに腰が抜けるほどの快楽を得ることができるのだそうで、そのあたりもアヘンの人気に一役買ったと言われています。
ところが日本軍が統治するところでは、アヘンの密売が規制され、しかも日本軍は、他の国々の軍と違って、彼らの得意の買収戦略もまったく効き目がありません。
当該家族集団にとっては、日本軍は「彼らのアヘンでの金儲けのための市場を奪い取った侵略者」であったわけです。
実はこれが、いまなお日本軍が侵略軍だと呼ばれる真の理由です。
国民党も八路軍も、そのトップはその家族集団です。
彼らは民族の異なる漢族等を操って日本軍への交戦を仕掛けるのですが、圧倒的に数が少ないはずの日本軍が、やたらと強い。
それは、沿道に2万のトーチカを設置し、ドイツ式の最新型の武器を揃えて20倍の戦力を持ってしても、日本軍が勝ってしまうほどでした(第二次上海事変)。
あまりに負け続けるところに、一方で欧米では、代々続く植民地の支配層の貴族や、その貴族らをスポンサーとする政治家たちにとって、日本は、東亜における植民地解放や、人種の平等を高らかに主張するので、建前上は口には出せないけれど、今風に言うなら、ウザい存在でした。
そこで彼らは満州事変で追われた張学良を用いて欧米で清王朝の財宝をバラまいて欧米のVIPを味方に付け、さらに米国にはその家族集団の女性を派遣して、対日排斥運動をはじめました。
先進諸国では、著名人はいたずらに女性に手を出すことができません。
そこでカネと財宝とチャイニーズの美人女性を使って、彼らは著名人の籠絡を始めました。
彼女たちは昭和13年に『日本の戦争犯罪に加担しているアメリカ』という小冊子を刊行し、
「1937年7月、China政府が和平のための努力をしたにもかかわらず、日本の軍事政権は北京郊外で、盧溝橋(Marco Polo Bridge)事件を起こし、これを利用してChinaへの全面的な侵略を開始した」という、荒唐無稽な主張を展開しました。
この荒唐無稽な主張を書いた小冊子を編集発行したのは、「日本の侵略に加担しないアメリカ委員会」という名の団体です。
荒唐無稽な主張など、客観的事実に対して無力だろうなどと考えるのは、世界の中でお人好しの日本人くらいなものです。
その荒唐無稽な主張に色とカネが着いてくるのです。
しかも、一度籠絡されてしまえば、その後は云うことを聞かなければ殺されます。
まさにアメとムチなのです。
結果この団体には、ヘンリー・スティムソン(元国務長官、後陸軍長官)、ロジャー・グリーン(元在漢口アメリカ総領事)、ハリー・プライス(元北京大学教授)、マーガレット・フォルシス(YWCA北米同盟)、フランク・プライス(在中宣教師)、アール・リーフ(元UP中国特派員)、ジョージ・フィッチ(中国YMCA主事)、ヘレン・ケラー(作家)、マクスウェル・スチュワート(『ネイション』副編集長)、フィリップ・ジャッフェ(『アメレジア』編集長)など、政界とメディアの大物がズラリと顔を揃えました。
そして小冊子には、ルーズベルトも寄稿して、
「宣戦布告もなく、いかなる種類の警告も弁明もなく、女性や子供を含めた民間人が空から降ってくる爆弾によって虐殺されている」
と書き、またパール・バック女史は、
「世界のためを考えるならば、
日本とChinaとどちらが勝者になってくれるのが好ましいだろうか。
Chinaが勝ってくれる方が、はるかに世界の利益に叶うように私には思われる。
日本が勝ったならば、
一等国に成り上がるばかりでなく超大国となって、
東洋全体を掌中に収めるであろう。
日本はさらにプライドを高めて
なお一層の征服に乗り出すであろう。」
と書き立てました。(史実を世界に発信する会・資料より)
そして米国の民衆のほとんどすべては誰も日本との戦争など望んでいなかったにも関わらず、これが米国の「世論」ということになって、ルーズベルトは日本を開戦へと追い込んでいくことになるわけです。
パール・バック女史は知りませんが、このとき、他の男性の米国要人のもとには、かなりの数のChinese女性が献上されたといいます。
こうして、なんと宋姉妹の工作活動は、スタートからわずか一年後には、米国の対日通商条約破棄という暴挙に至り、その3年後には、ついに真珠湾攻撃に至るわけです。
我々日本人は、スパイというと、007や忍者のイメージで、裏の世界でうごめく人を想像しがちですが、世界的な大スパイというのは、世間でも名の通った大物です。
そもそも影響力のある人であり、それなりのカネとヒトを動員できる人でなければ、工作などできないのです。
当然のことです。
よく、日本はChinaの宣伝工作によって追い詰められたという話を聞きます。
しかし宣伝なら、戦前の日本もしていたのです。
しかし、ただ宣伝したり、オフィシャルな正論を展開する日本に対し、Chinaはあらゆる非合法手段を駆使して、目的を遂げようとしました。
いまでもChinese美女が工作のために要人の夜の同伴をするということが行われるのだそうですが、それら美女はChina中から集められ、言うことを聞かなければ見せしめのために彼女たちが見ている前で、言うことを聞かない女性は処刑されます。
さっきまでこぼれるような笑顔が自慢だった女性が、形がなくなるまで機銃掃射をあびて五体バラバラにされるのです。
その様子を目の前で、他の女性達が見せられる。
言うことをきけば、ありとあらゆる贅沢が与えられ、聞かなければ残酷な処刑が待っている。
今も昔も変わらぬ、アメとムチの巧妙な使い分けがそこにあります。
個人的に、人を利用主義的に利用するということは、するのもされるのも絶対に受け入れられません。
人は、誰もが対等であり、おほみたからであり、安心と安全と、互いのよろこびや幸せのために自分なりに誠実をつくすことが大事なことだと思います。
なぜなら日本人にとって正義とは、多くの民衆が豊かに安全に安心して暮らせることです。
このことは、日本が古来、民衆を国家最高権威である天皇の「おほみたから」としてきたことに由来します。
民衆が国家最高権威の宝なのですから、その民衆に利益があることが正義なのです。
ところが世界には天皇の存在はありません。
ですからどこの国でも、どこの民族でも、上下の支配構造が秩序であり、正義です。
上がどんなに間違っていても、上に従うことが正義であり、従わないことは悪だということになります。
ですから上に立つ人にとって、下の人を利用主義的に利用することは正義です。
正義の根本概念が違うのです。
日本人の常識は、世界の常識ではないのです。
それからもうひとつ、上にご紹介した『暗黒大陸 中国の真実』にあった「糞尿を作物の肥料として活用する」ことは、日本でもごく普通に行われていたことです。
ただ、日本では、Chinaのように回収した糞尿をそのまま畑に蒔くのではなく、深い穴の肥溜めに糞尿を入れ、そこで発酵させて良質な肥料にして畑に撒きました。
発酵させて畑に撒いた方が衛生的でもあるし、肥料としても役立つのです。
ところがChinaでは、直接畑に撒いて、裸足で土とこねました。
どうしてそのようなことになったかというと、畑はいつ暴徒たちに襲われて、作物を根こそぎ持っていかれるかわからなかったからです。
ですから深々と肥溜め用の穴を掘って肥を発酵させることもできないし、仮に掘っても、万一そこに暴徒の誰かが落ちようものなら(昔は日本でも子供などがよく落ちたものです)、報復のために一族全員皆殺しに遭いかねなかったのです。
哀れといえばとんでもなく哀れなことですが、人が人を支配することが正義とされるウシハク国では、それが社会の常識なのです。
女性の服装が、綿でできた黒の半長パンツと、何度も洗いざらして色の抜け落ちた上着しかなかったというのも、同じ時代の日本が、相当、貧しい人達であっても、現実にもう少しましな服装をしていたことを考えれば、いかにChinaの民衆が虐げられていたかわかります。
Chinaが貧しかった理由のひとつに、作物の収量に対して人口が多すぎる、という問題がありました。
そこで昭和初期に、日本で従来の品種の5倍もの収量のある小麦(農林10号)を開発した稲塚権次郎博士が、この小麦をChinaに持ち込み、終戦後もまる二年Chinaにとどまって、その栽培指導をし続けました。
これは蒋介石の依頼があってのことです。
Chinaでは、日本からもたらされた新種の小麦によって、小麦の収量がいまでは当時の3倍になっています。
「これで、みんなが腹いっぱい食えるようになり、民度もあがるだろう」というのは、日本人の甘い見通しでした。
Chinaでは小麦の収量が増えた分、そのまま人口が増えました。
大東亜戦争開戦前のChinaの人口は4億5千万人です。
それがいまでは15億人です。
そしてその多くは、年間所得が30万円にも満たない貧しい人々です。
いかなる道徳も、社会システムも、それは人間が作るものです。
これはとても大事なことです。
「いかなる道徳も社会システムも、人間が作ったもの」なのです。
その道徳や社会システムが歪んでいれば、人間は弱肉強食の動物と同じになります。
人間に危害を加える動物たちがひしめきあっているところには、人間は近づかないのが、実は一番良い。
セオドラ・ルーズベルト・ジュニアは、米国の第25代副大統領であり、第26代大統領、そして大東亜戦争開戦時の第32代米国大統領であるフランクリン・ルーズベルトの遠縁にあたる人です。
そのセオドラ・ルーズベルトの奥さんが、昭和12(1937)年10月にChinaの視察から帰ってきて、『サタデー・イブニング・ポスト誌』に、婦人が実際に見た事実を述べています。
******
突然私達は叫び声を聞いた。
それは不機嫌なわめき声に変わっていった。
私達のすぐ下で、ひとかたまりの群衆が激怒した暴徒と化し、大声で叫びながら、5人の日本人を追っていた。
4人はうまくバスの中に逃げ込んだ
奇妙だが、中国人は日本人を引きずり出そうとしなかった。
ひとりがよろけて落ちた。
彼らはそこに襲いかかった。
それから彼は、血だらけになるまで蹴られた。殴られた。踏みつけられた。
肋骨が折れ、顔がどろどろと血まみれだった。
そこに白いターバンのシーク教徒の交通警察官が南京路の交差点からムチを持ってやってきて、暴徒をうさぎのように追い散らした。
それから救急車を呼んだ。
暴徒がまた集まってきた。
あきらかにやり返しに来たのだ。
私はあの日本人が死んでいると確信した。
しかし、担架に乗せられたとき、彼の手が動くのを見た。
(『中国の戦争宣伝の内幕』ウイリアムズ,フレデリック・ヴィンセント著 p.34~35)
******
貧しいChinaの民衆に同情し、彼の国で農業指導や教育などにあたった結果がこれです。
そしてセオドラ・ルーズベルトの奥さんが、この事件の目撃をしたのは、通州事件などが起きたあと、そして日本軍によって南京城にいた国民党が追い払われ、南京の治安が回復した直ぐ前の出来事です。
そして、そういう性質を持ったChineseたちが、いま、南シナ海に軍事施設を作っているだけでなく、東シナ海にも海上ヘリポートを建設しています。
その場所は、尖閣諸島のすぐ近くです。
そして日本国内には、人民解放軍の兵士達がウヨウヨいる状況です。
Chineseが全部悪いと言う気はさらさらありません。
そういう意味での差別には断固反対です。
まともな人もたくさんいるからです。
ただ、同じ日本人同士の親しい友人であっても、やはり、違いはあるものです。
早い話が、隣の家と我が家では、家風が違います。
ましてや国や民族や言語が違えば、その風俗習慣も、歴史伝統文化も、まるで異なるものであるのは当然です。
それを、あたまから「日本人と同じ」として、違いを理解したり区別したりすることさえも否定してしまうのは、それこそ、むしろ傲慢というものです。
他国には、他国の文化があるのです。
たとえば南洋のある島では、男性同士が親しくなった時、たがいの下半身を撫で合うという習慣をもった民族がいるそうです。
普通の日本人なら、まさに「たまげて」しまいそうな風習ですが、彼らにとっては、それはそれで意味のある立派な風習です。
日本式の礼がただしくて、その民族の礼は間違っているなどと、どうして決め付けることができるのでしょうか。
アフリカには、親しみを込めた挨拶に、たがいに唾をかけあうという風習をもった民族があります。
これまたびっくり仰天ですけれど、彼らにしてみたら、体を接してキスをすることのほうが、よっぽど異常に思えるのだそうです。
日本人はよく風呂に入りますし、温泉とか大浴場とか大好きです。
けれど、国や民族によっては、風呂もシャワーも、一生に何度か経験する程度という民族もあります。
おとなりのChinaでは、民衆は起きているときの服装のまま寝るのがあたりまえです。
パジャマに着替えるということが、奇妙に思えるそうです。
危険が迫った時に、着替えなければ逃げることができないからです。
民族ごとに、違いがあります。
だから国境があります。
「違いがある」ということを、ちゃんと認識して、お付き合いをする。
そこにある程度の距離感は、これはむしろ人間関係を円滑にしていくのに、必要なことです。
なんでもかんでも受け入れれば良いというものではないのです。
参考図書(お薦め本です)
◆『暗黒大陸 中国の真実』ラルフ・タウンゼント著
◆『中国の戦争宣伝の内幕』ウイリアムズ,フレデリック・ヴィンセント著
※この記事は2018年6月のねずブロ記事のリニューアルです。