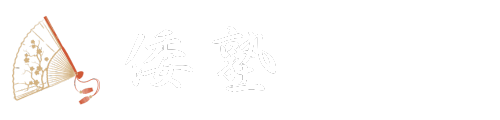明治19年(1886年)8月1日、清国海軍の北洋艦隊の軍艦「定遠(ていえん)」「鎮遠(ちんえん)」「済遠(さいえん)」「威遠(いえん)」が長崎に入港しました。
どれも最新鋭の軍艦で、特に「定遠」「鎮遠」は東洋一の威容をほこる大戦艦でした。
鉄は国家なりといわれた時代ですから、軍艦の大きさは国力の象徴でしたし、大戦艦は強国の証でした。
北洋艦隊が日本に立ち寄った表向きの理由は、「艦艇修理」でしたが、実際には、日本に対しての軍事的偵察(ていさつ)と威圧(いあつ)、恫喝(どうかつ)の任務を帯びていたといわれています。
中国は古くから儒教の国といわれています。
けれど同じ儒教でも、中国と日本では、ぜんぜん違った理解をされてきました。
中国の儒教では、上下関係こそ、あらゆる価値観に優先するとされています。
なぜそうなるかといえば、中国は古来、皇帝を頂点とした支配と隷属(被支配)の関係によって構築された国だからです。
真実や正義、道理よりも、「上からの意思」が優先されたほうが政治的に支配しやすいわけです。
そして下の人間は、常に上の人間に従うことが正しいとされます。
ですから、中国の人々にとって、「どっちが上か下か」は大問題になります。
日本人のような「対等」という概念はありません。
そんな中国人にとって、彼らの思想からみて「下」にある日本が、清国にたてつき、欧米列強から武器を購入して軍備を増強するなど、まさに不届き千万。懲らしめるべきことであったわけです。
こういう背景のもとに清国北洋艦隊は長崎に投錨しました。
そして8月13日、500名の水兵を無許可で長崎の街に上陸させたのです。
上陸した水兵たちは、市中をのし歩き、飲酒、放言、略奪、婦女子を追いかけまわすなど、日本人では考えられないような傍若無人(ぼうじゃくぶじん)な振る舞いをしました。
長崎には、日本三大遊郭のひとつである丸山遊郭がありました。
水兵たちは、そこへも殺到しました。
いくら丸山遊郭が大きな盛り場だったとはいっても、いきなり大人数の「ならず者」たちがやって来れば混乱します。
そして登楼の順番をめぐる行き違いから、水兵たちは、遊郭の備品を壊すなど、いきなり暴れはじめたのです。
「丸山遊郭がたいへんなことになっている」
通報を受けた派出所の巡査二名が現場に向かいました。
その巡査を、中国人水兵たちが取り囲みました。
暴行に及ぼうとしたのです。
ところが、当時の巡査というのは、武家上がりの武道の達人です。
通常の帯剣もせず、警棒しか持っていませんでしたが、たった二名で中国人たちを蹴散らし、中でも反抗的な態度であった二名の水兵をその場で現行犯逮捕したのです(残りは逃走しています)。
そして逮捕した水兵二名を、巡査たちは派出所に連行しました。
普通なら、これで一件落着です。
ところがしばらくすると、中国人水兵十名が派出所にあらわれました。
その中に先ほど逃げた水兵もいたので、巡査がその者を逮捕しようとしたところ、中国人水兵たちは古道具屋で手
に入れた日本刀を抜いて襲いかかってきたのです。
巡査らは、負傷しながらも応戦しました。
そこに応援の警察官らも到着し、水兵たちの刀を取り上げて押さえつけ、現行犯逮捕しました。
水兵たちは、長崎県警察部に送られました。
長崎県警察部では、犯人らを取り調べ、清国領事館に引き渡しました。日本側のここまでの対応は、きわめてまっとうなものです。
非の打ち所のない処置といえます。
翌日、長崎県知事の日下義雄(くさかよしお)が清国の蔡(さい)領事と会談し、
一 清国側は集団での水兵の上陸を禁止する
二 清国水兵の上陸を許すときは監督士官を付き添わせる
という二つの約束を交わしました。
これまた、当然すぎるくらい当然の措置です。
ところが翌十五日、前日の協定に反して、清国水兵約三百名が再び市内に上陸しました。
そして数十名の水兵が交番の前に集結し、放尿したり、大声や奇声をあげたりして、交番の巡査らに対して、露骨な挑発と嫌がらせをはじめたのです。
巡査らは彼らに注意しました。
この時点ではまだ彼らは人に対する暴力には及んでいませんから、口頭での注意です。
すると、彼らのうちのひとりが巡査の警棒を奪おうとしました。
巡査はこれを防ごうとし、もみ合いになりました。
いかに巡査が猛者(もさ)といっても、多勢に無勢です。
しかも清国側は、報復のために屈強な武道の達人を連れてきています。
三名の巡査は果敢に戦いましたが、水兵らに袋叩きにされ、ついにひとりが死亡、ひとりが重体(翌日死亡)という事態に至りました。
この様子を見ていた人力車の車夫が激昂(げきこう)して、清国水兵に殴りかかりました。
これに、人力車引きの仲間たちも加勢します。
すると、近くにいた別の清国水兵の一団が集まってきて、車夫たちを取り囲みました。
こうなると長崎の一般市民も黙っていません。
こうして清国水兵たちと、長崎市民との間で、路上の大乱闘が発生しました。
そこに長崎県警本部から応援に駆けつけてきた警察官も加わります。
ついに乱闘は斬り合いに発展しました。
結果、清国側は士官1名死亡、3名負傷、水兵3名死亡、50名負傷。
日本人側も警部3名負傷、巡査2名死亡、16名負傷、一般市民十数名負傷という大惨事に至ったのです。
これが長崎事件、あるいは清国長崎水兵暴行事件と呼ばれる暴行傷害事件の顛末です。
*
八月二十日、天津にいた李鴻章(直隷総督、北洋大臣)は、天津領事の波多賀承五郎を呼び出しました。
そして「わが方の死者は5名」と犠牲者を1名水増ししたうえで、
「貴国の巡査が刀で無防備のわが水兵を殺傷した」
と、全く事実に反したデタラメを並び立てて、日本の領事を恫喝しました。
死者だけをいうなら、日本側2名、清国側4名です。
しかも武器を持って暴れ回ったのは清国の水兵たちであり、しかもその数、300名です。
しかし、そういう事実を清国側は認めようとしなかったため、日清両国で事故の調査委員会を発足させることになりました。
そして調査の客観性を確保するために、欧米の法律家にも参加してもらい、正確な事態の把握に努めることになりました。
日本と清国の交渉は、何度も行われました。
けれど客観的証拠に基づく日本や欧米弁護士などの主張に対し、清国側は客観性のない主張を繰り返すだけでした。
やむなく決着は、政治に委ねられることになりました。
そして明治20年(1887年)2月、事態をまるくおさめようとする井上馨(いのうえかおる)外務大臣と徐承祖(じょしょうそ)全権行使の両名によって、日本側が一方的に悪いとする妥協案がまとめられました。
さらにその条項の中で、
「日本の警察官は今後帯刀することを禁ずべし」という要求まで突き付けられて、日本はこれを承諾しています。
なぜそのようなことになるのでしょうか。
悔しいことですが、当時の海軍力は、清国の「定遠」「鎮遠」が、共に排水量7千トン級の大戦艦であるのに対し、日本側は排水量4千トン級の巡洋艦「浪速」「高千穂」を擁(よう)するのみだったのです。
陸軍力でいえば、清国は2百万以上の動員兵力を持っていましたが、日本は総動員しても最大で25万でした。
ほぼ十倍の兵力差ですから、清国は日本に対して、「楽に勝てる」と踏んでいたのです。
「道理に合わない無理を言われても、
軍事力の前には屈せざるを得ない」
それが、いまも昔も変わらない、国際社会の冷徹な原則なのです。
そして、いざ戦争というときには、国際世論を味方に付けたほうが有利です。
そのためには、先に手を出すことは、得策ではありません。
ですから清国は日本に対して、ありとあらゆる挑発を行い、日本に先に手を出させて、自分たちは被害者を装って国際世論を味方に付けようとしました。
清国の日本に対する挑発は、その後も度々おきました。
*
長崎事件から8年後の明治27年(1894年)7月25日のことです。
朝鮮半島の北西岸の豊島沖で、日本の巡洋艦「秋津洲」「吉野」「浪速」の三隻が、会合予定だった巡洋艦「武蔵」と「八重山」を海上で捜していたところ、清国巡洋艦「済遠(さいえん)」および「広乙(こうおつ)」と遭遇します。
このような場合、軍艦は礼砲を発して挨拶するのが世界の通例です。
しかし清国艦船は、突然、21センチ砲を撃ってきたのです。
やむなく日本も反撃しました。
あきらかな正当防衛です。
日本の巡洋艦が応戦をはじめると「済遠」と「広乙」は逃走し始めました。
日本海軍は「秋津洲」で清の「広乙」を、「吉野」と「浪速」で、大きいほうの「済遠」を追いかけました。
「広乙」は追い詰められて座礁しました。
「吉野」と「浪速」が追った「済遠」は、国旗を降ろして降伏の意を示したかと思えば突如、逃走を図ることを繰り返しました。
そして海上にあった清国軍艦「操江(そうこう)」とイギリス商船「高陞(こうしょう)」のもとに逃げ込みました。
「浪速」は、清国軍艦「操江」に、「済遠」を引き渡すように要求しました。
押し問答をしている間に「済遠」はさっさと逃げてしまいます。
「吉野」は、これを追いかけました。
「吉野」の最高速度は23ノットです。
「済遠」は15ノット。
ですから日本の巡洋艦「吉野」のほうが、断然、船足が速いのです。
ところが「済遠」は逃げながら2門の21センチ砲をバンバン撃ってきます。
「吉野」はジグザグ航法で、敵の弾を避けながら、これを追跡しますから、なかなか追いつけません。
「吉野」の砲門は15センチで小さいけれど、狙いは正確です。
「吉野」は、「済遠」を2500メートルまで追い詰めました。
すると「済遠」は面舵(おもかじ)をとって船を浅瀬へと向かわせたのです。
「済遠」はドイツ製巡洋艦で2300トンで、喫水は4・67メートルです。
「吉野」はイギリス製の4216トンで、喫水は5・18メートルです。
浅瀬に逃げられたらどうしようもありません。
「吉野」は追撃を中止し、「済遠」は逃げてしまいました。
一方、「浪速」艦長の東郷平八郎大佐は「高陞」に停船を命じ、臨検を行おうとしました。
けれど、「高陞」は停船要求に従いません。
やむなく「浪速」は「高陞」を撃沈したうえで「高陞」に乗っていたイギリス人船員ら3名と、清国兵50名を救助して捕虜にしました。
これが豊島沖海戦(ほうとうおきかいせん)です。この海戦による日本側の死傷者及び艦船の損害は皆無です。
他方、清は「広乙」が座礁、「高陞」が撃沈されています。
ところが「吉野」が追撃を中止し、逃げたはずの「済遠」は、なぜか清国の発表では「大破」とされ、日本によって一方的に攻撃されたと発表されたのです。
さらにこの戦いで沈められた「高陞」はイギリス船籍で、清国の兵員を朝鮮半島に輸送する最中でした。
イギリスの船が日本の軍艦に沈められたため、イギリス国内では、日本に対する反感が沸き起こりました。
ところが日本の「高陞」攻撃は、完全に国際法にのっとったものでした。当時の日本政府は、その正当性を海外に訴えました。
そして、『タイムズ』紙に法学者による「違法性はない」という論文が載ると、イギリスの世論は沈静化していったのです。
あたりまえのことですが、ここは重要なポイントです。
いかに不当な宣伝工作が行われようと、堂々と「日本がなぜそのような行動をとったのか」という理由をきちんと説明すれば、世界は納得する、ということです。
言うべきことは、ちゃんと言う。
それが国際社会の常識です。
そこを説明しないでいると、いいように貶められてしまいます。
*
豊島沖海戦の二日後、朝鮮王朝の王妃、閔妃から、半島にいた大鳥圭介(おおとりけいすけ)日本公使に対して、
「牙山(あさん)に上陸した清国軍を撃退してほしい」という要請が出されました。
要請に応じなければ、半島にいる日本人に危害を加えるというのです。
これまた、めちゃくちゃな話ですが、日本は7月29日に、混成第九旅団を牙城に立てこもる清軍の攻撃に向かわせました。
現地に到着した午前2時、先に攻撃してきた清国兵によって松崎直臣(まつざきなおおみ)大尉が戦死しています。
これが日本の明治以降における初の戦死者です。
応戦した日本軍はわずか5時間で、成歓の敵陣地を完全に制圧してしまいました。
翌日、日本軍が牙山へ向かうと、清国軍はすでに敗走したあとでした。
これを「成歓(せいかん)の戦い」といいます。この戦いにおける日本側の死傷者は88名です。
これに対し、清国軍は500名以上の死傷者を出し、武器を放棄して平壌に逃走していたのです。
この戦いのとき、歩兵第二一連隊の木口小平(きぐちこへい)二等兵が、死んでもラッパを口から離さなかったという逸話が残っています。
実に立派です。
このお話は、戦前は尋常小学校の修身の教科書に載っていました。
翌々日、清国軍は牙山から逃げ帰った兵士とあわせて、合計1万2千の大軍を平壌に集結させました。
日本は、あくまで開戦を避けようと、外交交渉を継続しますが、清軍はこれに応じません。
8月1日、日本は、けじめとして清国に宣戦布告文を発しました。
清国が朝鮮の意思を尊重して、兵を引かないなら、日本は戦いますよ、という布告文です。
ここは注意が必要なところです。
我々日本人は、武道の慣習に従って、戦いというものは礼に始まって礼に終わると、なんとなく思っていますが、以上の経緯に明らかなように、すでに戦いは始まっていたのです。
そしてこの場合、宣戦布告文書は、むしろ「戦いをしないため」の警告文として発せられています。
国際社会においても宣戦布告文は、開戦と直接関係するものではありません。
むしろ単なる外交上の脅しとして用いられたり、あるいはそもそも宣戦布告文そのものがないのが普通です。
いまの半島の北側の国など、この数年の間に日本や韓国に向けて、何度も宣戦布告をしています。
しかも北と南はあくまで休戦中であって、いまなお戦争継続中です。
なんのための宣戦布告かと思ってしまいますが、これまた外交戦術として何度でも出されるわけです。
ドンパチをしなくても、一片の文書で済むなら安いものです。
もうひとつ、これまでの経緯で注意が必要なことがあります。
日本は、自分の国がさんざん騙されたり、ひどい目に遭わされたりしていても、それをずっと我慢し続けてきたということです。
和と結いを大切にし、隣人と対等なおつきあいを望む日本は、どこまでも不条理を我慢し、関係の良好化を希求
し続けていたのです。
もちろん、かかる火の粉は払わなければなりません。
しかし、日本はどこまでも和平を願い続けていたことを、私たちは忘れてはならないと思います。
*
日清戦争の宣戦布告文について、ウィキペディアの「日清戦争」をたまたま開いたら、この「詔勅は名目にすぎず、朝鮮を自国の影響下におくことや清の領土割譲など、『自国権益の拡大』を目的にした」と書いてありました。ど
このだれが書いた文章か知りませんが、日本が国家として戦争を行ううえで、明治大帝の名で出された詔勅に対し、「名目にすぎず」と書くのは、あまりにも不敬です。
名目にすぎないかどうかは、開戦の詔勅を読んだら分かります。
そこで日清戦争の「宣戦布告の詔勅」の現代語訳と原文を掲載します。
(現代語訳はねず式、原文は末尾に掲載)
*******
〔清国に対する宣戦布告の詔勅〕
われわれは、ここに、
清国に対して宣戦を布告します。
われわれは明治維新以来20有余年の間、
文明開化を平和な治世のうちに求め、
外国と事を構えることは、
極めてあってはならないことと信じ、
常に友好国と友好関係を強くするよう
努力してきました。
おかげさまで諸国との交際は、
年をおうごとに親密さを加えてきています。
ところが清国は、朝鮮事件に際して、
日本に対して、
日本側の隠すところのない友好の姿勢にそむいて、
互いの信義を失わせる挙に出ました。
そのようなことを、
私たちはどうして予測できたことでしょう。
朝鮮は、日本が、そのはじめより、
導き誘って諸国の仲間となした一独立国です。
しかし清国は、
ことあるごとに自ら朝鮮を属国であると主張し、
陰に陽に朝鮮に内政干渉してきました。
そして朝鮮半島内に内乱が起こるや、
属国の危機を救うという口実で
朝鮮に対し出兵までしています。
私たちは、
明治十五年の済物浦条約によって、
朝鮮に平和維持部隊を出して
治安維持をはかり、
事変に備えさせ、
また朝鮮半島から戦乱を永久になくして、
将来にわたって治安を保ち、
それをもって東洋全域の平和を維持しようと欲し、
まず清国に(朝鮮に関して)協同で
治安維持にあたろうと告げました。
けれど清国は度々態度を変え続け、
さまざまな言い訳をしてこの提案を拒み続けました。
私たちはそのような情勢下で、
朝鮮には、彼らの悪政を改革して、
治安の基盤を堅くし、
彼らが対外的にも独立国としての
権利と義務をきちんと全うすることを
勧めてきました。
けれども朝鮮が、われわれの勧めを
肯定し受諾したにもかかわらず、
清国は終始、裏にいて、
あらゆる方面から、その目的を妨害し、
それどころか言を左右にしながら口実をもうけて、
時間をかせぎながら、水陸の軍備を整え、
それが整うや、ただちにその戦力をもって、
(朝鮮征服の)欲望を達成しようとして、
大軍を朝鮮半島に派兵し、
また私たちの海軍の艦を黄海に要撃してきました。
清国の計略は、
あきらかに朝鮮国の治安の責務を担おうとする
私たちの行動を否定し、
私たち日本が率先して独立諸国の列に加えた朝鮮の地位を、
それらを明記した「天津条約」と共に、
めくらましとごまかしの中に埋没させ、
日本の権利や利益に損害を与え、
東洋の永続的な平和を
保障できなくすることにあるといえます。
清国のたくらみのありかを深く洞察するならば、
彼らは最初から朝鮮はじめ東洋の平和を犠牲にしてでも、
その非情な野望を遂げようとしていると言わざるをえないのです。
そして事態はここまできてしまいました。
われわれは、平和であることこそ国家の栄光と、
国の内外にはっきりと顕現させることに専念してきましたが、
残念なことではありますが、
ここに公式に宣戦布告を行います。
私たちは、国民の忠実さと勇武さに寄り頼み、
すみやかに、この戦争に勝って、
以前と同じ平和を恒久的に取り戻し、
帝国の栄光を全うすることを決意します。
(明治27年8月1日)
*********
宣戦布告は、8月1日です。
けれど日本は、その後もなんとか外交努力で事態を鎮静化しようと努力しました。
ところが事態は一向に改善しませんでした。
やむなく日本は、1カ月半後の9月15日になって、平壌にある清国軍の基地への攻撃を開始しました。
清国軍は、その日の午後4時40分には、白旗を掲げて翌日の開城を約束しています。
ところが、清国軍は、約束を違えて逃亡してしまいました。
そして、同日夜に日本軍が入城しました。
日本の大勝利です。
2日後の9月17日12時50分、黄海上で、日清両艦隊が遭遇しました。
日本側は、初代聯合艦隊司令長官伊東祐亨(いとうゆうこう)中将率いる旗艦「松島」以下12隻。
清国艦隊は、18隻です。
先に攻撃してきたのはこんどもまた清国です。
敵戦力のほうが大きかったのですが、日本艦隊は、果敢に戦い、清国艦5隻を撃沈、5隻を大中破、2隻を座礁させて、大勝利します。
この海戦によって、清国艦隊は威海衛(いかいえい)に閉じこもることとなり、日本海軍は黄海・朝鮮の制海権を完全に確保します。
さらに10月25日には、山縣有朋(やまがたありとも)率いる第一軍が鴨緑江(こうりょくこう)渡河(とか)作戦で清国陸軍に大勝利しました。
11月22日には、大山巌率いる第二軍が旅順を制圧します。
日本は、明治28年(1895年)4月の日清戦争の講和条約まで、清国軍を相手に連戦連勝し続けたのです。
*
明治19年の長崎事件から、明治28年の日清戦争講和までのおよそ9年の歴史をまとめてみました。
ご一読いただければ、今も昔も何も変わっていない・・・どころか、まったく同じ構図になっていることがおわかりいただけると思います。
その意味で、現代日本は何も歴史から学んでいない。
もったいないことだと思います。
「力なき正義は無力なり」といいます。
日清戦争の歴史を振り返る時、やはりそのことは正しいということがわかります。
このことを通じて、私たちは、世界では「力によってどんな非道も正義にされてしまう」ということを学ぶ必要があります。
ひるがえって現代を観たとき、いまの日本に力はあるでしょうか。
攻撃力、防衛力、そして民衆の意識はどうでしょうか。
日本は庶民の国です。
その庶民が目覚めなければ、日本の国護りは不可能なのです。
諸外国諸民族の場合、ごく一握りの、あるいはたったひとりの権力者によって、紛争も戦争も引き起こされます。
彼らは自分で戦う必要はありません。
人に「戦え」と命ずるだけで良いのです。
たとえ敗れても、彼らは傷ひとつ負うことはありません。
彼らにとって戦いは他人事であり、ただのゲームでしかありません。
けれど、それによって、生きて呼吸をしている多くの命が奪われ、そこには必ず庶民の涙があるのです。
精神性にも違いがあります。
日本人は縄文の昔から、公正を重んじます。
公正に世の中が動いていれば、それに対して誠実に対応します。
だからそこに信用があります。
けれど、相手が公正を破ったときには、日本人は古代からずっと、断固として戦いました。
ひとりひとりが戦ったのです。
この場合、自分の命が失われることはまったく問題にならないし、相手を斬り殺しても構わないとされてきました。
つまり日本では、上古の昔から武力行使の前に「公正」がありました。
チャイナは異なります。
武力行使の結果が「公正」を決定したのです。
これは文化性の違いです。
日本が米国の傘の下にあれば安心という時代は終わりました。
米国は、とっくの昔に、世界の警察という存在にあることを罷めているし、その米国自体が公正を失ない、いまや米国政府は、一部の人たちの利権のための政府と化しています。
これは米国民の求める政府の形ではありません。
つまり米国民と米国政府は、向かおうする方向が異なります。
米国だけではありません。
日本の周囲には、大日本帝国への対抗国家として成立したチャイナやコリアがあります。
彼らにとっては、暴力の結果が公正なのです。
そしてそのことは、人類普遍の原則である、公正と信頼を損ねるものです。
日本人がサラリーマン根性で、ぶら下がっていれば給料をもらえた時代は終わりました。
これからの時代は、日本人が、日本の足でしっかりと立っていかなければならない時代です。
日本が目覚めるときがやってきたのです。
そして、目覚めた日本にもたらされる未来は、愛と平和に満ちた、安全で安心な社会です。
そうあらなければならないのです。
そうであれば、いま我々は、そうした未来を築くために、一歩を踏み出して行かなければならないのだと思います。
※この記事は2020年7月の記事のリニューアルです。