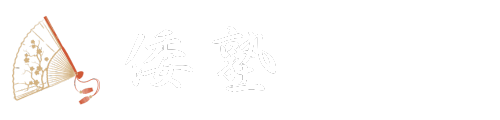和泉式部は平安日記文学の代表『和泉式部日記』でも有名な女性です。
和漢に通じ平安時代を代表する女流文学者である和泉式部が、晩年、自らの死を前にして詠んだ歌が百人一首に収蔵されています。
あらざらむこの世のほかの思ひ出に
いまひとたびの 逢ふこともがな
歌の意味は、
「私はもう長くはいきていない(在らざらん)ことでしょう。
けれどこの世の最後の思い出に、
今一度あなたに逢いたいです」
というものです。
この時代の「逢ふ」は、男女が関係するという意味がありますから、ここでの「もう一度逢いたい」は、「あの人にもう一度逢いたい、抱かれたい」という意味が込められます。
ストレートにも思える愛情表現です。
それだけなら、「ああ、そういう思いもあるのだなあ」という程度の話にしかならないかもしれません。
なかには「だから和泉式部はエッチな女性だったのだ」などと、下品な論評をしている先生もいます。
和歌に少しでも興味を持ってもらおうという気持ちからだとお察ししますが、そこまで品を落とさなくても、和泉式部は、ちゃんと解説したら、誰もが感動する歌です。
この歌で和泉式部は「あなたに逢いたい、抱かれたい」と歌っているわけですが、ところがこの歌を詠んだときの和泉式部は出家して尼さんになっていたのです。
尼さんというのは、色恋を含めて俗世のすべてを捨てて御仏に仕える人です。
そしてこの歌を詠んだとき、和泉式部は、すでに余命幾ばくもなく、相手の男性は、もしかすると既にお亡くなりになっている男性なのです。
この歌は『後拾遺集』に掲載されているのですが、詞書(ことばがき)には次のように記されています。
「心地(ここち)
例ならずはべりけるころ、
人のもとにつかはしける。」
病に侵され、余命いくばくもない、あと何日かしたら自分は死ぬのだとわかったとき、彼女は自らの思いを歌に託して、親しい女友達にこの歌を送りました。
誰に送ったのかはわかりません。
おそらく誰にも言えないような本音を語れる数少ない親しい同性の友達に渡したのであろうとされています。
ではいったい和泉式部は、何を思ってこのような歌を最後にのこしたのでしょうか。
少女時代の和泉式部は、歌も漢詩もよくでき、字も美しく、将来を嘱望される「とてもよくできた女の子」であったと伝えられています。
美人でかわいらしくて愛嬌があって、しかも勉強がよくできて、字もきれいで頭の良い。
振り返ってみれば、みなさんにも小学校時代の同級生に、そんな子が身近にもいたのではないでしょうか。
そんな彼女は、いつの日か自分のもとに美しい王子様があらわれて、きっと幸せな結婚をするのだと夢見る少女でもありました。
けれど現実の人生というのは、意外と「しょぼい」ものです。
二十歳になった彼女は、平凡な男性である橘道貞(たちばなのみちさだ)と結婚して、一女をもうけるのですが、漢学や和学の話を夫にしても、夫はそういう学問の話についてこれないのです。
大好きな学問の話をしても、夫にはまるで通じない。
彼女は夫とともに、任地である和泉国(いまの堺、岸和田市のあたり)に赴任するのですが(そのことがきっかけで、彼女は和泉式部と呼ばれるようになりました)、彼女の結婚生活は、必ずしも夢見ていた理想の生活ではなかったようです。
任期が終わり、ようやく夫婦で再び都に舞い戻ってきた時、彼女は子を連れて、夫と別居してしまいます。
ところがそんな彼女の前に、こんどは本物のプリンスが現れてしまうのです。
それが冷泉天皇の第三皇子である為尊親王(ためたかしんのう)です。
「ソウル・メイト」というのかもしれません。
二人はまさに「ひと目あったその日から」熱愛におちいってしまうのです。
けれど和泉式部には、別居しているとはいえ夫がいます。子もいます。
和泉式部の父親の越前守大江雅致(おおえまさむね)は、娘のこの交際に激怒しました。
我が娘は人妻であり子もいながら、冷泉天皇の皇子と関係してしまったのです。
「たいへんなことをしてくれた!」
怒った父は、和泉式部に為尊親王(ためたかしんのう)と別れるよう説得します。
しかし愛一色に染まってしまった和泉式部には、もはや殿下と別れるなど考えられないことです。
思いあまった父は娘の和泉式部を勘当してしまいます。
この時代、親子の縁を切られるということは、親から死んでしまえと言われるのと同じくらい重たい出来事です。
それでも和泉式部は、為尊親王を愛しました。
まさに全身全霊を込めて為尊親王を愛したのです。
為尊親王も和泉式部に夢中でした。
為尊親王には知性もあり、教養もあります。
和泉式部は誰より美しく、しかも教養にあふれています。
二人は、互いの会話も楽しくて仕方がない。
してはいけない恋、禁断の恋、不倫の恋だということはわかっています。
けれど、だからこそ、いけない恋は、麻薬のように人を狂わせ、夢中にさせます。
逢ってはいけないと思うほど逢いたい。
周囲の反対が強いほど、互いを意識し、求めあう。
そういうことは、世の中によくあるようです。
結局、和泉式部は離婚しました。
そして為尊親王と暮らしはじめました。
二人の愛は永遠に続くと互いに信じきっていました。
ところが、その為尊親王殿下が、弱冠二十六歳でお亡くなりになってしまうのです。
心の底から愛し、周囲の反対を押し切ってまで夢中になった彼が死んでしまう。
何もかも捨てて和泉式部は為尊親王に自分を捧げていたのに、その彼が亡くなってしまう。
和泉式部は、どうしたら良いのでしょう。
悲嘆に暮れる和泉式部の前に、為尊親王の弟の帥宮(そちのみや)敦道親王(あつみちしんのう)が現れます。
帥宮(そちのみや)は、とてもやさしく、兄の葬儀のときにも、まるで消えてしまいそうになっている和泉式部をみかねて、なんとかして彼女を元気付け、力づけ、彼女が再び生きる気力を取り戻してくれるように彼女を励ましてくれました。
殯(もがり)の間も悲しみに暮れる和泉式部をなぐさめ、ずっとそばに寄り添ってくれたようです。
自分も尊敬していた兄が愛した女性なのです。
その女性が、見る陰もなく、やつれ果てて悲しみに沈んでいる。
これを放っておくことができるほど、帥宮は冷たい男ではありません。
帥宮は、和泉式部を気遣い、一度、和泉式部のもとに訪ねて行って、兄貴のために線香をあげたいと彼女に何度も歌を贈っています。
けれど和泉式部にしてみれば、それはとってもありがたいお申し出ではあるけれど、いくら弟君とはいっても、相手は男性です。家に上げるのは気がとがめるし、まして愛した男性は為尊親王です。
ですから和泉式部は、帥宮の来訪をお断りしました。
けれどそうはいっても相手は宮様です。何度もお断りするのは、あまりにも失礼です。
ある日彼女は、帥宮が自宅にお越しになることを承諾します。
帥宮は、約束通り和泉式部を訪ねました。
和泉式部を元気づけようとする帥宮は、兄の子供時代の楽しい思い出などを和泉式部に語ってくれたようです。
兄は、二人にとって、共通の思い出の人です。二人の会話は弾みました。だって愛する為尊親王の、自分の知らない少年時代の思い出をお話してくださるのですもの。
もっと聞きたいと思うのは、ごく自然ななりゆきです。
気がつけば、もう夜中になっていました。
そして、二人は、関係をもってしまいます。
やさしい帥宮との出会いは、彼女に再び生きる気力を与えます。
けれど彼女の心には葛藤があります。
自分が愛したのは、兄の為尊親王なのです。
いま自分を愛してくださっているのは、弟の帥宮です。
その葛藤の半年を綴った日記が、有名な『和泉式部日記』です。
彼女は、一生懸命に帥宮を愛しました。
それは葛藤はあったけれど、帥宮のやさしさに包まれた、幸せな日々でした。
ところが、その帥宮が、わずか二十七歳の若さで亡くなってしまうのです。
和泉式部はどうしたらよいのでしょう。
何もかも神は奪い去ってしまう。
和泉式部の心中は察して余りがあります。
和泉式部は、いまでいう引きこもりのような状態になってしまいます。
そんな和泉式部を見かねたのが、一条天皇の中宮であられた藤原彰子(ふじわらのしょうし)です。
彼女は兄弟の御子二人に愛された女性です。
しかも和漢に通じた才媛です。
引きこもらせておくのは、あまりに惜しい逸材です。
中宮は、和泉式部の才を惜しまれ、彼女を自分の手元で宮中の仕事ができるように取りはからってくれます。
これはとてもありがたいことです。
和泉式部は、彰子のもとで働きました。
それは、とっても誠実で、まじめなお勤めでした。
けれど宮中の、それも女性ばかりの社会です。
周囲の女性たちの和泉式部を見る視線はとても冷たい。
紫式部が、和泉式部のことを次のように書いています。
「和泉式部といふ人こそ、面白う書き交しける。
されど和泉はけしからぬ方こそあれ」
歌や書き物の才能は認めるけれど、人品行状が怪しからんというのです。
せっかく中宮の好意で出仕させていただいた和泉式部ですが、周囲の視線は刺すように冷たいものでした。
それでも和泉式部は中宮の好意を無にしないように、一生懸命勤めを果たしました。そしていつしか十年の歳月が経ちました。
ある日、中宮のもとに、和泉式部をどうしても妻にもらい受けたいという男性が現れました。
五十歳を過ぎで武勇で名の知られた藤原保昌(ふじわらのやすまさ)です。
和泉式部は、このときすでに三十代半ばです。
当時の感覚としては、とっくに婚期を逸しています。
「それでもよい」
と藤原保昌は言いました。
彼女の過去も全部知った上で、彼女を妻に迎えたいと言ってきてくれたのです。
藤原保昌という人は、どちらかというと男性にはモテるけれど、女性にはトンと縁がない、そんな無骨者であったようです。
けれど男らしいやさしさを持つ男でもあります。
年齢も五十の坂を超え、人格にも深みと包容力が生まれています。
人格識見身分とも、申し分のない人物です。
つまり、これは良縁です。
和泉式部は、世話になった中宮彰子の勧めもあり、藤原保昌と結婚します。
藤原保昌は、男からみても、信頼出来る良い男です。
人間としても完成された大人であったし、なにより和泉式部を心から愛してくれていたようです。
二人の間には、ほどなくして男の子が生れます。
夫の藤原保昌は、二人の間に出来た子も、和泉式部の連れ子の娘も、わけへだてなく愛してくれました。
けれど和泉式部の心の中には、いまだに亡くなった為尊親王や帥宮がいます。
ときに昔を思い出し、ひとり涙に暮れる日もあったようです。
そんなとき藤原保昌は、すべてをわかって何も言わずに、黙って和泉式部の肩をそっと抱いてくれる、そんな夫でした。
すべてをわかったうえで、夫は和泉式部を心から愛したのです。
「そういう夫のやさしさに、自分もしっかりと答えていきたい」
和泉式部は、一生懸命になって夫の藤原保昌を愛そうとしました。
一番好きだった人には死なれてしまったし、次に現れたプリンスも亡くなってしまった。
けれどいまの夫の藤原保昌は、そんな自分を、そして大切な我が子二人を心から愛してくれている。
人として、そういう夫の気持ちにしっかりと応えて行くことが、いまの自分のつとめなのだ、和泉式部は、そう自分に言い聞かせていたようです。
けれど、そう思えば思うほど、為尊親王や帥宮の面影が、ふとしたはずみに浮かんでは消えます。
そうなると涙がとまらない。
そんなとき彼女は、誰にも見つからないように、ひとりでひそかに泣きました。
夫の保昌は、そんな彼女にちゃんと気づいていました。
そして、知っていて、そんな彼女をやさしく包み込んでくれました。
しかし、だからこそ彼女は自分の心が赦せない。
夫のやさしさが、とっても残酷に感じてしまう。
そんなとき、夫の保昌はいったいどうしたら良いのでしょう。
ある日、保昌は、
「妻をひとりにしておいてあげよう」
と、しばらく家を空けて実家に帰ってしまいます。
それは夫の妻を思いやる、男としてのやさしさです。
けれどそのことが和泉式部には、夫に見捨てられてしまったように感じられてしまいます。
そこで和泉式部は、縁結びの神様として有名な貴船神社にお参りに行きます。
その参拝の帰りに、和泉式部が詠んだ歌があります。
もの思へば 沢の蛍も 我が身より
あくがれいづる 魂かとぞみる
この歌には和泉式部の詞書があります。
そこには次のように書いてあります。
男に忘られて侍りける頃、
貴船にまゐりて、
御手洗川にほたるの
飛び侍りけるを見て詠める
和泉式部は、夫のおもいやりを、自分が夫に忘れられたと思えてしまったのです。
だから貴船神社にお参りをしました。
その帰り道、暗くなった神社の麓に流れる御手洗川に、たくさんのホタルが飛んでいる姿を見て、自分の魂も、もうこの肉体から離れて(死んで)あのホタルとなって、何も考えずに自由に飛び回りたい、そんな歌です。
ところがこの歌を詠んだとき、和泉式部の頭の中に、貴船の神様の声がこだまします。
その声を、和泉式部は歌にして書き留めています。
奥山に たぎりておつる 滝つ瀬の
たまちるばかり 物な思ひそ
貴船神社の御神体は、神社の奥にある滝です。
その滝が「たぎり落ちる」ように魂が散る、つまり毎日、多くの人がお亡くなりになっています。
要約すると神様の声は、次のようになります。
貴船神社の奥にある山で、
たぎり落ちている滝の瀬のように、
おまえは魂が散ることばかりを
思っておるのか?
人は、いつかは死ぬものじゃ。
毎日、滝のように多くの人が
様々な事由で亡くなっていることを
お前も存じておろう。
人は生きれば、いずれは死ぬのじゃ。
おまえはまだ生きている。
生きているじゃないか。
生きていればこそ
ものも思えるのじゃ。
なのになぜお前は
魂の散ることばかりを思うのじゃ。
和泉式部は、夫のとの間にできた男の子が元服したのを機会に、そのやさしい夫である藤原保昌から逃げるように、夫に無断で、尼寺に入ってしまいます。
彼女はそのとき、すでに四十七〜八歳となっていたようです(正確な年齢はわからない)。
寺の性空上人は、和泉式部が髪をまるめたとき、自分が着ていた墨染めの袈裟衣を和泉式部に渡してくれました。そして、
「この墨染の衣のように、すべてを墨に流して御仏にすがりなさい」
と仰しゃいました。
彼女も、その衣を着ることで、現世の欲望を絶ち、仏僧として余生を過ごそうと決意しました。
こうして和泉式部は京都の誠心寺というお寺に入りました。
この寺の初代住職が和泉式部です。
ところが住職となって間もなく、彼女は不治の病に倒れてしまうのです。
医師の見立てでは、あと二〜三日の命ということでした。
そうと知った彼女は、病の床で、最後の歌を詠みました。
それが冒頭の、
あらざらむこの世のほかの思ひ出に
いまひとたびの 逢ふこともがな
です。
彼女はその歌を、親しい友に託しました。
人生の最後に、和泉式部が「もう一度逢いたい、そのあたたかな胸に抱かれたい」と詠んだ相手が誰だったのかはわかりません。
彼女は亡くなりました。
和泉式部は生前にたくさんの歌を遺しました。
彼女の歌で、特に秀逸とされるのは哀傷歌といって、為尊親王がお亡くなりになったときに、その悲嘆の気持ちを詠んだ歌の数々とされています。
けれど小倉百人一首の選者の藤原定家は、和泉式部を代表する歌として、彼女の晩年の最後のこの歌を選びました。
歌に使われる文字は、たったの三十一文字です。
そして、その歌にある表面上の意味は、たんに「もう一度逢いしたい」というものです。
けれど、そのたった三十一文字の短い言葉の後ろに、ひとりの女性の生きた時代と、その人生の広大なドラマがあります。人の生きた証が、そこに込められているのです。
戦前から戦中にかけて、学校の授業で古典和歌を学ぶときは、教師がこのようなお話をしてくれました。
だから、生徒たちは誰もが、和歌に夢中になりました。
そして日本人としてのやさしさや思いやりの心を身につけました。
学校の授業は、単に知識を詰め込むだけのものではなく、そこに感動がありました。
だから子供たちは、片道何キロもの道を歩いて毎日登校したし、田植えなどで親から学校を休むように言われると、泣いて学校に行けないことを悔しがったし、友達からその日の授業のノートを見せてもらい、先生のお話を友達に再現してもらったりしていました。
そんな教育を、取り戻したいと思うのですが、みなさんはいかがでしょうか。
さて、今日は「ここだけのお話」を書いてみたいと思います。
謎解きのひとつの答えです。
あらざらむこの世のほかの思ひ出に
いまひとたびの 逢ふこともがな
歌の意味は、「私はもう長くはいきていない(在らざらん)ことでしょう。けれどこの世の最後の思い出に、今一度、あなたに逢いたい」というものです。
「逢」という字は、ただ会うのではなく、逢いたい、抱かれたいという意味が込められます。
「では、和泉式部が最後に逢いたいと思ったそのお相手は、
はたして、
最初の夫の橘道貞でしょうか。
為尊親王殿下でしょうか。
それとも
弟君の敦道親王殿下でしょうか。
はたまた最後の夫である
藤原保昌でしょうか。」
というのが、実は私の講義などでは決まり文句(笑)で、そのお答えはこれまで示してきていません。
ずいぶんと長い前置きになってしまいましたが、私なりの答えを書いてみたいと思います。
もちろん、その答えが「正しい」ものであるかどうかは、わかりません。
どこまでも答えは、和泉式部の心の中です。みなさまが、どのように思われるかは、それぞれ自由です。
さて、その解答ですが、私はやはり歌の中にその解答を見出すべきであろうと思います。
もういちど歌をよく見てみます。
あらざらむ
(私はもうこの世に居ないでしょう)
この世のほかの
(つまり「あの世」での)
おもひでに
(想い出の人に)
いまひとたびの
(もういちど)
逢ふこともがな
(逢えるといいなあ)
このように読むことができます。
最後にある「もがな」は、願望を表す終助詞で、「・・・になればいいなあ」といった感覚を表す言葉です。
自分の死を目前にした和泉式部が、死ぬ前に逢いたいと詠んでいるのではなくて、実は、死んだ後に、あの世で誰かに「もう一度逢いたいなあ」と詠んでいるわけです。
あの世での再会ですから、そのお相手は、和泉式部よりも先にお亡くなりになっている方であろうと思います。
ということは、和泉式部があの世で逢いたいと詠んでいるお相手は、為尊親王か、弟君の敦道親王のどちらかです。
もちろん、「あの世に行く前に思い出の人に」と解釈することもできます。
そうなると、最初の夫の橘道貞か、最後の夫の藤原保昌、あるいはもっと別な男性(たとえば性空上人など)ということになります。
しかしその解釈は、私は「ない」と思います。
なぜなら、和泉式部が生きた時代には、「肉体には魂が宿る」ということがあたりまえの常識だったからです。。
ですから和泉式部も、死ねば自分も肉体を離れて、もとの魂に戻ると考えていたであろうということは容易に想像がつきます。
そして人の死に際しては、お迎えがあります。
仏教では、そのお迎えは、阿弥陀如来様であったり、大日如来様、あるいは仏様であったりするわけですが、それだけではなく、先にあの世に行っている祖父母や両親、あるいは男性の場合であれば、先に逝っている戦友だったりもするわけです。
魂の永遠を信じる和泉式部は、だから「大好きだった、想い出のあの人に、あの世で逢えたらいいなあ、きっと逢えるよね?」と詠んだと考えられるのです。
そこには同時に、
「逢えたらどうしよう。あの人は若いままなのに私はこんなに歳を重ねてしまった。」
という女性らしい葛藤もあったかもしれません。
けれど、死んで御霊となった和泉式部は、その瞬間に、もとの若くて美しいお姿です。
そして思うのですが、和泉式部の御霊が、いよいよ肉体を離れたとき、きっとそこには、為尊親王殿下と、弟君の敦道親王殿下のお二人が、ニッコリ微笑みながら、和泉式部をお迎えに来ていたのではないでしょうか。
「よく頑張ってきたね」と微笑む為尊親王。
「兄貴、式部、よかったね」と二人を祝す敦道親王。
そのとき和泉式部は涙でいっぱいになって、もうお二人のお姿が、まぶししすぎて、きっと何もみえなくなっていたことでしょう。
その感動の中、
「お母さん」と呼ぶ声がします。
実は、和泉式部は、たいせつな娘の小式部内侍を、先に失っています。優秀であるがゆえに、周囲からイジメられ傷つけられた娘は、母より先に旅立っていたのです。
和泉式部は、その娘(小式部内侍)を失ったときにも、まさに悲嘆としか言いようのない悲しみの歌を数多く残しています。
ですから和泉式部の御霊が肉体を離れたとき、その場には、きっと娘の内侍も来ていたことと思います。
二人の殿下との再会し、愛する娘との再会を果たした和泉式部。
今度こそ、絶対に幸せを手放さないでね、と祈るような気持ちにさせられます。
和泉式部の歌は、どの歌も、まるで空中を落下する水滴を、落下の途中でピタリと停めてしまうような鋭敏な美にあふれています。
個人的には、おそらく和泉式部は、日本の歴史が生んだ、最高の女流歌人のひとりと断言できるほどと思います。
とびきり美人で優秀で才能にあふれ、それだけに感受性が人一倍鋭かった和泉式部は、その美しさと豊かな感受性の故に、素晴らしい出会いを経験しています。
けれど同時に、その愛を続けて二度も失い、さらに愛娘に先立たれるという悲しみを経験しています。
苦労が人の魂を育てるのです。
和泉式部は、女としての人生の悲しみの連鎖の中で魂を研いだのです。
だからこそ和泉式部の歌は、千年の時を超えて褪せない虹彩(こうさい)を放つのです。
逆にいえば、和泉式部の御霊は、そんな苦労の連続の中で、歌の才能を限界まで引き出すという苦難の道を、意図して選んでこの世に生まれてきたのかもしれません。
そして為尊親王殿下の御霊は、そんな和泉式部の御霊の持つ願いを叶えるために、敢えて先立つという選択をしてお生まれになられて来られたのかもしれません。
また敦道親王は、最愛の人を失うという死ぬより辛い目に遭った和泉式部の心が壊れてしまわないように、生前にしっかりと支えるためにと、生まれて来た御霊だったのかもしれません。
そして小式部内侍は、母より先に旅立ちましたが、母の歌への想いを受け継ぎ、次の人生で、思う存分、歌人としての才能を開花させる、そんな選択をしたのかもしれません。
実際のことはわかりませんが、私には、小式部内侍の歌風は、江戸時代の俳人の加賀の千代女の歌風と重なって見えるのです。
男性の私としては、不器用ながら和泉式部を最後まで愛し続け、まもりとおそうとした最後の夫の藤原保昌と「逢いたい」と言ってもらいたかったという気持ちがあります。
けれど保昌は、妻の求める幸せの半分も満たすことはできなかったかもしれないけれど、彼は式部との間に、男子を得ることができました。
だから彼はそれで良いとしなければならなかったのかもしれません。
ここまで書いたときに、日頃お世話になっている安田先生から、次のご指摘をいただきました。
「最愛の人の子を生むのではなく、
最初と最後の夫となってくれた人の子を授かる。
これも神のお計らい=神意でしょう。
神仏はちゃんと彼らにも救いをもたらしたのですね。」
さきほど「苦労が人を育てる」と書きました。
けれど、すこち違うかもしれません。
むしろ、
「苦労が『魂』を育てる」のです。
『古事記』の大国主神話は、どんな苦労があっても、愛する者のために戦うとき、必ずそこに道が開けると教えてくれます。
しかし和泉式部は、とびきりの美人で才能あふれる女性として生まれ、愛する人に身も心も捧げながら、その愛する人を幾人も失うという悲しみの人生を歩みました。
しかしそうすることによって、彼女は魂を研(と)ぎ、千年経っても色褪せずに私達の胸を打つ歌をのこしました。
そしてその歌が、なぜ私達の心をうつのかといえば、彼女の歌が、ただ肉体の持つ「心の歌」の域を越えて、「魂の歌」にまで昇華しているからではないでしょうか。
だからこそ藤原定家は百人一首の編纂に際して、「あらざらむこの世のほかの思ひ出に」と詠んだ和泉式部の最期の歌をこそ、百人一首に収蔵したのではないでしょうか。
百人一首に登場する百人の歌人のなかで「誰か一人好きな歌人は?」と聞かれたら、迷わずいの一番にお答えするのが和泉式部(いずみしきぶ)です。
たぶん、同じ思いを持つ方は多いと思います。
そしておそらく古今の歴史上、最高の歌人といえば、和泉式部を置いて他にない。
そして、その泉式部が、なぜそれほどまでの和歌を詠むことができるようになったのかといえば、もちろん才能もあったでしょうけれど、それ以上に彼女が本当に苦労したから。
親も教育も人を育てるものですが、本当に人が育つのは、その人にとっての苦労です。
そして苦労を、ストレスとするのではなく、試練とすることで、人が苦労を乗り越えて成長の糧(かて)にしてきたのが日本の文化です。さらにいうと、そんな苦労を乗り越えた先に、さらにすべてを捨て去る。
何もかも失った先に、本当にたいせつなことに人は出会うことができると、そのように考えられてきたのです。
ここに、古くて長い歴史を持ち、ひとりひとりを大切にしてきた日本文化の根幹があります。
※この記事は2017年4月のねずブロ記事のリニューアルです。