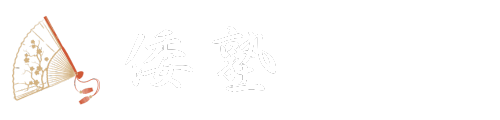忠臣蔵《赤穂浪士》といえば、主君である浅野内匠頭の仇を討たんと、赤穂藩を改易となった大石内蔵助以下47人の浪士たちが吉良上野介邸に討ち入りを行い、見事主君の仇討ちを成し遂げた物語として紹介されます。
しかしその討ち入りの理由が、
「吉良の老人にイジメを受けた若殿様が江戸城内でブチ切れて刃傷沙汰に及び、そのためその日の内に切腹を申し付けられたからだ」というのでは、これはあり得ないことです。
なぜなら、少々年寄りに嫌味を受けたからといって、それで切れるような軟弱な殿様であるのなら、むしろ家臣の側が主君を座敷牢に押し込めて、訓戒を与えるのが当時の常識です。
それが中途半端に終わり、結果として主君が禁とされている殿中で刃傷沙汰に及んで死罪となったというのなら、むしろ家臣たちは、そのような殿様を放置しておいた罪によって、素直に禄を捨て、赤穂藩が断絶となれば、それを謙虚に受け止めて、次の仕官先(就職先)では心を入れ替えて忠君に務めるべきというのが当時にあっての常識であったのです。
まして赤穂藩といえば、『中朝事実』を著した山鹿素行を、藩の教授として家老待遇で召し抱えたほど、学問に力を入れた藩でもあります。
さらに私達が今も使う円周率(3.14)を決めたのも、赤穂藩です。
このときの和算の大家(たいか)が家臣の村松茂清で、その息子の村松喜兵衛と、孫の三太夫は、親子で討ち入りに参加しています。
要するに知的なのです。
ちなみに当時の武士においては、単に勉強ができるというだけでは、知性があるとは認められません。
文武両道に秀で、学問を実生活に活かすことができなければ、一人前の武士とはされません。
ですからどのような大学者であっても、暴漢に襲われて刀も抜かずに斬られれば、武士にあるまじき腰抜けとして、生きていても死んでいても、禄を取り上げられました。
一方、松の廊下での刃傷沙汰は殿中の出来事です。
この場合は、殿中で刃を抜くことが固く禁じられていましたから、抜いた側が死罪です。
斬られながらも抜かなかったならば、それは武士として勇敢な振る舞いということになります。
当時の将軍が綱吉なのです。
綱吉将軍が出した生類憐れみの令は、お犬様さえも斬ってはならない、まして人を斬るなどもってのほか、というものです。
こうすることで、武士は帯刀し、斬捨御免が許されるけれど、人を斬ったら、自らも腹を切る文化が成立したのです。
その覚悟あって、はじめて人の上に立つ武士となりうる。
ある意味、当然のことと思います。
なぜなら、昨今の国会を見ると、どうみても自己の利益のためにというだけで、民を守ることへの命がけの覚悟が見られない。
国政を委ねるということは、ある意味、私達が命を委ねるということです。
果たして現在の政治体制が、これで良いのかと、ここは真剣に考えなければならないところです。
横田さんがおなくなりになりましたが、拉致から43年、北に乗り込んで拉致被害者を救出してきたのは、女性の中山恭子参議院議員ひとりだけです。
男に武士はいないのか、と忸怩たる思いになります。
人命が尊重された綱吉の治世にあって、主君が殿中で刃傷沙汰を起こしたわけです。
禁を破ったのですから切腹は当然ですし、赤穂藩のお取り潰しもやむを得ないことです。
ここの説明がうまくつかないものだから、吉良上野介義央(きらこうづけのすけよしひさ)のイジメがどれだけ激しいものであったのか、許せないものであったのか、そして上野介の人柄がどれだけ悪いものであったのかなどが、舞台や映画、小説などでは、さんざんに描かれています。
しかし、どれだけ描いたとしても、根本的に解釈に無理があります。
そもそも吉良上野介は、三河の吉良藩の藩主であり、地元においてもたいへんに立派なお殿様として慕われた人物です。
また吉良家は、室町幕府の足利家の親戚という高い家柄で、その当主である上野介もたいへん尊敬される立派な人であったから、息子は上杉家に養子に出て上杉藩の殿様になったし、娘は薩摩藩の島津綱貴の妻や津軽藩主の正妻、貴族の大炊御門家に嫁いで、その子は中御門天皇(114代)、桜町天皇(115代)、桃園天皇(116代)の三朝に亘って仕え、正二位・内大臣に進んだ大炊御門経秀(おほいのみかとつねひで)です。
また『徳川実紀』には、吉良上野介について、
「世に伝ふる所は、吉良上野介義央歴朝当職にありて、
積年朝儀にあづかるにより、
公武の礼節典故を熟知精練すること、
当時その右に出るものなし」
とあります。
人格識見家柄とも、申し分のない偉大な人物であったわけです。
それだけの人格者であり見識もあるからこそ、毎年行われる勅使下向の接待役を上野介は仰せつかっているわけです。
けれど、そこには大金がかかる。
だから、多少なりとも経済的に余裕のある諸藩が、吉良上野介の指導を受けながら、接待役を仰せつかります。
つまり吉良上野介と浅野内匠頭は、勅使下向の接待役としては、師匠と弟子の関係にあったわけで、この場合、弟子が師匠の指導が厳しいと、逆恨みするようなことは絶対にあってはならないのが当時の常識です。
その禁を破って師匠に刃を向けたというのなら、それは狂人の仕業と見られるべきものであるわけです。
ですから幕府は最初、浅野内匠頭を狂人として扱おうとしました。
狂人であれば、素行に問題があったとしても、それは心神喪失した狂人の所業ですから、処罰の対象にはなりません。
この場合は、浅野内匠頭は蟄居を命ぜられ、播州浅野家は、四代目当主として、他の誰かを立てればそれで一件落着となります。
当然、赤穂藩のお取り潰しもなく、家臣の身分も安泰です。
ところが浅野内匠頭は、狂人として扱われることを意図して拒否しています。
それは何故なのだろうか、ということです。
つまり浅野内匠頭には、自身の行為について、何の反省もないのです。
しかも殿中での刃傷において、浅野内匠頭は、吉良上野介の額(ひたい)に少々の傷を負わせるだけにとどめています。
殺意がないのです。
もし殺意をもって短い脇差で相手の命を奪おうとするなら、肋骨の間に刃を横にして心の臓を貫くか、あるいは無防備な首を狙います。
相手を傷付けるなら、太ももに刃を突き立てます。
額を斬って顔に傷を負わせるというのは、額が割れた場合、傷口は大量の出血を伴いますが、すぐに治る。
つまり、額を狙って傷を負わせたというのは、相手に対して殺意があるということではなくて、派手な流血と軽症によって相手に猛烈に反省を促すというものです。
このあたり、当時の武士の刃の使い方とその知識をバカにしたらいけません。
仮にも武士です。
刀をどうつかえば、どのような効果を生むかなどは、当時は研究しつくされていたし、それは武士の常識です。
つまり浅野内匠頭は、吉良上野介に何かの意思の変更を求めているのです。
このことは、当時江戸城内にいた、すべての武士たちには、即時理解できたことです。
訓練を受けた武士が刃を用いているのです。
素人が刃を用いるのではないのです。
要するに、これまで巷間言われてきた解釈には、いくつもの疑問点があるわけです。
疑問点があるということは、論理的整合性がないということです。
そして論理的整合性がなければ、ちゃんとした組織は動かないし、知性ある家臣たちを動かすことはできないのです。
つまり、これまでの解釈は、間違っているということです。
ただし、間違っているからといって、二者択一的な正邪で語るのは良くないことです。
そうした間違った解釈が普及された背景には、それをしなければならない、やはり論理的整合性のある理由があるからです。
このことは、もっとひらたく言うならば、意図的に間違った解釈が流布される背景には、必ず何らかの事情があるということを意味します。
ではなぜ赤穂浪士の討ち入りが行われたのか。
また浅野内匠頭は、なぜ吉良上野介の額(ひたい)に傷を負わせたのか。
その理由については、過去記事で何度も述べていることですので、ここでは、ひとこと、「播州赤穂藩が藩是としたことは、皇室尊崇にある」ということだけを述べさせていただきます。
詳しくは↓に述べていますのでご参照ください。
https://nezu3344.com/blog-entry-3958.html
大切なことは、「論理的整合性」を軸に、自分の頭で考える癖を付けるということです。
もちろん、自分では論理的と思っていたことが、実は情報不足のために論理的整合性が失われていたということもあるわけです。
これは勉強不足、知識不足に起因します。
いくら論理的に考えても、その思考のもとになる情報に不足があれば、論理的整合性はつかないからです。
もちろん、わからないことも、いくらでもあります。
けれど「わからないとわかる」こともまた大切なことだと思います。
「わからないとわかった」ら、その問題は頭の隅に、何年でも何十年でも置いておくのです。
すると、ある時点で一定の情報が揃ったとき、「そうか!」とわかる日が必ずやってきます。
なぜなら、知識や知恵というものは、神々が与えてくれるものだからです。
そして神々は、その人に必要なときに、必要な知識や知恵を授けてくださるものだと思っています。
誰に接するか、誰の教えを受け入れるかさえも、おそらくは神々のなせる技だと思います。
そのために必要なことは、日頃から勉強をして、心を素直にし、中今(なかいま)を大切にすることだと思います。
※この記事は2020年6月のねずブロ記事の再掲です。