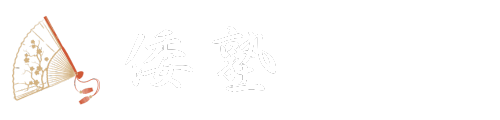百人一首の19番に、伊勢の和歌があります。
意味がわかると、ものすごく深い和歌なので、何度でもご紹介したいと思います。
難波潟 短き蘆の ふしの間も
逢はでこの世を過ぐしてよとや
(なにはかたみしかきあしのふしのまもあはてこのよをすくしてよとや)
ねず式で現代語に訳すと、次のようになります。
「大阪湾の干潟にある蘆(あし)の茎の
節と節の間くらいの短い時間さえ
逢わないでこの世を過ごすことなんて
できないとおっしゃったのは
あなたですよ」
なにやらちょっと攻撃的なような感じもしますが、一般な解釈は、
「難波潟に生える蘆の節と節の間のように
短い時間でさえも、あなたにお逢いできずに
この世を過ごせというのでしょうか」
(東京書籍・図説国語、冒頭の図)というものです。
これですと、まるで女性の伊勢が、あたかも上目遣いで男性に媚びているような解釈になります。
多くの解説書がこの解釈を取っています。
けれど歌の背景をよくよく調べていくと、この歌の意味はまるで違うものだということがわかるのです。
伊勢は平安前期の女流歌人です。
そして、その後の平安中期を代表する和泉式部や紫式部、清少納言などの女流歌人たちに、たいへん大きな影響を与えた女性です。
伊勢がいたからその後の平安女流歌人たちの興隆があったといっても良いのです。
それほどまでに伊勢の存在は偉大だったのです。
伊勢が「上目遣いに男に媚びて」と、そのような解釈自体、本来成り立たないのです。
伊勢は従五位上・藤原継蔭(つぐかげ)の娘です。
父が伊勢守であったことから、伊勢と呼ばれるようになりました。
十代で優秀さが認められて、宇多天皇の中宮(ちゅうぐう、天皇の妻のこと)藤原温子(ふじわらのあつこ)のもとに仕えるようになりました。
その藤原温子は、時の権力者である藤原基経(ふじわらのもとつね)の長女です。
父の藤原基経は、我が国初の「関白」となった、たいへんな実力者です。
その娘の温子の弟が、貴公子でありイケメンの藤原仲平(ふじわらのなかひら)です。
温子と仲平は仲の良い姉弟だったそうです。
仲平はよく姉の温子のもとに出入りしていました。
そして仲平は、姉のもとで働く同じ年頃の伊勢をみそめるのです。
互いに十代の、イケメン男子に、美人で才女の伊勢です。
二人は大熱愛におちいりました。
十代の恋、しかも互いに初めての相手です。
どれだけ熱く燃えたことか。
「もう蘆の茎の節と節の間のような短い時間さえ
お前なしで生きていくことなんて考えられないよ」
「うれしいわ。ずっと愛してくださいませ」
ところがその仲平が、熱愛のさなかに、別な女性と結婚してしまうのです。
この時代、何より重要視されたのが、家の存続です。
そもそも給料の概念さえも、いまとまったく違います。
現代日本では給料は働く人、個人に支払われますが、我が国では、ほんの少し前まで、給料は家(世帯)に支払われるものだったのです。
もちろん平安時代も同じです。
ですから偉い人であればあるほど、何より家を維持することが求められました。
時の最高権力者であった父の藤原基経からしてみれば、次男とはいえ、たかが国司ふぜいの娘を嫁にするわけにはいかないのです。
しかるべき身分の女性を妻に迎えなければ、家格の釣り合いが取れない。
この「家格の釣り合い」についても、すこし説明が必要です。
給料(所得)が家に払われるということは、家の財務の管理は、すべて嫁の管理になります。
嫁になった女性が、夫の稼ぎの全部の管理をするのです。
そして我が国は、権限と責任は常にセットにしてきた国柄を持ちます。
嫁が家計全部の管理を行うということは、万一、その嫁に不実があった場合、嫁の実家がその全責任を負います。
財産管理の一切を委ねるのですから、その保証が必要なことはいうまでもありません。
ですから、嫁となる女性は、その後見人となる実家が、主家の家計に万一のことがあったときに、これを保証できるだけの財力が求められたのです。
だから「家格の釣り合い」が必要だったのです。
この制度は明治の中頃まで続きました。
ですから基本的に結婚は見合いでしたし、どちらかというと嫁の実家の方が旦那の実家よりも家格が上という選択が行われていました。
現代でも、当人同士の恋愛結婚でありながら、実際の結婚式では「両家のご結婚」という言い方がされるのは、こうして千年以上続いた我が国の習慣に基づきます。
さて、十代の仲平には、最高権力者である父の命令を拒むことはできません。
仲平は、伊勢との大熱愛のさなかに、高い身分の家柄の善子(よしこ)と結婚するのです。
これは家を考えればいたしかたないことです。
しかし、まだ若い女性であった伊勢にしてみれば、これは大ショックです。
この頃の伊勢は、まだ十代の後半です。
十代の女性の熱い思いは一途です。
けれどその相手の男性が別な女性と結婚してしまったのです。
傷心の伊勢は、その頃父が大和に国司として赴任していたので、中宮温子におひまをいただいて、都を捨てて父のいる大和に去りました。
その大和で伊勢が詠んだ歌があります。
忘れなむ世にもこしぢの帰山
いつはた人に逢はむとすらむ
現代語訳すると
「もう忘れてしまおう。
あの人とのことは、もう峠を越えたのだから・・・」
となります。
伊勢の悲しい気持ちが、そのまま伝わってきます。
けれどもあまりに優秀な女官である伊勢を、世間は放ってはおけません。
一年ほど経ったある日、中宮温子から伊勢のもとに、
「再び都に戻って出仕するように」
とお呼びがかかるのです。
中宮温子は、ほんとうにやさしい、思いやりのある女性です。
弟の仲平と伊勢のこともちゃんと知っています。
それでも、
「あなたのように才能のある女性が、
大和などでくすぶっていてはいけません。
もう一度私のところに出仕しなさい。
あなたはもっとずっと活躍できる女性です」
と宮中に呼んでくださったのです。
中宮からの直接のお声掛かりとなれば、伊勢に断ることはできません。
伊勢は、再び都に戻って温子のもとに出仕しました。
もともと頭もいいし美人だし気立てもよい、才色兼備の女性です。
都にあって伊勢は、各種の歌会でもひっぱりだこになるし、頼まれて屏風歌(びょうぶうた)を書いたりもしています。
要するに宮中にあって、とても輝く存在となるのです。
こうして十数年が過ぎました。
ある日、宇多天皇が伊勢に、伊勢の家で見事に咲いていると評判の、女郎花(をみなえし)の献上を命じました。
それを知った仲平が、伊勢に歌を贈りました。
その歌は、
「一度お会いしませんか?」
というものでした。
このとき仲平は、すでに左大臣になっています。
左大臣というのは、天皇側近の朝廷内で太政大臣に次ぐ位(くらい)です。
いまで言ったら、総理大臣か副総理くらいの役職です。
家柄の良い仲平は、強大な権力を手にした男になっていたのです。
そんな強大な権力者である左大臣の仲平が「お会いしませんか?」といえば、それはお伺いにはなりません。
権力の強大さを考えたら、これは命令に等しいものです。
和歌には和歌でお返しするのが礼儀です。
伊勢は仲平に歌を送りました。
をみなへし 折りも折らずも いにしへを
さらにかくべき ものならなくに
現代語にすると、
「女郎花(おみなえし)の花は、
折っても折らなくても、
昔のことを思い出させる花ではありませんわ。
私は今更あなたのことを心にかけてなどいないし、
これを機会に昔を懐かしむ気持ちもありません」
キッパリしたものです。
相手がどのような政治権力者であっても、あたしはもう逢わないと決めたのです。
二人は別々の人生を歩くと決めたのだから、あたしには、あなたがどんなに昔を懐かしく思おうと、私にその気はまったくありません、というわけです。
男性の筆者には、仲平の気持ちがわかる気がします。
仲平の人生は順風満帆を絵に描いたような人生です。
15歳で元服していますが、このときの加冠は、宇多天皇が直々に行ってくれています。
19歳で昇殿して殿上人となり、後に左大臣にまで昇格しているのです。
大手一部上場企業に例えれば、最初から出世コースで58歳で専務取締役になったようなものです。
けれどそんな仲平にとって、『五番街のマリーへ』の歌詞じゃないけれど、若い頃に真剣に愛した伊勢に「悲しい思いをさせた、それだけが気がかり」です。
男の愛は責任です。
なんとかして伊勢を幸せにしてあげたい。
そしていまの俺には力がある。財力も権力もある。
伊勢の幸せを実現できる実力がある。
だから変な欲望ではなく、ただ会って、食事でもして、あのこぼれ落ちるような笑顔を見せてもらって、彼女に何か望みがあるのなら、どんなことでもかなえてあげたい。
「おまえを真剣に愛したひとりの男として、
おまえへの愛の責任をまっとうしたい」
それはひとりの女性を心から愛した「男の想い」であり、男の「愛」です。
けれど伊勢は女性です。
赤の他人、別な人、異なる人生、関係ない他人と、もう決めたのです。
そして、このときに伊勢が詠んだのが、冒頭の和歌です。
この和歌には、伊勢集に、詞書(ことばがき)があります。
次のように書かれています。
「秋の頃うたて人の物言ひけるに」
「秋の頃」というのは、まさに女郎花(おみなえし)の花が咲く頃です。
「うたて人」というのは、嫌な奴とか、大嫌いな奴、気味の悪い奴、不愉快な奴といった意味の言葉です。
伊勢は、強大な権力者の左大臣仲平を、「ただの嫌な奴」と書いているのです。
そしてその詞書に続く歌が冒頭の、
難波潟 短き蘆の ふしの間も
逢はでこの世を 過ぐしてよとや
です。
「遠い昔、
難波の干潟にある葦にある節と節の間くらいの短い時間さえも
おまえと逢わずにいられようか。
お前と俺はずっと一緒だよと、
おっしゃられたのは、あなたでしたわね」
要するに伊勢は、自分を裏切った(と感じた)仲平が、たとえ左大臣という政治上の要職者にまで出世し、巨大な権力と財力を得るようになったとしても、あたしはあなたを許していませんわ、と詠んでいるのです。
でも本当にそうなのでしょうか。
あれほど愛した仲平を、伊勢は、ただ許せない、嫌いだと、それだけなのでしょうか。
ここからが大事なところです。
仲平には「をみなへし折りも折らずもいにしへを・・」と和歌で返事を書いているのです。
にもかかわらず、わざわざ「うたて人(嫌な奴)の物言ひけるに」とこの歌を残したのは、
「揺れる想いに自分なりのけじめをつけようとした」のではないでしょうか。
というわけで、この和歌の勉強会をしたとき、参加いただいた女性陣に、伊勢の思いを聞いてみました。
「男だけじゃないわ。女だって引きずるわ」
「女としてというより、人としてのプライドの問題じゃない?」
「もしかすると伊勢は、仲平の気持ちを試したかったのかも」
「でも、別れたのにまた言いよってくる男って軽すぎない?」
「伊勢は人として成長したんじゃないかな。別れはつらいけどさ、心に区切りをつけたんじゃないかしら」
「それって、あんときの私じゃないわよ!ってこと?」
「そうそう(笑)」
「でもさあ、そこまで人を好きになれるって、うらやましいわぁ」・・・・
ものすごい盛り上がりになりました。
さて、伊勢の人生です。
温子のもとで働いていた伊勢は、宇多天皇の寵を得て、皇子の行明親王を産み、伊勢の御息所(みやすどころ)と呼ばれるようになりました。
御息所と呼ばれるのは、宇多天皇にとって、数ある妻(当時は一夫多妻制です)の中で、伊勢のもとが一番くつろくという意味です。
ところがせっかく授かった皇子は、五歳(八歳とする説あり)で夭折(ようせい)してしまいます。
悲しんだ宇多天皇は皇位を譲位され、落飾して出家されてしまわれました。
このことの持つ意味も重要です。
宇多天皇は、それほどまでに伊勢を愛したということだからです。
そして伊勢がお世話になった中宮温子も薨去(こうきょ)されました。
憂いに沈む伊勢は、この頃三〇歳を過ぎていたけれど、宇多院(もとの宇多天皇)の第四皇子である敦慶親王(25歳)から求婚され、結ばれて女児・中務(なかつかさ)を生んでいます。
中務は、立派な女流歌人として、生涯をまっとうします。
伊勢の歌は、古今集に23首、後撰集に72首、拾遺集に25首が入集し、勅撰入集歌は合計185首に及びます。
これは歴代女流歌人中、最多です。
そして伊勢の家集の『伊勢集』にある物語風の自伝は、後の『和泉式部日記』などに強い影響を与え、また伊勢の活躍とその歌は、後年の中世女流歌人たちに、ものすごく大きな影響を与えました。
百人一首で、伊勢の歌の前後を見ますと、
17番 在原業平(輝かしい王朝文化)ちはやぶる神代も聞かず竜田川
18番 藤原敏行(身分差と恋の葛藤)住の江の岸に寄る波よるさへや
19番 伊勢 (・・・・) 難波潟短き蘆のふしの間も
20番 元良親王(心と権力の葛藤) わびぬれば今はたおなじ難波なる
21番 素性法師(兵士に捧げる祈り)今来むといひしばかりに長月の
という流れの中に、伊勢の歌が配置されています。
伊勢のところの(・・・・)には、どのような言葉が入るでしょうか。
筆者はここに「権力の世から祈りの世へ」という言葉を入れたいと思います。
伊勢はもともとは、関白藤原基経、左大臣仲平らといった政治権力の中枢にいた女性です。
けれど仲平との別れを経て、祈りの世界の住人である宇多天皇やその子の敦慶親王と結ばれて子をなしています。
このことは伊勢が、「権力の世」から「祈りの世」へと、生きる世界を昇華させていったことを示しています。
そしてその伊勢の心の成長を、百人一首の選者の藤原定家は、国家統治を権力ではなく、祈りの世界において神々と接触される天皇をこそ国家の頂点とあおぐ形(これを古語でシラス(知らす、Shirasu)と言います)へと昇華させ、完成させていった日本の統治の形に重ねたのだと思います。
いまも天皇は国民の安寧を日々祈られる「祈りの御存在」であられます。
伊勢の和歌は、我が国が天皇のシラス国であり、天皇のもとに老若男女を問わず、すべての人が「おほみたから」とされてきたことを象徴する歌といえるのです。
このことは、言い換えれば伊勢の歌は、究極の民主主義を謳歌する歌だということです。
そして伊勢の歌は、同時に
「哀しいまでの女性の勁(つよ)さ」をあらわした歌でもあるのです。
学校で、百人一首を教えるときに、せっかくこれだけの意味のある和歌なのに、これを単に
「上目遣いで男性に媚びた和歌だ」とか、「男性への恨みの歌だ」と教えるのはいかがなものでしょうか。
百人一首が好きだという方はたくさんいます。
けれど、せっかくの素晴らしい歌の数々が、誤った解釈(誤ったで語弊があるなら、上辺だけの軽い解釈)で歌の意味が損ねられてしまっては、和歌を学ぶ意味がないのでは、と思います。
日本の教育が貶められているのは、歴史だけではありません。
国文学も、地理も、国語も、文系分野は、さまざまなところで日本を貶め、子どもたちが日本を嫌いになるような仕掛けがされています。
そうした反日教育が改められ、誰もが日本に生まれ、日本人として生きることができることに感謝の気持ちを持てるようになる。
そういう教育を取り戻すのは、私たち民衆の目覚めです。
最後にひとこと。
さまざまな和歌の新解釈を披露させていただいていますが、これはこれまでの様々な先生方のご研究を否定するものではありません。
むしろ、これまでの様々なご研究の成果があったからこそ、新たな考察に手が届くようになったのです。
学問は、常に上書きされるもの。
その意味で、先輩諸氏のこれまでの研究に心から感謝をしています。
※この記事は、拙著『ねずさんの日本の心で読み解く百人一首』の文を大幅に加筆したものです。
日本をかっこよく!