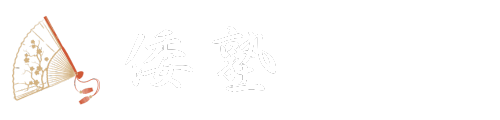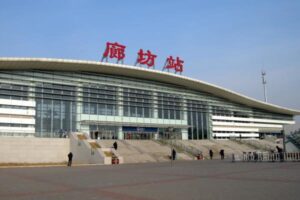日清戦争(明治27(1894)年8月~明治28(1895)年3月)のお話を書いてみようと思います。
日清戦争が起きた時代というのは、我が国において、
大日本帝国憲法が発布(明治22、以下同じ)され、
東海道本線が全線開通し、
パリで万博が開催され、
そのパリにエッフェル塔が建設されて、
日本ではいまはファミコンシリーズで名を馳せている任天堂が創業され、
少し前の明治23年には教育勅語が発布され、
前の年の明治26年には御木本幸吉が真珠の養殖に成功した、
そんな時代です。
要するに、我が国は明治の開花以降、急速に近代化が進み、欧米列強と肩を並べる実力を身に付けつつあった時代であったわけです。
この当時でも、おそらくは精神文化という面では、我が国の治安の良さや国民の文盲率の低さ、あるいは民度の高さといった点においては、決して欧米にひけはとらなかったものと思います。
けれど、日本と欧米では、武力が違う。経済力が違う。
力の差が圧倒的だったのです。
欧米諸国の東亜進出は、いわば西欧文明による東亜文明への挑戦です。
この挑戦に対して、東洋的中世体制では勝てない。国として生き残れない。
そのことは、清国の阿片戦争が、如実に証明していました。
大軍を要する清国でさえ、英国のほんの少数の海軍の前に、まるで歯がたたずに蹂躙されているのです(*1)。
(*1)このことを考えると、秀吉の明国出兵の理由も明確になります。当時マニラにあるスペイン総督府は、明国と日本を植民地支配しようと狙っていたし、そのままでは日本も植民地支配されてしまうという情況でした。幸い、日本には武士がいて、鉄砲の保有数も圧倒的であり、スペインに対して対等に物を言うことができるだけの力を備えることができましたが、明国は事大主義でそうではない。このまま明国がスペインの植民地になれば、スペインは圧倒的に数の多い明国兵を使って日本を支配しにやってくる。これを防ぐためには、日本が先に明国を支配下に置くしかない、という情況だったのです。ただ、実際に当時明国領だった朝鮮半島に上陸してみると、時を同じくしてスペインの無敵艦隊が英国に敗れたという情報が入ります。ということはスペインは国力を失う。だから当分様子見で、秀吉は博多から動かずに毎日宴会を催して遊んでいたわけです。
ならば、その挑戦に対して、むしろ積極的に西洋文明を取り入れ、これを我が国の血肉となし、国力を鍛え上げて欧米列強と「対等」に付き合えるだけの実力を持った日本になる。
これが日本の理想でしたし、幕末の志士たちが夢見た坂の上の雲であったのです。
「対等」という概念は、我が国においては、人々の価値観の根幹です。
「対等」も「平等」も、英語で書いたら同じ「イコール(Equal)」ですが、日本ではまったく別な概念として認識されます。
運動会の駆けっこで、順位をつけないで、全員並んで一等賞にするのが「平等」です。
俺は勉強の成績ではA君に勝てないけど、「運動会の駆けっこだったら俺が一等賞だい!」となるのが「対等」です。
「対等」は、相手の凄さをちゃんと認めたうえで、「その代わり俺にはこれが」とします。
自他の違いをちゃんと認識した上で、自己の存在の実現を図ろうとするのです。
「平等」は、ミソもクソも一緒ですから、「代わりに」という概念がありません。
近年、洋風にならって、男女平等論がかしましいです。
男女が「平等」というのなら、着替えも風呂も、男女とも同じ部屋、同じ風呂です。
すくなくとも、女性にそうしたことが歓迎されるとは思えません。
そもそも男には男の良さがあり、女には女の良さがあります。
男の良さと、女の良さを互いに認め合い、違いを認識し、男は男らしく、女は女らしく、互いに力を合わせて、未来を拓こうとするのが「対等」です。
最近の教育現場では、「平等」にこだわるあまり、彼我の違いをきちんと認識する「対等」という概念があまりに軽視されています。阿呆だ!と言わせていただきます。
幕末から明治にかけての志士たちが求め大切にしたのも、この「対等」です。
欧米列強の強さは認める。
彼我の実力にそれだけ大きな違いがあるなら、むしろ積極的に欧米の文物を学び努力して、欧米列強と「対等」に付き合える日本になろう。
それが、幕末の志士達の夢であったし、明治の政策の根幹でもあったし、日本人の対等意識の発露であったのです。
「対等」は、「追いつき追い越せ」ではありません。
あくまでも「対等」になることを望むものです。
いまも同じです。
日本車は欧米市場で人気ですが、日本のメーカーは、欧米のメーカーに「追いつき、追いつき」が基本戦略です。
決して「追いつき、追い越せ」ではありません。
彼らとどこまでも対等に付き合い、共存していく。
それが日本のメーカーの希望であり、姿勢です。
つまり「対等」というのは、彼我の違いを認めるだけでなく、実は、彼我の共存共栄を希望する概念です。
このあたりも「平等」とはまるで異なります。
「平等」は、「平等か不平等か」という対立概念しかありません。
ひらたくいえば、「◯◯ちゃんと一緒でなきゃヤダぁ」という幼児の我儘と同じものです。
一緒であることが認められなければ泣き叫ぶ。
プロ市民とか、モンスターペアレントといわれる人たちの言い分は、幼児の固執と同じです。
現実の世の中は「分布」です。
そのような人たちもいるから「対等な世の中」なのです。
全部が全部、同じ思考、同じ行動なら、それは全体主義であって、不自由で哀れな世の中です。
いろいろな人がいて、いろいろな考えが許容されているから、幸せだし、発展もあるのです。
幕末から明治の時代、強力な軍事力を持つ欧米列強諸国に対して、日本がどこまでも自国の正義だけを主張し、刀や槍や弓矢にかけて、戦うという選択をしたらどうなったでしょう。
実は、その選択をした民族があります。
北米のインデアンたちです。
その結果、彼らはどうなったでしょう。
北米大陸に800万人いたインデアンは、いまやたったの35万人です。
そして全員が白人との混血児です。
日本も、そうなる危険があったのです。
だからこそ、子を護り、妻を護り、老いた父母を護るために、日本は近代化を急速に進めたのです。
もちろん、これには功罪もあります。
全部が全部良くなったわけではない。
たとえば日本は、社会の規範者である武士の身分を廃止しました。
武士は「ならぬものはならぬ」という存在です。
けれど欧米型個人主義は、自由が大事とされます。
子どもには、親の言うことを聞かない自由があるというわけです。
馬鹿げた話です。
これは亡き加瀬英明先生からの受け売りですが、つい近年まで、日本では陛下が外国から国賓級の要人をおもてなしする晩餐会で、フランス料理を出していました。
世界中、どこにもそんな国はありません。
どの国でも、外国の賓客をおもてなしするときは、その国の最高級の伝統料理を出します。
お隣の韓国ですら韓国料理、中共も中華料理、アフリカの諸国でも、それは同じです。
けれど日本は、最高の日本料理でおもてなしするのではなくて、フランス料理です。
なぜフランス料理なのか。
それはひとつには、最高の日本料理というものが、実は生産地で生産者たちが食べる新鮮な魚介類や野菜類であったこと、日本のかつての貴族や武家では、何十万石という大大名のお殿様でさえ、ご飯に、味噌汁の他はおかずが一品だけ。それにおしんこが付いたら、それが最高の食事であったということがあります。
もともと日本社会では、生産者をたいせつにしたし、それをするのが武家や貴族の努めだと考えられていたし、石高の大小に限らずお殿様たちは、みんな貧乏で贅沢は禁じられていましたから、食事はそもそも粗末なものでした。
ウチも明治生まれの祖母が生きていた間は、食事は常に、ご飯と一汁一菜+おしんこだけでした。
それを正座し、背筋を伸ばしていただかなければ叱られました。
膝を崩して食べるのは、お百姓さんたちへの感謝の心が足りないからだ言われました。
食べるときに、ぺちゃくちゃしゃべるのも禁止でした。
おしゃべりやテレビに夢中になって箸がとまっていると、他の者が食べ終わったらさっさと食卓の上の料理を片付けられてしまいました。
逆に、食べ物を残すと、ご飯が傷んで糸をひくようになっても、それを全部食べ終わるまでは、次の食事を与えてもらえませんでした。
厳しいと思われるかもしれませんが、いま振り返ってみると、そのおかげで今でも、食事が、どんなものでもおいしくいただけます。
これはとても幸せなことだと思います。
食べる時間も、できるだけ短く、3分で食べ終えろと、これは父の教えでした。
江戸の昔では、食事の配膳は下女たちの仕事でした。
主人たち家族の食事が済まないと、彼女たちが食事する時間が遅れてしまいます。
つまり下女たちに迷惑がかかるのです。
時代は変わっているし、下女なんてのもいない20世紀に、そんなことを言われてもと、子供心にずいぶんと反発したものですが、けれど、どんなときにも、自分以外の周囲の人達に配慮をするという心得を、他界した父は教えてくれていたのだと思います。
話が脱線しましたが、そんなわけで、町人料理や庶民料理、あるいは料亭などでは、それなりの高給料理もあったのですが、そもそもそういう贅沢は、武家は厳禁だったわけですから、その意味では、日本では、高級日本料理などというものは、そもそも町家の言葉は悪いですが、下賎な贅沢料理くらいにしか思われてなかったわけで、その意味では、国賓に下賎の料理を出すわけにもいかない。
そこで明治時代の頃、世界最高の最先端高級料理とされていたのがフランス料理だったために、我が国では、国賓をお迎えするときはフランス料理を出すようになったわけです。
そしてここにも、欧米の実力を我が国の文化になんとかして取り入れようとする涙ぐましい努力があったわけです。
ちなみに加瀬先生の友人のフランス公使は、日本に赴任することが決まったときに、「皇居の晩餐会に招かれているので、きっと最高の日本料理を食べられるに違いない」とワクワクしながら来日したのだそうです。
ところがいざ晩餐会に招かれてみると、期待に反してでてきたのは自国の料理であった。
いまは世界中で日本食ブーム、世界最高の日本食が食べられると思って楽しみにしていたのにと、たいへん残念がっておいでだったそうです。
フランス料理がいいのか悪いのか、そういう議論はまた別として、ただ、明治時代に欧米に「対等な国」と認めてもらうために、我が国がそういう小さなことにまでこだわって、真剣に国を、私たち民衆を護ろうとしてくださっていた。
そのことに、わたしたちは感謝をすべきと思います。
もうひとつ我が国の近代化に、大きなファクターがあります。
すでにご案内の通り、明治政府はできた当時は、まるで貧乏所帯でした。
なにせ日本国内の金(gold)が米国に大量に流出していたのです。
明治政府は、政府のお役人の給料の支払にさえ困り、そのために苦肉の策として行われたのが、陰暦を太陽暦に変更するというものでした。
陰暦を太陽暦に変更すると、その年だけは、通常年よりも1ヶ月、一年が短くなるのです。
年間の人件費が、1ヶ月分浮く。政府の人件費ともなれば、これは大金です。
そんなことまでしなければならないほど、お金がなかった明治政府が、明治の中頃には、一定の経済力を身に付けています。
なぜそれができたのかといえば、政府の財政出動を積極的に行ったことによります。
ご存知の通り、日本国内のお金は、日本国政府の印刷した紙幣が使われます。
政府は、その紙幣をたくさん刷ることによって、国内に流通するお金の量を増やしたのです。
そしてそのお金をつかって、明治政府は各種インフラを整備しました。
その代表が、東海道本線の開通でもあったわけです。
紙幣を印刷し、公共事業を興して国内の雇用を創出し、国内経済の活性化を図る。
日本は、維新後、わずか20年少々で、世界の5大経済大国の仲間入りしています。
その伝統が、いまでもG5となっているわけです。
政府が財政投資を行う。
政府が積極的に様々な規制を設けて、各種産業を保護する。
これによって民間投資が活発化する。
民間需要が高まり、消費が拡大する。
景気が良くなる。
人々の生活が豊かになる。
これが明治時代の構造であり、昭和の戦後の日本の経済成長のカラクリでした。
だから日本は、明治時代においても、昭和の戦後においても、あっという間に経済力をつけ、国力を高めています。
この真逆をしているのが、バブル崩壊後の日本です。
景気後退がずっと言われ続けていますが、景気後退も好景気も、なるべくしてなる、起こるべくして起こるのです。
政府の財政投資を縮小する。
政府が規制を緩和して、各種産業をより厳しい競争に晒す。
安ければ良いという風潮が起こり、民間は儲からないから投資を縮小する。
民需が減り、消費が冷え込む。
景気がますます悪化する。
人々の生活が、一層貧しくなる。
歴史を直視すれば、いまの日本が何をすべきなのか、一目瞭然です。
富国強兵。
これはいまの日本にこそ大事なことです。
要するに、こうして明治日本は、真剣に欧米列強と対等な国になるために、必死の努力をしていたのです。
これに対し、まったく欧米列強と「対等」な関係など考えなかったのが、お隣のチャイナの清国であり、その清国の属国であった李氏朝鮮でした。
「対等」という概念は、相手の凄さをまず認めるところからはいります。
ところが中華思想というのは、常に「我こそ一番」です。
教条主義的に、最初にそれが来るから、相手を認めるということができない。
あるのは「どっちが上か」だけです。
そして世界の中心は中華にありとされています。
ですから、欧米列強に圧倒的な力があっても、それはただ頭ごなしに「受け入れない」だけです。
一方、李氏朝鮮はというと、これまたそのような清国政権の属国としての地位に甘んじていました。
この時代、つまり李氏朝鮮末期の国王が高宗です。
高宗は、色事好きで、政務をほったらかしで、もっぱら多数の宮女や妓生の漁色と酒におぼれているだけでした。
さらにチャイナや李氏朝鮮では、国務に関する政治的意思決定権の一切は、すべて国王ひとりにのみ存在しました。
ですから肝心のその国王が政務をほったらかして酒色に溺れていたら、国事行為の一切が前に進みません。
早い話が、李氏朝鮮の王宮が仕入れた野菜などの日々の食料品の代金の支払だって、国王の承認が必要です。
けれど、高宗王は、何もしない。
何もしないんじゃ困るから、そうした雑務や政治的意思決定を、正妻の閔妃(みんぴ)が取り仕切っていました。
ちなみにこの閔妃(みんぴ)のことを「明成皇后」などと言う人がいるけれど、この時代、皇帝はあくまでも清国皇帝であって、朝鮮は清国の属国です。
したがって朝鮮王は、あくまで清国皇帝の部下の「王」ですから、李氏朝鮮の国王の高宗は、「王」であって「皇帝」ではありません。
したがって、その高宗の正妻も、「王妃」であって「皇后」にはなり得ません。
もしこの時代に閔妃(みんぴ)が、私は「皇后よ」などと言い出せば、閔妃は、清国の官吏によって逮捕され、極めて残酷な方法をもって殺されたでしょうし、閔妃だけでなく、閔妃の一族郎党が、全員皆殺しにされていたことでしょう。
中華帝国は、そういう点は、とても厳しいのです。
では近年では、どうして明成皇后などと呼ぶのかといえば、答えは簡単です。
半島の人たちが、過去の歴史の事実から目をそむけ、歴史をファンタジー化しているからです。
もっとえいば、この閔妃、閔妃という名前さえ、実は伊藤博文が付けてあげた名前でしかありません。
当時の半島人女性は、国王の妻であり、皇太子の生みの親であっても、名前を名乗ることは赦されていません。
まして一般女性にいたってはなおのことで、名前はありません。
名前がないということは、人として扱われていなかったということです。
要するに、野良犬や野良猫と同じで、死んでも誰も振り向かない。
ただの粗大ゴミとして扱われるだけです。
生きていても、それはただ子を孕むための道具としてだけの存在であって、人間としての扱いは受けていません。
そういう意味で半島は、まさに「男尊女卑社会」であったし、それは今も続いています。
昨今、かつての日本社会のことを、それと同じように男尊女卑だとか言い出す馬鹿者が学者さんの中にもいますが、日本社会では、男女ともちゃんと名前があったし、だいたい結婚すれば、いまでこそ「夫婦(ふうふ)」というけれど、昔は「妻夫(めおと)」と呼びました。
それだけ女性が大事にされていたのが日本社会です。
だいたい、日本の最高神は、アマテラスオオミカミで、女性神です。
そして家庭においては、女性はカミさんで、まさに神様、絶対権力者です。
寺子屋のお師匠さんも、半数近くが女性教師です。
それでいて男尊女卑などと、とんでもないいいがかりです。
そもそも男尊女卑社会というのは、昔の半島のような社会を言うのです。
女性には、名前さえ与えられず、ただの子宮としてしかみなされない。
男尊女卑どころか、女性は人間としてさえ扱われていません。
そういう半島社会の中にあって、国王の妻であり、国母であり、しかも高宗王に変わって実質的な政治権限を揮う女性が、名前さえないのでは、たとえそれが半島社会の常識であったとしもて、あまりにも理不尽だし、不便です。
そこで、伊藤博文が、「あわれみの心をもったお妃(きさき)」という意味で付けてあげた名前が、閔妃(みんぴ)であったのです。
ところがこの閔妃、国王に代わって政治の実権を掌握すると、彼女の一族だけを積極的に重職に登用しました。
これは彼女の意思であったのか、あるいは政治権力を持った彼女の身内が、彼女に対して脅迫まがいに圧力をかけたのか、それはわかりません。
おそらくは後者であろうと思いますし、また閔妃自身、そうすることで自分の権力基盤を固めようという意思があったかもしれません。
その閔妃のもとには、清国が阿片戦争で大敗したこと、日本が明治維新をなしとげ、急速に国力を充実させてきていることなどの情報が寄せられています。
閔妃は、明治9(1876)年には、日本との間で、日朝修好条規(江華島条約)を締結しました。
そして閔妃は、日本に依頼して閔妃の王宮に、日本人の軍事顧問を招きました。
半島の軍隊の近代化を図ろうとしたのです。
閔妃の目にも、近代化した日本式の軍隊(新式軍隊)は、実に勇壮で頼もしい存在に思えたことでしょう。
ただ、そう思えただけなら良かったのですが、閔妃は、あまりに日本式軍隊が素晴らしいからと、従来からあった清国式の旧式軍隊をほったらかしにしてしまったのです。
「もういらない」というわけです。
そして旧軍隊の兵士たちへの給料も払わなくなり、食事の配給もしなくなってしまったのです。
日本式新式軍隊には、豊富な食料と給料が支給され、清式の旧軍隊には、飢えと苦しみが押し寄せる。
あたりまえのことですが、旧軍隊内には、新式軍隊に対する不満が募ります。
明治15(1882)年、旧式軍隊は、閔妃暗殺を目論んで反乱をおこします。
これが「壬午軍乱(じんごぐんらん)」です。
このとき、多くの閔妃派要人と数十名の日本人が殺されました。
日本の領事館も焼き討ちに遭っています。
このとき、事件を察知した閔妃は、侍女を身代わりにして、いち早く王宮を脱出しました。
閔妃の身代わりとなった侍女は、現場でとても口には出せないような卑劣で卑猥な拷問を受けて殺害されています。
そして逃げた閔妃は、当時半島に駐屯していた清の袁世凱(えんせいがい)のもとに逃げ込みました。
そしてこのとき閔妃が、清国の派遣軍側に逃げ込んだことが、問題をややこしくしました。
李氏朝鮮国内で反乱を起こしたのは、清の指導を受けている清式の旧半島軍です。
その旧半島軍が反乱を起こしたからといって、なんと閔妃は、その旧半島軍の指導部隊である清国軍に逃げ込んだのです。
いい度胸をしているといってしまえばそれまでですが、要するに閔妃は、清軍に反乱の鎮圧を委ねたわけです。
当然のことながら、閔妃を保護した清国軍は、閔妃に親日開化政策を取り下げさせ、親清の復古政策への転換を要求します。
閔妃も、これをのみます。
こうなるとやっかいなのが、日本の立場です。
閔妃の要求によって、李氏朝鮮に指導官を派遣し、新国軍を組織していたのです。
ところが、閔妃はあっさりと日本を切り捨て、もとのチャイナ冊封国に戻ってしまったのです。
しかも、新国軍襲撃の際、日本人も多数が殺されています。
そもそも日本は、国内の近代化のための手当が精一杯で、お隣の半島半島になんらかの責任を負っている立場でもありませんし、清国に手を出そうなどいうだいそれた欲望もまったく持ち合わせていません。
ただ、実際に満州あたりまで南下してきているロシアに対して、日本の安全のために警戒感を持ち、そのために清国も、朝鮮半島も「しっかりしてもらわなければ困る」と考えているだけです。
この時代、日本は日本列島が日本の領土であるという国家としての明確な領土観を持っています。
ところが李氏朝鮮は、領土意識は強いけれど、具体的にどこに国境があるのかといった、近代国家にある明解な線引きがあるわけでもありません。
ですからロシアが満州エリア(いまの東北省)あたりに南下してきても、そのどこまでが領土であり国境であるかという意識がありませんから、ほぼ、放置に近い状態です。
国境の曖昧なエリアや、王朝が弱化しているエリアは、欧米の帝国主義国家はこれを「無主地」と見ます。
領主がいない土地ですから、そういう土地は、そこに住む人民ごと、近代国家が面倒を見てやらなければならない・・・と、そう言いながら、勝手に領有し、そこを自国の植民地にしてしまうわけです。
そういう中世的国家と、欧米の帝国主義的近代国家との違いを明確に認識し、国を護るために具体的行動を起こして自国の近代化を図ったのが日本であり、それがまるで理解できずに、ただ尊大な中世を続けていたのが、当時の清国や朝鮮でした。
一方半島の民衆の暮らしはあいかわらず貧困のどん底です。
その隣には、どんどん近代化をすすめ、進歩し、国民が豊かになっていく日本がある。
福澤諭吉(慶応大学創始者)や、大隈重信(早稲田大学創始者)らとの親交を深めた半島の金玉均・朴泳孝・徐載弼ら、理想に燃える韓国人は、このままではいけないという思いを深くしました。
そして彼らは、閔氏一族が贅沢三昧をして国政を壟断する中、むしろ能はないけれど権威だけはある国王高宗を立てることで、国政を改善しようとしました。
国王の高宗も、この頃になると閔氏一族や清に実権を握られて、何一つ思い通りにいかないことが内心面白くない。
朝鮮国王高宗は、金玉均らの理想に燃えた近代化政策の実行を快諾します。
明治17(1884)年12月、金玉均らは、クーデターを起こしました。
「郵政局」の開庁祝賀パーティーの際、会場から少し離れたところで放火を行い、「すわっ火事だ!」会場が混乱する中、金玉均らは祝賀パーティ会場から逃げ出す閔妃一派の政府高官らを殺害し、一瞬にして閔妃一派を一掃しようと計画したのです。
ところがこの計画には、大きな穴が空いていました。
クーデターに成功しても、閔妃一派は、清国との関係が深く、その清国は袁世凱の軍隊を朝鮮半島内に駐屯させているのです。
つまり、そのままでは、清国の大軍が介入して、クーデターが鎮圧されます。
そもそも半島は清の属国なのです。
そこで金玉均らは、クーデターと同時に、朝鮮国王高宗を経由して、日本に半島の保護を依頼しようと計画します。
日本に軍を派遣してもらい、朝鮮国王を保護するとともに、開化派による新政権を発足させ、朝鮮国王をトップとする清国から独立した立憲君主制国家をうちたてる。
そうすることで、半島は、日本の助力のもとで近代国家への道を突き進もう、と計画したのです。
金玉均らは、計画を実行しました。
放火を実行しました。
放火したのは一カ所です。
ですから、火はすぐに消し止められてしまいました。
それでも金玉均らは、火事場から逃げ出そうとする閔泳翊ら閔氏一族の殺害は成功し、高宗王を打ち立てて、新政府樹立を宣言しました。
そして首謀者の金玉均は、首相にあたる「領議政」に大院君の親戚の一人の李載元を据え、副首相に朴泳孝、自らを大蔵大臣のポストに置くと表明し、その日のうちに、
(1) 朝鮮国王は今後殿下ではなく、皇帝陛下として独立国の君主とする。
(2) 清国に対して朝貢の礼を廃止する。
(3) 内閣を廃し、税制を改め、宦官の制を廃止する。
(4) 宮内省を新設して、王室内の行事に透明性を持たせる。
などと高らかに宣言しました。
もしこの新政権が、順調に滑り出していれば、その後の東亜の歴史は大きく変わっていたかもしれません。
ところが、このクーデターは袁世凱率いる清の大軍にによって、またたくまに崩壊するのです。
日本も、そもそも朝鮮半島に対する領土的野心などまったくありませんし、征韓論が起こったのも遥か昔のことで、この時代には西南戦争もとっくに鎮圧されています。
一方袁世凱は、クーデター派のたてこもる半島王宮に対して、堂々と攻撃を仕掛けています。
王宮に高宗王がいるのだから、そこは配慮して、まずは取り囲んで軍使を使わし、避難勧告を出し、なとという悠長なことはしません。
いきなり正規軍をもって、王宮を襲撃したのです。
これには、元の朝鮮旧国軍も、味方し、手引きしています。
圧倒的武力の前にクーデター派は壊滅し、からくも危機を脱した金玉均らは日本へ亡命しました。
ところが、こういうところが実に中世的国家らしいのだけれど、主犯の国外逃亡を知った袁世凱らは、金玉均らクーデター派の家族を三親等まで全員捕縛し、チャイナ・半島風のきわめて残虐な方法で、全員を公開処刑してしまうのです。
さらにクーデター派に殺されそうになった閔妃は、日本に亡命した金玉均らに対して、刺客を差し向けています。
金玉均らは、日本各地を転々と逃げ回り、最後には上海に渡るのだけど、結局、暗殺されてしまう。
半島に移送された金玉均の遺体は、見せしめのために群集の前で五体を引き裂かれ、身体の各部を各地で腐るまで晒されました。
残酷な話ですが、民衆を愚民化して支配する中世王朝や植民地支配では、これが常識です。
なぜなら民衆は愚民ですから、道理をもって諭(さと)そうとしても、そもそもその道理を持ち合わせていないのです。
ですから愚民に対しては、徹底して威をもって脅し、恐怖を植え付けたのです。
日本のように、民衆の知性を高めることによって、道徳で治安を維持しようなどという国は、世界に類例がないのです。
日本だけが、特別なのです。
なぜ日本だけがこれを実現できたのか。
答えは、日本に天皇の御存在があったからです。
民は天皇の「おほみたから」であり、政治はこの天皇の民を護るためのものだとされたからです。
これに対し、天皇という存在がなく、国の頂点にある人がそのまま政治権力者である中世国家においては、民はただの私有民です。
私有民は、私物です。
私物が思うように動かなければ、処刑し破壊し、言うことを聞くまで徹底的に懲らしめる。
民衆の面前で、肉を削ぎ、その悲鳴を民衆に聞かせる。
これは大げさでもなんでもなくて、陵遅刑といって、実際にチャイナで行われていた一般的な刑罰の方法です。
ちなみに、このクーデターのとき、高宗国王から依頼をうけて王宮の警備指導にあたっていた日本人30名が、袁世凱率いる清軍によって全員殺害されています。
それもかなり酷い殺され方をしている。
亡くなられた将兵の方々は靖国神社に祀られています。
翌、明治18(1885)年4月、伊藤博文全権大使とする日本は、この問題の解決のために、中国・天津で、清の李鴻章と会談しました。
日本側は、李氏朝鮮に頼まれて派遣していた日本人将兵30名が残虐な方法で殺害されているのです。
本来ならこれだけでも報復戦争をするか、あるいは巨額の損害賠償請求できる事柄です。
けれど戦争をすれば、ふたたび多くの血が流れるのです。
伊藤博文は、殺された日本の将兵に対する賠償は放棄するから、お互いもう朝鮮半島から撤兵しようではないかと李鴻章にもちかけました。
一方的な被害者の側が、今回のことで賠償請求も武力をもってコトを構えることもしないから、全部水に流そうではないか、ともちかけたのです。
いまは、日本も清国も、互いに東亜の民同士が争っている場合ではない。
欧米列強の植民地支配という脅威に対して、互いに力を合わせて国力を充実させることこそが肝要、それが日本側の姿勢です。
そしてさらに伊藤博文は、今回のように朝鮮半島のたったひとりの女性によって、清国と日本が互いにひっかきまわされるのはおかしな話なのだから、日本も半島から兵を退くから、清国も一緒に兵を退かないかともちかけました。
難しい交渉になると苦り切っていた清の李鴻章にしてみれば、日本の申出はまさに願ったりかなったりです。
李鴻章は、ふたつ返事で伊藤博文の提案を飲みました。
この天津会談の結果、日本も清国も、あっさりと朝鮮から兵をまるごと引き上げました。
そしてなんと、この後10年もの間、半島に、外国軍隊の駐留がなくなったのです。
平和を手にした半島の民間人たちは、日本人の民間人によるボランティアなども得て、産業を大幅に活性化させました。
1890年代になると、なんと半島から日本への輸出は、当時の半島の輸出総額の90%以上、日本からの物品の輸入が50%を占めるようになります。
つまり、半島の対日貿易収支が、大幅な黒字になったのです。
400年、死んだように眠っていた韓国経済は、これによっていっきに成長していったのです。
けれど急激な経済成長は、朝鮮半島に、ごく一部の大金持ちをつくる一方で、物価を高騰させ、貧富の差を増大させました。
米や大豆の値段が高騰し、貧しい半島庶民の生活は、ますます圧迫されてしまったのです。
一方、李氏朝鮮の閔妃は、富んできた半島政府の財政のもとで贅沢三昧の生活を送りながら、もっと贅沢をしようと企みます。
何をしたかというと、満州を勢力下におこうと南下してきたロシアに、朝鮮半島ある鍾城・鏡源の鉱山採掘権や、半島北部の森林伐採権、関税権などを次々に売り渡したのです。
そりゃあ、閔妃の一族は大儲けです。
基本的な世の中の仕組みですが、売ってはならないものを売り渡せば、大儲けができる。
日本を特アに売り渡す政治家、麻薬を売買する暴力団、貞操を売る売春婦、みな同じです。
逆に大切なものを守ろうとする行動は儲からない。
いまの日本の保守活動など、その典型です。
朝鮮半島では、民衆の暮らしがますます貧窮してくる中で、一方では閔妃一派だけが、我が世の春を謳歌している。
「こういう事態を招いたのも、
閔妃一派が政治を私物化し
国民生活をかえりみないせいだ」
朝鮮半島内に当時広がっていた東学教という宗教団体が中心となり、明治27(1894)年5月、東学教団の全琫準を指導者とする甲午農民戦争(東学党の乱)が起こります。
東学教団が、民衆の生活の改善を求めて、農民一揆をおこしたのです。
そして5月末までに羅道全州を占領してしまう。
こういうことが起こると、自国の軍や警察で鎮圧にあたろうとせず、すぐに他国の手を借りようとするのも、半島王朝の特徴です。
そもそも李氏朝鮮自体が、そういう手段によって成立した国です。
明治27(1894)年6月1日、李氏朝鮮の閔妃政権は、清に派兵を要請しました。
日本との約束があって、10年間朝鮮半島に入り込めなかった清は、待ってましたとばかり大軍をもって朝鮮半島内に侵入します。
そして東学教一派を片端から殺害していきました。
一方、当時の朝鮮半島内には、多くの日本人民間ボランティアの人たちがいました。
以前、半島国内で日本人婦女子が、虐殺され、なぶり殺されたという事実があります。
日本は邦人保護のため、6月10日になって、海軍陸戦隊400名(たった400名です)と大鳥圭介公使を漢城に派遣しました。
6月11日、清軍と閔妃政権は、一揆軍の弊政改革案を受け入れ、暴動を鎮圧させました。
事件はこれで終わったかに見えたのですが、翌12日に、清国は牙山に陸軍を上陸させてます。
これは約束が違う。
朝鮮半島内に有事だから一時的に清と日本は派兵をしたのです。
事態が収まれば、当然、もともとの約束通り、撤兵するのが道理というものです。
日本は、6月15日、大島公使が清に対し、半島の平和のために、両軍が半島から撤兵すること、ならびに、半島の内政改革については、日清共同で平和りに進めたらどうかと、進言します。
しかし半島を属国視し、かつ、日本軍の上陸部隊がわずか400であるとあなどった清軍は、この日本の提案にウンといいません。
大鳥行使は6月20日、朝鮮王である高宗に、
「半島から、清も日本も撤退してほしいと交渉したらどうか」と、申し出ました。
ところが7月にはいると、牙山の清軍は、ますます増強され、7月20日には、さらに4千人の清国陸戦隊が上陸してきます。
7月25日には、半島の北西岸の豊島沖で、日本の巡洋艦「秋津洲」「吉野」と「浪速」が、会合予定だった巡洋艦「武蔵」と「八重山」を捜していたところ、突然、海上にあらわれた清国巡洋艦の「済遠」と「広乙」から、21センチ砲で、砲撃を受けました。
清の軍艦が、突然、何の警告もなく一方的に撃ってきたのです。
こうなると日本も反撃しないわけにはいかない。
これはあきらかな正当防衛行為です。
日本の巡洋艦が応戦をはじめると、「済遠」と「広乙」はいきなり逃亡を始めました。
一方的に撃ってきといて、反撃されたらスタコラサッサと逃げ出す。
まいどおなじみの手口ですが、日本海軍は「秋津洲」で、清の「広乙」を、
「吉野」と「浪速」で、大きいほうの「済遠」を追いました。
「広乙」は追い詰められて座礁しました。
「済遠」を追った「吉野」と「浪速」は、「済遠」が国旗を降ろして降伏の意を示したかと思えば突如、逃走を図るなんてことを繰り返し、ついには海上にあった清国軍艦「操江」と「高陞」(英国商船旗を掲揚)のもとに逃げ込んでしまう。
「浪速」は、一時攻撃と追跡をやめ、清国軍艦「操江」らと押し問答をしたのですが、その隙に、「済遠」はさっさと逃走しまっています。
「吉野」の最高速度は23ノットです。
「済遠」は15ノット。
ですから日本の巡洋艦「吉野」のほうが、断然、船足が速い。
ところが「済遠」は逃げながら2門の21センチ砲をバンバン撃つ。
「吉野」はジグザグ航法で、敵の弾を避けながら、これを追跡する。
「吉野」の砲門は15センチですが、狙いは正確です。
「吉野」は、「済遠」を2500メートルまで追い詰めた。
すると「済遠」は面舵をとって船を浅瀬へと船を向かわせます。
「済遠」はドイツ製巡洋艦で2300トンで、喫水は4.67メートルです。。
「吉野」はイギリス製の4216トンで、喫水は5.18メートルです。
浅瀬に逃げられたらどうしようもないのです。
「吉野」は、追撃を中止し、「済遠」は逃げてしまいました。
一方、「浪速」艦長の東郷平八郎大佐は「高陞」に停船を命じ、臨検を行おうとするのだけれど、「高陞」は停戦命令に従わない。
やむなく「浪速」は、「高陞号」を撃沈したうえで、「高陞」に乗っていた英国人船員ら3人と、清国兵50名を救助し、捕虜としています。(豊島沖海戦)
この海戦による日本側の死傷者及び艦船の損害は皆無です。
他方、清は「広乙」が座礁、「高陞」が撃沈されています。
ところが「吉野」が追撃を中止した「済遠」は、なぜか清の発表では「大破」とされ、日本によって一方的に攻撃されたと発表しました。
この海戦は、いまから117年前の日清戦争の直前に起こった出来事です。
いまも昔も、チャイナは何も変わらない。
彼らにとっては、その場その場の「都合」がすべてであり、物事の道理や筋道とかは眼中にありません。
あるのは「どちらが上か」だけです。
そして、そのために自分に都合のいいように事実をねじまげます。
ちなみにこの戦いのとき、清国の軍艦「高陞」は、英国商船旗を掲揚していたために、英国商船旗を掲げた「高陞」が撃沈されたことで、英国内では、日本に対する反感が沸き起こりました。
これまた毎度おなじみのチャイナの宣伝工作です。
けれど、日本の「高陞」攻撃は、完全に国際法に沿ったものでした。
そもそも「何の警告もなく、一方的に撃ってきたから、撃ち返した」のです。
当時の日本政府によって、正しい事実が報道されると、英国世論は、見事に沈静化しました。
あたりまえのことです。
いまどきの日本政府は、チャイナに南京大虐殺とか、韓国の従軍慰安夫人、あるいは尖閣諸島、あるいは竹島問題について、外務省のHPでネット上でちまちまと反論する程度で、必要な事実関係のステートメントをきちんと説明しない。
だから、工作に嵌められ、いいように日本が貶められるのです。
いうべきことは、ちゃんと言う。
それが国際ルールです。
同時に、もうひとつ大きなファクターがありました。
それは、このとき日本が「高陞」を攻撃したことについて、単に政府がステートメントを発表しただけでなく、その政府発言が、「嘘だと思うなら、腕で来い!」という軍事力に裏付けられたということです。
要するに、真っ向から意見が対立しているとき、単に平手で「話し合いを」というだけでは物事は解決しない。
このことは、我々が歴史に学ぶべきことです。
世界は、特にチャイナの常識は、我々日本とは違うのです。
その昔、魏の曹操は、呉を攻めたとき、降伏を勧告する一片の文書を送るだけでなく、それがお嫌ならまた別なご挨拶をもってといえる「実力」を、水陸から100万の大軍をもって呉に向けて進発させました。
吉川英治は、新・三国志の中で
「いかなる外交も、
その外交辞令の手元に、
これがお嫌ならまた別なご挨拶をもって
といえる「実力」がいる」
と書いています。
もちろんこれは小説の中の話ですけれど、世の中の真実を見事に表していると思います。
話を戻します。
この海戦があった2日後、7月25日のことです。
朝鮮の閔妃政権から、大鳥圭介公使に対し、
「牙山(あさん)に上陸した清国軍を撃退してほしい」
という要請が出されました。
しかも、「それを日本がやらなければ、半島にいる日本人に危害を加える」というのです。
めちゃくちゃな話ですが、邦人保護のために軍を派遣しているのです。
やむなく日本は、翌7月29日、第9歩兵旅団によって牙城に立てこもる清軍の攻撃に向かいました。
現地に到着した午前2時、清国兵の襲撃によって松崎直臣陸軍歩兵大尉が戦死されています。
これが明治日本における、初の外地での日本側戦死者となりました。
やむなく日本は攻撃を開始しました。
そしてわずか5時間で、清国正規軍陣地を完全に制圧してしまいました。(成歓の戦い)
この戦いで、日本側の死傷者は82名です。
これに対し、清国兵は500名以上の死傷者を出し、武器を放棄して平壌に逃走しました。
この戦いで、第21連隊の木口小平(きぐちこへい)二等兵が、死んでもラッパを離さずに吹き続けたという逸話が残っています。
それが実に立派な態度であったということで、戦前は尋常小学校の修身の教科書に木口小平二等兵の話が載っていました。
翌々日、清国軍は牙山から逃げ帰った兵士とあわせて、合計1万2千人の大軍を平壌に集結させました。
日本は、あくまで開戦を避けようと、外交交渉を継続しますが、清はこれに応じない。
やむなく日本は、けじめとして、8月1日に清国に宣戦布告文を発しました。
これは、半島の意思を尊重し、兵を引かないなら、日本は戦いますよ、という詔です。
要するに「宣戦布告文」です。
が、ここで、いわゆる宣戦布告文というものが、戦争の開始そのものを目的としたものではない、ということを、我々は今一度確認しておく必要があります。
「宣戦布告」というのは、それがあるからはじめて戦争が始められるというものではなく、開戦ギリギリの状況下で、戦争となることを防ぐためのものでもあるのです。
宣戦布告が、必ずしもドンパチの始まりを意味するものではないし、また国際法上必要な開戦のための要素と思い込んで思考停止におちいるようなものでもないということは、我々日本人が認識を新たにし、GHQや戦後左翼の洗脳を解く鍵でもあるのです。
我々日本人は、武道の試合が「礼にはじまって、礼に終わる」ことから、開戦に際しては、礼として、はじめに宣戦布告があるもの、ということが、なんとなくイメージとなっているようです。
けれど、宣戦布告というのは、それがあってはじめて戦争行為がはじまるのではありません。
そこが武道の礼と違うところです。
宣戦布告は、
あくまで戦争を避けるためのものであり、
また、
内外に我々が何のために開戦するのかを明らかにするためのものである、
ということを是非、ここで学んでいただきたいと思います。
大東亜戦争において、真珠湾攻撃の宣戦布告が遅れたということが、我々日本人の負い目になっている傾向がありますが、それは「そのように米国が誘導した、それによって日本人に贖罪意識を植え付けようとした」というだけのものであって、実際の日米開戦は、すでに支.那事変の段階で米軍がフライングタイガー隊を派遣するなど、すでに対日戦に参戦しています。
また、本稿における日清戦争においても、先にドンパチがはじまっていることに、あらためてお気づきいただければと思います。
昨今では、北朝鮮が、ほとんど月に一度は「宣戦布告」のような発言を繰り返していますが、それはいわば口戦であって、だからすぐにドンパチが始まるというものではないのです。
日清戦争の宣戦布告分について、ウィキペディアの「日清戦争」をたまたま開いたら、この「詔勅は名目にすぎず、半島を自国の影響下におくことや清の領土割譲など、自国権益の拡大を目的にした戦争」と書いてありました。
どこのだれが書いた文章かしらないけれど、日本が国家として戦争を行う上で、明治大帝の名で出された詔勅に対し、「名目にすぎず」と書くのは、あまりにもご失敬です。
そのことは、開戦の詔勅を読んだらわかります。
はじめに要点の口語訳、そのあとに原文を掲載します。
========
【清国ニ対スル宣戦ノ詔勅】
(しんこくにたいするせんせんのしょうちょく)
(口語訳)
朕は、ここに、清国に対して宣戦を布告する。
朕の即位以来、二十有余年の間、文明開化を平和な治世のうち に求め、外国と事を構えることは、極めてあってはならないことと信じ、政府に対し て、常に友好国と友好関係を強くするよう努力させてきた。
さいわいに、諸国との 交際は、年をおうごとに親密さを加えてきた。
にもかかわらず清国が、半島事件によって日本に対し、日本側の隠すところのない友好関係にそむき、信義を失なわせる挙に出ようとは、どうして予測できたであろう。
半島は、日本が、そのはじめより、導き誘って諸国の仲間となした一独立国である。
しかし清国は、ことあるごとに自ら半島を属国であると主張し、陰に陽に半島 に内政干渉し、そこに内乱が起こるや、属国の危機を救うという口実で半島に対し出兵した。
朕は、明治15年の済物浦条約により、半島に兵を出して事変に備えさせ、更に半島から戦乱を永久になくし、将来にわたって治安を保ち、それをもって東洋全域の平和を維持しようと欲し、まず清国に(半島に関しては)協同で事にあたろうと告げたのだが、清国は態度を変え続け、さまざまないい訳をもうけて、この提案を拒んだ。
日本は、そのような情勢下で、半島に対して、その悪政を改革し、国内では治安の 基盤を堅くし、対外的には独立国の権利と義務を全うすることを勧め、半島は、既に その勧めを肯定し受諾したのにもかかわらず、清国は終始、裏にいて、あらゆる方面 から、その目的を妨害し、それどころか言を左右にしながら口実をもうけて、時間をかせぐ一方、清国の水陸の軍備を整え、それが整うや、ただちに その戦力をもって、(半島征服の)欲望を達成しようとし、更に大軍を朝鮮半島に 派兵し、我が海軍の艦を黄海に要撃し、ほとんど 壊滅の極となった。
すなわち、清国の計略は、あきらかに半島国の治安の責務をになうものとしての日本を否定し、日本が率先して、独立諸国の列に加えた半島の地位を、それらを明記した「天津条約」と共に、めくらましとごまかしの中に埋没させ、帝国の権利、利益 に損害を与え、東洋の永続的な平和を保障できなくすることにある。
これは疑いよう がない。よくよく清国の為す所に関して、そのたくらみごとのありかを深く洞察するならば、実に最初から清国は、半島はじめ東洋の平和を犠牲にしてでも、その非情な野望を遂げようとしていると言わざるをえない。
事は既に、ここまできてしまった。
朕は、平和であることに終始し、もって帝国の栄光を国内外にはっきりと顕現させることに専念しているけれど、その一方で、公式に宣戦布告する。
汝ら、国民の忠実さと勇武さに寄り頼み、すみやかに、この戦争に勝って、以前と同じ平和を恒久的に 取り戻し、帝国の栄光を全うすることを決意する。
~~~~~~~~~~~~
【清国ニ対スル宣戦ノ詔勅】
(しんこくにたいするせんせんのしょうちょく)
【原文】 天佑ヲ保全シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝国皇帝ハ、忠実勇武ナル汝有衆ニ示ス。 朕茲ニ清国ニ対シテ戦ヲ宣ス。 朕カ百僚有司ハ宜ク朕カ意ヲ体シ、陸上ニ海面ニ清国ニ対シテ交戦ノ事ニ従ヒ以テ国家ノ目的ヲ達スルニ努力スヘシ。 苟モ国際法ニ戻ラサル限リ各々権能ニ応シテ一切ノ手段ヲ尽スニ於テ必ス遺漏ナカラムコトヲ期セヨ 惟フニ朕カ即位以来茲ニ二十有余年、文明ノ化ヲ平和ノ治ニ求メ事ヲ外国ニ搆フルノ極メテ不可ナルヲ信シ有司ヲシテ常ニ友邦ノ誼ヲ篤クスルニ努力セシメ幸ニ列国ノ交際ハ年ヲ逐フテ親密ヲ加フ。何ソ料ラム。 清国ノ朝鮮事件ニ於ケル我ニ対シテ著著鄰交ニ戻リ信義ヲ失スルノ挙ニ出テムトハ。 朝鮮ハ、帝国カ其ノ始ニ啓誘シテ列国ノ伍伴ニ就カシメタル独立ノ一国タリ。 而シテ清国ハ毎ニ自ラ朝鮮ヲ以テ属邦ト称シ、陰ニ陽ニ其ノ内政ニ干渉シ其ノ内乱アルニ於テ口ヲ属邦ノ拯難ニ籍キ兵ヲ朝鮮ニ出シタリ。 朕ハ明治十五年ノ条約ニ依リ兵ヲ出シテ変ニ備ヘシメ更ニ朝鮮ヲシテ禍乱ヲ永遠ニ免レ治安ヲ将来ニ保タシメ、以テ東洋全局ノ平和ヲ維持セムト欲シ先ツ清国ニ告クルニ協同事ニ従ハムコトヲ以テシタルニ、清国ハ翻テ種々ノ辞柄ヲ設ケ之ヲ拒ミタリ。 帝国ハ是ニ於テ朝鮮ニ勧ムルニ其ノ秕政ヲ釐革シ内ハ治安ノ基ヲ堅クシ外ハ独立国ノ権義ヲ全クセムコトヲ以テシタルニ朝鮮ハ既ニ之ヲ肯諾シタルモ清国ハ終始陰ニ居テ百方其ノ目的ヲ妨碍シ剰ヘ辞ヲ左右ニ托シ時機ヲ緩ニシ以テ其ノ水陸ノ兵備ヲ整ヘ一旦成ルヲ告クルヤ直ニ其ノ力ヲ以テ其ノ欲望ヲ達セムトシ、更ニ大兵ヲ韓土ニ派シ我艦ヲ韓海ニ要撃シ殆ト亡状ヲ極メタリ。 則チ清国ノ計図タル明ニ朝鮮国治安ノ責ヲシテ帰スル所アラサラシメ帝国カ率先シテ之ヲ諸独立国ノ列ニ伍セシメタル朝鮮ノ地位ハ之ヲ表示スルノ条約ト共ニ之ヲ蒙晦ニ付シ、以テ帝国ノ権利利益ヲ損傷シ以テ東洋ノ平和ヲシテ永ク担保ナカラシムルニ存スルヤ疑フヘカラス。 熟々其ノ為ス所ニ就テ深ク其ノ謀計ノ存スル所ヲ揣ルニ実ニ始メヨリ平和ヲ犠牲トシテ其ノ非望ヲ遂ケムトスルモノト謂ハサルヘカラス。 事既ニ茲ニ至ル朕平和ト相終始シテ以テ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚スルニ専ナリト雖亦公ニ戦ヲ宣セサルヲ得サルナリ汝有衆ノ忠実勇武ニ倚頼シ速ニ平和ヲ永遠ニ克復シ以テ帝国ノ光栄ヲ全クセムコトヲ期ス 御名御璽 明治二十七年八月一日
==========
日本は、半島を独立国として遇し、日本と同様に庶民生活が向上するよう半島に協力してきたが、清は、条約によって半島の独立を認めた後も、なお半島を属国扱いし、日本との間で、「派兵はしない」と取り決めまであったのに、これを「蒙晦ニ付シ(いいかげんな目くらましとごまかし)」で無視して派兵をしてきた。
だから日本は、公式に清国に宣戦布告する、と述べているのです。
そしてこれこそが事実であり、真実です。
宣戦布告は、8月1日です。
けれど日本は、その後もなんとか外交努力で事態を鎮静化しようと努力したのです。
ところが事態は一向に改善しない。
やむなく日本は、1ヵ月半後の9月15日、平壌の清軍基地へ攻撃を開始しました。
清国軍は、その日の午後4時40分には、白旗を掲げて翌日の開城を約束しました。
ところが、清国軍は、約束を違えて逃亡してしまいました。
そして、同日夜に日本軍が入城しました。
日本の大勝利です。
2日後、9月17日12時50分、黄海上で、日清両艦隊が遭遇しました。
先に攻撃してきたのはこんどもまた、清です。
日本側は、初代連合艦隊司令長官伊東祐亨(いとうゆうこう)率いる旗艦「松島」以下12隻。
清国艦隊は、18隻。
敵戦力の方が大きかったのですが、日本艦隊は、果敢に戦い、清国艦5隻を撃沈、5隻を大中破、2隻を擱座させて、大勝利しました。
この海戦によって、清国艦隊は威海衛に閉じこもることとなり、日本海軍は黄海・半島の制海権を完全に確保します。
さらに10月25日には、山形有朋率いる第一軍が鴨緑江渡河作戦で清国陸軍に大勝利しています。
10月24日には、大山巌率いる第二軍が旅順を制圧。
日本は、明治28(1895)年4月の日清講和条約まで、清軍を相手に連戦連勝したのです。
日本は、自分の都合よりも約束優先する国です。
朝、出勤するときに、前日どんなに疲れていても、なんとかして時間に間に合うように出勤しようとする。
朝「眠い」という自己都合より、あらかじめ決められた約束事、「朝何時出社」という約束事をきちんと守る。
それが日本人の国民性だし、世界の常識です。
ところが閔妃や、当時の清国、あるいは昨今の日本国内に巣食う売国左翼や韓国政権などは、国民や他国との約束より、自分の都合を優先します。
自己の利益ばかりを追うのです。
なぜそうなるかといえば、国家という集合体として動いているのではなく、一部の権力者が自己の都合で、国や組織を壟断しているからです。
約束しながら、それを平気で無視して都合よく兵をすすめたり、多勢に無勢をいいことに虐殺の限りをつくす不条理に対して、明治から昭和にかけての日本は、我慢に我慢をかさねて、それでも平和的解決の道を模索し続けてきました。
このことは、日清・日露、第一次大戦、大東亜戦争と、日本が一貫して貫いてきていることです。
いまも昔も変わりません。
日本は約束を守る。
依頼された仕事を完璧に仕上げる。
そういうバカ正直さこそ、結果として国際的信用を勝ち得、経済の復興が図られた鍵なのだと思います。
約束を守り、平和を愛し、信頼を築き、互いに成長できるように気遣う日本。そして一朝事あれば、正々堂々と果敢に戦い、連戦連勝の勝利を果たす日本。
これに対し、大言壮語するけれど、いざとなったら逃げ出してしまう、嘘八百を並べ立てる、自己の金儲けだけしか考えない。多勢に無勢で相手より絶対に強い立場にあると思ったら、ありとあらゆる非道を平気で行う。
日清戦争は、信頼を重んじ、必死に努力して富を得た日本と、干渉ばかりして努力をせずに事大主義に凝り固まった清国との戦争でした。
結果は、明らかでした。
正しい者が、最後は勝つのです。
※この記事は2013年9月のねずブロ記事のリニューアルです。