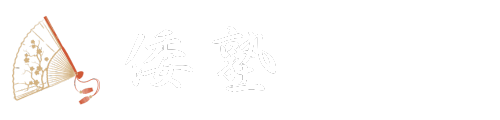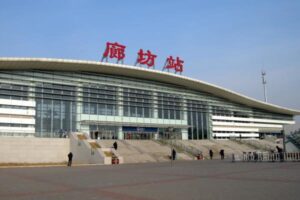87年前の今日、つまり昭和12(1937)年7月26日に北京で起きたのが「広安門事件(こうあんもんじけん)です。
昨日の廊坊事件は、26日の朝には鎮圧されるのですが、続いて翌日にはこの事件が起きています。
この日北京にいた日本人居留民の保護のために、日本陸軍のチャイナ駐屯歩兵第二連隊第二大隊(約千名)が、26台のトラックに分乗して、北京城内の日本軍の兵営に向かいました。
このときも廊坊事件同様、事前に松井特務機関長が、部隊が北京城の広安門を通過することを国民党の政務委員会に連絡し、秦徳純市長の承諾をちゃんと得ています。
すこし補足します。
本来なら日本は国際条約である北京議定書に基づいて駐屯しているのですから、チャイナ側に通告する義務はありません。
当時のチャイナには複数の「政府」を名乗る連中があり、それぞれが軍を持っていました。
なかでも蒋介石率いる国民党は、当時のチャイナにあって最大の軍閥であり自称政府ではありましたけれど、政府といいながら民政のための行政機構を持っていません。
つまり、蒋介石の国民党もまた、ただの軍閥でしかなかったということです。
ちなみにチャイナにおいては、今も昔も軍と警察とヤクザと暴徒は同じものです。
それでも日本は、日本人の常識として「他所の国で兵を動かしているのだから」と、国民党に配慮しています。
これは日本人の対等感としての常識からすればあたりまえのことですが、チャイナの常識ではありません。
なぜならチャイナには上下関係しかないからです。
許可をする人、される人がいれば、許可をする人が「上」になります。
日本側が許可を申し出れば、あちらさんは、「日本人は我々の下アル」としか考えないし、上にある者は、下の者に対して何をしても良いというのが、彼らの文化です。
ですから本当なら日本軍は、高圧的に彼らを徹底弾圧していた方が、結果としては彼らに無用な乱暴を防ぐことができたのです。
広安門通過に際しても、許可など得ず、堂々と通過し、文句を言ってきたり、発砲でもされようものなら、徹底殺戮して言うことを聞かせるといった行動をとっていれば、日本はむしろ安泰だったかもしれない。
実際、北京議定書に基いてチャイナに駐屯していた西欧10カ国はすべてそのようにしています。
だから彼らは襲われなかったのです。
ところが日本人には、これが理解できないし、したいとも思わない。
どこまでもChineseを愛し、Chineseたちを人として対等に扱ったのです。
だからこそ、広安門でも、事前通告までキチンとしていたのです。
無政府状態の荒廃地となっていたチャイナへの派兵です。
各国の軍は、各国の都合で動けば良く、それに対してチャイナの軍閥が文句を言って来たら(彼らの国では軍とヤクザと暴徒は同じものなのですから)、火力にものを言わせて蹴散していました。
そのために、米英などは、チャイナに駐留している自国民1名につき、1名の軍を派遣しています。
そして言う事を聞かなければ、徹底して攻撃しています。
これに対し、日本の派遣部隊は、日本人居留民6名につき、軍人が1名の割合です。
あきらかに欧米と比べて軍の派遣要員数が少ないことに加え、同じ有色人種に常に公明正大であるべきという姿勢から、Chineseたちに対して非道を働くものさえ、まったくありませんでした。
日本軍は、午後6時頃、広安門前に到着しました。
ところが、事前に告知してあったにも関わらず、彼らは城門を閉鎖したままにしました。
門を開けてくれないのです。
連絡の不徹底は、チャイナではよくあることです。
そこで大隊顧問の桜井少佐が事情を説明して開門の交渉をし、その結果、午後7時半頃になって、やっと城門が開門されました。
ところが、日本の大隊が門を通過し始め、部隊の3分の2が通過したときに、いきなり門が閉ざされました。
部隊は、城門の内と外に分断されました。
その状態で、いきなり国民党軍が、手榴弾と機関銃を猛射して、日本側に猛攻撃を加えてきたのです。
敵は、城壁の上から、至近距離で攻撃してきました。
何もしないでいれば、日本側は全滅してしまいます。
たいへん危険な情況です。
撃たれた日本側兵士が、バタバタとたおれました。
やむなく日本側も応戦を開始しました。
すると国民党軍は、兵力を増強して大隊を包囲し、日本側に対して殲滅戦を挑んできたのです。
この包囲戦に対する感覚も、日本人とChineseではまるで感覚が異なります。
これは毛沢東が、実際に日本軍の南京戦を例にとって述べていることですが、
「日本軍は敵を包囲しても、
敵がそこで降参すれば、
まるごとその兵たちを逃がしてやっている。
こんなことをしているから、
何度でも敵は武装をし直して襲って来るのだ。
包囲したら、
たとえ敵が降参しても皆殺しにする。
それが戦いというものだ。」
これが毛沢東の考え方だったし、Chineseの古来変わらぬ戦いなのです。
日本側は多数の死傷者を出しながらも、至近距離、しかも塀の上から狙って来る敵を相手に、よく持ちこたえました。
これも、情況を考えれば、本当によく持ちこたえる事ができたものだと思います。
普通なら、とっくに全滅しています。
こうして最初の発砲から約2時間が経過したとき、旅団からの日本軍救援隊が到着しました。
そして敵に対して、次の内容で一時的な停戦を呼びかけました。
1 国民党軍は、いったん離れた場所に集結せよ
2 日本軍のうち、城内にいる者たちは、城内公使館区域に向かえ。
3 城外に残されたものは豊台の日本軍旅団に帰投せよ
こうして、広安門では、ようやく午後10時過ぎに停戦が整ったのです。
この戦いにおける日本軍の死傷者は19名(戦死2名)でした。
他に同行していた軍属や新聞記者も負傷しています。
そしてこのときの広安門事件の首謀者や残党たちが、28日までに集結したのが、通州駅だったわけです。
日本は、明治34(1901)年に交わされた北京議定書に基づいてチャイナへの派兵をしていました。
そのチャイナは、いわゆる無政府状態の混沌にありました。
だからこそ世界11カ国が議定書に基づく派兵をしていました。
この事件は昭和12(1937)年ですから、派兵開始から36年が経過していました。
当時の日本は、国際連盟の安全保障理事国であり、世界の治安維持に責任があり、また日本は、隣国であるチャイナに、一日も早い治安の回復と民生の安定を、どこの国より願っていました。
けれど対立していたチャイナ国民党とチャイナ共産党は、前年12月の西安事件で裏で手を結び、半年の準備を経て突然に日本に襲いかかってきたわけです。
これが虎視眈々とチャイナの征服を狙う欧米列強であれば、おそらくは最初の盧溝橋事件があった時点で、あるいは廊坊事件があった時点で、あるいは広安門事件の時点ならほぼ完全に、敵対を理由に敢然としてチャイナにクレームをつけ、徹底した殺戮と破壊を行い、巨額の賠償の請求をした上で、チャイナの一部を自国の植民地にしたことでしょう。
世界の常識では、そうした行動を「侵略」とはいいません。
「侵略」というのは、挑発(Provocation)がないのに、攻撃(Attack)することをいうからです。
挑発(Provocation)を受けて攻撃(Attack)することは、たとえそれが外地であっても、国家の正当な自衛権の発露であり、正当な自衛権の発露だというのが国際法の考え方です。
そしてこの場合、個人の犯罪の場合に適用されるような「過剰防衛」という考え方はありません。
いざ攻撃(Attack)となったら、相手が全滅するまで戦い抜いても構わないというのが国際社会における戦争です。
けれど日本は、どこまでもチャイナの平和と安定を願いました。
だからこそ、ここにきてなお、事件の不拡大方針を採りました。
それが果たして良いことであったのかは、はなはだ疑問です。
こうして昭和12年に始まった日華事変は、その後昭和20年の終戦に至ってもなお落ち着かず、昭和24年の中華人民共和国成立の時点まで盛大な内紛と殺し合いが続き、国家成立後も今度は自国内で7,800万人もの同朋を殺害しています。
むしろ戦争が終わったあと、日本が事実上米国に占領され、その後も米国の保護国として安保があってくれたおかげで、当時の虐殺の矛先が日本に向かなかっただけでも、僥倖というべきできごとであったということができます。
もし日本で7800万規模の殺戮がなされていたら、いまごろ純粋な日本人が果たして世界に何人残っているだろうかという話だからです。
現に、成立したばかりの中共政府は人口600万人のチベットにいきなり侵攻し、なんと人口の4分の1にあたる150万人を虐殺しています。
チベットは敬虔な仏教国ですが、「人民解放」を自称する中共軍は、チベットの僧侶たちの腕や足を切り落し、信仰の力でくっつけてみろ!と武器を持たない僧侶たちの前でゲラゲラ笑ったといいます。
武器を持たない弱者の前では、集団でとんでもなく居丈高になるのが、彼らなのです。
私たちは歴史を直視し、学ぶべきです。
※この記事は2016年7月のねずブロ記事のリニューアルです。