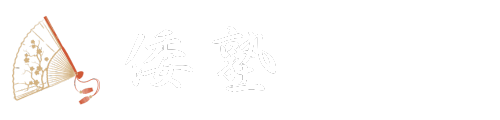■□■━━━━━━━━━━━━━■□■
共に学ぶ『倭塾サロン』
サロンメンバー大募集中
https://salon.hjrc.jp/
■□■━━━━━━━━━━━━━■□■
トップの写真は、特攻隊の光山文博(本名・卓庚鉉)大尉です。
知覧基地から飛び立ち、散華された特攻隊員です。
その光山大尉の物語が、日本弥栄の会が発行する雑誌『玉響』(平成28年11月号)に掲載されていました。
古い記事ですが、編集部と著者のW氏両方のご許可を得ていますので、再掲したいと思います。
特攻に20名ほどの半島系日本人が散華しているのです。
その代表的な人物の一人、光山文博大尉(本名・卓庚鉉)。
日韓併合以降、半島よりも賃金状況の高い日本へ多くの半島人が海を渡りました。
戦後に蔓延る「強制連行」や「徴用」などとはもちろん全く別で、当時半島は日本だったのです。
卓庚鉉もその一人で、祖父が半島での事業失敗から一家で京都に移住してきたのです。
創氏改名とは、
「日本が半島植民地支配の際に、
皇民化政策の一環として、
半島人から固有の姓を奪い、
日本式の名前に強制的に変えさせた。
これを拒否しようとしたものは非国民とされ、
様々な嫌がらせを受け、
結局は日本名に変えた」
というような説が流布されていますが、これも事実ではなく、「半島名のままだと商売がやりにくい」といった理由から、多くの半島人が日本名に改名したのです。
そもそも「創氏改名」という字をみたらわかります。
半島では、金や朴といった、いまでいう姓が多いですが、こうした姓のことを昔は「氏(うじ)」と言ったのです。
氏(うじ)は血縁関係を意味します。
ですから、金さんという氏があれば、全員が金さんの一族であり、血縁関係者ということになります。
けれどこうなると、同姓同名があまりにも増えてしまう。
日本でも昔、源平藤橘といった有力な氏(うじ)がありましたが、こうなるど、どこの誰だか特定が難しくなるということから、住まいのある地域を名字(苗字)として用いるようになりました。
日本では、昔は、たとえば徳川家康なら、その本当の名は
「源 朝臣 徳川 次郎三郎 家康」です。
意味は、
源 氏(源平藤橘)
朝臣 姓(官職名)
征夷大将軍 (官職)
徳川 苗字(得川)
次郎三郎 通称
家康 諱(いみな)
という構成になっていて、ですから通常用いられるのは「征夷大将軍次郎三郎様」です。
家康という名は、生涯隠しておく大切な魂魄の名前で、家康のことを「家康」と呼んで良いのは、せいぜい父母くらいなものとされていました。
同様に、上州 新田郡 得川村の紋次郎こと、源宿禰家定(みなもとのすくねいえさだ)なんていうのが、本来の名乗りで、けれど通常は、上州 新田郡 得川村の紋次郎とだけ名乗るわけです。
氏姓制度は歴史がっ古く、歴史が古いということは、その構造がたいへんにややこしい。
そこで明治に入って四民平等となった際、
「上州 新田郡 得川村」までは、役場がその名前を代行するから、得川村の何の太兵衛と名乗れということになって、
真ん中の田んぼだから中田、西側の田んぼだから西田などの名字が戸籍に登録されるようになりました。
ですからいま私たち現代日本人が、小名木善行などと名乗っているのは、このときの名字と通称であって、本来の名は、
源の 亭主関白 越中褌の守 遠州浜松の郡 廣澤村 小名木の善行 鼻の下長
などといった、まるで落語の「じゅげむ」みたいな長い名前の構造をしていたわけです。(名前は冗談です)
それが、「源の 亭主関白 越中褌の守」までは、四民平等で廃止になり、「遠州浜松の郡 廣澤村」までは、住民登録をする役場がこれを代行するから、名字と通称だけを住民台帳に登録すれば良いということになり、これがたいへん好評であったことから、日韓併合のあと、半島でもこれを行ったのが、いわゆる「創氏改名」なのです。
つまり、これまでの金とか朴といった氏を無くすわけではなくて、住民台帳に登録する際に、
「自分で新たな氏を名乗っても良い」としたのです。
これはたいへんに好評となり、当時、多くの半島人が、日本人のような漢字二文字の氏で登記を行っています。
卓庚鉉の一家も、このときに「卓」という氏ではなく、役場には「光山」という氏を届け出ました。
こうして生まれた子供は、光山文博となったのです。
光山文博さんは小学校を卒業後、名門であった立命館中学へ進学しています。
たいへんに優秀な少年であったのです。
そして陸軍特別操縦見習士官(特操)を志願。
見事、試験に合格して、同校の第一期生となりました。
ちなみに日韓併合後、日本は半島人に徴兵制を適用していません。
早坂隆(ノンフィクション作家)によれば、昭和12年(1937年)、日本の衆議院議員となっていた半島出身の朴春琴が「半島人志願兵制度」の請願がなされ、
翌昭和13年(1938年)、「陸軍特別志願兵令」が公布されたときになって、ようやく半島人による兵卒の志願が認められるようになりました。
日中戦争下、半島人の志願兵は右肩上がりに増え続けました。
当時の半島人は、日本軍が半島人に門戸を閉ざすことこそ「差別」「屈辱」であると主張していました。
日韓併合によって半島は日本の一部になり、半島人は日本人になったのだし、しかも日本人と同じ教科書(ただし使用する文字はハングル)で勉強しているのです。
「同じ日本人なのに、どうして俺達だけが国を護る兵隊になれないのか」
これは当時の半島の人たちの気分としても、十分に理解できることであると思います。
だから、少なからぬ半島人が「日本人と共に戦いたい」と入隊を希望したのです。
そんな時流の中にあって、光山文博さんも志願により昭和18年(1943年)10月、鹿児島県の南部に位置する大刀洗陸軍飛行学校知覧分教所に入校しました。
そう、そこで富屋食堂との物語が始まるのです。
光山文博さんも他の若き青年たちと同じように、休みになれば富屋食堂に顔を出し、優しく出迎えてくれるトメさんを母親のように慕っていました。
出会って間もない頃、光山文博さんは自分が半島人だとトメさんに打ち明けました。
当時、半島人の民度は日本のそれとは圧倒的に低く、今と同じように問題を起こす事も少なくなかったし、このため多くの日本人が半島出身者を警戒する風潮があったといいます。
けれどトメさんは、そんな光山文博さんを誠心誠意迎え入れました。
光山文博さんも、このことにすごく感謝していて、転属した先からさえもトメさんに便りを綴っていたほどです。
そして昭和19年10月、光山は陸軍少尉を拝命します。
ところが光山文博さんに、突然の不幸の知らせが届きます。
京都にいる母親が逝去されたのです。
母の死に目に会えなかった光山文博さんに、父から手紙が届きました。
そこには、
「文博、お前はもうお国に捧げた体だから、
十分にご奉公するように」と書かれていたそうです。
その後光山文博さんは、何かを決したように特攻を志願しました。
当時は、白人国では、戦線の最前線に植民地兵を配備し、自分たちは戦場を後ろから組み立てているのが世界の常識でした。
しかし当時の日本軍は、熾烈な戦場で他の民族を前線に送る事はしませんでした。
常に日本人の兵が最前線に立ちました。
それは日本が世界に人種差別撤廃を掲げていた事と無関係ではなかったと思います。
当時光山文博さんの特攻志願に対しても、上官は、何度もこのことを光山文博さんに確認したそうです。
けれど光山文博さんの決意は硬い。
心を動かされた上官は、ついに光山文博さんの特攻志願を許可します。
日本に誇りを持つ光山の父の想い。母親の死。
そして心の支えであった富屋食堂のトメさんたち。
次々と飛び立つ戦友たち。
日本人でも半島人でもなく、光山文博さんは一人の人間として、男として、未来を背負って飛び立ちました。
いよいよ飛び立つとき、光山文博さんはトメさんに言いました。
「長い間、いろいろありがとう。
おばちゃんのようないい人は見たことがないよ。
俺、ここにいると
半島人っていうことを忘れそうになるんだ。
でも、俺は半島人なんだ。
長い間、本当に親身になって世話してもらってありがとう。
実の親も及ばないほどだった」
「おばちゃん、
飛行兵って何も持っていないんだよ。
だから形見といっても、
あげるものは何にもないんだけど、
よかったら、
これを形見だと思って
取っておいてくれるかなあ」。
光山文博さんはトメさんに自らの財布を手渡しました。
トメは、自分と娘たちが写った写真を彼に差し出したそうです。
光山文博さんは、遠い半島の歌であるアリランを唄いました。
トメさんも、トメさんの娘たちも、それに声を合わせて歌いました。
四人は最後の晩に肩を抱き合うようにして大粒の涙を流しました。
***
流鏑馬(やぶさめ)というのは、第59代宇多天皇が896年に源能有に命じて制定されたことがはじまりなどと、いろいろなところに書かれていますが、実は、これはある事実の隠蔽工作です。
では、実際にはいつ流鏑馬が始まったかというと、539年に、第29代欽明天皇が、宇佐八幡宮で、三矢を射たのが起源です。
たとえ神事としても天皇が矢を射るというのは、なにやらものすごいことです。
何のために三矢を射たのかというと、
半島半島における「高句麗・百済・新羅」の三国を鎮めるためでした。
この頃の日本は、すでに天皇を中心とする国民国家が成立していましたが、半島半島は、要するに、上古の昔から反日と親日が入り交じる非常に複雑な場所だったわけで、その半島人たちが極めて親日的になったのは、この2千年ほどの歴史の中で、大東亜戦争の終戦までのほんの20年ほどだったわけです。
引用を続けます。
***
半島半島における日本統治時代とは1910年から45年までの35年間であり、その日韓併合は欧米の凶悪な植民地支配とは全く性質は異なるものでした。
欧米の植民地支配とは自国の利益のために隷属化し、搾取、暴力の蔓延る支配でした。
白人以外に人権などなく、今で言う家畜のような扱いだったのです。
そのような白人列強の時代の中、李氏半島王朝の腐敗は凄まじく、国民の文化・生活・精神レベルは筆舌に尽くしがたい状況すらありました。
そんな中、日本が半島半島で行った事は、原始的な生活文化から道路、鉄道、大学、病院など全て含めたインフラを整備し、教育を施し、近代化をはかりました。
その累計支援総額は現在の価値ならば約63兆円と言われており、これはあくまでも日本政府の支援であり、官民からの資産は簿外されています。
更に日本は敗戦後1951年9月8日に締結したサンフランシスコ講和条約により在外資産を放棄していますが、その中で半島半島に日本が残した資産価値は、GHQの試算によると現在のレートで約17兆円。
また1965年に日韓基本条約を締結し、日本政府は韓国に対して「無償で3億ドル」「有償で2億ドル」さらに「民間借款として3億ドル」を供与しています。
もちろんこれは経済的な要素であり、それ以上に日本人が半島半島で心血を注いだエネルギーは計り知れません。
もちろん何かしらの利益の為に半島半島に渡るものはいたとしても、世界の植民地ではその国の民族は激減するのが常と言う中、半島人人口は35年の間に倍増している事から、植民地支配などと言うものとは真逆のものである事が容易に理解できます。
しかし戦後の極度な左翼的自虐史観が日本国民を覆いつくし、こうした先達の苦労、そしてその愛と勇気はいつの間にか汚名に変わります。
阿部元俊さんは大正九年、三歳のときに半島に渡り、そこで学生時代を過ごした人です。
文字通り、日本統治下の半島を体験したのですが、氏はこのように当時を振り返ります。
「私が半島にいたころ、
日本人による半島人いじめの話は、
噂としてもまず聞いたことがありません。
とくに、ソウル郊外の水原にいたころは、
日本人が少ないからと珍しがられて、
地域の人たちはみな親切にしてくれていましたしね。
少なくとも水原では私の知る限り、
日本人と半島人とが衝突したとか、
喧嘩したとか、
何かのトラブルがあったといった話は
聞いたことがありません。
ソウルでもそうでした。
学校では、
『ここは半島だ、
我々は他人の国によそからやって来て住んでいる。
半島人と喧嘩したり、
半島人をいじめたりは
絶対にしてはいけない』
と盛んに言われていましたし、
親からも厳しくそう言われていました。
私の父は医者で、
貧困な農民たちの治療に励んでいましたが、
それで病原菌をもらってしまいまして、
腸チフスと赤痢にかかってしまいました。
父が病院を辞めるときには、
多くの半島人が家にやって来て、
『どうか辞めないで、ここにいてください』
と泣いて別れを惜しんでいました。
戦後、日本に帰ってから、
半島に住んでいた日本人は
半島人をさかんに苦しめたという言葉を、
当然のようにぶつけられましたが、
自分の体験からすると、
いったいそれはどういうことなのか、
どう考えてもわかりません。
喧嘩ということだけでなくて、
問題になるようないじめとか、差別とか、
一般生活者の間ではほとんどなかったということを、
私は自分自身の実体験から自信をもって言うことができます」
敗戦と同時に日韓併合が終了すると、日本にいた半島人の多くが戦勝国民と言い始め、暴力から身を守るすべも失い弱り切った日本人に暴行や拉致、虐殺を始めました。
続く半島戦争では、半島で自国民への暴行や虐殺の嵐が吹き荒れたため、一部の人たちが日本に密航する半島人も続出しました。
それらが更に暴力によって日本社会の闇を作り上げ、慰安婦問題を筆頭に様々な捏造を繰り返し、日本の中枢に食い込み利権を固めてきました。
***
ということで、記事はまだまだ続くのですが、以上の展開を、いわゆる在ニチ問題と捉えても、おそらく問題の解決はありません。
もっと根が深いのです。
国の形のことを英語で「ネイション」「ステイト」と言います。
「ネイション」は、歴史的民族的な集合体としての国です。
「ステイト」は、政治的組織としての国です。
戦後の日本は、いわば敗戦利得者ステイトです。
戦争を経済として考えると、日清日露戦争の頃は、日本は軍艦も武器も、西欧製のものを使っていました。
日本が日進日露に勝利できたのは、西欧諸国が日本の味方に付いたことが大きく影響しています。
ところが大正時代には、内需拡大のためにと、武器の生産が国内に切り替えられました。
このことは内需を拡大し、結果、大正デモクラシーの日本の繁栄をもたらしたのですが、その一方で、西欧諸国からすれば、実は日本はなんの商売相手にもならなくなりました。
さらに日本は、第一次世界大戦後のパリ講和会議で「人種の平等」を語り始めました。
この主張は、人道的には正しい主張です。
けれど、西欧諸国で支配層にある植民地利権を持った大金持ちたちにとっては、自分たちの財産を失わせる(日本に侵略され、日本に奪い取られる)ことを意味しました。
こうして日本は世界の敵となりました。
終戦後、日本は再び西欧諸国(とりわけ米国)の支配下に置かれることになりました。
米国にしてみれば、日本は市場です。
日本人は勤勉でよく働きますから、よく働かせて、その利益を吸い上げる。
これを効率的に行うために、日本国内にある少数民族の半島人に特権が与えられ現在に至っています。
567も、迷惑駐車も、防衛予算倍増問題も、すべてその延長線上にあります。
しかし、そうして収奪をしてきた西欧諸国は、米国を中心に自壊が始まっています。
一部の権益者である大金持ちが、その財産を増やすために、公然と多くの人の命や財産を奪う。
およそ6000年続いたこの世界の仕組み、とりわけ600年続いた植民地支配の構図が、いま最終段階の終わりを迎えようとしているのです。
そのなかで日本は、財力と武力による支配の時代から、庶民を宝とする和の文化、結びの文化の担い手として、なる新たな世紀のはじまりに、重要な役割を担っています。
日本は、いま、新たな世界のリーダーとしての未来を担いうる日本になるための、新たなステイトに生まれ変わろうとしているのです。
日月神示に、「一厘の神仕組み」という言葉があります。
この「一厘の神仕組み」によって、世界はグデンとひっくり返るのです。
いま、世界の人口は100億人です。
日本人は1億人です。
10億で1割、1億が1分です。
そして日本の中でも、9割の人は、西欧的我の文化、闘争の文化に染まっています。
つまり、日本の持つ和の文化、結びの文化を大切に保っている人というのは、1000万人。
これは世界の人口の1厘にあたります。
その1厘の人が、これからの新しい世界の担い手となるのです。
もしこれが「一厘の神仕組み」の正体なら、私たちに課せられた責任は重い。
神々の道は、険しく厳しいものです。
心に少しでも穢れがあれば、容赦なく捨てられる。
その自覚を持って、「グデン」が起きる前に、堂々と、粛々と、日本人としてしっかりと學び、生きていく。
半島に出自を持つ人たちの中にも、素晴らしい人はたくさんいます。
新たな世界へ。
新たな日本へ。
日本は、いま、6000年の時を超えてよみがえろうとしているのです。
※この記事は2018年10月のねずブロ記事のリニューアルです。