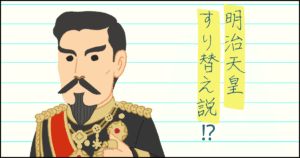「原爆投下は事前に知られていた」の真相とは?
都市伝説とされる2つの説
「原爆投下は、実は日本側が事前に察知していた」──。
このような説が、戦後しばらくしてから一部の出版物やメディアで語られるようになりました。
たとえば、
「長崎では空襲警報が一度出たのに、なぜか解除され、その直後に原爆が落とされた」
「大本営はB-29の無線通信を傍受していたのに、なぜか何も手を打たなかった」
というような主張です。
これらは、一見すると「本当かもしれない」と思わせるような説得力を持って語られることがあります。
まるで事実であるかのように、雑誌の特集記事や戦後検証本の一節として引用されたり、YouTubeなどの動画サイトでは「軍部の陰謀」や「情報操作」の一部として取り上げられることもあります。
こうした言説は、ある種の“歴史の闇”を暴くかのようなロマンに満ちているようにも見えます。
しかし、これらの説の多くは、断片的な情報の切り貼りや、一次資料に基づかない伝聞、あるいはプロパガンダ的な思想を帯びた論者によって語られていることが少なくありません。
事実として、原爆投下前後に起きた出来事を丁寧に検証していくと、そこには「知っていたのに何もしなかった」というよりも、「どうにかして守ろうとした人々の行動」が、数多く確認できるのです。
忘れ去られた“抵抗の記憶”に光を当てる
この記事では、「原爆投下を事前に知っていたのか?」という問いに対して、一方的な糾弾や陰謀論的な立場からではなく、事実に基づき、またその背後にある“人々の行動”に焦点を当てていきます。
特に、あの日原爆の第一目標とされた北九州・小倉で、市民や軍部がどのようにして「未然の迎撃」を果たしたのか。
そして第二目標となった長崎では、投下前に何が起き、何ができたのか。
それらの過程を通じて見えてくるのは、誰もが黙って見ていたわけではなく、誰かが、命がけで「この国の人々を守ろう」と立ち向かっていたという事実です。
歴史を振り返るとき、つい私たちは「結果」にばかり目を奪われがちです。
だが、大切なのはその結果に至るまでの「過程」ではないでしょうか。
「原爆投下は事前に知られていたのか?」という問いの先には、“あの日”、見えない空の下で繰り広げられた戦いがあります。
長崎原爆投下の概要と被害状況
午前11時2分に起きた閃光と地獄
1945年8月9日、午前11時2分。
静けさに包まれていた長崎の空に、突如としてまばゆい閃光が走りました。
次の瞬間、爆風とともに押し寄せる灼熱の波が、街という街を飲み込みました。
人々の営みがあったはずの住宅地、学校、教会、病院──すべてが、無音の地獄と化したのです。
投下されたのは、プルトニウム型原子爆弾「ファットマン」。
爆心地は長崎市松山町、上空約500メートルでの空中炸裂でした。
その威力はTNT火薬換算で約22キロトン。広島に投下された「リトルボーイ」の約1.5倍に相当します。
瞬時にして吹き飛ばされた家屋、人々の肉体が蒸発するように消えたその情景は、まさに人類が初めて目の当たりにした“終末の光景”でした。
市民の62%が命を失ったという現実
当時の長崎市の人口は約24万人とされています。
そのうち、およそ14万9千人が、原爆によって命を落としました。
その割合は、実に市民の約62%──。
しかしこの死者数は、単に「爆風で吹き飛ばされた人々」だけを指しているのではありません。
原爆の被害は、非常に多面的です。
・爆心地直下での即死
・爆風や瓦礫に押し潰されての即日死
・熱線による全身火傷
・放射線被曝による細胞破壊
・その後の白血病や臓器不全といった後障害
・火災による焼死
・逃げ遅れた家族を探す中での被曝──
死は、爆心地からの距離に比例するわけではなく、また被爆したその日だけではありません。
爆心地から1キロ以内では即死・即日死が大半を占めました。
その外周でも、被爆から数日、あるいは数週間〜数ヶ月後に命を落とす人が続出しました。
広島との違いはどこにあるのか
広島と長崎。
この2つの都市は、人類史上唯一、実戦で原爆を投下された都市という“重すぎる共通点”を持ちます。
けれど、両者の被害には明確な違いもありました。
まず爆弾の種類。広島にはウラン型、長崎にはプルトニウム型の原爆が投下されました。
そして威力。長崎に投下されたファットマンの方が、広島のリトルボーイよりも圧倒的に強力でした。(関連記事:原爆は広島と長崎どっちがひどい?歴史が語る真実とは)
にもかかわらず、広島の方が死者数は多い。
その理由の一つが「地形」にあります。
長崎は山に囲まれた盆地地形であったため、山々が爆風の一部を遮断する役割を果たしました。
また、爆心地が市街中心部からややずれていたことも、被害の拡大を一定程度抑える要因となりました。
しかし、逆に言えば、そうした“偶然”がなければ、長崎の死者数は20万人を超えていたかもしれないのです。
原爆投下の第一目標は長崎ではなかった
小倉が第一目標だったという事実
一般に「長崎に原爆が落とされた」と聞くと、そこが最初から標的だったように感じられるかもしれません。
しかし事実は異なります。1945年8月9日、米軍の原爆投下作戦における第一目標は長崎ではなく、小倉市(現在の北九州市)でした。
この作戦に投入されたB-29爆撃機は6機。原爆を搭載した2機のB-29は、他の機体とともに硫黄島を経由し、九州南部から北上するルートを取っていました。
小倉には、当時の日本の主要軍需工場の一つである小倉陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)がありました。
この工場は、兵器・弾薬の生産と整備を行う重要拠点として、連合国側にとって戦略的にも高い優先度を持っていたのです。
そのため、米軍は小倉市を第一目標、長崎市を第二目標として飛行計画を立てました。
この「目標の優先順位」が後に、2つの都市の運命を大きく分けることになります。
小倉が攻撃された場合の被害想定
当時の小倉市(現在の北九州市)の人口はおよそ30万人。長崎と同程度、あるいはそれ以上の規模でした。
ただし、被害の広がりという点では、小倉の方がはるかに深刻だった可能性があります。
その理由の一つが「地形」です。
長崎は三方を山に囲まれた盆地構造ですが、小倉の市街地は、より開けた平野部に広がっており、周辺地域との連続性も高い地理でした。
熱線や爆風の到達範囲が広がりやすく、遮蔽物が少ないため、爆発による被害は周囲にまで及んだと推定されます。
小倉の市街地だけでなく、戸畑、若松、八幡、門司といった工業地域、さらには関門海峡を挟んで対岸に位置する山口県下関市にまで影響が及んでいた可能性が高いのです。
実際、当時の爆弾の威力と人口密度を考慮すると、仮に小倉に原爆が投下されていた場合、即死者数は30万人を超え、後障害などを含めた被害者数は40万人以上に達した可能性があると試算されています。
この数字は、あくまで推定に過ぎません。
しかしそれが、単なる空想ではないことは、長崎と広島の実際の被害データを見れば明らかです。
つまり、小倉に原爆が落ちていたら、現在の北九州市とその周辺が、全く異なる風景となっていた可能性すらあるのです。
小倉での熾烈な迎撃戦|B-29はなぜ長崎へ向かったのか
陸軍守備隊の決死の煙幕作戦
1945年8月9日午前9時44分、原爆を搭載したB-29爆撃機2機が小倉市の上空に到達しました。
しかし、米軍の乗員たちは目標地点をなかなか視認できませんでした。
その原因は、空一面に広がった濃密な煙でした。
前日の空襲による煙と、加えてこの日、小倉陸軍造兵廠に配置されていた守備隊が意図的に作り出した煙幕が空を覆っていたのです。
日本軍の高射砲はB-29の通常の高高度飛行には届きません。
しかし、爆撃のために高度を下げてくることが分かっていたため、守備隊はB-29が接近すると同時に、炸裂弾や煙幕弾を使って、視界を遮る作戦に出ました。
実際、彼らは弾薬の残量や精度を問わず、手持ちの火砲を次々に使用し、空を覆うように弾幕を展開しました。
それによって爆撃機の乗員たちは、爆撃目標の小倉造兵廠を視認することができず、攻撃のタイミングを逃していきます。
当時の米軍は、原爆の投下を「目視」で行う方針を採っており、レーダーや自動制御による投下は許されていませんでした。
したがって、視界が確保できないままでは任務を果たすことができなかったのです。
陸海軍の戦闘機が空を守った
状況はさらに緊迫します。
小倉上空での視界不良に業を煮やしたB-29が低空飛行に切り替えた直後、日本軍の戦闘機部隊が迎撃に向かいます。
陸軍の芦屋飛行場からは五式戦闘機、海軍の築城基地からは零戦を擁する第203航空隊が出撃。
合計10機以上の戦闘機が小倉の空へと向かいました。
当時、B-29は「空の要塞」と称され、上下左右すべてに機銃を備えた強力な航空機でした。
しかし、日本の戦闘機部隊はこれまでに数百機のB-29を撃墜、または損傷させた戦歴を誇っており、
この日も果敢に空中戦を仕掛けます。
連携と操縦技術に長けた日本側のパイロットは、防衛機銃を巧みに避け、B-29に緊張を強いる行動を続けました。
このような複合的な圧力──視界を奪う煙幕、対空砲火、そして迫り来る戦闘機──に直面したB-29の搭乗員たちは、最終的に小倉への投下を断念する決断を下すことになります。
小倉を断念せざるを得なかったB-29
米軍の作戦には、原爆投下に関して明確なルールが存在していました。
目標地点が視認できない場合、爆弾の投下は行わない。
そして、最初の目標が不可能であれば、第二目標へ向かう──。
小倉における45分におよぶ滞空・視認試行の末、B-29はこのルールに則って進路を変更します。
彼らが次に目指したのは、第二目標である長崎市でした。
小倉における防衛行動は、限られた時間と物資の中で行われたものでした。
それでも、その「時間稼ぎ」が、結果として原爆投下を防ぎ、約40万人とも推定される犠牲を回避するに至ったのです。
たった1つの都市の空で、軍民が一体となって行った抵抗が、都市の命運を分けた。
それは単なる偶然ではなく、明確な「行動の結果」でした。
長崎に原爆が落とされた本当の理由
雲に覆われた長崎と「奇跡の割れ目」
小倉での投下を断念したB-29は、予定通り第二目標の長崎へと進路を変更しました。
午前10時50分、長崎上空に到達します。
しかしそのとき、長崎の空は厚い積雲に覆われており、地上の様子はほとんど確認できませんでした。
ここで問題となったのは、米軍の原爆投下作戦における「目視投下」という原則です。
高度な自動誘導装置を使用せず、爆撃手が目視で目標を確認し、タイミングを見計らって手動で投下する──
それが当時の投下ルールでした。
積雲に覆われた空では、その「目標確認」ができない状態が続きます。
通常であれば、ここでも投下は断念される可能性が高かったと言えるでしょう。
ところがそのとき、分厚い雲に、偶然とも言える一時的な“割れ目”が生じました。
爆撃機の乗員がその隙間から地上を覗くと、長崎の市街地が確認できたのです。
この瞬間、爆撃手は即座に投下を決断。
午前11時1分、原爆が放たれました。
手動操作で放たれた22キロトンの爆弾
原爆「ファットマン」は、投下後約1分間の自由落下を経て、午前11時2分に長崎市松山町上空503メートルで空中炸裂しました。
その爆風、熱線、放射線の威力は凄まじく、爆心地にあった建物や人々は、一瞬で消し飛びました。
しかし爆心地は、米軍が本来狙っていた市街中心部から約3キロメートルずれていました。
これは、厚い雲による視界不良の中での「割れ目投下」が原因であり、結果として目標のズレが生じたのです。
このずれが、間接的に一部の地域にとっての“被害軽減”につながった可能性もあります。
仮に中心部に正確に命中していた場合、死傷者数はさらに増えていたと考えられています。
また、長崎の地形──山に囲まれた盆地構造も、爆風の拡散をある程度抑える効果がありました。
広島との違いは、こうした地形と爆心地の位置によって説明できます。
爆撃の決断はなぜ下されたのか
ここで改めて考えるべきは、「なぜ長崎では、最終的に投下が実行されたのか」という点です。
その背景には、いくつかの要素が重なっています。
まず、1つ目は「時間の制約」です。
B-29の航続距離には限りがあり、長時間の滞空や別目標への移動は燃料消費を伴います。
小倉での45分間の滞空の末に投下できなかった以上、次に失敗すれば、作戦自体が中止になる可能性がありました。
2つ目は「政治的・軍事的圧力」です。
当時、アメリカは原爆の実戦使用によって、日本に対する心理的な打撃と、戦争終結への圧力を最大限に引き上げたいと考えていました。
2発目の投下が中止されれば、「一度きりの兵器」で終わってしまうリスクもあったのです。
そして3つ目が、「偶然の割れ目」という予測不能な天候の変化です。
このタイミングが合致したことで、投下は実行に移されました。
すべてが計画通りに進んだわけではなく、さまざまな要素が絡み合い、結果として原爆は長崎に落とされることになった。
この点を理解することが、歴史を一面的に捉えないための鍵となります。
「原爆投下を事前に知っていた」は本当か?
無線のミスが導いた情報漏洩
「原爆投下は事前に知られていたのではないか?」──この疑問の背景には、あるエピソードがあります。
それは、米軍のB-29爆撃機の乗員による、偶発的な“通信の誤送信”でした。
長崎へ向かう途中、2機のB-29のうちの1機で、航法士が「現在地の確認」を求められた際、
内部通信(インターホン)と外部通信(無線)を取り違え、誤って無線で位置情報を発信してしまったのです。
この無線は、作戦からはぐれて迷走していた別のB-29機が偶然キャッチします。
その際、もう一機のパイロットが「チャック、いまどこにいる?」と応答。
これにより、B-29の現在地が電波上に浮上することになりました。
この短いやり取りが、偶然にも日本側の通信傍受部隊の耳に届きます。
鹿児島沖から長崎方面にかけて飛行中のB-29の存在を、通信傍受班が突き止めたのです。
この情報はただちに警戒本部へと送られ、長崎方面に警報が発せられることとなります。
つまり「日本側は原爆投下を事前に知っていた」という言説の根拠の一部は、実際には、こうした突発的な情報取得による「緊急対応」であったのです。
警報は再び鳴り、ラジオは叫び続けた
長崎では、午前10時過ぎ、一度出されていた空襲警報が解除されていました。
それは、小倉上空にB-29が現れたことが確認されたためであり、長崎への空襲リスクが下がったと判断されたからです。
しかし、先述の無線傍受情報を受けて、長崎市では再び空襲警報が発令されました。
さらに、軍と市が連携して、ラジオを通じて緊急の避難呼びかけが行われます。
「長崎市民は全員退避せよ。繰り返す、長崎市民は全員退避せよ。」
臨時ニュースは繰り返し、アナウンサーの声がラジオから流れました。
市民たちは再び防空壕へ向かい始め、職場や家庭で一時的な混乱が広がったと記録されています。
そして、そのラジオ放送が「全員退避……」と語りかけた、そのわずか数秒後──
午前11時2分、原爆は長崎の空で炸裂します。
その閃光と衝撃波が放送局を直撃し、アナウンサーの声は途中でぷつりと途絶え、以降は無変調となりました。
つまり、日本側はB-29の接近を察知し、警報を再発令し、放送まで行っていたのです。
それにもかかわらず、「警報は鳴らなかった」「何の対策もなかった」とする主張は、事実と異なります。
「情報を放置した」は明確な誤解
「大本営は無線をキャッチしていたが、黙殺した」
「長崎は、軍が見殺しにしたのだ」
こうした言説は、しばしば一部の出版物やメディアで繰り返されてきました。
しかし、実際の記録や証言を見ていくと、むしろ当時の関係者たちは限られた時間の中で、最大限の対応を取っていたことが分かります。
傍受した無線は、偶然の産物であり、事前にすべてを把握していたわけではありません。
しかし、それでも即座に防衛体制を再構築し、避難呼びかけを行い、最悪の事態を回避すべく動いた人々が確かに存在したのです。
それは、命を守るために最後まであきらめなかった現場の判断であり、行動でした。
こうした努力や苦悩を無視し、結果だけを取り上げて「知っていたのに動かなかった」と断定するのは、歴史を一面的にしか見ていない証拠であり、かえって事実をゆがめる危険があります。
戦争のかたちが変わる現代、私たちにできること
「超限戦」の時代に生きるということ
第二次世界大戦が終結してから、およそ80年が経ちました。
現代の戦争は、より見えにくい形をとります。
軍事力の行使だけではなく、経済制裁、情報操作、サイバー攻撃、法制度の悪用、文化的影響力──
こうした手段を駆使して相手国を内側から崩す戦略が重視されているのです。
中国人民解放軍の戦略文書では、これらを「超限戦(ちょうげんせん)」と呼び、軍事・外交・経済・テロ・心理戦を含めた、あらゆる手段を戦争に含める考え方が示されています。
つまり、戦争はすでに、誰にも気づかれないまま始まっている可能性がある。
現代に生きる私たちは、その前提を持って世界を見なければなりません。
情報・心理・法律までもが武器になる
かつての戦争では、爆弾や銃が戦争の象徴でした。
しかし現代では、情報が最大の武器となり得ます。
間違った情報を流すことで、世論を操作し、相手国の団結を崩す。
正確な歴史認識をゆがめることで、自国への信頼や誇りを失わせる。
さらには、相手国の法律や制度に介入し、法的な“外圧”を加えることで主権を侵害する──
こうした行為もまた、「戦争の一種」と見なされる時代です。
そのような時代にあって、私たち市民に問われるのは、「なにが事実なのかを、自分で考える力」です。
情報があふれる現代では、SNSやメディアの見出しだけを見て判断するのではなく、できる限り一次情報に近づき、自ら検証し、判断することが何より重要です。
真実を学ぶことが最大の自衛
では、私たちは何ができるのでしょうか。
戦争を直接止める力を持たない私たちにとって、有効な行動のひとつは、「真実を学び、伝えること」です。
過去に何があったのか。
なぜ、そうなったのか。
そこにどんな人の意思や行動があったのか。
それを知り、考え、自分の言葉で語れるようになることは、他者に振り回されないための“心の防衛力”となります。
小倉で原爆を阻止した軍の対応も、長崎で最後まで避難を呼びかけ続けた放送局の職員も、いずれも「行動した人々」でした。
それを今の私たちが正しく理解し、次の世代に語り継ぐこと。
それこそが、未来を守るための最も確実な「自衛手段」であり、静かで確かな“抵抗”なのかもしれません。
おわりに|最後にものを言うのは「底力」である
現代社会において、目に見える「力」や「支配力」が注目されがちです。
経済、軍事、外交、情報戦──それぞれの分野で優位に立つ国や組織が世界を動かしているようにも見えます。
しかし、このような力の背後にある構造を冷静に見つめると、一つの真理が浮かび上がってきます。
それは、「支配する」ということは、すなわち「奪うこと」に過ぎないということです。
奪うことで一時的に富や影響力を得ることはできます。
けれども、奪えるのは「いま、そこにあるもの」だけです。
まだ存在していない未来の価値、まだ誰も築いていない技術、まだ表れていない文化──
それらは、どんなに力を尽くしても、支配することも奪うこともできません。
たとえば、今の世界で最も富を生んでいるのは半導体産業です。
この分野は日進月歩であり、ほんの半年遅れるだけで技術は陳腐化してしまいます。
動画コンテンツ、AI、通信技術、ソフトウェア──どれもが日々進化しており、昨日の優位が今日の優位とは限りません。
このような時代において、真に必要なのは「底力」です。
底力とは、一時的な優位性ではなく、長期的に価値を生み出し続ける力。
文化、教育、誠実さ、勤勉さ、歴史への理解と継承──
それらが積み重なることでしか、未来は創られていきません。
あの日、原爆が投下され、都市が焼け、数えきれない命が奪われた日本。
それでも人々は立ち上がり、街を再建し、社会を築き直してきました。
それはまさに「建設の力」であり、底力のあらわれです。
支配によって得られるものは有限ですが、底力があれば、新たな価値を無限に生み出すことができる。
この国が持っている真の強さは、経済力や軍事力ではなく、幾度となく困難を乗り越えてきた人々の「積み重ね」にあります。
それは、日本が受け継いできた歴史、伝統、文化、そして誠意そのものです。
結局、最後に勝つのは、こうした目に見えない力なのです。
だからこそ私たちは、過去を正しく知り、誇りとともに未来を築いていかなければなりません。
そして信じたいのです──
たとえ夜がどれほど長くとも、陽はまた昇る。
お知らせ
この記事は2024/08/10投稿『8月9日は長崎に原爆が投下された日』のリニューアル版です。