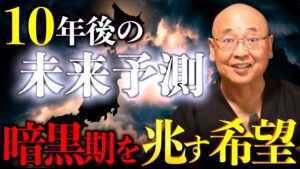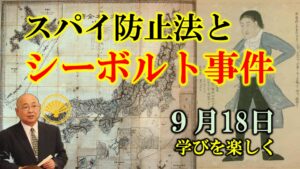神の時間は順序に縛られず、人の時間は直線的——この差を軸に、善悪と人格の分岐、予言の読み方、迫る転換期への備え(自助・共助・情報の選び方)を整理しました。
Ⅰ.神の時間と人の時間──“非連続”という視点
対談の出発点は「人間と神様の時間軸は違う」という日月神示の指摘でした。
人の時間は左から右へ直線的に進む感覚がありますが、神の時間は順序や距離に拘束されず、
「変化の連続そのもの」
が把握されると語りました。
過去・現在・未来が一列に並ぶのではなく、屋上から景色を俯瞰するように同時に見渡される、という比喩が示されます。
この違いは、記憶の扱いにも現れます。
幼少期の体験を思い出すとき、数十年の距離が一瞬で縮むように、心の世界には時間・空間の制約が緩む瞬間があります。
インナーチャイルドに向き合う実践も、その“非連続”の感覚を使うものです。
物理学でも時間の非連続性や複数軸の可能性が論じられますが、神示は先回りして同様の世界観を提示している、というのが今回の核でした。
ここから「預言(預けられた言葉)」の読み方にも踏み込みます。
本文の語尾や叙述の位置関係を丁寧に照合すると、神の側からは“すでに見えた結果”が先に語られ、人の側には“これから備えるべきこと”が後から届く場合がある、と整理されました。
順序が入れ替わって記されるゆえに、直線時間の前提で読むと誤解が生じます。
鍵は、「何が既了で、何が未了か」をテキストの調子から見抜き、同一の出来事に対する別位相の呼びかけとして重ね合わせることにあります。
Ⅱ.成長の分岐とリンク──人格の磨き、善悪の相互作用
次に提示されたのが、人生の発達段階を“分岐する線”として描いた図のイメージです。
赤子の段では大差がなくとも、選択が重なると上方(徳を磨く道)と下方(利己や暴力性に傾く道)に枝分かれします。
ここで重要なのが、「どの層とリンクするか」です。
喜びを人と分かち合う“上の神々”と共鳴すれば、人格の精度が上がりやすく、反対に“割れよし”(自分さえ良ければよい)的な存在と結べば、短期的な利得は得られても長期の破綻を招きます。
善と悪は単純な二項対立ではなく、相互作用の中で互いを研ぎ澄ませる面もあります。
長い歴史の中で、人は「足の速さ→腕力→見た目・経済力→成熟した優しさ」という価値の推移を経験してきました。
個体発生が系統発生を反映するように、個人の成長段階も社会の価値転換を映し出します。
この観点に立つと、分岐は“誰もが持つ多重の可能性”であり、どの層と結び直すかは常に開かれている、と結論づけられました。
ただし、日月神示にいう「大掃除」の段階では、割れよし的な層が大きく淘汰され、時間の矢印そのものが“上向き(神人一体)”に折れ曲がる局面が到来すると読み解かれます。
善悪の緊張で横方向に保たれてきた均衡が、上方ベクトルを強める転位へと移る。
ここでは、信念や作法(プロトコル)に基づく結節が重視され、個の成熟と共同体の成熟が同時進行する姿が展望されました。
Ⅲ.「大峠」の読み解きと現実への備え──自助・共助の設計
転換期のキーワードとして語られたのが「峠」です。
医療の比喩では急性期を越えて安定に向かう局面ですが、神示の「大峠」は一段と峻烈で、価値の総点検と選別が伴う段階だと指摘されました。
政治の場では、保守系の選択肢が増えた一方で、大局の進路は惰性で直進しており、岐路でのハンドル操作が遅れるとガードレールに擦れて落ちかねない——そんな危機感が共有されます。
社会リスクの一例として、供給網に潜む“食の安全”が挙がりました。
具体名の列挙は避けつつも、冷凍・加工食品の調達構造や海外報道の断片が示唆する課題に注意を促し、安価・大量供給の裏側を点検する視点が必要だと述べました。
情報空間では、主要プラットフォームに依存しすぎる脆弱性にも触れ、発信の工夫(言語・体裁・媒体の分散)を含む“情報BCP”の発想を紹介しました。
では、何を備えるのか。
まず、公助一辺倒の期待を下げ、自助・共助の比重を上げること。
水・食料のローリングストック、現金小口、連絡手段の多重化、地域単位の助け合いプロトコルづくり(連絡網、役割分担、避難・見守り)など、当たり前のことを当たり前にやり切る設計です。
加えて、価値観の面で“恐怖で締める”仕組みから“作法でつなぐ”仕組みへ——命令ではなく約束、中央集権ではなく相互接続という方向に舵を切る必要があると整理しました。
読み解きの技法としては、
①テキストの位相(既了/未了)を語尾と文脈で判定、
②現実の指標(政治・経済・供給網・災害リスク)と相互照合、
③感情的反応より作法的行動へ落とす、
の三段を提案。神の時間の“非連続”を人の側で扱うために、段取りと合意形成のプロトコルに翻訳して実践する、という姿勢を強調しました。
総じて、本対談は「時間の違いをめぐる思索」から始まり、「人格の分岐とリンクの実践」、「転換期の読み解きと備え」という三層で構成されています。
非連続な神の時間を畏れつつ、人の時間の現実に足を置き、恐怖ではなく作法で結び直す。大切なのは、ドラマチックな予言合戦ではなく、日々の備えと、互いを支える手順を淡々と整えることだと結びました。
【所感】
時間は一本の線ではなく、実は“平面”として存在しているのではないか。
3次元(縦・横・高さ)を y 軸にまとめれば、x 軸の「時間」に沿って物体は変化していく。これが通常の4次元世界の理解である。
ところが5次元になると、4次元まですべてを y 軸にまとめたとき、x 軸上にもう一本の「時間」が現れる。すると、x と y の二つの時間軸が織りなす“時間の平面”が立ち上がる。
そこでは時間はただ一方向に流れるのではなく、前後に行きつ戻りつ、あるいは停止しながら、自由に線を描くことができる。4次元から見れば不連続に見える現象も、この平面上の運動としては自然に理解できる。
神の時間が「非連続」「同時性」を帯びるのは、この“時間の平野”に立脚しているからではないか——そんな風に考えている。