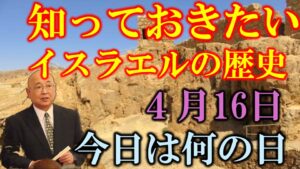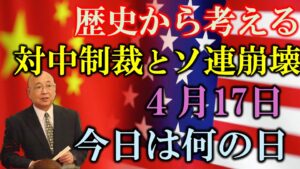今回は、坂東忠信氏と共に「大祓詞」を日月神示の視点から読み解きます。なぜ祝詞には主語がないのか、日本人と神々の本質的な関係、そして人間の魂の成長や天皇の意味まで、古代から続く祈りの本質を明らかにします。
◉ 大祓詞の成り立ちと主語の不在
大祓詞は、日本最古級の祓い詞として、全国の神社で今も唱えられている重要な祝詞です。その文言には主語がはっきり書かれておらず、誰が何をしたのかが曖昧な部分が多いという特徴があります。
この主語の不在は、神話的世界観の中で神々が「大宇宙」そのものとして描かれているためであり、誰か一人や一柱の神に限定できない“万物一体”という日本古来の精神性を反映しています。
たとえば、天照大神が天孫・瓊瓊杵尊を「豊葦原瑞穂国」に降臨させる場面も、祝詞文中では主語が省略されています。
そのため、単に文面を追うだけでは、神話の背景や語り手が何を意図しているのか分かりづらいのです。
◉ 明治以降の祝詞改変と“削除された部分”
また、明治維新以降、近代国家化の過程で「大祓詞」から一部の文言が削除されている事実も紹介されました。
たとえば「天つ罪」や「国つ罪」など、一見して現代的な倫理や道徳観にそぐわないと判断された箇所がカットされています。
しかし元々は社会秩序や自然との関係、地域社会の善悪を明確にするために重要な意味を持っていたもので、これらの省略は日本人の精神性を狭めてしまった可能性があります。
地方によって伝わる祝詞にもなまりや言葉の違いがあり、かつては地域ごとの神事の多様性も大切にされていました。こうした「多様性と統一」のバランスが、神道本来の柔軟性であり、日本文化の強みでもあることが語られました。
◉ 「日月神示」と祝詞の本質
坂東氏は警察官時代に様々な宗教や神話に触れる中で、「日月神示」に出会い、そこから日本神道や大祓詞の奥深い意義を再発見します。「日月神示」には、「祝詞はただ読むものではなく、心を“乗せて”祈ることで初めて意味を持つ」という趣旨の記述があります。
現代の神職や参拝者の中には、「祝詞はただ声に出して唱えればいい」と考える人も増えていますが、本来は“意(こころ)を込めて祈る”ことこそが大切だと、神示は警告しています。
また、主語が抜けているのは「祈りの対象が“宇宙全体”である」という日本独自の宇宙観、世界観を示していると解説されました。
◉ 神話から読み解く人間の魂と天皇の役割
話題はさらに深まり、「天孫降臨」にまつわる神話の構造や、天皇の存在意義、そして人間の魂についての考察へと及びます。
祝詞や神話においては、人間もまた“神が宿る存在”であり、肉体は魂の「宮(みや)」=住処とされること、さらには日本人全体が天皇を“最高神官”として中心にいただく共同体意識を持っていることが指摘されました。
魂は何度も生まれ変わりながら磨かれていき、やがて神に近づく。天皇はそうした最も高貴な魂を持つ者として歴代続いてきたという解釈が紹介され、
人間と神々、そして自然と社会が一体となった世界観が、日本の祓い詞や神話に深く根付いていることが語られました。
◉ 大祓詞に込められた普遍的な祈り
大祓詞の最大の特徴は、「読まれる側」「祈る側」「聞く神々」「万物」すべてが等しく祓われ、浄められるという普遍的な祈りにあります。
これは「分離」や「二元論」に陥るのではなく、すべてを包み込む“大きな和”を目指す日本独自の精神性の現れであり、その本質は今もなお私たちの心の奥深くに息づいています。
最後に、祓い詞の意味をただ言葉の上で理解するだけではなく、心を込めて“祈ること”こそが現代人にも必要だと強調されました。
◉ まとめ──現代に生かす「大祓詞」の知恵
動画では、こうした祝詞や神話が、単なる伝統ではなく、「現代の日本人が生きるための知恵」として活用できること。
“我々は生きているのではなく、生かされている”という謙虚な感覚と、魂を高め合い、和の精神で日々を歩むことの大切さが語られています。
【参考】
大祓詞(おほはらへのことば)
高天原(たかまのはら)に神留(かむづま)り坐(ま)す。
皇(すめら)が親(む)つ神(かむ)漏(ろ)岐(ぎ)
神(かむ)漏(ろ)美(み)の命(みこと)以もちて
八百萬󠄄神(やほよろずのかみ)等(たち)を神(かむ)集(つど)へに集(つど)へ賜(たま)ひ
神議(かむはかり)に議(はか)り賜(たま)ひて
我(あ)が皇御孫(すめみま)の命(みこと)は
豐葦󠄂原水穗國(とよあしはらのみづほのくに)を
安國(やすくに)と平󠄁(たひらけ)く知(しろし)食󠄁(め)せと事依(ことよさ)し奉まつりき
此(か)く依(よさ)し奉まつりし國中(くぬち)に
荒󠄄振(あらぶる)神等(かみたち)をば 神(かむ)問(と)はしに問はし賜(たま)ひ
神掃(かむはらひ)に掃(はらひ)賜(たま)ひて
語問(こととひ)し磐根(いはね)樹根(き)ね立(た)ち
草󠄂(くさ)の片葉󠄂(かきは)をも語(こと)止(や)めて
天(あめ)の磐座放(いはくらはな)ち
天(あめ)の八重雲(やへぐも)を伊頭千別(いつのちわき)に千別(ちわ)きて
天降(あまくだ)し依(よ)さし奉まつりき
此(かく)依(よ)さし奉まつりし四方(よも)の國中(くになか)と
大倭(おほやまと)日高見國(ひだかみのくに)を安國(やすくに)と定(さだ)め奉まつりて
下(した)つ磐根(いはね)に宮柱(みやばしら)太敷(ふとしき)立(た)て
高天原(たかまのはら)に千木(ちぎ)高(たか)知(し)りて
皇御孫(すめみま)の命(みこと)の瑞(みづ)の御殿(みあらか)仕(つか)へ奉まつりて
天(あめ)の御蔭(みかげ)、日(ひ)の御蔭(みかげ)と隱(かくり)坐(ま)して
安國(やすくに)と平󠄁(たひらけ)く知(しろし)食󠄁(め)さむ
國中(くぬち)に成(なり)出(い)でむ
天(あめ)の益人(ますひと)等(ら)が
過󠄁(あやまち)犯(をかし)けむ種種(くさぐさ)の罪事(つみごと)は
天(あま)つ罪つみ 國(くに)つ罪(つみ)
許許太久(ここだく)の罪(つみ)出いでむ
此(か)く出(い)でば
天(あま)つ宮事(みやごと)以(も)ちて
天(あま)つ金木(かなぎ)を本(もと)打(う)ち切(き)り
末(すゑ)打(うち)斷(たち)て
千座(ちくら)の置座(おきくら)に置(お)き足(た)らはして
天(あま)つ菅麻󠄁(すが)そを本(もと)刈(か)り斷(た)ち
末(すゑ)刈(か)り切(きり)て
八針(やはり)に取(と)り辟(さき)て
天(あま)つ祝詞(のりと)の太祝詞(ふとのりと)事(ごと)を宣(の)れ
此(かく)宣(の)らば
天(あま)つ神(かみ)は天(あめ)の磐門(いはと)を押(お)し披(ひら)きて
天(あめ)の八重(やへ)雲(ぐも)を伊頭(いつ)の千別(ちわき)に千別(ちわき)て
聞(きこ)し食󠄁(め)さむ
國(くに)つ神(かみ)は高山(たかやま)の末(すゑ)
短山(ひきやま)の末(すゑ)に上(のぼ)り坐(ま)して
高山(たかやま)の伊褒理(いほり)
短山(ひきやま)の伊褒理(いほり)を搔(か)き別(わ)けて聞(き)こし食󠄁(め)さむ
此(かく)聞(き)こし食󠄁(め)してば
罪(つみ)と云(い)ふ罪(つみは)在(あら)じと
科(しな)戶(ど)の風(かぜ)の天(あめ)の八重雲(やへぐも)を吹(ふ)き放(はなつ)事の如(ごと)く
朝󠄁(あした)の御霧(みぎり)
夕(ゆふべ)の御霧(みぎり)を
朝󠄁風(あさかぜ) 夕風(ゆふかぜ)の吹(ふ)き拂(はら)ふ事(こと)の如(ごと)く
大津邊(おほつべ)に居(を)る大船(おほふね)を
舳解(へとき)放(はな)ち
艫(とも)解(とき)放(はな)ちて
大海原(おほうなばら)に押(お)し放(はな)つ事(こと)の如(ごと)く
彼方(をちかた)の繁(しげ)木(き)が本(もと)を
燒鎌󠄁(やきがま)の敏鎌󠄁(とがま)以(もち)て
打(う)ち掃(はら)ふ事(こと)の如(ごと)く
遺󠄁(のこ)る罪(つみ)は在(あら)じと
祓(はら)へ給(たま)ひ淸(きよ)め給(たま)ふ事(こと)を
高山(たかやま)の末(す)ゑ 短山(ひきやま)の末(すゑ)より
佐久那󠄁太理(さくなだり)に落(お)ち多岐(たぎ)つ
速󠄁川(はやかは)の瀨(せ)に坐(ま)す瀨織津比賣(せおりつひめ)と云いふ神(かみ)
大海原(おほうなばら)に持もち出いでなむ
此(かく)持(もち)出(い)で往いなば
荒󠄄潮󠄀(あらしほ)の潮󠄀(しほ)の八百道󠄁(やほぢ)の八潮󠄀道󠄁(やしほぢ)の潮󠄀(しほ)の八百會(やほあひ)に坐(ま)す速󠄁開都比賣(はやあきつひめ)と云(い)ふ神(かみ)
持(もち)加加呑(かかのみて)む
此(かく)加加呑(かかのみて)ば
氣吹戶(いぶきど)に坐(ま)す氣吹戶主(いぶきどぬし)と云(い)ふ神(かみ)
根國(ねのくに) 底國(そこのくに)に氣吹(いぶき)放(はなち)てむ
此(かく)氣吹(いぶき)放(はな)ちてば
根國(ねのくに) 底國(そこのくに)に坐(ま)す速󠄁佐須良比賣(はやさすらひめ)と云(い)ふ神(かみ)
持佐須良(もちさすらひ)失(うしなひ)てむ
此(かく)佐須良(さすらひ)失(うし)なひてば
罪(つみ)と云(いふ)罪(つみ)は在(あら)じと
祓(はら)へ給(たま)ひ淸(きよ)め給(たまふ)事(こと)を
天神(あまつかみ)、國神(くにつかみ)、八百萬󠄄神(やほよろづのかみ)等共(たち)ともに
聞(きこし)食󠄁(め)せと白(まを)す