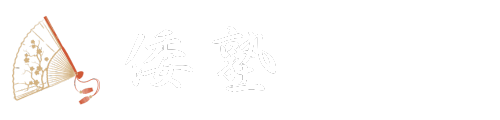「曲者でございます。お出会えそうらえ!」
よく時代劇などで、大奥のお女中たちが大薙刀を手にして屋内を駆け回る姿が描写されます。江戸時代、武家の女性たちに大人気だったのが薙刀です。薙刀は初心者でも、剣道の有段者を手もなくやっつけることがでるという、実はたいへん強い武器です。そんな薙刀を江戸時代の武家の娘たちが愛した原因となったのが、白拍子であり薙刀の名手であった静御前でした。
ある日のことです。後白河法皇に招かれて参内した静御前は、「おもてをあげよ」と言われて顔をあげました。
「こちらに居るのがの、平家を打ち破った源義経じゃ。義経殿、こちらが都一の白拍子の静御前じゃ。静はの、舞で雨乞いができる都一の白拍子じゃ」
「はっ」と法皇に挨拶をして顔をあげて静御前を見る源義経、
「この御方が義経様……」と義経を見る静御前。
ひと目会ったその日から、二人の心は固く結ばれてしまいます。
静御前のあまりの美しさと人柄の良さに、すっかり夢中になってしまった義経は、鎌倉にいる兄の源頼朝から、「すぐに鎌倉に帰るように」との矢のような催促を受けても、都を離れようとしませんでした。何度使者を送っても鎌倉に帰ろうとしない義経に、ついに頼朝は「義経謀反!」の疑いをかけ、鎌倉から捕縛の兵を派遣しました。
頼朝が義経に「帰れ」と命じたことには理由があります。もともと源平の戦は、新田の開墾百姓であった武士たちが私田を守るための戦いです。平家も武家ではあったのですが、平清盛の時代にすっかり朝廷に取り込まれ、そうなると新田の開墾百姓である武士たちにとっては、自分たちの田が貴族の荘園に組み込まれてしまうのではないかという危機意識となったのです。ですから頼朝は都から遠く離れた鎌倉に、武家のためだけの政権を築こうとしていました。ところが平家を討ち果たした弟の義経が都にいて朝廷に組み込まれてしまったら、なんのために鎌倉で政権を築こうとしているのか、意味がなくなってしまう。兄としては、弟の義経の幸せは第一の願いとしたいところです。けれど政治的にそれを許すことはできなかったのです。
捕縛の兵を送られたと知った義経は、兄と戦うことを選択します。岩手県にある奥州平泉まで行けば、そこで兵を整えることができる。義経は近習である弁慶らとともに、静御前を連れて船で京の都を出発します。ところが大阪湾を出たところで、船が難破してしまいます。嵐の中でもしっかりと手を握り合って離さなかった二人です。ようやく陸にたどり着いた一行は、船をあきらめ、陸路で奥州へ向かうことにしました。
冬の寒い朝のことでした。あたり一面に雪が降り積もっていました。吉水院という僧坊から、大峰山(おおみねさん)の入り口に差し掛かった一行は、その山道の入り口に「女人禁制」の碑を見ます。大峰山は神聖な山で、女性は立ち入ることができないとされていたのです。
誰も見ていないのだから良いではないかというのは、現代人の思考です。誰も観ていなくてもお天道様が見ている。女の身である静御前を連れたままで、ご禁制の山に入ることはできません。神仏との約束事は破ることはできない。
「静(しづ)、ここからなら、都もさほど遠くない。
そなたは都の生まれ。
必ず戻るから、都に帰って待っていておくれ」
静御前は、「私は義経さまの子を身ごもっています」と打ちあけました。そして、「別れるくらいならいっそ、ここで殺してください」と涙ぐみました。このときの静御前は鎧をつけ大薙刀を手にした男装です。
義経は泣いている静御前に、いつも自分が使っている手鏡を、そっと握らせまました。
「静、これを私だと思って使っておくれ。
そして私の前でもう一度、あの舞を見せておくれ」
静御前は、山の中で舞いました。
見るとても嬉しくもなします鏡
恋しき人の影を止めねば
「鏡など見たって嬉しくありません。なぜなら鏡は愛するあなたの姿を映してくれないからです……」
雪の山道を登っていく義経の一行。その姿を、いつまでも見送り続ける静御前。一行の姿が見えなくなった山道には、義経たちの足跡が、転々と、ずっと向こうのほうまで続いていました。文治元年(一一八五)十一月のことです。
二名の小物を連れて山を下ると、山の裾(すそ)から、大勢が山狩りに登ってくる声が聞こえました。静御前は荷を解き、「お前たち、これまでありがとう。これは少ないけれど、とっておいておくれ」と小物たちに荷役の代金を渡しました。
「静様、おひとりでは危のうございます」
「鎌倉方が村人たちを動員しての山狩りです。とうてい逃げおおせるものではありませぬ。私は大丈夫です。むしろお前たちに咎(とが)がおよぶようなことがあってはなりませぬ」
静御前は、鎌倉方に捕縛され、麓(ふもと)の村で取り調べを受けることになりました。けれど、静御前は凛(りん)として断じて口を割らない。やむなく静御前の身は、鎌倉まで護送されました。厳しい取り調べは鎌倉でも続きました。
「義経はどこに向かったのか。どのルートで逃亡しているのか」
何も言わない静御前に、鎌倉でもなすすべもなく、そのまま静御前は鎌倉で幽閉されました。
年が明けて四月八日、鎌倉では、源頼朝臨席での大花見会が鶴岡八幡宮で行われることになりました。美しい桜に、美しい女性。しかも静御前は都一の舞の名手です。頼朝は静御前に、花見の席での舞の披露を命じました。「命じた」のです。けれど静御前にしてみれば、大好きな義経様の敵の前で舞わされるわけです。
「私はもう二度と舞うまいと心に誓いました。今さら病気のためと申し上げてお断りしたり、わが身の不遇を理由とすることはできません。けれど義経様の妻として、この舞台に出るのは、恥辱です!」
頼朝の妻の北条政子が言いました。
「天下の舞の名手がたまたまこの地にいるのに、その芸を見ないのは残念なこと。舞は八幡大菩薩にご奉納するものです。どのような状況であれ、神に仕える白拍子がこれを断ることはできませぬ」
当日となりました。静御前は着替えを済ませて舞台にあがりました。会場はなみいる歴戦の鎌倉御家人たちで埋め尽くされています。その御家人たちは、夫の義経の追手たちです。静御前は舞台で一礼して扇を手にとりました。そして舞を歌いながら舞い始めました。曲目は「しんむしょう」という謡曲です。
素晴らしい声、そして素晴らしい舞です。けれど何かが足りません。続けて静御前は「君が代」を舞いました。けれどやはり、何かが足りません。ちなみに「君が代」を軍国主義ソングのように思おっしゃる方がいますが、大東亜戦争よりも八百年以上前に、静御前がこうして舞った歌でもあります。
およそプロの歌や舞というものは、舞台に立って一声発した瞬間、あるいは舞を舞い始めた瞬間から、観客の心を惹き付けてしまうものです。ところが・・・。
「なんだ、都一とか言いながら、この程度か?」
「情けない。工藤祐経の鼓がよくないのか?それとも静御前がたいしたことないのか」
会場がざわつきました。敵将の中にたったひとりでいる静御前にとって、そのざわめきは、まるで地獄の牛頭馬頭たちのうなり声のようにさえ聞こえたことでしょう。普通ならその恐怖は、手足が震えて立つことさえできなくなるほどです。
二曲を舞い終わった静御前は、床に手をついて礼をしたまま、じっと動かなくなりました。
「なんだ、どうしたんだ」
会場のざわめきが大きくなりました。それでも静御前は動きません。この時、御前は何を思っていたのでしょう。遠く、離ればなれになった愛する義経の面影でしょうか。このまま殺されるかもしれない我が身のことでしょうか。
「二度と会うことのできない義経さま。
もうすぐ殺される我が身なら、これが生涯最後の舞になるかもしれない。
会いたい、逢いたい、もういちど義経様に会いたい……」
このとき静御前の脳裏には、愛する義経の姿が、はっきりと浮かんでいたのかもしれません。『義経記』はこのくだりで、次のように書いています。
「詮ずる所敵の前の舞ぞかし。思ふ事を歌はばやと思ひて」
(どうせ敵の前じゃないか。いっそのこと、思うことを歌ってやろうと思って)
静御前は、ゆっくりと、本当にゆっくり立ち上がりました。なにが起こるのでしょう。それまでざわついていた鎌倉武士たちが、静まりかえっていきました。そして、しわぶきひとつ聞こえない静寂が訪れた時、静御前が手にした扇を、そっと広げました。そして歌い始めました。
しずやしずしずのをだまき繰り返し
昔を今になすよしもがな
吉野山峰の白雪踏み分けて
入りにし人の跡ぞ恋しき
「いつも私を、静、静、苧環(おだまき)の花のように美しい静と呼んでくださった義経さま。幸せだったあの時に戻りたいわ。吉野のお山で、雪を踏み分けながら山の彼方に去って行かれた義経さま。あとに残されたあの時の義経さまの足跡が、今も愛(いと)しくてたまりません……」
歌いながら、舞う。
舞いながら歌う。
美しい。あまりにも美しい。
場内にいた坂東武者たちは、あまりのその舞の美しさに、呆然として声も出ません。その姿は、まさに神が舞っているかのようであったと伝えられています。
歌の中で静御前は、紫色の苧環(おだまき)の花にたとえられました。背景となる鶴岡八幡宮は真っ赤な社殿、周囲はは桜色の満開の桜花、空には澄み切った真っ青な空に、白い雲が浮かんでいます。その中で、美しい静御前が歌い、舞う。このようにして物語を立体的な総天然色の世界として読み手にイメージさせるのが日本の古典文学の特徴です。
静御前が舞い終えました。扇子を閉じ、舞台の真ん中に座り、そして頭(こうべ)を垂れました。会場は静まり返っています。静御前が愛する人を思って舞ったのです。どれだけ澄んだ舞だったことでしょう。どれだけ美しい舞であったことでしょう。しかも舞台は敵の武将たちのど真ん中。そこで静御前は、女一人で戦いを挑んだのです。
この静寂を破ったのは頼朝でした。
「ここは鶴岡八幡である。その神前で舞う以上、鎌倉を讃える歌を舞うべきである。
にもかかわらず、謀叛人である義経を恋する歌を歌うとは不届き至極!」
日頃冷静な頼朝が怒りをあらわにされました。このままでは静御前は、即時捕縛されて死罪となるかもしれない。会場に緊張が走ったとき、頼朝の妻の北条政子がいいました。
「将軍様、私には彼女の気持ちがよくわかります。
私も同じ立場であれば、静御前と同じ振る舞いをしたことでしょう」
「敵将の子を生かしておけば、のちに命取りとなるであろう。
そのことは自分が一番よく知っている。生まれてくる子が男なら殺せ」
この時、静御前は義経の子を身ごもっていました。妊娠六カ月です。北条政子が言いました。
「では、生まれてくる子が女子ならば、母子ともに生かしてくださいませ」
同じ女として、政子のせめてもの心遣いです。頼朝は、これには、「ならばそのようにせよ」と言いました。
七月二十九日、静御前は出産しました。男の子でした。その日のうちに頼朝の命を受けた安達清常(あだちきよつね)が、静御前のもとにやって来ました。お腹を痛めた、愛する人の子です。静御前は子を衣にまとい抱き伏して、かたくなに子の引き渡しを拒みました。数刻のやり取りのあと、安達清常らはあきらめて、いったん引きました。安心した静御前は疲れて寝入ってしまう。初産を終えたばかりなのです。気力も体力も限界だったことでしょう。けれど御前が寝入ったすきに、静御前の母の磯禅尼が赤子を取り上げ、安達清常に渡してしまいました。子を受け取った安達清常らは、その日のうちに子を由比ヶ浜の海に浸けて殺し、遺体もそのまま海に流してしまいました。
と、義経記に描かれた物語はここまでです。けれど我が国の古典文学には、「いちばん重要なことは隠す」というなわらしがあります。お気づきいただけましたでしょうか。実は安達清常は赤子を殺していないのです。
安達清常は武家の「近習の道」を開いた男として知られる人物です。「近習」とは、土地持ちの御家人ではありません。また単なる「配下」《部下のこと》でもありません。上役の考えを「察して、責任を持って、自己の判断で行動する」のが「近習」です。そしてそんな近習が、土地がなくても才覚と努力で御家人となる道を開いたの最初の人物が安達清常です。
ただ赤子を殺すだけなら、小物を派遣すれば足りるのです。けれど頼朝が、近習のなかの近習、最も信頼できる安達清常を派遣したのは、「清常なら、この問題をきちんと処理してくれる」という期待があったからです。そしてそういう人材こそが、幕府の官吏としてふさわしいとされ、そうであればなおのこと、御家人たちは、さらにもっと深く察して行動できる力量が求められるようになっていったのです。ここが他所の国と日本の武士文化の異なる大事なところです。命令されたからと言って、何の感情もなく、ただ人を殺せるような痴れ者は、鎌倉武士のなかにはひとりもいない。そう断言できるだけの武家文化を、頼朝は構築したのです。だからこそ、江戸時代に至っても、男子が戦慄する武士の模範的姿は、常に鎌倉武士とされました。
そうした背景をもとに考えてみてください。いかなる理由があれ、生まれたばかりの赤子を殺すのはおよそ武士として恥ずべきことです。だから由比ヶ浜に流して遺体が見つからないことにしたのです。安達清常は、赤子を家に連れ帰って乳母を雇って子を育てました。そして静御前が産褥期間を終えて鎌倉を去るとき、峠で静御前を待ちました。
坂の下の方から、静御前と、その母の磯禅尼が歩いてきました。我が子が殺された、しかも信じる母によって、我が子が奪われ殺された。そう思い込んでいる静御前です。歩いてくる姿は暗く沈み、並んだ母との間に言葉のやりとりもありません。
坂の上で馬を降りて待つ安達清常のわきを通り過ぎようとした静御前を、清常が呼び止めました。
「静殿、こちらを通られると思い、お待ち申しておりました」
けれど目も合わせようとしない静御前に、清常は「おい!これへ」と馬の後ろにいる女性に声をかけました。その女性が、赤ちゃんを抱いています。
(私の子も、生きていればこれくらいになったろうか)
意識の片隅で、なんとなく目線を向けた静御前に、清常が声をかけます。
「ささ、抱いてやってください。ほら、わ子や、母君ですぞ。
静殿、ささ若君ですぞ」
静御前には、まだ事態が飲み込めません。けれど、母というのは不思議なものです。何十人も似たような赤ちゃんがいても、わが子を瞬時に見分けます。このときの静御前もそうでした。静御前は、母を見ました。母の磯禅尼は、にこやかに微笑み、静御前を見ながら、大きくうなづきました。
胸に抱いた赤子の重み。
「生きていた。和子だ。生きていた!」
赤ちゃんを抱きながら、静御前の目から大粒の涙がこぼれ落ちました。そして静御前の頭のなかで、すべてがつながりました。母の磯禅尼は、清常を武士と信じて赤子を渡したのです。祖母にとって孫というのは、我が子以上にかわいいものです。孫が殺されるとわかって他人に手渡せるような祖母は、我が日本にはひとりもいない。見れば、笑顔で立っている髭面の安達清常も、こうしてみれば清々しい良い男です。
その後の静御前の足取りは、母の磯禅尼、生まれた子も合わせて、歴史からまったく消えています。そして何故か不思議なことに、その後の静御前ゆかりの地なるものが、全国各地にあります。その後の静御前の行方が、全国に散らばっていて本当のことがわからないのは、むしろ「そのように工作した」ということで、実は静御前は子を連れて、母の磯禅尼とともに大陸に渡ったのかもしれません。そしていまや偉大なチンギス・ハーンとなった義経と、大陸で結ばれたのかもしれません。
それが静御前にとって幸せなことであったかまではわかりません。大陸での夫は、諸国と血を結ぶため、世界中の王族から献上された後宮の女性たちに日々、子種を授けなければなりません。それは大ハーンの勤めであったとはいえ、そんな後宮を抱える義経に嫉妬もあったことでしょう。女性である静御前にしてみれば、心中必ずしもおだやかではななかったかもしれません。
ちなみにジンギスカンの第一后は、ジンギスカンより1歳年上のボルテです。そのボルテの出身はキャト族とされています。キャトは、もしかすると京都のことかもしれない。またボルテはジンギスカンの「ウジン」と呼ばれていたという記録があります。これは夫人を意味する単語なのだそうです。
そのボルテの息子がオゴデイ、つまりモンゴル帝国の二代目皇帝です。なんだかありそうな話ですよね。
ただ静御前のことを思うとき、男女のことはあまりよくわからないのですが、どんなに巨大な富を手に入れたとしても、結ばれたいと願いつつ結ばれないことのほうが、もしかしたら幸せであったということも、世の中にはあるのかもしれません。
ちなみに戦前戦中までは、この「チンギス・ハーン、日本人の源義経説」は、モンゴルの人たちにたいへん歓迎された説であったのだそうです。
ところが近年では、そのようなことを言うと、モンゴルの人たちは逆に怒り出すそうです。
なぜかというと、そこに文化の違いがあります。
遊牧民族であるモンゴル人たちは、とにもかくにも「強い」ことが男性のリーダーに求められます。
そして強ければ、何をやっても許される。そういう濃厚な文化を持っています。
来日にした朝青龍などが、横綱になりながら、ある意味傍若無人なのも、強い者は何をやっても許されるというモンゴル族の文化が根底にあるからです。(このあたりの説は宮脇淳子先生の『モンゴル力士はなぜ嫌われるのか──日本人のためのモンゴル学』に依拠しています。ちなみに宮脇先生は義経説には反対です。)
要するに戦前の日本は、世界的に見ても「強い国」だったから、モンゴル族から尊敬されたし、自分たちが日本人、源義経の子孫であると言われると、ものすごく彼らは喜んだのです。
ところがモンゴル人たちからみたとき、戦後の日本は「腰抜けチキン」です。そんな腰抜けに、自分たちの祖先のチンギス・ハーンと血がつながっていたなどとは、口が裂けても言われたくない!
と、そういうことなのです。
我々日本人は、すこしは考えなければなりませんよね。