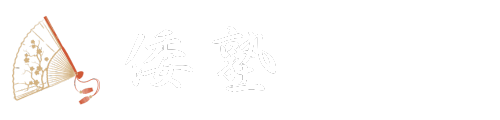「宋は蒙古を軽く見て、だらだらと交渉を続けていました。
そしてその間に元の大軍によって侵略され、国をなくしてしまいました」と、日本に禅宗を伝えた宋の僧侶の蘭渓道隆が言いました。また蘭渓道隆の後継者である無学祖元も言いました。
「莫煩悩(ばくぼんのう)です」
これは「あれこれ考えずに正しいと思うことをやりとおしなさい」という意味です。こうして幕府の執権、北条時宗の意思は固まりました。そしてついに執権の命令が鎌倉御家人たちに下りました。
「蒙古軍を制圧せよ!」
東北地方の山間部に、「モッコ」という言葉があります。「モッコ」というのは、ふるくから“この世の中で一番怖いもの”とされるもので、「何だかわからないけれども、とにかく一番怖いものなの」だそうです。その「モッコ」は、実は蒙古のことだといわれています。元寇の恐怖が、東北の山の中で、いまでもこのような形で語り継がれています。それほどまでに蒙古襲来は、鎌倉時代の恐怖のできごとだったのです。
一二六八年、高麗の使いによって元の大帝国の皇帝フビライからの書簡が九州の太宰府にもたらされました。そこには次のように書いてありました。
「天に守られている大蒙古国の皇帝から日本国王にこの手紙を送る。
昔から国境が接している隣国同士は、たとえ小国であっても貿易や人の行きなど、互いに仲良くすることに努めてきた。まして大蒙古皇帝は天からの命によって大領土を支配してきたものであり、はるか遠方の国々も代々の皇帝を恐れうやまって家来になっている。例えば私が皇帝になってからも、高麗が蒙古に降伏して家来の国となり、私と王は父子の関係のようになり喜ばしいこととなった。
高麗は私の東の領土である。しかし日本は、昔から高麗と仲良くし、中国とも貿易していたにもかかわらず、一通の手紙を大蒙古皇帝に出すでもなく、国交をもとうとしないのはどういうわけか?
日本が我々のことを知らないとすると困ったことなので、特に使いを送りこの国書を通じて私の気持ちを伝える。
これから日本と大蒙古国とは、国と国の交わりをして仲良くしていこうではないか。我々は全ての国を一つの家と考えている。日本も我々を父と思うことである。このことが分からないと軍を送ることになるが、それは我々の好むところではない。
日本国王はこの気持ちを良く良く考えて返事をしてほしい。
至元3年8月(1266年・文永3年)」
相互に仲良くしようといいならが、日本が一通の国書を送らないとささいなことでケチをつけ、すべてをひとつの国であるなどと調子のいいことをいい、さらに元の帝国を父と思えと都合のいいことを云いながら、その一方で「言うことを聞かないのなら軍を送るぞ」と脅かしています。
ちなみにこの書簡をフビライが書いたのは一二六六年でしたが、その書簡が高麗を経由して、ようやく太宰府に届くまでに、なんと二年が経過しています。どこで書簡が停滞していたかというと、高麗です。元の属国となっていた高麗は、蒙古と日本が戦争になると兵員や食糧を負担しなければなりません。高麗が「どうしよう・・・」と国内であれこれ議論やっている間に、二年が経過していたわけです。
書簡が、いよいよ大宰府にもたらされると、太宰府はこの書簡を朝廷に転送しました。転送された朝廷もまた、書簡を見てびっくりし、連日閣議を重ねたあげく、鎌倉幕府に蒙古襲来に備えよと命じました。「命じた」だけでした。大国である元の侵攻を前に、具体策などなにもなかったのです。
フビライの書簡が鎌倉に転送されたとき、幕府の執権の北条時宗は、若干18歳で執権の座に就いたばかりでした。幕府内では、連日会議が開かれましたが、主戦派と穏健派に分かれて結論はでませんでした。時宗もこの時点では、まだ執権に就いたばかり。幕府の意向が固まるまでは、どうにも結論を出せずにいました。
しびれをきらしたフビライは、高麗に日本への使者の派遣を命じました。ところが高麗は、天候が悪いの海が荒れたのと理屈をつけて途中で帰ってしまったかと思えば、今度は日本と蒙古が通交するようにすすめたりと、まるでらちがあきません。
怒ったフビライは、四度目(日本には二度目)の使者として漢族の趙良弼に六千人の兵を持たせて高麗へと向かわせました。わずか六千の兵ですが、そのために高麗は彼らのための食べ物を提供しなければならず、これを民間から強引に調達したため、高麗の民衆は草や木を食べて飢えをしのいだと記録されています。高麗の国力や知るべしです。
太宰府に着いた趙良弼は「天皇や将軍に会わせないならこの首を取れ」とまで言い放ち、日本側の返事を待ちました。ところが待てど暮せど返事がない。滞在四カ月に及んだ趙良弼はいったん高麗に戻り、再び日本にやってきて太宰府で一年を過ごしました。この滞在は、戦争準備のための日本の国力調査のためだったといわれています。趙良弼の報告を聞いたフビライは「大変よくできている」と褒めたそうです。
こうして最初の使いから六年経った一二七四年一月、フビライは高麗に、日本遠征のための造船を命じました。高麗はそのための人夫三万五千人と食糧・材料の木材を出すことになりました。このため労働者として使われたり食料を出さなくてはならない庶民の生活は苦しくなり、ここでもまた、飢えて死ぬ人が多くいたと記録されています。
それでも高麗は、わずか十ヶ月の間に大型船三百艘、中型船三百艘、給水用の小型船三百艘、あわせて九百艘の船を造りました。ところが、このときに造船された船は、すべて頑丈な中国式ではなく、簡単な高麗式の船でした。
一二七四年十月三日、モンゴル兵六千、高麗兵二万四千、合計三万の兵を乗せた船が高麗の合浦を出発しました。そして十月五日には対馬、十四日には壱岐を襲いました。島民の数は、当時おそらく数千人です。いきなり襲ってきた三万の兵にかなうはずもなく、対馬・壱岐の人々は殺され、生き残った人は手に穴をあけられ、そこをひもで通して船のへりに鎖のように結ばれて吊るされました。
モンゴルと高麗の軍は、十九日に博多湾に集結しました。そして十月二十日、筥崎・赤坂・麁原・百道原・今津に上陸を開始しました。ところが一夜明けると、高麗の船が全部消えていました。博多湾を埋め尽くしていた高麗船が一艘もいないのです。このときの模様を日本側の記録である八幡愚童記は、「朝になったら敵船も敵兵もきれいさっぱり見あたらなくなったので驚いた」と書いています。
なぜ消えてしまったのでしょう。壱岐対馬では、非武装の住民を、圧倒的な戦力を持つモンゴル軍が一方的に襲撃しました。けれど博多湾では、北九州地域の武士たちが、果敢に彼らに挑みました。圧倒的な多勢に無勢でしたが、モンゴル側が、奴隷兵たちに雲霞のように大量の矢を射掛けさせる戦法であったのに対し、日本側は彼らの指揮官を、一撃必殺の弓矢で正確に射るという戦法でした。奴隷兵による戦闘は、指揮官が倒れると奴隷兵たちは戦意を失って逃散します。要するに、無抵抗だった壱岐対馬と異なり、意外にも日本側が武器を持って戦を挑み、これによって指揮官たちを失ったモンゴル兵たちが、慌てて船で逃げ帰ってしまったのでした。
このときの模様について、高麗の歴史書である「東国通鑑」は、夜半に大暴風雨があり、多くの船が海岸のがけや岩にあたって傷んだと書いています。しかし、これはどうやら意外な抵抗を受けて逃げ帰ったモンゴル軍が、本国である元に報告する際に、記録を捏造したというのが、最近の通説です。ここまでが文永の役です。
これに対し、ほんとうに神風が吹いたのが、その七年後に起った一二八一年の弘安の役です。
文永の役のあと、
文永の役の翌一二七五年四月十五日、元は、杜世忠を正使として、日本に降伏を迫る書簡を届けました。「文永の役は蒙古の恐ろしさを知らせるのが目的であったから早々に撤退したけれど、こんどはもっとたくさんの軍隊を送る。降参するなら今のうちだよ」という趣旨です。
戦うべきか、降伏すべきか。幕府の執権北条時宗は悩みに悩みました。そしてこのとき日頃尊敬する蘭渓道隆から受けた教えが冒頭の言葉です。断固戦う決意を固めた北条時宗は、竜の口で、杜世忠一行五名全員を処刑し、見せしめとして首をさらしました。北条時宗は、こうすることで国内世論を、開戦やむなしに固めたのです。
ところが問題が起きました。使者を全員殺してしまったので、肝心の元の側は、使者が死んだとわからない。いつまでたっても杜世忠が帰ってこないので、元は翌年六月に、周福を正使とする一行を、再度日本に送り込みます。
北条時宗は、この周福一行を博多で斬り捨てました。ただし今度はひとりだけは逃して元に戻しました。
杜世忠と周福が首を刎ねられたとを知った元は激怒し、「日本を伐つべし」の大号令が発せられます。
一方、北条時宗は、全国にいる鎌倉御家人たちを博多に派遣し、さらに博多に防塁を築かせました。この工事への参加に、時宗は一切の反論を認めなかったといいます。
一二八一年(弘安四年)、元は范文虎を総大将とする十四万の大軍を博多に差し向けました。対する日本側の武士団は、小者の数まで入れて6万5千人。武士だけなら、おそらく1万人です。兵力でいえば、日本側は十四倍の敵を迎え撃つことになったのです。
日本の武士たちは、夜陰にまぎれ、敵船に乗りこんで火をつけたり、敵兵の首を取るなどゲリラ戦を用いて果敢に戦いました。一方、元軍は、あらかじめ日本軍が用意した防塁に阻まれて、侵攻できない。戦線が膠着状態となり、運命の七月一日がやってきました。旧暦の七月一日は、いまの新暦なら八月十六日頃です。
この日、北九州方面を、大暴風雨が襲いました。港を埋めつくしていた四千艘の船は、台風のまえに、ひとたまりもなく破壊されました。なんといっても船は手抜きの高麗船です。嵐の前にどうにもならない。
翌朝、嵐がおさまると、博多湾は船の残骸と無数の死体で埋め尽くされていました。当時を記した「八幡愚童記」は、このときの様子を「死人多く重なりて、島を作るに相似たり」と記しています。
「高麗史」もまた「大風にあい江南軍皆溺死す。屍、潮汐にしたがって浦に入る。浦これがためにふさがり、踏み行くを得たり」と書き残しています。つまり海を埋め尽くす死体の上を歩くことができたほどであったといことです。
同史によれば、生存兵一万九三七九人。士官や将官などの上級軍人の死亡率が七~八割、一般兵士の死亡は九割に至りました。
すっかり戦意を無くした范文虎らは残った船で宋へ引き上げました。港には、置き去りにされた元の兵士が多数残りました。残されたモンゴル兵(主に高麗兵)たちは、ただ残されただけですから、食べ物がありません。そこで彼らは民家を襲い、食料を奪い、住民を惨殺しました。日本側の御家人たちは、そんなモンゴル兵たちを探し出し、次々と倒して行きました。この残党狩りは七月七日まで続いたといいます。
今でも博多周辺には蒙古塚とか首塚と呼ばれる場所が残っています。これらは当時のモンゴル軍兵士の首を埋めた場所です。日本は、遺体を丁重に埋葬し、供養としていまなお、踊り念仏が毎年行われています。
また断固戦うことを選択した北条時宗は、このときに亡くなった幕府の御家人たちや、モンゴル兵たちの供養のために鎌倉に円覚寺を建てて、この寺を臨済宗円覚寺派の大本山とし、自身もこの寺への埋葬されました。敵味方を問わず、戦いが終われば御仏としてちゃんと供養する。これもまた日本の武士道精神です。
最後にひとつ。もし弘安の役で日本が戦うことを選択しなかったなら、元の大軍は、易々と日本上陸を果たしていたことでしょう。そして上陸していたならば、彼らは台風で船団ごと壊滅することもなかったことでしょう。つまり、明確に戦う意思を示した北条時宗の英断と、命を的に戦いぬいた鎌倉武士たちの活躍がなければ、その後の日本の歴史は大きく変わっていた、ということです。これは少し考えたら、誰にでも理解できることだろうと思います。
日本を守ってくれた北条時宗、そして鎌倉武士団に、わたしたちは深く感謝すべきだと思うのです。
そして、本当の意味での神風は、このとき断固戦うことを選択した北条時宗の決断そのものであったといえるのです。
※この記事は2021年11月のねずブロ記事の再掲です。