
神話は、その国や民族等が持つ文化の根幹を形成すると言われています。
別な言い方をするなら、神話は思考際の価値判断の基準を形成するものであるということができます。
西洋の場合、様々な民族が入り混じって互いに殺し合いを繰り広げた結果、それぞれの民族ごとに持っていたであろう神話が失われ、結局、ルネッサンス運動による「ギリシャ・ローマの時代に帰れ」という標語のもとで、ギリシャ神話と、旧約聖書に依拠するものとなりました。
ギリシャ神話では、オリンポスの十二神に、ゼウスの妻のヘラ、娘のアテナ、愛と美と性の女神のアフロディーテ、狩猟と貞操の女神のアルテミス、穀物の女神のデメテル、炉の女神のヘスティアなどの女性神が登場しますが、それらはあくまで神々のみ、初期の人類には男性しかいなかったとされています。
では人類初の女性は誰かと言うと、これが有名なパンドラです。
そう、パンドラの箱の、あのパンドラです。
もともとオリンポスの神々よりも以前には、ティーターンと呼ばれる巨人の神族が栄えていました。
ゼウスが人と神とを区別しようとして、人類から火を取り上げたとき、巨神のプロメテウスは、火のない人類を哀れに思い、人類に火を渡します。
ところが火を得た人類は、武器を作って互いに戦争をするようになるのです。
事態を重く見たゼウスは、プロメテウスを磔にするのですが、不死身の身体を持つプロメテウスは死なず、3万年の後にヘラクレスによって助け出されます。
一方、プロメテウスの弟のエピメテウスも、兄の罪によってオリンポスを追放されています。
追放されたプロメテウスは、地上で人類の一員となって暮らします。
火を用いるようになった人類、エピメテウスの人類への仲間入り。
こうして人類の力が強大になることで、人類の力が神々に近づくことをおそれたゼウスは、何でも作れる鍛冶屋の神のヘパイストスに命じて、泥から女性のパンドラを造らせます。
そしてゼウスは、パンドラに命を吹き込むとともに、
「美しさ、歌と音楽、賢(かしこ)さと狡(ずる)さと好奇心」を与えるのです。
ゼウスは、これだけでもまだ心配だったのか、さらにアテナから機織や女のすべき仕事の能力、アプロディーテから男を苦悩させる魅力を、ヘルメスからは犬のように恥知らずで狡猾な心を与えさせます。
そしてゼウスは、
「これは人間にとっての災(わざわ)いだ」
と述べるのです。
要するに女性の要素は、泥でできた美しさ、歌と音楽、賢(かしこ)さと狡(ずる)さ、好奇心、機織りの仕事はするけれど、男を苦悩させ、恥知らずで狡猾だ、というのです。
ものすごい男性目線です。
ゼウスの行動はこれだけにとどまらず、パンドラに鍵のかかった箱を持たせると、
「この箱は決して開けてはいけない」
と命令します。
ここまで準備して、ゼウスはパンドラを人類のいる地上に送り込むのです。
パンドラをひと目見たエピメテウスは、兄のプロメテウスから、
「ゼウスからの贈り物は決して受け取ってはならない」
と言われていたにもかかわらず、一目惚れしてパンドラと結婚します。
二人は幸せに暮らします。
けれどどうしても箱の中身が気になってしかたのないパンドラは、ある日、禁を破って、ついに箱を開けてしまうのです。
すると箱からは、夜の女神ニクスの子供たちが飛び出します。
その子供たちというのが、
「老い、病気、痛み、嘘、憎しみ、破滅」
です。
そして次には争いの女神のエリスが高笑いとともに箱から飛び出していきます。
そして箱の中に最後に残ったものが、ギリシャ語で心を意味する「エルピス(ελπις)」であったとされます。
この「エルピス(ελπις)」が英語圏では「希望(hope)」と訳されています。
ちなみにこの「エルピス(ελπις)」、スペイン語では「エスペランサ(esperanza)」、フランス語では「エスポワール(espoir)」と訛(なま)ります。
要するにギリシャ神話は、人類の厄災が、まず「争い」であり、「破滅、憎しみ、嘘、痛み、病気、老い」であり、それらは女性の持つ好奇心から生まれていると述べているわけです。
すごい解釈だと思います。
「トロイの木馬」で有名なトロイア戦争は、美女ヘレネがきっかけです。
トロイの王子パリスは、スパルタ王メネラオスの妃のヘレネに恋をします。
要するに人妻に恋をするのですが、ただの恋にとどまらず、なんとヘレネを拉致して強引にトロイに住まわせてしまうのです。
これがトロイア戦争の原因となりました。
戦争は10年に及びますが、トロイの城塞は難攻不落。
そこでイタケ島の王であったオデッセウスが提案したのが、トロイに、兵を潜ませた巨大な木馬を献上し、トロイの城塞を内側から滅ぼすという物語が、有名な「トロイの木馬」です。
このオデッセウスが、ポセイドンの怒りに触れて船の難破で浜辺に打ち上げられたとき、彼を助けたのがパイエケス人の王女のナウシカです。
ナウシカは、やさしさと愛の象徴のような美しい女性ですが、オデッセウスは、ナウシカの愛を振り払うことで、国に帰還することができたとされます。
こうしたギリシャ神話の物語は、繰り返し小説や演劇、オペラ、映画、ドラマなどで繰り返し作品化され、西洋の人々にとってのアイデンティティを形成してきました。
アイデンティティとは、ひとことで言うなら「国民精神」です。
その国民精神の根幹に、こうして女性=美しくて歌や音楽が上手で賢(かしこ)いけれど、狡(ずる)くて、好奇心旺盛で、男を苦悩させ、恥知らずという概念が、西洋文明には存在するわけです。
だから女性には暴力を用いてでも、男性の言うことを聞かせなければならない。
顔を殴ると跡が残るから、尻を叩いて、言うことを聞かせる。
あまり語られませんが、女性を叩くことは、ですから社会常識にもなっているわけです。
中世ヨーロッパで行われた魔女狩りは有名ですが、女性ばかりがターゲットとなった理由もまた神話にあったといえるのです。
女性にとっては受難の時代といえます。
さらに女性には割礼の儀式もありました。
いまも続く儀式で、全世界でおよそ2億人の女性が割礼を受けていると言われています。
男性の割礼は、包皮を切除するだけでたいした痛みを伴わないと言われていますが(それでも痛そう)、女性の場合は外性器をまるごと切除し、陰唇を縫い合わせるというものです。
麻酔無しで行われるこの儀式の痛みは、想像を絶すると言われています。
他にも、中世までは美女の条件として、ウエストが葉書一枚分くらいに細くなるように、成長期の女児のウエストに金属製のコルセットをはめるという制度もありました。
結果、成人した女性は、肋骨の下部がぐちゃぐちゃに折れ、これが30代くらいになると、いわゆるリウマチ化して、たいへんな苦痛を女性に強いることになりました。
こうした女性蔑視は、旧約聖書でも、
イブの好奇心によって、アダムとイブがリンゴを食べて智慧を付け、神からそのことをとがめられたイブは、
「蛇に騙されたのです」と、自分の罪を責任転嫁したために、神から「産みの苦しみと夫からの支配」という原罪を与えられたのだとしているわけです。
要するに「嘘つきだ」と書かれているわけで、これまたずいぶんな話です。
英国文学で有名なハーベイの『テス』という小説があります。
大好きな小説で、英国文学で最高の小説をひとつあげろと言われたら、迷わず『テス』をお勧めしているくらいですが、その主人公の女性のテスは、たいへんに魅力的な女性ですが、やはり何を考えているのかよくわからない存在として描写されています。
日本人の感覚からすると「?」マークがいっぱい付いてしまいそうな捉え方ですが、ギリシャ神話を読むと、それが西洋社会における女性の定義なのだとわかります。
西洋社会では、ジェンダーフリーとか、女性の人権云々といった議論が盛んですが、日本とは文化の成り立ちそのものが異なるということを、私達はしっかりと踏まえる必要があります。
では日本ではどうだったのでしょうか。
日本の最高神は天照大御神であって女性神です。
そしてその最高神と直接会話を交わすことができるのは、やはり女性神である天宇受売神(あめのうずめ)です。
男性の神々は、天照大御神に何事かを奏上するときも、あるいは天照大御神からのご下命をいただくときも、常に女性神である天宇受売神を通してでなければならないとされています。
これは縄文以来の日本人の伝統的思考で、子を産むことができる、つまり命を産むことができる女性は、もっとも神に近い存在であるとされてきことに由来するといわれています。
ですからいまでも、たとえば神社で御神楽を奉納するときに、神様に捧げる舞を踊るのは女性の巫女さんに限られます。
男性が舞う御神楽は、聴衆に御神楽や神様を説明するための舞です。
つまり、
女性の御神楽舞は、神様に捧げる舞。
男性の御神楽舞は、聴衆に説明をするための舞、
であって、こうした伝統がいまでも固く守られているわけです。
さらに男女の始祖神といえばイザナギとイザナミですが、二神はともに手を携えて、一緒にオノゴロジマを築いています。
男女は、役割の違いこそあれ、対等な存在であり、さまざまな葛藤や誤解があっても、力を合わせることで未来をひらくというのが、日本の神話の特徴です。
いま、我々に伝わっている神話は、持統天皇が皇后時代から、天皇、上皇となられた間、日本をひとつの国にまとめるためにと編纂を行った日本書紀や古事記に基づく神話です。
たとえば古事記にある出雲神話が、正史である日本書紀にはまったく書かれていないことに象徴されるように、古代においては神話は、私達が知ることができる物語以上に、もっとずっとたくさんあったことでしょう。
もしかすると、地方に残る日本昔話などは、その残滓(ざんし)といえるものなのかもしれませんし、古史古伝にあたるホツマツタヱや、竹内文書、九神文書といった文献史料もあります。
興味のある方は、それらをご参照になると良いでしょう。
ただひとついえることは、我が国の神話や、その後の歴史を日本書紀としてあらためて編纂した、その中心人物が、女性の天皇である持統天皇であったということです。
持統天皇の正式な諡(おくりな)は、「高天原廣野姫天皇」(たかまのはらひろのひめのすめらみこと)です。
歴代天皇で、高天原の天皇と記述された天皇は、持統天皇ただひとりです。
そして高天原の広い野にある最高の存在といえば、そのまま天照大御神を想起させます。
当時の人々は、持統天皇をして、天照大御神に匹敵する偉大な女性としたわけです。
そしてその持統天皇が、我が国の神話や歴史編纂事業を発案し、記述を監督し、完成までのレールを敷いたということは、普通に考えても、そこに女性差別はありえません。
実際、日本書紀に女性蔑視や女性差別の概念など微塵(みじん)もないのです。
それどころか、男女は、違いはあるけれど、どこまでも対等であり、互いに違いがあるからこそ、力を合わせていくことが大切とされてきたのが、我が国の神話や歴史における考え方です。
現代の一般庶民においても、外で働く男性にとって、家にいる女性は神様だから、親しみを込めて「カミさん」と呼ぶ習慣にも至っています。
最近、女性のことを「よめ」と言う言葉が、差別用語だと言い出したおかしな人がいるのだそうで、テレビなどでしきりに囃し立てていましたが、「よめ」も「良(よ)い女(め)」から来た言葉であって、とても良い言葉です。
西洋と日本の男女観の違いは、文化の成立の違いに依拠するものでもあります。
日本の場合は、縄文時代の1万4千年という途方もなく長い期間にわたって、そもそも人が人を殺すという文化がまったく存在していません。
それ以前(つまり縄文以前)の日本は、海で魚を採って暮らす海洋民族であったとされる説が有力ですが、3万年近く続いたそうした長い期間においても、男たちは船に乗って漁をしますが、その漁労の際の釣り針に使う釣り糸は、長い間、女性の長い髪の毛が用いられました。
女性の髪の毛は、細くて丈夫で切れません。
ですから、良い女(め)の長い髪の毛は、男性の漁には不可欠でしたし、幼子を危険な海に連れていくわけにはいきませんから、村にある良い女(め)は、男にとって、とても大切な宝でもあったわけです。
この点について、瀬織津姫について、ひとこと添えておきたいと思います。
もともと瀬織津姫は、海洋民族であった倭人たちの共通の神様です。
その倭人たちの住むエリアは、裸国、黒歯国の名前に遺るように、海を一年渡った先までありました。
ところが、7世紀のチャイナに唐という軍事超大国が出現し、白村江の騙し討ちのあと、唐の脅威の前に我が国は、中央集権化を急ぐことになります。
それまでの倭国は、遠く南米までをも含む広大な海洋国家であり、その国家は島ごと国ごとの豪族たちの集合体です。
これを統一国家にしていく必要が生まれたのです。
このとき、天照大御神のもとにある日のもとの国として、現代風に言うなら絶対的防衛圏として編成されたのが、現代日本に続く本州、四国、九州と、それに関連する近隣の島々で、これを日のもとの国、日本と呼びました。
そしてこのことを定着させるために作られたのが記紀です。
ところが記紀には、瀬織津姫が載っていません。
載っているのは、大祓詞です。
どういうことかというと、この時代の認識として、倭人が住む倭国のエリアは、本土以外にも太平洋の島々から中南米にまで広がっています。
その広大なエリア全体の浄化のための神様が瀬織津姫です。
そして、日のもとにあるエリアの神様が、天照大御神です。
もちろん天照大御神は、地球全体をあまねく照らされます。
つまり最高神です。
その最高神の直轄地が、やまとであり、それ以外のすべての地域を含めて統括するのが瀬織津姫という理解であったものと思われます。
さて、明治以降、西洋化が文明開化だとされて、日本社会にも西洋式の軍制が導入され、哲学や男女についての考え方にも、西洋風の思考が随分と取り入れられるようになりました。
そこから秦の時代の関尹子(かんいんし)に書かれいた「夫唱婦随」や、それ以外にも「男尊女卑」などという言葉がさかんにもてはやされるようになりました。
なるほど江戸時代でも「男女七歳にして席を同じうすべからず」と言われましたが、これは間違いが起こらないようにという大人の配慮を意味するものでしかありません。
むしろ、江戸時代までの一般的な慣習として、旦那の給料は、その家に支給されるものというのが、日本の大昔からの考え方です。
そして夫の小遣いを含めて、家内の一切のやりくりや面倒を見るのは、女性である妻の役割とされてきました。
その意味では、旦那の俸禄は、お殿様からいただいているというより、現実的には妻からもらっているようなものであり、何事も家族で責任を持って行うというのが、日本における普通の常識であったということができます。
おそらくですが、たとえば世界の企業における給料の支払いや、銀行口座の管理の一切が、その家の妻の役割ということが世界の常識となったら、世界から戦争の多くは無くなるし、今般のアメリカ大統領選挙のような不正もなくなるのではないかとさえ思います。
いまから数千年の昔、世界の文明を開いたのは、間違いなく、縄文人たちによる実績です。
しかしその後の世界は、暴力と殺戮、しかもその暴力や殺戮を、なんと「女性のせい」にするという悪辣さを持つに至るようになりました。
そうした世界の歪みを、あらためてまっすぐに正していく。
もしかするとそれがこれからの日本人に与えられた、神からの遠大な使命なのかもしれません。
※この記事は2020年12月のねずブロ記事に大幅に加筆したものです。
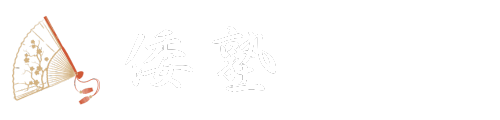


世界の文明の始まりが縄文人であったなら、なぜ日本と西洋ではこれほどまで文化が違ってしまったのでしょう。