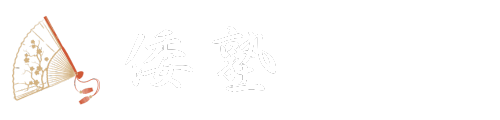江戸時代、江戸の町では芝居小屋が大人気で、とりわけ浅草三座と呼ばれる3つの芝居小屋は、千両役者が立ち並ぶ我が国きっての名門芝居小屋とされていたことは、ご存知の方も多いかと思います。
この江戸の芝居小屋が、現代に続く歌舞伎に至っているというわけですが、この千両役者というのは、江戸時代、本当に千両役者で、一日の公演でまさに千両(いまで言ったら6千万円)のチップを本当に稼いだのだそうです。
すごいものですね。
この江戸の芝居小屋で欠かせない演目といえば、「曽我兄弟」に「忠臣蔵」です。
特に「曽我兄弟」は、新春の出し物として三つの芝居小屋が同じ「曽我兄弟」の演目で舞台を演じて華を競いました。
ですから江戸っ子としては、曽我兄弟物語は、まさに常識で、幼い子供から大人まで誰でも知っている物語であったわけです。
同じ演目を三つの芝居小屋がやるなんて、なんと芸がないのだろうと思うのは、素人のあさはかさ。
実は新春の出し物は「曽我兄弟」と決まっていますが、その演じる内容は、年ごとに、そして芝居小屋ごとにも、まったく違ったのです。
それぞれの芝居小屋で、毎年、異なる筋書きで「曽我物語」で演じる。
役者が違い、筋書きが違い、当然、衣装も化粧も異なる。
この違いを観て、楽しむというのが、江戸っ子の「粋(いき)」ってものであったわけです。
まあ、江戸っ子風にいえば、
「べらんめえ、この違げえがわかんねえようなやつぁ、江戸っ子たあいわねえってんだいっ」てな感じです。
では、その「曽我物語」というのは、どのようなお話だったのでしょうか。
時は平安末期、平家全盛の時代、東国では地方豪族たちの領地争いが絶えず、伊豆では工藤祐経(くどうすけつね)と伊東祐親(いとうすけちか)が、長年の争いを繰り返していました。
そんなある日、工藤祐経が家来に命じて、狩りをしていた伊東祐親に弓を射たのです。
放たれた矢は伊東祐親をかすめて、脇に立っていた息子の河津三郎(かわづさぶろう)に命中しました。
三郎は即死でした。
悲報は三郎の妻と二人の息子に伝わりました。
亡骸(なきがら)と対面した妻は泣きながら息子に言いました。
「よくお聞き。
父君(ちちぎみ)は工藤祐経に殺されました。
お前たちはまだ幼くてわからないでしょうが、
お前たちが大きくなったら、
母は、お前たちに
父君の仇(あだ)をきっと取ってもらいたいのです」
三歳の弟にはまだ理解できないことでした。
けれど五歳の兄は、目の前に横たわる父の顔をじっと見つめて言いました、
「母君、必ずお父さんの仇を取ります。」
その後、母は曽我(そが)氏と再婚し、兄弟も曽我姓になりました。
兄は、曽我十郎祐成(すけなり)と名乗りました。
弟は、曽我五郎時致(ときむね)です。
厳しくも愛情あふれる義父のもと、二人は弓に剣術に学問に、優秀な若者に育ちました。
ある日、野で遊ぶ二人の上に、五羽の雁(かり)が飛びました。
兄は言いました。
「雁が一列になって飛んでいる。
2羽は親で、
3羽は子供だろう。
おれたちにも親がいる。
しかし今の父君は本当の父ではない。
本当の父は工藤祐経に殺された。
血のつながった父はもういないのだ」
「兄者(あにじゃ)、
工藤祐経に会ったら、
俺が弓で射て首を刎(は)ねてやる。」
「しっ。五郎、大声を出してはならぬ。
このことは誰にも話してはならぬのだ。
仇討(あだうち)は二人だけの秘密だ」
時が経ち、1192年、源氏の棟梁の源頼朝が征夷大将軍に任ぜられ、そのお祝いにと翌年、富士の裾野で大掛かりな狩の大会が開催されました。
「いざ、亡き父の仇を取る絶好の機会」
と兄弟は逸(はや)ります。
しかし工藤祐経は大物です。
いつも大勢に囲まれていて近づくことすらできません。
二人は頼朝の家臣団にもぐりこんで、その晩の工藤祐経の宿所を突き止めます。
そして祐経の宿所に如何に近づくか相談しました。
しかし、ひそひそ話をする兄弟の耳に、近くにある滝がゴーゴーと鳴り響いて、互いの声が聞き取れません。
兄がふと「心なしの滝だなぁ」と、ためいきをつきました。
するとあら不思議。
激しい滝の音がぴたりと止んだのです。
そして兄弟の相談がすむと、再びゴーゴーという滝の音があたりに響きました。
この滝が、静岡県富士宮市にある「音止めの滝(おとどめのたき)」で、いまは日本の滝百選のひとつになっています。
落差約25メートルの名瀑で、豪快で雄雄しい男滝とされています。
名前の由来が、まさに曽我物語からきているわけです。

兄弟が相談している間に、滝が止まったのは、神々が賛同してくださった瑞兆(ずいちょう)とされました。
地震・水害等の場合はその逆張りで、神仏を軽んじ、神仏の「おほみたから」である民を軽んじて世を乱す治世が行われると、必ず神仏は、何からの大きなペナルティを与える。
その神々というのは、私達の共通の遠いご祖先の御霊の集合体であり、その神々と、いまを生きている者とが一体となってこの世を動かしているというのが、古くからの日本人の思考でもあったわけです。
ちなみに脱線ついでにもうひとついうと、仏教では亡くなられた方は極楽浄土へと旅立ちます。
これをお送りするための儀式がお葬式です。
これに対し神道では、亡くなられた方は祖先神として家の守り神となります。
従って神式の葬儀では「神葬祭(しんそうさい)」と言い、手水を使い、二礼二拍一礼をします(この拍のとき、両手を打つ直前で止めて音を立てないのが作法です)。
実は葬儀が仏式でも、お位牌を仏壇にお供えするのは、仏教と神式が、ある意味融合した型になっているわけで、これまた日本独自の作法です。
とまあ、脱線しましたが、二人が音止めの滝で相談した夜のこと、月が雲間から顔を出し、その月明かりを頼りに兄弟は工藤祐経の宿所までやってきます。
月が雲間に隠れる。
するとたちまち豪雨があたりを包みます。
雨音は、二人の侵入の足音を消しました。
「起きろ祐経!
河津三郎の息子、十郎なり」
「同じく弟、五郎なり。
亡き父の積年の怨みを晴らしに参上!」
祐経の手が刀に届こうとした、その寸前、
兄は、工藤祐経の左肩から右わきの下にかけて袈裟に斬り下ろします。
弟は、刀で工藤祐経の腰を貫いてとどめを刺しました。
兄弟は勝利の雄叫び(おたけび)をあげました。
「遠からん者は音にも聞け!
近くば寄って目にも見よ!
我こそは河津三郎が子、十郎祐成、
同じく五郎時致なり。
たった今、父河津三郎の仇、
工藤祐経討ち取ったり。
我ら宿願を果たし候」
兄弟は工藤祐経の家来に取り囲まれます。
兄弟は果敢に戦うのだけれど、兄は斬り合いの最中に殺され、弟は囚われの身となります。
このあたりハリウッド映画なら敵を倒した時点で兄弟が英雄(ヒーロー)になるのでしょうが、日本ではそうはなりません。
なぜなら暗殺という手段に打って出たものの、工藤祐経もまた部下から尊敬を集めた立派な源氏の御家人なのです。
日本的な思考というものは、勝者と敗者という二項対立ではないのです。
正義と悪の対決ではなく、どちらにも正義があり、どちらにも非があると考える。
翌日、弟は、将軍頼朝の前に引き出されました。
工藤祐経は将軍頼朝の寵臣でです。
見事、父の仇を討ったとはいえ、死罪は免れない。
覚悟の定まった弟・五郎は、恐れ気もなく堂々と、頼朝に父が射殺されたことを述べました。
そして、自分たち兄弟の18年の艱難辛苦の日々を語ります。
頼朝も若い頃、政治犯の息子となって流刑となり、辛い日々を過ごした過去を持ちます。
そして頼朝のみならず同席の誰もが、子を持つ親です。
その子が親を思う気持ち。
これに痛く感動するのです。
頼朝は寛大に処理しようとしました。
しかし工藤祐経の遺児の犬吠丸(いぬぼうまる)は、父殺害の五郎に「死罪を」と嘆願します。
最高権力者の将軍といえども、騒動という事実と、遺族の歎願を前にして、自分の気持を押し通すことはできません。
これまたたいへんに日本的なところで、権力者の鶴の一声で、なんでも思い通りになるわけではない。
このあたりは、皇帝や国王、あるいは役人や両班(やんばん)の贔屓(ひいき)次第で、どうにでもなってしまう国と日本の大きな違いです。
結局、裁決は死罪ときまりました。
これを聞いた五郎は、
「本望なり」と言いました。
「死は覚悟の上のこと。
あの世とやらで
亡き父や兄と、
とく(早く)対面いたしたし」
名ゼリフです。
享年、兄十郎22歳、弟五郎20歳。
「曽我物語」は、鎌倉時代の実話が基になっています。
そしてこの物語は、その後の時代を通じて人々に愛され続けました。
それは儒教的な意味における兄弟の「孝」ではありません。
登場人物の誰もが、真面目であり、真剣であり、誠実でありながら、すべてが丸く収まるわけではない。
だからそこに共感があったのだと言われています。
このあたり、例えてみれば1978年公開のアニメ映画『さらば宇宙戦艦ヤマト』と、2010年公開の実写版『SPACE BATTLESHIP ヤマト』の違いに似ています。
40年前の『さらば・・』では、主人公の古代君も森雪も真田さんも島君も沖田艦長も司令長官も、誰もがみんな真面目です。
真面目であるがゆえに、誰もが追い詰められていって、最期にはみんな死んでしまいます。
そこに日本人の共感性があったし、だからアニメーションは、いまどきのアニメ映画と比べたら、ものすごくダサいかもしれないけれど、それが大ヒット映画となったのです。
ところが実写版の方は、素晴らしい映像に、キムタクさんや黒木メイサさんなどの人気俳優を配し、しかも大人気の宇宙戦艦ヤマト物語でありながら、全くヒットしなかった。
なぜかといえば、基本となるマインドがまったく日本的でなかったから、日本人の共感を呼ばなかったからだと言われています。
基本設定がゆがんでいるのです。
同じストーリーでありながら、実写版では「才能はあるけれど、わがままな不良がかっこよく勝利する」という物語になっていました。
戦場においても、企業戦士においても同じですけれど、不良というのは、まともな仕事ができないから不良なのです。
不良品でできた宇宙戦艦なら、それ自体が不良品です。
その不良品が、必死にまじめに戦って勝利したというのなら、まだわかりますが、不良がカッコつけてカッコよく戦って、破れて死んだ、というのでは、誰もそのような筋書きに納得などしないのです。
私は日本女子バレーのファンですが、日本の選手たちは点が入るたびにみんなでよろこび合い、点を取られると、みんなで励まし合います。
それを本当に一生懸命に、しかも笑顔でやっている。
どこかの国の女子バレーチームは、ひとりの超強力とされるいかにも不良の選手がいて、その選手だけをささえるチームになっています。
そしてその選手が点を入れれば、その選手一人が「どんなもんだい」と傲慢な顔や態度をし、点を取られたら、あたかもそれが他の選手のせいだといわんばかりに、露骨に嫌な顔をします。
日本人には、そういう軽薄や傲慢は受け入れられないのです。
そうではなくて、みんなが誠実で一生懸命でひたむきで、必死だから、同じものに共感するのです。
ところがそんな女子バレーボールの試合になると、どこぞの放送局のアナウンサーなのか誰なのかしりませんが、大声を張り上げて、「サリナ、サリナ」とか、興奮して喚き散らしている。
必死で応援したい気持ちはわかりますが、さりとて他人の迷惑を省みず、また相手チームだって真剣勝負してきているのに、そんな相手チームのことも考えず、ただ日本チームひいきで、大声を張り上げているようなものに、誰も共感などできないのです。
時代は変わり、昨今では、曽我物語を知る人も少なくなりました。
しかし昭和天皇は、終戦の御詔勅で「志操を堅固に保て」とおっしゃられました。
日本人の本来持つ生真面目さ。
そこにこそ、「志操」を保つ土壌が育まれます。
我々は、もっと日本という国の持つ文化の素晴らしさを、愛し、知る必要があるのではないかと思います。
※この記事は2009年8月のねずブロ記事のリニューアルです。