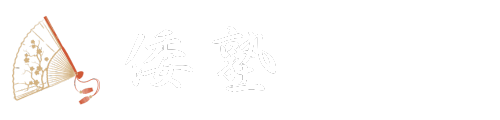長谷川 伸(はせがわ しん)といえば「沓掛時次郎」、「 一本刀土俵入」など 股旅もので、一世を風靡した作家です。
その長谷川伸の書いた本の中に『日本捕虜志』があります。
第4回菊池寛賞を受賞した本で、その中で二木可南子さんという実在の女性が紹介されています。
現代文に訳してご紹介します。
あとに私の所感を書いてみたいと思います。
きっと何かを感じていただけると思います。
ーーーーーーーーーーー
彼女は、日本が降伏した昭和20年当時、数え年20歳でした。
(いまで言ったら19歳です。※ねず注)
東京で陸軍に徴用され、同じ年頃の娘3人とともに、シンガポールの医薬部隊に配属されていました。
可南子さんの父、二木忠亮氏は、はイギリスのロンドンで個人商店を営んでいました。
そのため可南子さんはロンドン生まれのロンドン育ちです。
もちろん英語はペラペラです。
ある日、可南子さんの母がロンドンで亡くなり、父は娘を連れて日本に帰国しました。
やがて戦争が始まり、父は徴用され、大尉相当官として英語通訳を命ぜられ、マレー半島の攻略軍に配属されました。
娘の可南子さんも徴用されました。
可南子さんは「父のいるシンガポールへ行きたい」と条件をつけたのが聞き入れられ、医薬部隊に配属されました。
医薬部は軍医少将の指揮下で、軍医中佐3人と、薬剤の中佐と主計少佐などが6人、そして徴用の技術者が600人いました。
女性は可南子さんを含めて4人です。
いずれも英語が書けてタイプが打てる女性です。
ことにロンドン生まれの可南子さんの英語は格調が高かったそうです。
終戦を迎えたとき、このシンガポール医薬部には、イギリス人が部局の接取にくることになりました。
医薬部としては、接収のときのもつれを未然に食い止めるためにも、英語が堪能でタイプの打てる4人の日本人女性は、いてもらいたい人たちです。
しかし接収に来るイギリス人が、すべて敬虔で紳士的とは限りません。
乱暴狼藉をはたらかれる危険はじゅうぶんにあります。
結局ひとりひとり説得することとし、可南子さんには軍医官があたりました。
軍医官は勇気を奮ってこう言いました。
「あなた以外の三人の女性にも、残留してもらいたいと、それぞれ今お話をしています。」
「喜んで残留いたします。」軍医官の言葉が終わると同時に可南子さんはそう答えました。
軍医官「え?」
可南子「わたくし、東京へ帰っても父はおりません。」
軍医官「そうでしたね。あなたのお父さまはあのころから消息が絶えたのですね。」
可南子さんの父はその言動が軍の一部の怒りを買い、危険な地域に転出され、消息が絶えていたのです。
「ええ、ですから残留を喜びます。父はいつになってもシンガポールに、わたくしがいると信じているはずです。父は消息が絶える少し前に言いました。『父子のどちらが遠くへ転出となっても、一人はシンガポールにいようね。もう一人はいつの日にかシンガポールに必ず引き返してこよう。いつの日にかシンガポールで再会の時があると信じて』」
軍医官「二木さん、有難う。今後の仕事はあなたを疲労させるでしょうが元気を出してやってください。お願いします。」
可南子「はい。愛国心は勝利のときだけのものではないと、散歩しているとき父がそう言いました。」
軍医官「そうでしたか。勝利のときより敗北のときこそ愛国心をと、お父様が言ったのですか・・・・。
二木さん、もう一つ。
人すべてが善意を持っていはいない。忌まわしい心を持つものもいます。
僕は、いや僕たちは、あなた方4人の女性に危機が迫ったとき、人間として最善をつくすために、死にます。これだけがあなたがたの残留に対して、わずかに確約できる全部です。」
可南子「いえ、そのときには少なくともわたくしは、一足お先にこれを飲みます。」
襟の下からチラリと見えたのは青酸カリでした。
軍医官は、唇をかみ締めて嗚咽を耐えました。ついに咳を一つしました。
それは咳ではなく押し殺したしのび泣きでした。
可南子さんは続けました。
「できたらどうぞ、わたくしの死骸にガソリンをかけて、マッチをすっていただきたいのです。」
当時、終戦で復員する日本人を狙って、乱暴をはたらき、その女性が死んでもなお恥ずかしめをあたえられるという事件が実際にあったのです。
9月1日キング・エドワード病院にイギリスのハリス軍医中佐が、イギリスの300名の武装兵とともにやってきました。
4人の女性は青酸カリに手をかけて、窓のカーテンに隠れるように成り行きを見ていました。
ハリス中佐と老紳士が印象的でした。
老紳士は、医学博士のグリーン氏です。
彼は穏やかなまなざしで言いました。
「日本人の皆さん、私はまだあなたがたの気持ちがのみこめないので、武装した兵を必要としました。日がたつにつれ、武装しない兵をごく少数とどめるだけにしたいと思います。皆さんはそうさせてくれますか」とにこっと笑いました。
ある日、日本刀が幾振りも隠されていたのが発見されました。
グリーン博士は激しく怒りました。
「ここの日本人が私を裏切ったのが悲しい。
私の憤りを和らげうる人があれば、言うがよい。」
可南子さんは、軍医の意を受けて発言しました。
芸術としての日本刀の在り方、名刀の奇蹟の数々、新田義貞が海の神に捧げて潮を引かせた刀、悪鬼を切り妖魔をはらった刀などの伝説等々。
日本の言葉で昼行灯という言葉があります。
これを人にあてて薄ぼんやりした人のことをいいます。
マレー人の言葉では、白昼に灯を点じていくとは、心正しくうしろ暗いことのない人をいいます。
「人種と言葉の差のあるところ、感情と思慮にも差があるはずです」とユーモアを交えて可南子さんは説きました。
苦りきったグリーン博士の顔は、いつか和らぎ、何度もふきだしそうにしました。
グリーン博士は、時折、可南子さんのロンドンなまりの英語を懐かしむように眼を閉じて聞いました。
グリーン博士はロンドン生まれだったのです。
可南子が席につくと、グリーン博士は言いました。
「発見された日本刀は直ちに捨てます。
日本刀を捨てたものの追求はやりません。」
軍医たちは語りあいました。
「いつか警備隊員で色男ぶってるのがいたろう。あいつが上村美保江さんに失礼なことを言ったのさ。
すると彼女は、『汝は警備隊員か侵略隊員か』と毅然として言ったそうだ。後でグリーン博士は『お前の頭の中の辞書にはレディという項がないのだろう』と言ったそうだ。そこでその兵は転属を志願して二度と顔を見せなくなったそうだ。」
「それはね、可南子さんが教えたんだ。降伏直後、3人の女性を集めて、イギリスの女性という超短期講座を開いたそうだ。だからあの4人はイギリスの兵隊につけこまれることはない。だけど、その3人は、イギリス人の将校に階段で会えば、どうぞお先に道を譲るけど、可南子さんは決して譲らないね。
僕は何度も見ているよ。あの子はロンドン育ちだけど、それだけじゃない。
国は負けても、個人の権利をそのために自分で進んで割り引くのは卑劣だという信念があるのだね。」
グリーン博士がかくも寛大だったのには、昭和17(1942)年イギリス軍が降伏して日本軍が入ったとき、博士も捕虜になった経験があったからです。
監獄はひどかったが、やがて日本軍が、敵と味方を一つに視て、双方をあわせて供養した無名戦士の碑を建てたという話を聞きました。
そして、たびたび監獄に来て、私財を投じて食糧や薬や日用品をながいあいだ贈ってくれた何人かの日本人もいました。
グリーン博士は、「自分たちが生き延びたのはこのお蔭です。いつの日か報いたい」と語り合っていました。
「わたしは、チャンギー監獄で日本人によって人間愛を贈られたのです。わたしはこれに答えなければならない。」
雨季に入ってグリーン博士はロンドンに帰り、後任としてカンニング博士がくることになった。
ある日、カンニング博士が着任しました。
前日に可南子さんは、タイプした残留60人の日本人の名簿を博士に提出しました。
グリーン博士はその名簿を読み上げました。
「上村美保江、守住浪子、成田由美子それから二木可南子」
「Oh! フタキ。フタキですね。」
「そうです。カンニング博士」
「私はこの名をずっと尋ねていたのです。」
まもなく二木可南子さんが呼ばれて部屋に入ってきた。
カンニング博士は、またたきを惜しむように可南子さんを凝視しました。
「ドクター・カンニング、お忘れになっている言葉をどうぞ」と可南子さんは毅然として言いました。
「あっ、おかけください」
「ぶしつけに見つめて大変失礼しました。
私があなたをみつめたのは、
あなたの顔に見出したいことがあったからです。
タダスケ・フタキを知りませんか?」
可南子さんの心は胸打ちました。けれど声に変化はいささかもありません。
「私の父です。」
「OH!」
「1940年、東京へ帰るまでロンドンにいた二木忠亮ならばです。」
「そうです。そうです。
そして1942年にシンガポールに日本軍の通訳でいた人です!」
「父です、確かに。」
可南子さんの頬が赤く染まりました。
「あなたはあの人の娘か。」
「父をご存じですか?」
「忘れるものですか。」
「父は生きていますか?」
「ああ、あなたも私と同様、
あの人の現在を知らないのですか。」
カンニング博士は可南子のそばに来て抱き寄せ、「カナコの父が、カナコの前に立つまで、私がカナコの父になります」とささやきました。
カンニング博士も日本軍のマレー攻撃で捕虜になってチャンギー監獄に入れられていたのです。
200名の捕虜はそこから連れ出されて、タイとビルマをつなぐ鉄道の大工事にかりだされました。
その時の捕虜係通訳が二木でした。
二木は、捕虜の辛苦をます生活の中で、献身的につくしました。
病人やけが人、衰弱者があるごとに二木はできるかぎりのことをしました。
捕虜たちは二木を、神の使徒ではないかと噂しあっていました。
二木は長期間捕虜達と一緒だったけれど、1944年に入って突然姿を消し、二木の後任者も彼がどうなったかを知りませんでした。
カンニング博士は可南子に遭遇してから、イギリス軍、アメリカ軍、オーストラリア軍、オランダ軍と二木の生死を照会したが一向にわかりませんでした。
激しい雷雨が去ったある日、カンニング博士が、「カナコ、誰かカナコを呼んできてくれ」と言った。
可南子さんが姿を見せると
「カナコ、お父さんは生きていたよ!
妻から電話で知らせてきた。
グリーン博士も電話で知らせてくれた!」
そのときの可南子さんの深い微笑みを、後でカンニング博士は、
「東洋の神秘の花」
とたたえたそうです。
「カナコ、お父様はフィリピンにいた。アメリカ軍が今朝知らせてくれた。すぐに希望のところに二木を送還するそうだ。」
これを聞いて可南子さんの眼に涙があふれてきました。
可南子さんは一人シンガポールにとどまり、フィリピンから来た父と再会できたのでした。
たおやかにやまとなでしこ咲きにけり
りんと気高くたじろぎもせず
ーーーーーーーーーーー
なんとなく、最近の日本人は、かつての日本人が、ものすごい勢いで海外に出ていたことを忘れてしまっているような気がします。
朝鮮半島はもとより、ハワイ、ブラジル、Korea半島、China、満州、千島列島、樺太、モンゴル、中央アジア、東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ、カナダ等々、それら外地に、普通の日本の民間人、それも特別な商社マンとかそういう人ではなしに、普通の日本人が、多数出かけて行って、観光ではなく、その国で暮らしていました。
いまでは、海外にでかける日本人は、バブルの頃は普通のOLさんが世界中に観光旅行やバカンスにでかけていましたけれど、平成・令和となってからは、日本人の外地での活動は、商社マンや留学生、ごく一部の観光地、観光客に限られてしまっているかのようです。
ちなみに昭和初期頃の日本円の為替相場は、1ドル1円くらいです。
これはいまでいったら、1ドル100円だったわけで、円はそれだけ強い通貨だったのです。
当時、海外にでかけるのは、まだ旅客機は発達していませんでしたから、その多くは船旅です。
そして船でロンドンにでかけ、ロンドンで生活していたのが、二木さんの家だったわけです。
話の中に、二木さんの父親が、私費まで投じて英国人捕虜たちのために、いろいろな便宜を図っていたという記述が出てきます。
これも二木さんが軍規を無視して、あるいは上官に逆らってそれをしていたということではないことにも、注意が必要です。
戦時中の日本は、日本人自身が満足に食べれないほど極端に物資が不足していました。
ですから官営で支給される食事などの物資は、必ずしも贅沢に慣れた英国人たちに満足のいくものではありません。
そのことがわかるから、当時の兵隊さんたちが、みんなでお金を出し合って、英語のわかる二木さんを通じて、捕虜たちのために、できる限りの手当をしていたのです。
それが英国人捕虜から見ると、二木さんの慈愛に見えた、ということです。
実際には、その裏側に、二木さんと一緒にいた連隊や大隊のみんなの好意があったのです。
いかにも日本人らしいじゃないですか。
日本が戦争に負けたとき、可南子さんは「愛国心は勝利のときだけのものではない」と、自ら残留を希望しました。
辛い時は、自分だけが辛いわけではない。みんなも辛いのです。
ならば自分も一緒になって、その辛さのなかに身を置こう。
こうした心理もまた、当時の日本人のあたりまえの姿勢でした。
ロンドン生まれのロンドン育ちの可南子さんにも、やはりそういう日本人としての血が流れていたということを、この一文は物語っています。
そういう可南子さんに、軍医官は、「自分は人間として最善をつくすために死にます。これだけがあなたがたの残留に対して、わずかに確約できる全部です」と話しています。
ここも大切なポイントだと思います。
軍医官にとって、可南子さんは、部下のひとりです。
自分の彼女でもなければ許嫁でもありません。単に同じ職場のスタッフです。
上下と支配の関係でいえば、勤務医の下にいる看護師でもない、ただの通訳です。
けれど、その女性ために軍医官は、
「万一のときは、自分は人間として最善を尽くして死にます」
と覚悟を決めているのです。
しかも、「それが自分に確約できる全てです」とまで述べています。
ここにも、かつての日本にあった職場における人間関係の姿が浮き彫りになっています。
西洋においても、ChinaやKoreaにおいても、部下は上司の私物もしくは奴隷です。
ですから南京城攻略戦のときも、蒋介石は日本軍が攻めてくるとわかったときに、いの一番でそこから逃げ出しています。
マッカーサーも開戦初期に日本軍がフィリピンに上陸したとき、やはりいの一番にフィリピンから逃げ出しています。
そして最高指揮官が「逃げた」ことについて、どこからも苦情もなければ、責任の追求もありません。
なぜなら、それが彼らにとっての常識だからです。
ところが日本では違います。
たとえ軍隊であっても、そのなかの医局であっても、役割分担としての上下はもちろんあります。
けれど、人としてはどこまでも対等というのが、日本人の考え方です。
だからこそ軍医官は、自分の彼女でもない、ただのひとりの部下のために、自分の命を進んで投げ出そうと言っています。
部下の可南子さんは、陛下の「おおみたから」であり、親御さんから預かっているかけがえのない、そして毎日をすごす職場の大切な同胞だからです。
一方で、可南子さんも「いいえ、もしそういうことがあれば、私はこれを飲みます」と青酸カリを見せています。
このことは、「ですからどうぞ軍医様は、私のことをお気遣いなくお逃げください」と言っています。
我が身を殺してでも、周囲の人を助けようとする。
こういう展開は、極限の事態に追い込まれたときに日本人が見せる「魂の特質」といえると思います。
ただしこのとき可南子さんは、ひとつだけ軍医にお願いをしています。
「できたらどうぞ、わたくしの死骸にガソリンをかけて、マッチをすっていただきたい」というのです。
この時代、外地に散っていた日本人について、終戦後の復員が行われた時代ですが、特に満州方面から朝鮮半島を経由して帰ろうとした日本人の、特に武器を持たない民間人の婦女子を狙って、数々の暴行が行わていました。
このことは、特に朝鮮人の蛮行として紹介されることが多いのですが、実はそればかりではありません。
当時の世界の戦争において、勝った側の兵士等が、負けた側の国の女性たちを、負けた側の男性たちが見ている前で強姦する。
これは当時の世界における常識であり、もっというなら義務でもありました。
義務というと、びっくりされる方もおいでかもしれません。
しかし民族間の戦いというものは、相手の民族がある限り続くわけです。
だから血を混ぜる。そのために女性を強姦し孕ませる。そうして混血児を生む。
混血したら戦いがなくなる、というわけです。
そうした伝統が20世紀になってもまだ残っていたわけです。
ですからドイツのベルリンが陥落したとき、ベルリンの女性たちは、年齢に関わりなく8割が強姦されたといわれています。
敗ける、ということは、そういうことなのです。
同じことはベトナム戦争で韓国兵が徹底して行っています。
聞きたくないことだと思いますが、事実の理解のためにもうひとつ申し上げると、負けた側の国の女性たちを、夫や父親の見ている前で強姦する。
銃を突きつけられ、あるいは半殺しにされた状態で、自分の恋人や妻や娘が目の前で強姦されると、男たちは完全に抵抗力を奪われるのだそうです。
そしてそれをやった連中に対して、二度と逆らわなくなる。
人類史の、それが現実です。
言いたくはないですが、戦後の混乱期に、白昼堂々街のそこここで三国人を自称した在日朝鮮人たちが、日本人の婦女子への暴行を働きました。
そのことの結果が、いまに残る在日の横暴に対して日本政府がまるで及び腰という形で現れています。
けれど、悪は悪です。
しかも日本は彼らを保護しさえすれ、彼らを虐めたことは一度もありません。
二度と蹂躙されない未来を、私達は築いていかなければならないのです。
さらに可南子さんは、自分の遺体を辱められないように「焼いてくれ」と申し出ています。
これは斜め上の半島国の伝統芸です。
屍姦と言って、死体を強姦する。
常軌を逸していますが、これまた彼の国の伝統です。
終戦後復員してくる途中で、多くの日本人女性が、こういう辱めを受けました。
そしてそんな情報を、当時まだ二十歳そこそこであった可南子さんも「知っていた」ということなのです。
人の皮をかぶったケダモノ、という言葉がありますが、そういう人種が世界にはあるのです。
それだけに私達は、決して無防備でいたらいけないのです。
英国人の兵隊が女性に下品な口をきいたとき、可南子さんは「汝は警備隊員か侵略隊員か」(原文のまま)と言い放ち、階段の道すら譲ろうとしませんでした。
当時は、イエローは家畜以下とされた世界です。
しかも大柄な英国人兵士と比べれて、可南子さんの身長は、150cmくらい。
英国人兵士は、平均身長190cm以上です。
その大柄な英国人の将校が、前からやってきて、小柄な可南子さんが、道さえ譲らす凛として胸を張り、道さえも譲らない。
現代日本人よ、その凛々しい姿を見よ、と言いたくなります。
このことを、彼女が、英国生まれの英国育ちでレディファーストの国に育った、彼女における特殊な事情がそうさせたのである、といった人がいましたが、違います。
戦いに勝ったとか、負けたとか、戦勝国だとか敗戦国だとか、白人だとか有色人種だとか、男とか女とか関係ない。
戦いが終われば、ひとりの人間であり、人間である以上、人として対等だ、というのが日本人の日本人としての考え方です。
その日本人としての誇りがあればこそ、彼女は堂々と、英国人将校に道を譲れと迫ったのです。
「紳士なら、そうするのがあたりまえでしょ?」ということです。
そうした気丈さに心打たれたからこそ、英国人の将校が、可南子さんのために、真剣になって父親を探してくれるわけです。
父親が見つかった知らせを受けたときの可南子さんの微笑みを、博士は
「東洋の神秘の花」
と讃えています。わかる気がします。
当時のことです。捕虜の日本人女性は化粧などしていません。スッピンです。
けれど、命の輝きというか、人格からにじみ出る美しさというのは、下手な化粧などよりも、はるかに気高く美しいのです。
実は、この「生命の輝き」こそが《日本美》です。
「生命の輝き」は、整形では決して出すことができないものです。
*
さて、この物語には後日談があります。
ある日、グリーン博士が、
「帰還の目処がついた、昭和21(1946)年の桜の花咲く頃に、あなたがたは日本に帰れるでしょう」とうれしい知らせを告げにきたとき、ちょっと気になることを言ったのです。
「ジェロンの収容所にいる日本人諸君が、ある英国人に不満をもっているそうですね。そういう話を聞いていますか?」
「いえ、聞いていません」
「私も確実には知らないのですから、今の話は取り消します。」
実は、こういう話なのです。
ジェロン収容所はシンガポールから5マイル離れたところにありました。
日本への復員船が3隻あったのだけれど、輸送指揮官の少佐が男だけ乗せて、女性の乗船を許さなかったのです。
その後、暴風雨が吹く季節風が吹く時期となり、帰還船は停まってしまいました。
そこで日本人女性たちから怨嗟の声が起こったのです。
それに残った男どもが声を合わせるから、不満はますます大きくなりました。
3月下旬にやっと1隻入ったのですが、このときもやはり女性の乗船は許されません。
少佐に対する怨嗟の声は、ますます高まりました。
やっと次の引き上げ船がタンジョン・バガーの大桟橋に入ってきたとき、ようやく女性たちと子供全員の乗船が許されました。
女性たちは満腔の不満を胸いっぱいにして乗船してきました。
するとその英国人の少佐がお別れにきてこんなことを話したのです。
「皆さんは私を怨んでいたそうですね。
でも私は皆さんに少しでも楽に
日本で帰れることのほうが、
私は大切だったのです。
私は船が入選するたびに検分しました。
そして一番気になるところを見に行きました。
この船には婦人用のトイレを心して作ってあります。
これならば、
ほかのところもよいだろうと思いました。
私は戦時用の輸送船にあなたがたをおしこめて、
不快な不自由な思いをさせたくなかったのです。」
女性たちの顔から恨みや不満の表情が消え、感謝の表情に変わりました。
そしてその船が桟橋を離れる時、少佐へのせめての感謝のしるしにと、どこからともなく「蛍の光」が歌われ、歌声は60人ほどの女性たちの声で唱和されたのです。
英国兵たちは、いついつまでもその船の影が見えなくなるまで見送っていたそうです。
この英国人少佐の日本人復員女性にたいする対応は、彼の意識の中に、二木可南子さんによる、日本人女性に対する畏敬の念があったからだといわれています。
たったひとりの日本人女性の毅然とした態度と行動が、勝者である英国人将校の心を変え、多くの日本人女性を救ったのです。
このことも、私たち戦後の日本を生きる者が忘れていけないエピソードではないかと思います。
こうした二木可南子さんの凛とした姿勢は、彼女が英国在住経験があったからなのでしょうか。
違うと思います。
なぜなら、海外におけるこうした凛とした日本人女性の姿は、他にも数多く伝えられているからです。
古来、我が国では、神様と直接対話できるのは、女性だけに与えられた特権と考えられてきました。
ですから、神社のお神楽でも、女性の巫女さんが舞うお神楽は、すべて「神に捧げる舞」です。
男性が舞うお神楽もありますが、それらはすべて「観客に、その神様のことを説明するための舞」です。
お雛様のひな壇は、最上段に天皇皇后両陛下がおわしますが、その下の段は三人官女で女性、次の段が五人囃子で童子、男性最高位の左大臣、右大臣は、その下の段です。
なぜなら神に通じる主上と対話できるのは、女性だけに与えられた特権だからです。
どうしてそのような思想になったのかと言うと、縄文以来の万年の単位で続いてきた我が国は、古い昔から魂を持った子を生むことができる女性のみが、神から直接に魂を授かることに偉大な神聖を見出してきたからです。
そしてこのことを裏付けたのが、神話に登場する最高神であり女性神である天照大御神であり、またその天照大御神と直接対話することを役目とする天宇受売命(あめのうずめのみこと)です。
神道では、なくなった方は、その家の守り神になります。
その守り神となったご先祖と直接対話できるのは、その家を代表する女性です。
だから世帯を取り仕切る女性のことを東日本では「カミさん」といい、西日本では「佳(よ)き女(め)」で「よめ」といいます。
西洋では女性は、イブの時代から、男性(夫)によって支配されることが人類女性としての原罪です。
我が国では女性は神の代理です。
だから責任があります。
その責任の自覚が、我が国の女性をして、古来、凛とした女性を育てたのだし、だからこそ世界最古の女流文学も女性の手によって書かれたし、現代につながる日本の形もまた、女性の天皇である推古天皇や持統天皇によって築かれています。
女性を礼賛するために申し上げているのではありません。
力の強さなら、男性の勝ちです。
世界中、どこの国においもて、どの民族においても、歴史を通じて権力とは「力」です。
そして国の軍事と警察と財務を握った者が、その国の最高権力者です。
けれど、我が国では、その「力」を超える存在を、社会の中心に置きました。
それが天上の神々とつながる天子様であり、その天子様によって、権力者が支配する民衆が「おほみたから」とされたのです。
天子様は、人であり、権力者よりも上位にある国家最高の「権威」です。
そして権威は、権力を超えることができます。
権威は、古くて長い歴史伝統文化によってのみ育まれます。
なぜなら、権力には「古い」ということがないからです。
権力は常に入れ替わり、「古さ」を持つことはできません。
なぜなら政変によって、毎度、権力が根底から否定されてしまうからです。
「力」による権力は、より大きな力の前に屈するのです。
そして、どんな理不尽でも、力があれば許されるというのでは、決して人類社会に平和と安定をもたらされることはありません。
そしてその力を理知的に抑えるものが、何が正しく、何が間違っているのかということを明確にする価値観です。
そして価値観は、「古い」ということが価値になります。
我が国では、こうして「力よりも、正しいことがある」という信念が育まれました。
つまり男性の持つ「力」を凌駕することができる正義を、女性たちが保持することができるようになりました。
そしてこのことが、我が国の女性が外地に出たとき、多国の人々から、
「日本人女性は凛としている」
とみられるようになった根拠です。
※この記事は2009年2月のねずブロ記事をリニューアルしたものです。