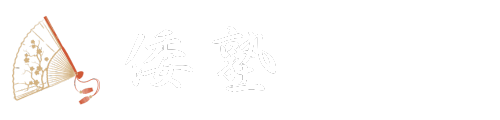古事記の国譲り神話に、高天原から派遣された天若日子(あめのわかひこ)が、神罰によってお亡くなりになるシーンがあります。
このときちょっと不思議なお話が書かれています。
全文になると難しくなるので、できるだけやさしく、また短く要約してみます。
高天原(たかあまのはら)から、天孫降臨のための前振りとして葦原中国(あしはらのなかつくに)派遣された天若日子(あめのわかひこ)は、その報告が充分でなくて高天原の高木神から「仕事をしていないのではないか」と疑われてしまいます。
高木神は、「もし天若日子が悪意なら、この矢によって罰を当てよ」(あくまで意訳です)と、高天原から矢を放ちます。
その矢は天若日子の胸に刺さり、天若日子は亡くなってしまいます。
天若日子の妻の下照姫(したてるひめ)です。
彼女は葦原中国の大王である大国主神の娘です。
天を照らすのが天照大御神、だから地上(下の国)を照らす立派な女性になってほしいという大国主神の願いが、この下照姫という御名に込められています。
下照姫は夫の死を悲しみ、その哭(な)く声は風とともに響いて高天原まで聞こえました。
泣き声で天若日子の死を知った天若日子の父の天津国玉神(あまつくにたまのかみ)とその妻子(つまり母と兄妹)たちは、高天原から中つ国まで降りて来ると、下照姫とともに嘆(なげ)き悲しんで、天若日子の亡くなったところに喪屋(もや)を建てて、八日八夜、葬儀を行いました。
そんな葬儀のときに、阿遅志貴高日子根神(あちしきたかひこねのかみ)が、天若日子を弔(とむら)いにやってきます。
すると天若日子のご両親や妻の下照姫たちが、
「我が子は死ななかった。
我が君は死んでなかった!!」
と、みんなで阿遅志貴高日子根神の手足に取りついて涙するのです。
古事記はここで、「天若日子と阿遅志貴高日子根神の二柱の神の容姿がたいへんよく似ていたから間違えたのだ」と書いています(原文:其過所以者、此二柱神之容姿、甚能相似、故是以過也)。
ところが阿遅志貴高日子根神(あちしきたかひこねのかみ)は、これにおおいに怒り、
「我は愛(うるは)しい友だからこそ弔(とむら)いに来たのだ。
なにゆえに吾(あ)を穢(きたな)き死人に比べるのか!!」
と云うと、腰に佩(は)いた十掬剣(とつかのつるぎ)を抜いて喪屋を切り伏せ、バラバラになった喪屋を足で蹴散らして、そのまま忿(いか)って飛び去ってしまわれます。
そして古事記は、このあと次のように述べています。
この事件があった場所は、美濃国の藍見河の河上の喪山です。
そして上にある十掬剣(とつかのつるぎ)の名は、大量(おほはかり)で、またの名を神度剣(かむどのつるぎ)といいます。
こうして阿遅志貴高日子根神が、忿(おこ)って飛び去ったとき、高比売命(たかひめのみこと=下照姫)は、その御名をあきらかにしようと思われ、その思いを歌に託されました。
あめなるや おとたなはたの
阿米那流夜 淤登多那婆多能
(天上界においでになる若い機織り娘が首に架けている首飾り)
うなかせる たまのみすまる
宇那賀世流 多麻能美須麻流
(その首飾りの 緒で貫いた宝玉は)
みすまるに あなたまはや
美須麻流邇 阿那陀麻波夜
(緒ひもで貫いた 宝玉は)
みたに ふたわたらす
美多邇 布多和多良須
(二つの美しい御谷(みたに)を渡る)
あちしきたかひこねのかみそや
阿治志貴多迦比古泥能迦微曾也
(阿治志貴高日子根神だったのです)
そして古事記は、
「この歌は夷振(ひなふり)といい、
いまも楽器とともに演奏されている歌です」
と、この物語を〆ています。
さて、実はこの歌が、この物語の種明かしをしています。
歌の中に「二つの美しい谷を渡る(美多邇 布多和多良須)」とあります。
天上界とは、高天原のことです。
その天上界のひとつの宝玉が二つに渡るというのは、
1 天若日子が高天原と中つ国を渡る神であるということと、
2 天若日子の魂と阿遅志貴高日子根神が、同じひとつの魂である
という二つの意味が掛けられています。
そしてその名が「阿治志貴高日子根神」です。
なぜか物語に出てくる「阿遅志貴高日子根神」の「阿遅(あち)」が、歌では「阿治(あち)」と字が替わっています。
「阿遅志貴高日子根神」は、下照姫の兄だというのですから、そうであれば大国主神話の子です。
そしてこの時代、妻のことを妹(いも)、夫が婿殿であれば兄(あに)と呼ばれました。
つまり婚姻は、互いに身内となったということだからです。
そして「阿遅志貴高日子根神」という名をよく見ると、
「志貴」は貴い志
「日子根」は、日が天照大御神をあらわしますから、天照大御神の子孫(子)を根とするというお名前になっています。
つまり「阿遅志貴高日子根神」は、天照大御神の血筋ですと名前に書いてあるのです。
そして「阿遅」は「遅れてやってきた」という意味です。
葬儀のとき、その阿遅志貴高日子根神がやってきました。
すると天若日子の父とその妻らは、皆、泣きながら、「我が子は死んでなかった」、「我が君は死んでなかった」と言って、手足に取りついて泣きました。
なぜかというと、その阿遅志貴高日子根神が、亡くなった天若日子とそっくりだったからです。
そして歌は、「玉を緒で貫き、二つの美しい御谷(みたに)を渡る」と詠んでいます。
そしてその玉の緒は、天上界で紡がれたものであるとあります。
天若日子は、天上界である高天原で生まれた神です。
その御魂が緒でつながっているということは、「死んでない」ということです。
その死んでない天若日子が、「阿治志貴高日子根神ぞ」と詠んでいます。
「阿遅(あち)」が、歌では「阿治(あち)」に替わっています。
はじめの「阿遅」は、葬儀に遅れて(葬儀が始まってから)やってきたということです。
あとの「阿治」は、間違いを整えようとしたということです。
「治」には、間違いを整えるという意味があるからです。
「治」が間違いが整えられたという意味なら、後年、天若日子は嫌疑が晴れて、再び下照毘売と幸せに暮らしたということを意味します。
だから下照姫のお名前も、ここで高比売(たかひめ)と変わっています。
夫が「志貴(貴い志)」なら、妻は「高」です。
二神揃って、高い貴い志を遂げられたという意味になります。
つまり、天若日子は、生きていたのです。
天照大御神のもとで、高天原の統治を行う高木神に疑いをかけられて矢を射られた天若日子は、自分は死んだことにして世から身を隠したのでしょう。
ところが自分の葬儀の様子を見に行くと、父母兄妹から愛する妻まで悲しみに暮れている。
とりわけ愛する妻が涙している様子は、遠目に見ていてもあまりにしのびない。
そこで喪屋の隙間から妻に「おい、俺だ」とこっそり声をかけたのです。
このときの妻の下照姫の喜びは、想像するにあまりあります。
なにしろ「死んだ」と言われながら、ご遺体さえもないままに、葬儀を営んでいたのです。
「きっとどこかで生きているに違いない」という思いと、愛する夫が帰らぬ人となったのだという悲しみと、その両面から打ちのめされていたところに、物陰から夫が現れる。
おもわずびっくりして「あなた!!」と声をあげたら、そこにいる天若日子の両親もそれに気づいて、みんなで天若日子を取り囲んで、「良かった、良かった」と涙するわけです。
けれども表向きは天若日子は死んだことになっているのです。
生きていたとわかれば、再び追っ手に襲われることになる。
だから天若日子は、
「俺は葬儀に遅れてやってきた(阿遅)志の高い(志貴)高天原の天照大御神の末裔(高日子根)の神だ」
と、別人を装うわけです。
そして喪屋を蹴散らし、祭壇を壊して、去っていく。
下照姫は後日、歌を詠みます。
その歌は、
あちしきたかひこねのかみそや
阿治志貴多迦比古泥能迦微曾也
(阿治志貴高日子根神だったのです)
さらに古事記は、この歌の中で「阿遅」を「阿治」と書くことによって、天若日子への嫌疑が間違いであったこと、そしてその間違いが整えられる(なおされる)ことを強く希望していることを明らかにしています。
そしてその結果がどうなったのかというと、
「この歌は夷振(ひなぶり)なり(原文:此歌者夷振也)」
と書いています。
夷振(ひなぶり)というのは、楽器とともに演奏される歌謡のことです。
そして天若日子と下照姫の愛の物語は、その後も長く歌い継がれたのです。
表向きは言えないことを、歌に託して真実を伝えるといった取り組みは、幕末ころまでよく行われたことです。
坂本龍馬が紀州藩に持ち船を沈められたとき、紀州が金を払わないと揶揄(やゆ)する歌を流行らせたり、高杉晋作もまた、幕府を揶揄する小唄を作って流行らせたりしています。
その昔も同じで、流行歌(はやりうた)にして、これを広げて言えないメッセージを伝える。
こうしたことは、かつての日本ではよく行われてきたことです。
「阿遅」と「阿治」、その違いを歌にした下照姫の歌は、当然、高天原にも聞こえたことでしょう。
そして天若日子への嫌疑が晴れたことは、下照姫が「高比売命」となったことに明らかです。
なぜなら下界を意味する「下照」が、高天原を意味する「高」に替わったのです。
つまり、高天原出身の天若日子の妻として、正式に認められたということです。
常識的に考えて、天若日子への処罰を取り消すことは、高天原の高木神にはできません。
矢に当たったことは、神々の意思であり、これをくつがえせば、高天原が神々の意思を軽んじたことになってしまうからです。
けれど、阿治志貴高日子根神と下照姫が二人仲良く余生をまっとうすることまでは、高天原にも否定できません。
つまり、二人はこの事件の後、仲睦まじく余生をまっとうしたということになるのです。
物語のあった場所は、美濃国の藍見河の河上の喪山(原文:此者在美濃國藍見河之河上喪山之者也)です。
場所には二説あり、
現在の岐阜県美濃市御手洗にある天王山と長良川のこととするもの
岐阜県不破郡垂井町にある喪山とするものがあります。
ここでひとつの疑問が起こります。
この物語は出雲神話で、大国主神は出雲(いまの島根県)に在あります。
ところがその娘の下照姫は、結婚した夫が亡くなったとき、美濃国(いまの岐阜県)で葬儀を行っているのです。
これはどういうことを意味しているのでしょうか。
昔の人には常識であったことが、現代では非常識になっているものというものがよくあります。
まして日本の神話の場合、そこに描かれた世界観は、2〜4万年もの昔までさかのぼるものです。
万年の単位となれば、地形も違えば気温気候も現代とは異なります。
そして高天原というのは、これをこの世の他の神々の世界としたのは、江戸時代の本居宣長です。
それまでは、高天原は地上にあった国であるとされ、その所在地も北は北海道から南は沖縄まで、全国随所に、その所在地が散らばっていました。
散らばっている理由は、江戸時代まではわからなかったことなのですが、現代では、万年から千年の単位となると、その間に気候が著しく変動したことが学問的に解明されています。
そして数千年の昔なら、それは縄文時代ですが、縄文時代後期の日本列島全域の人口がおよそ26万人。
中期以前ならおよそ10万人程度であったことも判明しています。
日本列島全体で、人口が10万〜26万人なのです。
土地の所有権も、県の境界線もなかった時代です。
しかもいまのようなヒートテックはないし、エアコンによる冷暖房もありません。
当然のことながら、人々は寒冷化すれば南へと向かうし、温暖化すれば住みよい北へと向かいます。
つまり、高天原は、時代とともに移動していたし、移動していたことが、全国各地に「ここに高天原があった」という場所がある結果になっていると考えられるのです。
そして、美濃国の北側にあるのが、旧行政区分の飛騨国です。
飛騨(ひだ)は、いまでこそ飛騨と書きますが、もともとは「日高見国(ひだかみのくに)」と呼ばれた地です。
『大祓詞』にも「大倭日高見国」として、その用語は出てきます。
漢字は、後から当てられたものですから、もともとの大和言葉では「ひたかみの国」、「ひ」は天照大御神、「たかみ」は、高所で天照大御神のお姿を見ることですから、「日高見国」は、高天原に近い場所、高天原を見ることができる高所、もっというなら、天照大御神にお目にかかることができる気高い場所という意味の言葉とわかります。
そしてこの物語が、飛騨に高天原があった時代とするならば、大国主神話がその娘を嫁がせた場所は、その高天原により近い場所、つまり美濃国であったとして、物語が自然につながるのです。
要するに、天照大御神直系の天若日子と、大国主神の娘の下照姫は、事件後、美濃国で二人、幸せに暮らしたのです。
このように『古事記』は、たとえ罪人としてお亡くなりになった方であっても、ただ悪人だった、裏切り者だったと軽んずるのではなく、「結果として謀反人になってしまったけれど、真剣な愛に生きたという良い面もあり、また妻に心から愛された男であった」ということを、ちゃんと書いています。
そしてそのことが歌となり、永く語り継がれているとも書いています。
どんなに良くしてもらっても、戦いに破れたら手のひらを返したように、彫像までつくって通行人に唾をはきかけることを強要する国もあります。
けれど『古事記』は、どこまでも、人の愛を尊重しています。
それが日本のこころです。
そして人の愛を尊重する、あるいは活きる、ないしは認められる社会というものは、たいへんに民度が高い社会です。
民度が低く、誰もが自分の利益ばかりを追求するような国では、「咎人であってもその愛を尊重」するなどという甘いことは言ってられないからです。
すこしでも甘い顔をしたら、すぐに民がつけあがって、自分の利益だけを声高に主張し、我儘を押し通そうとする。
ですからそのような民を持つ国では、政府は厳罰主義で、一片の情のカケラもない苛斂誅求の辛き政府にならざるをえません。
これは福沢諭吉が説いていることでもあります。
そしてそのような国では、政府が民の民度を信じる姿勢を見せれば見せるほど、民衆はつけあがり、一部の者だけが利権を貪り、その利権を貪る者が、心が貧しくなった民衆を扇動して、より一層、愚かな貪りをし抜くようなになります。
悲しいことですが、そのような国においては、政府が民を人間と思ってはいけない。
李承晩は、朝鮮戦争のときに自国民を片端から虐殺しました。
朝鮮戦争による南朝鮮の死者は、北に殺された人の数より、自国の軍隊に殺された人の数のほうが圧倒的に多かったとも言われています。
そしてそのことの罪を問う声は、いまだに国の内外からひとつもあがっていません。
毛沢東も、1億人以上の自国民を殺したと言われています。
けれど彼もその国、その民族にとっては「偉大な英雄」です。
李承晩にしても毛沢東にしても、それぞれその本人にとっては、ある意味幸せで充実した生涯であったかもしれません。
しかし、そうした人をリーダーに仰ぎ、そうした人の持つ政府によって虐殺されたり収奪されたり、あるいはかろうじて生き残っても、極貧生活を余儀なくされる国民、あるいは民衆にとって、その時代は幸せな時代であったということができるのでしょうか。
なにより大切なこと。
それは誰もが豊かに安心して安全に暮らせる。
そういう社会の建設です。
そしてそういう社会であり、民族であればこそ、たとえ咎を受けたとしても、その夫を愛する妻の想いとその心が大切に尊重され、歌にまでなって、永く讃えられたのではないでしょうか。
冒頭にある小灘一紀(こなだいっき)画伯の絵は、その下照姫(下照比売)です。
小灘一紀画伯は、古事記を題材に様々な絵を書き、展示会等を通じて古事記の普及に携わっておいでの境港ご出身の洋画家です。
どの絵も、とても美しい絵です。
※この記事は2016年8月の記事を大幅リニューアルしたものです。