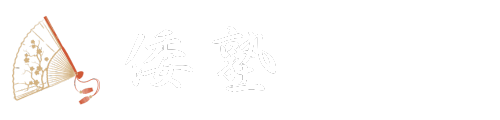戦争とはなにか。
これに明確な答えを出したのが19世紀初頭に活躍したプロイセン王国のカール・フォン・クラウゼヴィッツの名著
『戦争論』
です。
クラウゼヴィッツは、ナポレオン戦争にプロイセンの将校として参戦した人です。
この戦いで戦闘での敗北と捕虜としての抑留経験を持ちます。
虜囚を解かれてベルリンに帰還したとき、当時のプロイセン王国はフランスの占領下にありました。
プロイセン国王のもと、プロイセン陸軍の再編に尽力したクラウゼヴィッツは、第3軍団参謀長としてワーテルローの戦いを勝利に導き、その後に本書を起草しています。
そして彼の死後に遺稿として発表されたのが、この『戦争論』です。
クラウゼヴィッツはこの本の中で、戦争とは「暴力による決闘」でと説きました。
そしてその暴力は、政治的、社会的、経済的、地理的な要因によって抑制される。
つまり戦争は、政治に従属されたものである。
だから戦争は、
「国家の行う究極の外交手段である」
と説きました。
戦争は、「国家が行う、政治に従属した、外交手段」なのですから、当然、戦争にルールが必要です。
このルールが定められたのが、1899年、および1907年のハーグ陸戦条約です。
この条約には、当時の世界の主要44カ国が条約を批准しています。
そしてこの条約によって、世界の各国は、戦争において、交戦者は正規軍、民兵、義勇兵に限ることになりました。
具体的には、交戦者の資格を得るのは、
1 部下の責任を負う指揮官が存在し
2 全員が遠方から識別可能な固著の徽章を着用し
3 公然と兵器を携帯していること。
および、
4 一般の民衆であっても、公然と兵器を携帯していれば交戦者とする
とされました。
そしてこれ以外の者、たとえば一般の民衆等は交戦者ではないので、これを殺害することは交戦行為とは認められないと定められました。
「交戦行為として認められない」ということは「ただの殺人行為だ」ということです。
「ただの殺人行為」なら、そこに戦時国際法は適用されません。
適用されないということは、それはただの不法な暴力であり、ただの殺人や傷害であるということです。
そして万国共通で、殺人や傷害は、それが軍人が行うものであろうがなかろうが、刑法上の罪にあたるものとなります。
もっとも世界には、条約やルールというものは、あくまで「相手に守らせるもの」であって、自分が守る必要はなく、勝てばすべてが正当化されるという考え方を持つ野蛮な国や民族もあります。
あるいは、一般人を大量虐殺しても、戦争に勝ちさえすれば良いという考え方も、世の中には存在します。
これらを称して「野蛮国」といいます。
我が国は「野蛮国」ではありません。
世界に冠たる武士道の国です。
ですからハーグ陸戦条約批准後、その内容が明治45年1月13日に、
『陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約』
として公布され、軍においても、これを徹底することが求められました。
国際条約は国内法に優先することが、世界の常識です。
我が国はこの条約を遵守して、以後の戦争を戦ったのです。
大東亜の戦いにおいて、チャイナの国民党軍は、はじめからこの条約を護る姿勢がありませんでした。
それでも我が国は、あくまでこの条約を国際法として遵守しながら、戦いを進めています。
いかなる卑怯卑劣な仕打ちを受けても、だからといって日本までもが同じ卑怯卑劣な振る舞いをすれば、それは、平和を求めるチャイナの民衆の規範にならないからです。
だから日本にとって、条約を護ることは、世界に規範を示すことでもあったのです。
このことは、我が国がもともと武士道の国であったことも、おおいに関係しています。
武士は、殿の命令とあれば、果敢に敵と戦わなければなりません。
そしてこの場合、戦って自分が死ぬことは、まったく問題にされません。
相手がどんなに強い相手であっても、果敢に正々堂々と戦うのが武士であって、結果が自分の死であっても問題にならないどころか、それこそが名誉とされてきた歴史を持つのです。
逆に、戦わない(たとえば剣を抜かなかった)ということであれば、それは士道不覚悟として、処分の対象となりました。
武士は、社会の規範でしたから、そういうものなのです。
また、シナ事変の場合、これはそもそも戦争でさえなかったという面があります。
この時代、日本はもちろん国でしたが、当時のチャイナには、ちゃんとした行政機能を持った政府もなければ、法もありません。
単に軍閥である国民党や八路軍が暴れていただけの状態です。
そしてチャイナは、軍閥とヤクザと愚連隊が同じものという伝統を持った地域です。
日本は、そんなチャイナに、あくまでも北京議定書に基づく国際協調による平和維持部隊として、軍を派遣していたのです。
当時の日本が願ったことは、どこまでも平和を愛するチャイナ政府が誕生すること、その政府によって、チャイナに平和が戻ることでしたし、そのための派遣軍であったのです。
その派遣軍が、率先して「戦争論」でいう「殺戮行為」に走るなら、派遣軍としての意味さえもなくなってしまう。
だから日本軍は、どこまでも公正な軍であろうとし続けたし、日本の民間人もまた、その意識を強く持っていたのです。
ここにひとつの逸話があります。
通州事件のとき、通州でさんざん暴虐の限りを尽くしたチャイナの学生たちは、日本軍がやってくると、通州から逃げ出して、その多くが北京市内に流れ込みました。
腹を減らして逃げてきた若者たちに、当時北京に住んでいた日本人は、食事を出してあげ、故郷へ帰る路銀まで私てあげて、「まっとうな人間になれよ」と説諭して逃がしてあげています。
また、通州事件の模様が日本国内で報道されたとき、日本には当時もチャイナタウンがありましたが、そのチャイナタウン限らず、日本にいるチャイニーズたちが日本人によって暴行を受けるような事件も、一件も起きませんでした。
日米戦争においても、初期から中期にかけて戦いは、日米ともに条約を遵守して行われていたといえます。
日本軍は、民間への攻撃をすることはなかったし、米英仏欄軍もまた、日本の民間人への攻撃は行っていません。
(米国では米国内に居住する日本人が隔離されていますが、これは日本人の安全を確保するためという理由もまた成り立つものです)
ところが、グアム、サイパン戦あたりから、この様子が変化し、さらにこの戦争が明らかに民間人への虐殺行為へと変化したのが、広島、長崎への原爆投下です。
原爆投下は、これはもはや国家の外交交渉の延長線上にある戦争行為を明らかに逸脱する、民間人への虐殺行為です。
民間人への虐殺は、戦争行為ではありません。
完全な暴力行為です。
たとえ国家意思のもとで行われたとしても、これは明らかな犯罪です。
我が国は、正々堂々の戦争を行なったのです。
我が国は、国家として、暴力や犯罪に加担する意思は持ち合わせていません。
原爆投下によって、日米戦争は戦争ではなく、ただの虐殺、ただの暴力に変化しました。
そのような暴力に我が国は加担する意思は一切持ち合わせていません。
ですから、我が国は、8月15日に自主的に戦闘行為を終結させたのです。
だからこの日を「終戦の日」と呼びます。
日本は、白旗を掲げて降参したのではないのです。
「誇りを持って暴力を否定した」のです。
我々は、昭和天皇のこの御聖断を、誇りに思うことです。
このことは、いずれ、世界の常識になっていくことです。
※この記事は2022年8月の記事のリニューアルです。