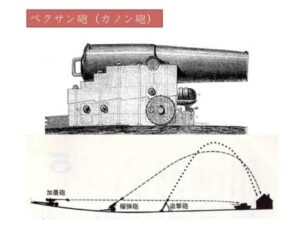昭和12(1937)年にヘレン・ケラーが来日しました。57歳のときです。
このとき日比谷公会堂で、ヘレン・ケラーに大きな日本人形が渡されました。
渡したのは中村久子さんという、当時41歳の女性です。
上はそのときの写真です。
大きくて美しい日本人形が写っています。
みるからに、しっかりとした作りです。
一緒に写っているのが中村久子さんです。
写真を見て、なにか気付きませんか?
この中村久子さんは、実は、両手両足がありません。
一緒に写っている人形は、彼女が、クチを使って、器用に縫った人形です。
中村久子さんは、明治30(1897)年に、岐阜県北部の高山で生まれました。
「飛騨の高山」として有名なところです。
冬は、深い雪に埋もれます。
その寒さのために、彼女は2歳のときに、凍傷に罹ってしまうのです。
最初は、左足の甲だけだったそうです。
けれど凍傷は、次第に左手、右手、右足へと広がり、脱疽(だっそ)をひき起こします。
脱疽というのは、体の組織が壊死(えし)していくことです。
そして壊死した部位は、こんどは腐敗菌に感染します。
すると人の体は、肌色ではなくて、まるで墨を塗ったみたいな真っ黒になります。
本当に墨のように真っ黒になります。脱疽です。
そうなっていく過程で激痛を伴ないます。
真っ黒になったところは、すでに組織が死んでいますから、その部位は切り取らなければなりません。
つまり手足を斬り落します。
そうしなければ、感染部位が体全体に広がり、命が失われるからです。
切れば、命は保たれます。けれど両手両足がなくなります。
切らなければ、死にます。
ご家族は、親戚まで集まって、たいへんに悩まれたそうです。
そして幾度となく親族会議が行われ、決断がでないうちに、左手が手首からポロリと崩れて落ちてしまったのだそうです。
結局、右手は手首から、左足は膝とかかとの中間から、右足はかかとから切断しました。
中村久子さんが、まだ3歳になったばかりのときのことです。
7歳の時に、父が世を去りました。
10歳のときには、弟が亡くなりました。
そんななかにあって、祖母と母は、久子さんを、ただ甘やかす育て方はしなかったそうです。
おかげで、久子さんは、口をつかって器用に文字を書き、さらには編み物まで、自分でできるように育っていきました。
大正5(1916)年、20歳になった久子さんは、地元高山を離れて上京し、横浜市などで一人暮らしを始めました。
けれど、母と再婚した継父に、見世物小屋に「だるま娘」の名で身売りさせられてしまいます。
見世物小屋での久子さんは、文字通り手足のないダルマ女として見せ物になりながら、手足のない体で、裁縫や編み物を見せる芸を披露しました。
後年久子さんは、当時を振り返って、次のように語っています。
「(障碍者だからといって)恩恵にすがって生きれば、甘えから抜け出せません。一人で生きていく。そう固く決意しておりました。」
実際、久子さんは、生涯を通じて国による障碍者保障を受けることをしませんでした。
そして彼女は、見せ物となって全国行脚して生計を立てながら、結婚し、二女をもうけています。
そして昭和12(1937)年には、来日したヘレンケラーと会い、口を使って作った日本人形をヘレンケラーに贈りました。久子さん41歳のときのことでした。
久子さんは、50歳頃から執筆や講演などの活動をはじめました。
彼女は講演で、自身の奇異な生い立ちを語るとともに、自分の体について恨まず、むしろ障碍のおかげで強く生きる機会を貰ったと語りました。
中村久子さんの言葉です。
「『無手無足』は、私が仏様から賜った身体です。
この身体があることで、
私は生かされている喜びと尊さを感じています」
「人は肉体のみで生きているのではありません。
人は心で生きています。」
「人の命は、つくづく不思議なものです。
確かなことは自分で生きているのではない、
生かされているのだということです。
どんなところにも必ず生かされていく道がある。
すなわち人生に絶望なし。
いかなる人生にも決して絶望はありません。」
昭和43(1968)年3月19日、中村久子さんは、脳溢血のため、高山市天満町の自宅でお亡くなりになりました。享年72歳でした。
三つのことを申上げたいと思います。
1 自立する
ひとつは、障碍者でありながら、自立した女性として強く生き抜いた中村久子さんという女性の強さと輝き、そして強い心です。
辛いこと、苦しいこと、どうしようもないことを、他人のせいにし、恨み、ねたみ、そねみ、他人の足を引っ張っる。
自分は弱者だと規定し宣伝し甘える。
特に政治関連ですと、政治的に敵対し、他人の悪口を言って貶めることで自分自身の小さな自己満足に浸る。
昔の人は、そういうことを良しとしませんでした。
どんなに辛くても、苦しても、自立し、魂を磨いていく。
男女を問わず、それが人としてあたりまえのことだという認識が社会人としての常識でした。
それこそが誇りであり、気骨であったわけです。
2 不自由であっても不幸ではないという気骨
二つめは、来日したヘレンケラーが、中村久子さんに、「私より不幸な人、そして、私より偉大な人」と言ったのは、単にヘレンと比較して、久子さんの傷害が重くて不幸だと言っているのではない、ということです。
ヘレンケラーは、自分以上にたいへんな傷害を抱えながら、挫けることなく、明るく強く生きている中村久子さんを「偉大だ」と言っているのです。
先般も書きましたが、徴兵され戦地の最前線に行ったのは、徴兵検査で「甲種合格」となった方々です。
徴兵検査は、結果が甲乙丙丁戌の5種類でしたが、その基準を見てびっくりでした。
現役時代の私は、柔道をやっていたし身体頑健には自信があったのですが、基準に照らしたら丙種でした。
これは現役兵にはなれず、後方での国民兵になれるだけ、という結果です。
では、甲種合格となる人はどういう人かというと、だいたいひとクラスに1人いるかいないか。
つまり、級友の中で、とびっきりの健康優良児の優秀な若者しか、兵役にとってもらえなかったのです。
そういうとびっきりの健康優良児が、兵役にとられ、30キロの背嚢を背負って何百キロも行軍し戦う。
戦えば怪我人も出ます。
なかには手足を失う者もでます。
そんな不具者がどうなったかというと、治療後にいまでいうリハビリ施設にはいるのですが、そこで徹底的に厳しい訓練を受けて社会復帰したそうです。
そういう人達の伝記が、東京・九段下の「しょうけい館」に展示されていますが、彼等が語った言葉に、愕然としました。
そこに書かれていたのは、
「私の人生は、不自由だったが、不幸ではなかった」
3 見世物小屋のこと
もうひとつ、久子さんが「見世物小屋に売られた」ということについてです。
「売られた」というと「ひどいことをされた」と条件反射的に思うとしたら、それは戦後史観に染まっています。
なるほど親元を離れるわけですから、さみしさもあるでしょう。
他人の中で暮らすというのは、つらいこともあるでしょう。
けれど、子が親元を離れ、丁稚奉公に出るというのは、どこの家庭でもあったことです。
その丁稚に出たのが、たまたま障碍を抱えていたから見世物小屋だったということです。
その見世物小屋は、すこし大きな縁日といえば、屋台の露天だけでなく、化け物屋敷(幽霊屋敷)などと並んで、昔は必ず出たものです。それは定番の屋台といって良いものでした。
そして障碍を持った人の見世物小屋というのは、ただ障碍者をそこに座らせて見せるだけでは、お客さんは入りません。
あたりまえのことです。
そんなもの見たがる人の方が、よほどの変人です。
むしろ、見たがる人こそ、見世者にしたいくらいです。
見世物小屋のお客さんは、もちろん「こわいもの見たさ」に入るケースもあるでしょう。
けれど、ただ「こわいもの」がそこにあるだけでは、お客さんは二度と来てくれないのです。
たとえば今日のテーマの中村久子さんのようなケースでは、手足のない「だるま女」として見せ物になりました。
そう言われて恐いもの見たさに入場したお客さんも、その興行を許可するお上も、ただ手足のない女性を見るというだけなら、お客さんたちは二度とその小屋に入らないし、お上もそんな見世物小屋は絶対に許可などしません。
そうではなく、手足がなくても、和裁をしたり、きれいな書を書いたり、けっしてくじけず芸事を磨いて必死に生きている。
その姿を、お客さんたちは見たのです。
そのために見世物小屋の興行主は、障碍者だからといって決して甘やかせたりはしませんでした。
身の回りのことは全部自分でやらせたし、両手両足がないダルマ女であっても、口にくわえた筆で、健常者でさえも及びもつかないほどの見事な書を書いたのです。
だから見世物小屋にはいったお客さんは、そこで障碍を抱えながらも一生懸命まじめに努力して生きている姿を目の当たりにしました。
そして次には、友達を連れてきてくれました。
障碍があっても頑張って生きている。まして自分たちは五体満足に生まれてきているのだから、もっと一生懸命生きなければと、あらためて感じることができるからです。
だからそこには感動がありました。
それが「見世物」だったのです。
つまり「見世物」にしたのは、「両手両足がない」ことを見世物にしたのではなくて、そういう障碍を抱えたひとりの女性が、両手両足がなくても立派に書を書き、裁縫をし、健常者以上の仕事をこなしている。
その凛とした姿が「見世物」となったのです。
ここが日本における興行の、ちょっと違うところです。
だからお客さんも、木戸銭を払って中にはいるけれど、出るときにはその障碍者のためにと、寄付までしてくれる。
その寄付金は、見世者になっていた障碍者だけではなく、小屋に出れないもっと重度の障碍者のために使われる。
そうやって互いに助け合い、ともに支えあって生きる社会を築いてきたのが、私達日本人だったのです。
綺麗ごとを言っているのではありません。
感動がなければ、お客さんははいってくれないし、二度と来てくれないし、ましてリピーターなどないのです。あたりまえのことです。
見世物小屋が人を見せ物にすることは、昭和50年に法律で禁じられました。
「それは人道的ではない」ということが理由です。
けれど、障碍者を、ただ手足が不自由だからと法で社会から隔離したり排除したりする社会と、みんながむしろ障碍者から学び、みんなの力で障碍者を支えた社会と、果たしてどちらが人道的な社会といえるのでしょうか。
北島三郎が歌った演歌『風雪ながれ旅』のモデルになったのが、津軽三味線の高橋竹山です。
3歳で失明し、盲目の戸田重次郎のもとで三味線を習い、門付け三味線芸人として身を立てる一方で、それだけでは飯が食えずに鍼灸師とマッサージ師の資格をとり、それでも努力を重ねて、いまでいう津軽三味線のスタイルを確立したのが高橋竹山53歳のときです。
障害者だからといって甘えないし、甘えさせない。
むしろ障害があるからこそ、障害者自身は自分を磨いて凛々しく生きようとしたし、周囲もそれを温かく見守った。
どんなに辛くても、その辛さ自体が自分を磨くことだと考えた。
それが日本人であったのだということを、私たちは学ばなければならないのではないでしょうか。
※この記事は2015年9月のねずブロ記事の再掲です。