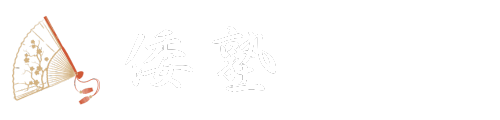もともと何もない荒れ果てた荒野だった満洲が、なぜ日本が関与した時代から急激に発展したのでしょう。
満洲について政治、軍事から語るものは多いが、経済の面から紐解(ひもと)いたものは少ないようなので、これについて考えてみます。
その答えが大豆(だいず)にあります。
きっかけは明治の中頃、商社マンとして満洲に一番乗りした山本条太郎(やまもとじょうたろう)にあります。
後に満鉄総裁になった男です。
彼は慶應三(1867)年生まれ、福井県旧御駕町出の元福井藩士の子です。
明治十三 (1880)年、12歳で神田淡路町の共立学校(現・開成高校)に入学したのですが、病弱なため2年で中退しています。
そして学問をあきらめ、三井洋行(現・三井物産)横浜支店に丁稚奉公(でっちぼうこう)に出ました。
働き者で主人の覚(おぼ)えもめでたく、21歳のとき、選ばれて上海支店に転勤しました。
ここでも彼は抜群の商才を買われています。
明治二十三(1890)年、彼が23歳のとき、上海フランス租界(そか)の近くの交差点口に、三井支店長の社宅が建設されました。
この建物は一万坪の土地に、三階建ての本館と別館、更に付属の建造物があり、広大な庭には池、温室、芝生の野球場と5面のテニスコートが作られ、正門から本館の玄関までには、実に百メートルの小道があり、樹齢30年以上の桜が280本も植えられていたそうです。
そしてここで毎年3月に園遊会が開かれ、国内外の2千人の官民人が招待されました。
当時この園遊会に招待されなかった者は社会的に紳士として認められていないとまでいわれたそうです。
それだけに招待客の選出には細心の配慮と苦心が重ねられたのですが、これを完全に取り仕切っていたのが山本条太郎でした。
とにかく頭が切れ、礼儀正しく、よく働く男だったのです。
そういう人物だからこそ招待客の接待役を仰(おお)せつかったのでしょう。
明治三十四(1901)年、山本条太郎は34歳の若さで三代目上海支店長に就任しました。
当時の上海支店長の社宅は、車庫には防弾処理を施された8人乗りのキャディラックが1台、8人乗りビュイック1台、中型車が2台、支店長専用車として停(と)まっていました。
車そのものが大金持ちか大臣でもなければ乗れなかった時代です。
これだけの車を備えることができたのは、それだけ三井物産上海支店に実力があったということです。
車のウインドガラスはどれも3センチ以上の厚さがあり、ドアも不注意に開けて人にぶつかると、人が吹っ飛んでしまうほど重量のあるものであったそうです。
もっともそれだけに車が重く、リッター1キロも走らないから、条太郎はもっぱら営業マンの乗る普通車ばかり使っていたそうです。
営業マン用の車は、防弾処理などされていないから危険な車ですが、軽くてよく走る。
このあたり身の安全より行動を優先した条太郎らしさがあらわれていておもしろいと思います。
上海支店長に就任した山本条太郎は、日本の商社マンとして、はじめて満洲に乗り込んでいます。
当時の満洲は、広大な荒れ地が広がるだけの緑のない半(なか)ば砂漠地帯でした。
当然、作物など作れません。
けれど条太郎は、この荒れ地で、細々ながら大豆が栽培されていることに目をつけました。
大豆は温帯、亜熱帯産の植物です。
満洲は亜寒帯です。
本来気象条件が合わないのです。
ただ大豆を筆頭に、いわゆるマメ科の植物は、根に「根粒菌(こんりゅうきん)」が繁殖(はんしょく)します。
根粒菌が繁殖するから、根の又(また)のところに、コブのようなものができます。
コブの中で繁殖した根粒菌は、大豆が空気中から吸った窒素や地中から吸い上げた水から、アンモニアなどの有機物を排泄します。
この有機物を栄養源にするから、大豆は痩(や)せた土地でも育つのです。
山本条太郎は、これに目を付けました。
気候を調べたり、品種改良の可能性を検討し、徹底して満洲での大豆の栽培の可能性を探りました。
条太郎が面白いのは、満洲での大豆の生育を研究している最中、つまりまだ満洲で大豆が生産段階に入っていないときに、早々と販路の開拓に手をつけている点です。
彼は大正九(1920)年には、英国に赴(おもむ)き、欧州での満洲大豆の独占販売権を得てしまっています。
当時の欧州には、大豆を食べるという習慣がなく、大豆はもっぱら油をとって燃料にするためにのみ栽培されていました。
これを食べさせる。
条太郎は大豆の加工の仕方や料理の指導まで行い、欧州全土に大豆の売り込みをかけています。
こうして、ほんの数トンあるかないかだった満洲の大豆は、山本条太郎が名付けた「満洲大豆(まんしゅうだいず)」の商品名とともに広く栽培されるようになり、条太郎が満鉄総裁に就任した昭和二年には、満洲の大豆生産高は、じつに年間500万トンに達するものとなりました。
このうち400万トンが輸出用で、欧米向けが200万トン。日本向けが200万トンでした。
なんと満洲は、世界最大の大豆生産国になったのです。
満洲において日本は、明治三十八(1905)年の日露戦争の勝利で、長春から旅順口までの満洲鉄道全ての権利を手に入れました。
翌明治三十九(1906)年には「南満洲鉄道株式会社」(満鉄)を設立しています。
少し考えればわかることですが、鉄道があっても、ただやみくもに大地が広がっているだけのところに列車が走るだけでは、なんの収益も産(う)みません。
日露戦争以前にロシアが、そんな、なんの収益のあてもない満鉄を作ったのは、あくまでチャイナや朝鮮、日本への軍事侵攻、南下政策のためです。
ところがその満鉄を、日本は民生用、つまり満洲の産業育成のために用いたのです。
とにかく大豆は欧州に無限ともいえる市場が開けたのです。
大豆は作れば作るだけ売れました。収穫量の8割以上が商品として輸出されたのです。
売れるから作る。
作るから売れる。
そのために荒れ地を開拓する。
開拓するから農地が広がる。
農地が広がれば、生産された大豆を運ぶために、鉄道が必要になる。
そこで満鉄が満洲全土にアメーバのように伸びたのです。
そして路線が交差するターミナル駅には、多くの物資や人が集まりました。
こうして、わずか20年前には荒涼とした漠土(ばくど)にすぎなかった満洲は、短期間に緑豊かな一大農園地帯に変貌(へんぼう)したのです。
満洲に住む農民は、大豆と小麦を売り、自分たちはトウモロコシやアワを食べたといいます。
それほどまでに売れたのです。
大豆は満洲の住民にとって、まさに黄金となったのです。
当時の記録によれば、満洲の対外貿易の50%以上が大豆です。
日本が経営した満鉄は、ただ大豆栽培を奨励しただけではありません。
大連(だいれん)には「農事試験場」と「中央試験所」が建設されましたが、「農事試験場」は大豆の品種改良や栽培試験、「中央試験所」は大豆の利用研究を進めています。
ここで研究開発されたのが、大豆油(サラダ油)の近代的製造法です。
おかげでいまや世界中の食卓をサラダ油が潤(うるお)しています。
中央試験所には、当時総勢千名を超える人員がいたといいます。
さらに満鉄中央試験所では、大豆蛋白質(たんぱくしつ)による人造繊維、水性塗料、速醸醤油製造法の技術展開、大豆硬化油、脂肪酸とグリセリン製造法、レシチンの製造法、ビタミンB抽出、スタキオースの製造法の確立などを行っています。
現在世界が大騒ぎしている大豆油を原料とするバイオ燃料の研究も、世界の先鞭をきって開発研究に取り組んだのは、満鉄中央試験場であったのです。
それだけではなく、満鉄が設置した農事試験所関係施設はなんと満洲全土で90ヶ所に及んでいます。
発表された研究報告は約千件、特許が349件、実用新案47件です。
試験所の様子については、夏目漱石も視察した模様を小説の中で紹介しています。
満鉄が大豆に注いだ情熱は並大抵のものではなかったのです。
満洲は、大豆農場が広がることで、関連産業が発展し、生産穀物の中継点となるターミナル駅が発達し、そこが街になり人口が増えることで、人々が使用する電力や交通、流通などの産業が発展していきました。
こうして満洲に大都市が誕生しました。
そして日本は、満洲において五族共和と人種の平等を目指したのです。
日本は満洲統治にあたり、つぎの三項目を基本として掲げました。
1 悪い軍閥や官使の腐敗を廃し、
東洋古来の王道主義による
民族協和の理想郷を
作り上げることを建国の精神とし、
資源の開発が一部の階級に
独占される弊を除き、
多くの人々が餘慶(よけい)を
受けられるようにする。
2 門戸開放、機会均等の精神で
広く世界に資本をもとめ、
諸国の技術経験を
適切有効に利用する。
3 自給自足を目指す。
日本はこの理想を実現するために、満洲国建設に伴う産業開発5カ年計画を策定し、当時のカネで48億円という途方もない資金を満洲に提供しています。
そして大豆、小麦といった農産物に加えて、鉄、石炭、電力、液体燃料、自動車、飛行機などの産業を育成したのです。
さらに日本は、満洲における人材教育に力を注(そそ)ぎました。
なぜなら、満洲経済の発展のためには、人材の育成が不可欠だからです。
約束を守り、時間を守るという、いわば「あたりまえのこと」があたりまえにでき、人々が創意工夫をし、公に奉仕する精神がなければ、経済の発展などありえないのです。
このことは、いまの日本の教育と真逆です。
日本経済が衰退するのも道理です。
満洲では、農業、産業、教育の振興と都市部の発展にあわせて、満鉄の路線の総延長が、昭和十四(1939)年には、なんと1万キロメートルを超え、バス路線は2万5千キロメートルに及ぶものになりました。
満洲航空輸送会社による国内航空路も、網の目のように張り廻らされました。
こうして満洲は、世界有数の経済大国として成長していったのです。
しかし日本が満洲に施(ほどこ)したこと、これはチャイナから満洲までの広大な大地の植民地支配を狙う米英からすれば「余計なこと」でした。
なぜなら、たとえば英国は満洲から大豆を大量に輸入しています。
ならば満洲を自国の支配地に置けば、すなわち完全自由貿易状態、TPP状態に置けば、そこで生まれる利益は、すべて自国のものになるのです。
しかも植民地ならば、有色人種に給料を支払う必要もありません。
そうなれば人件費コストは下がり、儲けは倍加します。
同様に、その時点でいまだ大陸内に支配地を持たない米国にしてみれば、満洲を支配することは、そこで生産される大豆やトウモロコシ、小麦の栽培で、世界の食卓を支配できることになります。
当時の米国は、フィリピンや太平洋の島々を植民地にしていましたが、そうした島々では、広大な地所を必要とする農場の経営はできないのです。
貧乏人には誰も振り向きません。
けれども儲けて金を持っている人物のところには人が集まります。
なかにはそれを奪おうとする者たちも現れます。
人も国も同じです。
満洲が豊かになると、ここに欧米が垂涎(すいぜん)を流し出したのです。
満洲国は民度も高く、産業も発達していました。
ここを植民地として奪えば、奪った国は繁栄が約束されるのです。
同時に満洲には、前々からロシアが南下圧力をかけていました。
このことは日本にとって脅威であるだけでなく、チャイナの中南部を実質的な支配下に置いていた米英にとっても、同じく脅威でした。
ロシアに生まれたコミンテルンは、平気で治安を乱し人を殺すからです。
さらにいえば、当時まだ新興国であった米国は、とにもかくにもアジアの大陸中に植民地がほしい。
いまでは米国は、自国で大豆やトウモロコシや小麦を作っていますが、広大な大地が広がる黄色人種の国家を植民地にすれば、なにも自分たちで汗水たらして働らかなくても、カラードを使役して、彼らの土地で農作物を作らせればよいのです。
目の前には、満洲の荒れ地が、見事なまでの農地となって広がっていました。
荒れ果てた大地が、見事なまでの緑豊かな豊穣な大豆畑になっていました。
しかも大豆は、もともと亜熱帯性植物です。
そうであれば、これを満洲ではなくチャイナで作らせれば、収穫高は北のはずれの満洲の比ではない。
市場はすでに日本がヨーロッパで作っています。
ジョンウエインさながらに、これを銃で奪えば、彼らにとって「人類の原罪」である労働をしなくても、腹いっぱい飯が食えて、贅沢三昧できるのです。
ひとつ付け加えておきます。
農作物は、人の子と同じで、愛がなければ育ちません。
このようなことを申し上げると、放っといても育つじゃないか!とお叱りを受けそうです。
けれど、人の子も農作物も同じなのです。
手間ひまをかけ、たっぷりと愛情を注がれた子は、すくすくと元気いっぱいに育ちます。
他方、ただ育ちさえすれば良いとばかり、機械的な育てられ方をすると、(もちろん年が経てば大人になりますが)、大人になっても、どこか斜めというか、歪みを持ってしまうのです。
植物も同じで、たっぷりと愛情を注がれて、元気いっぱい育った大豆から種を採り、これをまた蒔いて育てることを繰り返すのです。
それが毎年、幾世代にも渡って繰り返されるのです。
愛情を注がれた大豆は、世代を重ねるごとに、元気いっぱいのエネルギーに満ち溢れた大豆になっていきます。
こうした大豆は、とても美味しく、お豆腐などに加工しても、味がぜんぜん違うし、食べた人を元気にします。
ところが幾世代にもわたって、ブルドーザーと農薬で機械的に育てられた作物は、やはり味も機械的になります。
人が、人の形をしていれば、人であると言えないように、人と共に生きる農作物もまた「大豆の形をしていれば大豆」ではないのです。
日本文化は、古来、体験をとても大切にします。
断食や水行、座禅など、万巻の書をいくら読んでも、いくら話を聞いても、体験してみなければ、その凄みはわかりません。
これと同じで農作物も、たとえばピーマンの形をしていればピーマンではないのです。
愛情込めて育てられたピーマンと、機械的に育てられたピーマンでは、形は同じピーマンですが、味がぜんぜん違います。
こういうことは、実際にそういう食べ物に接してみないとわからない。
わかりやすい上手な説明が思い浮かびませんが、たとえば、です。
縄文時代に行って、縄文人たちに機械的に育てられた農作物を、入手しやすいからといって彼らに売っても、おそらく彼らは自前の畑や、山や林から採ってくる作物を捨てないのではないかと思うのです。
なぜなら、味がぜんぜん違う。エネルギーが違う。
ウチの畑の作物は、食べたら元気になるけれど、工業生産された作物は食べてもお腹は膨れるけれど、元気にはならない。それどころか病気になる。
近年の日本人は、商業資本の宣伝のせいで、味付けが美味しければ、美味しい料理と思っています。
けれど欧米では、もちろん味付けも大事だけれど、オーガニック野菜であることや、無農薬であることが、それ以上に大切にされているし、メディアでそういうことの大切さを、まさにふんだんに国民教育しています。
知らぬは日本人ばかりです。
話が脱線しました。
米国は、満州の大豆を奪いたい。
そこで行われたこのとのひとつがABCD包囲網です。
(これも付言しますが、国家レベルの意思決定は、常に複数の要素によって決定されます。ここで述べているのは、そのなかのひとつが大豆であった、ということです)
満洲経済の根幹が大豆であることはここまでに述べた通りですが、満洲はもともと土壌(どじょう)が酸性です。
大豆の栽培は、土壌がアルカリ性である必要がありました。
酸性の大地をアルカリに改良するためには、大量のリンが必要だったのですが、そのリンを、当時の満洲は米国から輸入していたのです。
米国はこれを一方的に打ち切りました。
大豆は満洲経済の根幹です。
その大豆は、リンがなければ大豆が育ちません。
満洲経済は基盤を失うのです。
同時にこのことは日本人の食卓にも重大な影響を与えます。
日本人は大豆を味噌汁や醤油、豆腐などで、主食並みに消費するからです。
陸海軍の糧食も同じです。
満洲大豆で腹をうるおしていた日本人にとって、米国のリン輸出規制はまさに一大事となったのです。
日本が大東亜戦争の開戦に踏み切らざるを得なかった理由のひとつに、満洲におけるリンの輸出規制というファクターがあったことも忘れてはならないのです。
しかし、チャイナの大陸から満洲の大地に手を伸ばし、そこを植民地支配しようとする米英の目論見は、大東亜戦争における日本軍の奮戦によって潰(つい)えました。
植民地支配によって働かずに食おうとした米英は、結局は日本と戦って多くの人命を犠牲にしただけでなく、植民地をことごとく手放すことになったのです。
彼らはよほどくやしかったのでしょうか。
米国はGHQを日本に派遣するや否や、日本が満洲や本国で研究していた農作物や新種の種などをこぞって米国に持ち帰りました。
そしてこれを米国内の広大な農地で栽培しました。
それらは荒れ地に強い農作物でした。
結果としていまや米国は、世界最大の農業国家になっています。
それだけでなく、負けた日本には、農業政策に干渉し続け、結果として小麦も大豆も今では日本の農家がいくら生産しても儲からないような仕組みになっています。
おかげでかつては日本中いたるところで見られた麦畑や大豆畑は、昨今ではほとんど見かけることがなくなりました。
日本は国内で年間434万トンの大豆を消費しますが、このうち420万トンを輸入に頼っています。
いまや日本は世界第三位の大豆輸入国です。
大豆を、暗い所で発芽させたものがモヤシです。
未熟大豆を枝ごと収穫して茹(ゆ)でたら、ビールのつまみの枝豆です。
完熟大豆を搾(しぼ)ると、大豆油(サラダ油)ができ、煎(い)って粉にしたものが、きな粉です。
蒸して発酵させると味噌・醤油、納豆菌で発酵させたものが納豆です。
熟した大豆を搾(しぼ)れば豆乳、その残りカスがおから、豆乳を温めてできる表面の膜が湯葉(ゆば)、これににがりを入れて固めたものが豆腐です。
豆腐を揚げたものが厚揚げ、焼けば焼き豆腐、茹(ゆ)でれば湯豆腐、凍(こお)らせれば高野豆腐ができあがります。
今日、我々日本人が大豆を、これだけ様々な形で加工して食しているのは、それだけ大豆が日本人にとって古くてなじみの深い食品だからです。
そしてここまで多種多様に大豆に工夫を凝らして食しているのは日本だけです。
ビールを飲みながら、もやし炒(いた)めを食べながら、納豆ごはんを食べながら、豆腐をつつきながら、是非、ご友人やご家族の方々に、大豆と満洲のお話をしていただけたらと思う次第です。
※この記事は2011年2月のねずブロ記事をリニューアルしたものです。