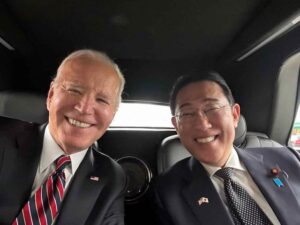「絵のタイトルが、かきつばただから」、まあ、そうです。
けれど、実はこの絵は、確かになるほど、誰がどうみても、「かきつばた」なのです。
「いずれ文目(あやめ)か杜若(かきつばた)」などといって、どちらともつかない(見分けも付かない)代名詞のように言われている「あやめ、しょうぶ、かきつばた」ですが、実はこの3つの花、見分け方はとても簡単です。
そのヒケツは、花の根元にあります。
まず「あやめ」です。
「あやめ」は、漢字で書いたら「文目(あやめ)」です。
「あやめ」がどうして「文目」と書くかというと、その花の根元が、文字通り「あみ目模様」になっているからです。
あやめ(文目)の編み目模様

よく、「文子」さんと書いて、「あやこ」さんと読む方がおいでになりますが、「文(ふみ)読む子」ではなくて、あえて「あやこ」と読む名を付けた親御さんは、あやめ(文目)のように可憐で清楚、美しく育ってもらいたいという親心であったのかもしれません。
アヤメもショウブも、どちらも漢字で「菖蒲」とも書いて、アヤメ、ショウブと読ませますので、これはとってもまぎらわしいです。
ショウブは「菖蒲」でも良いですが、アヤメは「文目」と書く方が、花を見分けるためにも都合が良いかもしれません。
ちなみに「いずれあやめか、かきつばた」という言葉ですが、これは実は源頼政(みなもとのよりまさ)の故事に由来します。
源頼政といえば、第76代近衛天皇(このえてんのう)のご治世のとき、都に出た鵺(ぬえ)と呼ばれる妖怪を退治したのです。
鵺(ぬえ)は、顔が猿で胴体が狸、手足には虎の爪があって、尾が蛇のような姿をしている妖怪です。
近衛天皇は、この妖怪にお悩みになられ、武勇の誉れ高い源頼政に、その退治を命じました。
源頼政は、鵺を見事討ち果たし、鳥羽院(第74代天皇、後に上皇)から、褒美をいただきます。
その褒美というのが、天下に名高い美女の「あやめ御前」だったのですが、このとき鳥羽院は美女二人に、あやめ御前と同じ服、同じ化粧をさせ、三人の美女を源頼政の前に出して、
「どれが本物のあやめ御前か、見事当てたら御前を譲ろう」と、こう申されたわけです。

ところが、三人とも実に美しい。
困った源頼政は、そこで即興で歌を詠みます。
それが、
五月雨(さみだれ)に 沼の石垣水こえて いずれかあやめ 引きぞわづらふ
ひらたく言ったら「あまりに美しくて感情がたかぶり、どの姫があやめ御前かわからず病になってしまいそうですな」といった意味の即興歌ですが、鳥羽院はこの当意即妙の頼政にいたく感激され、あやめ御前を頼政に下賜されたのだそうです。
このときの「いずれかあやめ」の句が、後に転じて「いずれあやめか、かきつばた」になりました。
ちなみに「あやめ」は、背丈はだいたい60cm以下で、あやめ、しょうぶ、かきつばたの中では、花も背丈も、いちばん小柄です。
小柄でも、その美しさは群を抜く。
また花の根元の編み目模様も、女性の複雑な心をあらわしているかのような感じもします。
次に「菖蒲(しょうぶ)」です。
こちらは背丈が80〜100cmあり、文目(あやめ)、菖蒲(しょうぶ)、杜若(かきつばた)の3種の中では一番大きな植物です。
見分け方のポイントは、やはり花の根元にあります。
菖蒲は、花の根元に、はっきりした黄色いマークが付いています。
菖蒲(しょうぶ)は3つの中で一番大柄であり、名前も「しょうぶ」であることから、この花は「尚武(しょうぶ)」に通じるということで、邪気を払う花、そして武士の花とされました。
また5月5日には、この菖蒲の花をお風呂に入れて、菖蒲湯なんてしゃれる習慣も、ここから生まれたと言われています。

「かきつばた」は、漢字では冒頭の燕子花図にあるように「燕子花(かきつばた)」と書きますが、「杜若」とも書かれます。
その「かきつばた」ですが、お能に「杜若」という演目があります。
「唐衣(からころも)着(き)つつ馴(な)れにし妻(つま)しあれば
遥々(はるばる)来(き)ぬる旅(たび)をしぞ思ふ」
と謡(うたい)が入る演目で、ここに杜若の精霊が登場します。

かきつばたの背丈は60〜80cmと、文目と菖蒲の中間くらい。
見分け方のポイントは、やはり花の根元のマークでで、
「かきつばた」のマークは、「白」です。

ということで、冒頭の尾形光琳の絵は、花の根元が白なので、「かきつばた」が正解です。
それにしても、四季折々の花が咲く日本って、良いですね♫
最後にひとつ、おまけです。
本文中に源頼政の鵺(ぬえ)退治のお話が出てきましたが、実はお能に、その後の鵺(ぬえ)の物語があります。
頼政に倒された鵺ですが、成仏できずにこの世をさまようのです。
これを旅の僧が見つけて鵺から事情を聴き、しっかりとお弔(とむら)いをしてあげる。
すると鵺は、たいへんよろこんで、泣きながら成仏していく・・・という物語です。
お能は武家の常識ともいえるほど、かつては普及していた芸能で、武士はこういう物語に幼い頃から接してきたから、敵将や敵兵といえども、戦いが終わればしっかりと供養してあげるということが習慣化していました。
支那事変や大東亜戦争のときにも、日本の軍人さんたちは、戦いのあと、敵兵を決して粗末にすることなく、きちんと埋葬して供養を捧げてきましたが、それはこの鵺(ぬえ)の物語が、お能を通じて武士の道として常識化していたところから来ていたものです。
このことについては、また稿をあらためて詳述したいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。
※この記事は2014年5月の記事のねずブロ記事のリニューアルです。