
磐代(いはしろ)の 浜松が枝(え)を 引き結び 真幸(まさき)くあらば また還(かへり)り見む
この歌は万葉集の中で「挽歌(ばんか)」に分類されている御歌です。
挽歌は、雑歌(ぞうか)・相聞(そうもん)とともに万葉集における歌の三大分類のひとつです。
挽歌は、のちには哀傷歌(あいしょうか)と呼ばれるようになります。要するに悲しみの歌です。
有間皇子が生きた時代は、中大兄皇子が、唐に攻め込まれない日本にしていくために、かなり強引に内政改革を進めた時代です。
改革には、もちろん目的があります。
そうしなければならないから、行われるのです。
けれど改革は、改革によって利益を得る者もいれば、不利益を被る人もいます。
そして不利益は、そのまま朝廷における立場の喪失や、財産の喪失を意味します。
それだけに抵抗もまた必死で、中大兄皇子への対抗馬として、中大兄に匹敵する血筋である有間皇子を次の天皇に担(かつ)ごうとしました。
成功すれば反中大兄皇子派の人たちは、中大兄皇子らを粛清(しゅくせい)して、自分たちの時代を築くことができると考えたわけです。
(※ すこし補足します。日本の天皇が国家最高権威であって、政治権力を持たないという国の形は、万古の昔からあったわけではありません。斉明天皇の時代の中大兄皇子によって開始され、(そのために中大兄皇子は天皇にならず、あくまで皇族筆頭として内政の改革である大化の改新等を行っています)、天武天皇に引き継がれ、中大兄皇子(後の天智天皇)の娘である第41代持統天皇によって完成したものです。)
けれども内外の情勢は、そのような内紛をしていれるような情況にありません。
唐という超巨大軍事帝国が、我が国への侵略を虎視眈々と狙っているのです。
このことを有馬皇子から見れば、自分が担がれることは、イコール日本が滅びることを意味します。
そこで有間皇子がどうしたかというと、自分が担(かつ)がれないように、気がふれた様子を装(よそお)うのです。
一方、中大兄皇子によって蘇我氏の惣領(そうりょう)の入鹿(いるか)を乙巳(おっし)の変で殺された蘇我氏系列の豪族の蘇我赤兄(そがのあかえ)は、なんとかしてこの混乱を利用して、一族の地位向上を図ろうとしていました。
そして天皇および朝廷の高官たちが牟婁温泉(むろおんせん)に湯治(とうじ)に行幸されている間に、有間皇子にそっと近づくのです。
そして
「有間皇子(ありまのみこ)様、
赤兄(あかえ)はどこまでも皇子様(みこさま)のお味方でございます。
いま天皇と中大兄皇子様は湯治にお出かけです。
いまこそ蹶起のチャンスです。
皇位を奪うには、いましかありませぬ。
行幸先を急襲しましょう。
皇子様、どうかご許可を!」
ともちかけるわけです。
もちかけられても有馬皇子は気がふれた風を装(よそお)っているのです。
曖昧な態度しかとれません。
当然です。はっきりした態度を取れば、気が触れていたことが嘘であったことになる。
しかし・・・気が触れたままを装う皇子の態度は、同時に賛成反対どちらの意思表明ともとれるものとなりました。
赤兄は有馬皇子と面談後すぐに中大兄皇子のもとに行き、
「有間皇子謀反(むほん)」
と密告します。
有馬皇子は即刻逮捕され、行幸先の紀伊(きい)の牟婁温泉に取り調べのため護送されることになるわけです。
この御歌はその護送途中の和歌山県日高郡南部町の海岸で食事休憩となったときに詠んだ歌です。
取り調べによって得られる結果は二つ。
ひとつは有馬皇子に謀反の心がないことが立証されて、蘇我赤兄らが処罰されること。
もうひとつは有馬皇子ひとりが処罰され、蘇我氏が安泰となることです。
では御歌を読んでみましょう。
ちなみにこの歌、ボクの出身が浜松なこともあって、なにやらとっても親近感を持っている歌です。
【有間皇子自傷結松枝歌二首】
いはしろの 磐白乃
はままつのえを 浜松之枝乎
ひきむすひ 引結
まさきくあれは 真幸有者
またかへりみむ 亦還見武
けにあれは 家有者
けにもるいひを 笥尓盛飯乎
くさまくら 草枕
たびにしあらは 旅尓之有者
しひのはにもる 椎之葉尓盛
《現代語訳》
【有間皇子がご自分で悲しまれながら松の枝を結んだ歌二首】
護送される途中、和歌山県日高郡南部町の海岸沿いの岩代というところで、浜にあった松の木の枝を結びました。これは思いが通じるというおまじないです。
運が幸いして訊問(じんもん)を見事にかわすことができたなら、きっとこの松の木のもとにまた来ようと思います。
家にいたなら食器に盛る飯を、草を枕に寝る旅の途中なので椎の葉に盛りつけています。まだまだ評定が定まったわけではないのだから、四角い法定で述べる言い分を、旅の途中のいま、思いのままに考えてみよう。
万葉集はこの歌を「挽歌」に分類しています。
「挽歌」は誰かの死を悼いたむ歌ですから、悪人として処刑されたはずの有間皇子に、万葉集は同情を寄せていることになります。
ということは、この御歌を考えるときには、「なぜ同情しているのか」を考え合わせる必要がある、ということです。
はじめの歌は「おまじないをして必ずこの松の木のもとに帰ってこよう」という歌です。
次の歌は「自分なりに充分に事実関係の言い分を述べて最後まで前向きに戦おうという決意を込めた歌」です。
ところが日本書紀によれば、有間皇子は中大兄皇子の
「何故謀反《なにゆえ謀反を起こしたのか》」
という尋問に、たったひとこと、
「天与赤兄知、吾全不解」
と答えただけであったと記されています。
意味は、
《天と蘇我赤兄が知っている。
私は全容を知らない》
という意味です。
そしてそれ以外のことを一切語らずに、従容(しょうよう)として処刑されています。
歌では「また戻ってくるよ」「ちゃんと答弁するよ」と詠んでいた有間皇子は、ではどうして、なにも語らずに処刑を受けられたのでしょうか。
先程述べましたように、この時代は唐という軍事大国が虎視眈々とわが国を狙っていた時代です。
その力は強大です。
これに抗するためには、なにが何でもわが国を統一国家にしていかなければならない。
防衛網も整備しなければならない。
その一方で、強引な改革には異論反論も続出するという難しい政局の時代です。
反対派の人たちは、皇位継承権のある有間皇子を担ごうとすることでしょう。
けれど国論を分裂させることは、結果として国のためになりません。
ですから有間皇子は暗愚(あんぐ)になったフリまでして、自分が皇位継承者に担ぎ出されて政争の具にされないようにしていたのです。
国を護るために暗愚になったフリをするというのは、スケールは違いますが、後年徳川幕府に睨まれないように、わざと鼻毛を伸ばして暗愚を装った加賀藩の二代目藩主の前田利常がいます。
ところがそうまでしても有間皇子は、その血筋ゆえに政治利用されてしまうわけです。
利用された以上、責任は上に立つ者、つまり有間皇子にあります。
蘇我赤兄のせいにはできない。
ですから有間皇子は他人に嵌められた濡れ衣であっても、利用された不徳を恥じて、一切の釈明をしないまま、処刑を受け入れるほかなかったのです。
そもそも臣下とは、出世のためにそういう裏切りや欺罔(ぎもう)、欺瞞(ぎまん)をするものなのです。 人の上に立つ者は、いちいちそれを恨(うら)んではいけない。 それが人の上に立つ者の在り方であり、皇族の在り方であり、人としての在り方なのだという、これこそが生まれたときから人の上に立つように定められた者が持つ、無私(むし)の心です。
真実を述べることは、今度は蘇我赤兄以下、多くの人々を罪に落とすことになります。
唐の脅威に抗するための大切な一族とその兵力と、自分ひとつの命と、どちらが大切か、どちらを採るべきか。
これは、公と私と、どちらを優先すべきかという問いなのです。
誰だって生きていたい。
理不尽な濡れ衣なら、なおさら生きることを選択したい。
けれど、国の利益を考えたときに、自分がどうあるべきなのか。
生きたいという渇望と、無私の心で罪を受け入れるという葛藤。
そのなかで有間皇子は、生への渇望を、この二首の歌に託して、捨てたのです。
こうすることで心に踏ん切りをつけた有間皇子は、裁(さば)きの場で、一切の言い訳をしないで、ただ「天と赤兄が知っている」とだけ述べて刑死の道を選ばれたのです。
それは有間皇子の、どこまでも国の平穏を想う心のなせる選択です。
我が身の犠牲を問わない。 これこそが、日本のご皇族の無私から生まれる愛の心です。
そして我が国の中心にある国家最高権威が、そのような態度姿勢であるがゆえに、その下にある権力機構もまた、わたしくに背(そむ)いて公(おほやけ)に向かう、「背私向公(はいしこうこう)」なのです。
戦後の日本では、個人主義こそが幸せであると、盛んに宣伝されました。
それは、一面においては正しいことであると思います。
けれど、社会の上に立つ人たちまでが個人主義になってしまったら、世の中はどうなるのでしょうか。
その典型が、中共であるし、あるいは米国です。
そしてそれらは、果たして良い国といえるのでしょうか。
逆に、日本が目指した国というのは、どのような国であったのでしょうか。
そのことを、あらためて考え直す時期に来ていると私は思います。
最後にひとつ。
静岡県に浜松市があります。
そこに家康公ゆかりの浜松城があります。
家康の時代、そこは曳馬(ひくま)と呼ばれる地でした。
天竜川の氾濫がひどく、水田が営めない。
そこで馬を育てることが、主な産業となっているところでした。
だから曳馬(馬を曳く)と呼ばれる地となっていたのです。
ちなみに、隣に磐田(いわた)市があります。
昔は、盤石の水田地帯であったことから、その名が付いたし、中央朝廷の古くからの荘園がおかれていたところです。
磐田と曳馬、地名には意味があるのです。
さて、その曳馬を浜松と改名したのが家康です。
当時、岡崎に城を構えていた家康は、妻の瀬名姫が、いろいろな事情があって、どうしても城に入ってもらえない。
時は戦国の世です。いつまでも岡崎城近くのお寺の築山脇の仮小屋で妻子に寝泊まりされていては、あまりに危険です。
そこで家康は、自分が曳馬城に引っ越し、その代わりに築山御前に岡崎城に入ってもらうようにしました。
そしてこのとき家康は、曳馬城を浜松城と改名しました。
理由は、「浜松が枝を引き結び」という有間皇子の歌によります。
歌に、離れてしまった築山御前との縁を、また結びたいという情(こころ)を込めたのです。
けれどその後、結果としては、家康は築山御前と長男の首を刎ねることになりました。
このことは、家康にとって、とてもつらい出来事でした。
後年、50歳の坂を過ぎた家康が、いまだ正妻を娶らず、また仕える美女たちに目もくれず、あまり器量の良くない農家の後家さんばかりを側室にすることを、ある人が、「どうして?」と尋ねたそうです。
すると家康はひとこと。
「そのようなことをすれば、瀬名が悲しむ」
そう、述べたそうです。
日本の歴史は、まさにいろいろな出来事があった歴史です。
けれど、その歴史は、常に深い愛に支えられた歴史でもあるのです。
この記事は拙著『ねずさんの奇跡の国 日本がわかる万葉集』からの引用をもとに補足を書いたものです。
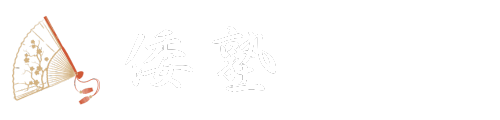

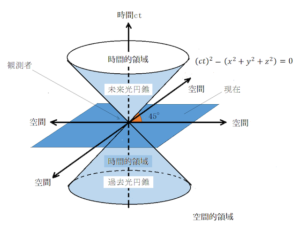
勉強になりました。ありがとうございました。