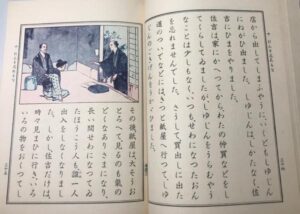源平合戦の締めくくりとなる壇ノ浦の戦いは、旧暦ですと寿永4年3月24日、西暦ですと1185年4月25日の出来事です。
山口県下関の沖合で行われました。
治承4(1180)年に源頼朝が平家打倒の兵をあげて以来5年、屋島の戦いで兵を引いた平家一門は、長門国引島(山口県下関市)まで後退していました。
源氏と平家は、いろいろに対比されますが、戦い方の手法も、正反対です。
平家は、弓矢を用いて離れて敵を討つという戦い方を得意としました。
これは特に水上戦で有効な戦い方です。
大量の矢を射かけ、敵を粉砕します。
対する源氏は、馬を多用した陸上での接近戦が得意です。
実は、こうした戦闘形態の違いは、近代戦も同じです。
先の大戦での島嶼(とうしょ)部での戦いも、米海軍は艦砲射撃やら空爆やらで、あめあられと砲弾を撃ち込む戦いをしました。
対する日本陸軍は、上陸した敵に肉薄して接近戦で敵を粉砕する戦い方でした。
前者がが平家、後者が源氏の戦い方です。
さて、だいぶ春めいてきた新暦の4月25日、平家一門は、関門海峡の壇ノ浦に、無数の船を浮かべて義経率いる源氏を待ち受けました。
静かに夜が明ける。
そして午前8時、いよいよ戦いの火ぶたが切って落されます。
源氏は潮の流れと逆ですから、船の中で一定の人数は常に櫓を漕ぎます。
平家は、潮の流れに乗っていますから、櫓を漕がなくても舵だけで船が前に進みます。
潮の流れに乗る平家は、流れに乗って源氏の船に迫り、盛んに矢を射かけました。
なにせ漕ぎ手が不要です。
ですから総力をあげて矢を射続ける。
一方、潮の流れに逆らう源氏の船は、平家の射る矢の前に、敵に近づくことさえできません。
船を散開させ、なんとか矢から逃げようとする源氏、密集した船で次々と矢を射かける平家。
こうして正午頃までに源氏は、あわや敗退というところまで追いつめられていきます。
ところが、ここで潮の流れがとまる。
追いつめられていた源氏は、ここで奇抜な戦法に討って出ます。
義経が、平家の船の「漕ぎ手を射よ」と命じたのです。
堂々とした戦いを好む坂東武者にとって、武士でもない船の漕ぎ手を射るなどという卑怯な真似は、本来なら出来ない相談です。
ところが開戦から4時間、敵である平家によってさんざんやっつけられ、追い落とされ、陣を乱して敗退していた源氏の武士達も、ここまでくると卑怯だのなんだのと言ってられない。
むしろ義経は、源氏の武者たちがそういう気分になるまで、待っていたのかもしれない。
そのために朝の8時を開戦時間にしたのかもしれません。
義経の命に従い源氏の兵たちは、平家の船の漕ぎ手を徹底して射抜きました。
この時点で平家は、狭い海峡に無数の船を密集させて浮かべています。
そこに源氏の矢が、漕ぎ手を狙って射かけられたわけです。
船の漕ぎ手を失った平家の船は、縦になったり横になったり、回ったりして、平家船団の陣形を乱します。
平家の軍団が、大混乱に陥いる。
すでに潮の流れは、源氏側から平家側へと移り変わっています。
まさに潮目が変わったのです。
潮の流れというのは、一見したところあまりピンとこないものだけれど、まるで川の流れのように勢いの強いものです。まして狭い海峡の中となれば、なおのことです。
勢いに乗った源氏は、平家一門の船に源氏の船を突撃させました。
船同士を隣接させれば、船上の戦いとはいえ、源氏得意の近接戦です。
一方、平家一門は、ここまで約4時間、矢を射っぱなし。
すでに残りの矢が乏しい。
それを見込んでの源氏の突進を矢で防ぎきれない。
接近戦になれば、源氏武者の独壇場です。
離れて矢を射かける戦い方に慣れた平家は、刀一本、槍一本で船に次々と飛び移って来る坂東武者の前にひとたまりもありません。
平家の船は次々と奪われ、ついに平家一門の総大将、平知盛の座乗する船にまで、源氏の手が迫ってきました。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」で有名な平家物語はこのあたり、まるで錦絵を見るような色彩豊かな描写をしています。
平清盛の弟・教盛(のりもり)の子の平教経(たいらの のりつね)25歳は、若くて体も大きく武芸の達人でした。
迫り来る敵を前にした平教経は、そのときすでに、部下ともども、矢を射尽くしていました。
そこに源氏の兵が潮に乗って迫って来ました。
平教経(たいらの のりつね)は、今日を最後と肚に決めました。
この日の教経(のりつね)の服装は、
赤地の錦の直垂(ひたたれ)に、
唐綾縅(からあやおどし)の鎧です。
そして厳物作りの大太刀を腰にして、
白木の柄の大長刀(おおなぎなた)の鞘をはずすと、
波のように押し寄せる敵を次々となぎ倒していきました。
その壮絶な戦いぶりに、教経の叔父で総大将の平知盛(たいらのとももり)が使者を遣わしました。
「教経殿、あまり罪を作りなさるな。
そんなことをしても相手は立派な敵だろうか」
ここ、大事なとこです。
戦いの最中に平知盛は、
「雑兵を殺すことが、
武将として立派な戦いでしょうか?」
と伝えているのです。
雑兵というのは、日頃はお百姓さんです。
ということは、源氏だ、平家だと言う前に、彼らは天皇(すめらみこと)の大御宝(おほみたから)です。
武士ならば戦いはやむを得ない。
けれど、雑兵は、普段は民百姓(たみひゃくしょう)です。
たとえ敵であったとしても、
すこしでも守ってやり、
命をながらえてやるのが、
誇りある武士の勤めだ、
と言っているのです。
おそらく今どきの人なら、「戦(いくさ)のさなかに、何を能書き垂れてんだ!」と思ってしまいそうです。
けれど当時の貴族や武将にとって、このことは命を賭けるほどに大事な哲学でしたし、この精神はその後の鎌倉時代も、室町時代も、戦国時代も江戸日本も、そして明治、大正、昭和の時代もまったく変わりません。
先の大戦のときも同じです。
戦いは武人(先の大戦時は兵士)が行うものであり、一般の民間人への殺傷は一切許さない。
それは日本の武人の心得であり、日本軍の心得でもありましたし、ハーグ陸戦条約における国際社会の戦争のルールでもありました。
このルールがあるから、支 ナ事変で蒋介石は、さかんに「日本軍が一般庶民を殺生した」と、ありもしないことを宣伝したし、その後の中凶は南キン事 件をでっちあげてまで宣伝しているのです。
けれど実際には日本は、常に武人の誇りを重んじたし、軍は出身地の村落毎の編成です。
ルールを破ればその者は村の恥、故郷の恥とされ、末代まで悪事が語り継がれてしまうという仕組みになっていました。
ですから日本軍が一般人を虐殺するなど、まさに「ありえないこと」でした。
一方、先の大戦は、もともとは戦争であったけれど、島嶼での戦いから本空襲に至り、戦争が、兵士同士の戦いではなく、民間人を狙った虐殺に変化しました。
そして極めつけが広島と長崎への原爆投下となりました。
戦争の反対語は、平和ではなく、虐殺です。
日本は、やむを得ず戦争はしたけれど、虐殺に加担する気はない。
だから名誉ある終戦を選択したのが昭和20年8月15日の玉音放送です。
たとえ敗れてでも名誉を重んじるという習慣は、こうして平家物語にもくっきりと描かれているのです。
平知盛のひとことに、ハッと気がついた教経(のりつね)は、
「さては大将軍と組み合えというのだな」
と心得、長刀の柄を短く持つと源氏の船に乗り移り乗り移りして、
「義経殿はいずこにあるか」
と大声をあげました。
残念なことに教経は、義経の顔を知らない。
そこで鎧甲(よろいかぶと)の立派な武者を義経かと目をつけて、船をめぐらせたのです。
義経は、まるで鬼神のように奮戦する教経の姿に、これは敵わないと恐怖を持ちます。
他方、部下の手前、露骨に逃げるわけにもいかない。
そこで教経の正面に立つように見せかけながら、あちこち行き違って、教経と組まないようにします。
ところが、はずみで義経は、ばったりと教経に見つかってしまう。
教経は「それっ」とばかりに義経に飛びかかります。
義経は、あわてて長刀(なぎなた)を小脇に挟むと、二丈(およそ6メートル)ほど後ろの味方の船にひら〜り、ひら〜りと飛び移って逃げました。
これが有名な「義経の八艘飛び」です。
教経の周囲は敵兵ばかりです。
すぐに続いては船から船へと飛び移れない。
そして、今はこれまでと思ったか、その場で太刀や長刀を海に投げ入れ、兜(かぶと)さえも脱ぎ捨てて、胴のみの姿になると、
「われと思はん者どもは、
寄つて教経に組んで生け捕りにせよ。
鎌倉へ下つて、頼朝に会うて、
ものひとこと言わんと思ふぞ。
寄れや、寄れ!」
(われと思う者は、寄って来てこの教経と組みうちして生け捕りにせよ。鎌倉に下って、頼朝に一言文句を言ってやる。我と思う者は、寄って俺を召し捕ってみよ!)
と大声をあげます。
ところが、丸腰になっても、教経は、猛者そのものです。
さしもの坂東武者も誰も近づけない。
みんな遠巻きにして、見ているだけです。
そこに安芸太郎実光(あきたろうさねみつ)という者が、名乗りをあげます。
安芸太郎は、土佐の住人で、三十人力の大男です。
そして太郎に少しも劣らない堂々たる体格の家来が一人と、同じく大柄な弟の次郎を連れています。
太郎は、
「いかに猛ましますとも、
我ら三人取りついたらんに、
たとえ十丈の鬼なりとも、
などか従へざるべきや」
(いかに教経が勇猛であろうと、我ら三人が組みつけば、たとえ身長30メートルの大鬼であっても屈服させられないことがあろうか)
と、主従3人で小舟にうち乗り、教経に相対します。
そして刀を抜くと、教経にいっせいに打ちかかりました。
ところが教経、少しもあわてず、真っ先に進んできた安芸太郎の家来を、かるくいなして海にドンと蹴り込むと、続いて寄ってきた安芸太郎を左腕の脇に挟みこみ、さらに弟の次郎を右腕の脇にかき挟み、ひと締めぎゅっと締め上げると、
「いざ、うれ、さらばおれら、死出の山の供せよ」
(さあ、おのれら、それではワシの死出の山への供をしろ)
と言って、海にさっと飛び込んで自害するわけです。
まさに勇者の名にふさわしい最後を遂げたのです。
このとき、教経、享年26歳です。
このあたりの描写は、吉川英治の新・平家物語よりも、むしろ琵琶法師の語る原文の平家物語の方が、情感たっぷりに描かれていて、素敵です。
激しい戦闘の中にも、愛や勇気、女たちの涙の物語などが盛り込まれている。
こうして壇ノ浦の戦いで、平家は滅びました。
平家物語は、壇ノ浦の戦いで命を救われた建礼門院(清盛の娘で安徳天皇の母)を、後白河法皇が大原にお訪ねになられて、昔日の日々を語り合う場面で、語りおさめとなります。
建礼門院は、平教経からみたら従姉妹の関係になります。
とりわけ美しく、優秀で、才色兼備の素敵な女性でした。
京都の大原の里は、三千院のすぐ近くにあります。
そこにある大原寂光院に、後白河法皇がご到着あそばされたとき、建礼門院はたまたま不在で、寺には留守の尼僧がひとりでした。
「建礼門院はいずこへ?」
との問いに、その尼が「山に花を摘みに」と答えました。
後白河法皇が、
「左様な事にお仕え奉る人もいないか。
おいたわしいことだねえ」
と仰ると、尼は
「五戒十善の御果報つきさせ給ふによって、
今かかる御目を御覧ずるに候へ。
捨身の行に、
なじかは御身を惜しませ給ふべき」
と答えます。
尼は、あまりに粗末な、絹なのか麻や木綿の布なのかの区別もつかないようなボロを縫い合わせて着ています。
ところがそんな尼が、あまりに教養高い答えぶり。
後白河法皇があらためて尼に名を問うと、
「亡くなった少納言信西入道の娘で、
阿波内侍(あわのないし)と申したものでございます。
母は紀伊の二位。
法皇様よりかつて深いご寵愛がございましたのに、
私を見忘れなさったことにつけても、
我が身の衰えてしまった程度が思い知られて、
今さらもうどうしようもないことと
かなしく思われます」
と涙を見せます。
つまり、家柄もしっかりしていて、かつては後白河法皇のご寵愛も受けたことがあるほどの女性であったのです。
それほど高貴な女性が、いまやすっかりボロを着ている。
そのうち戻ってきた建礼門院もまた、姿を見ても法皇にはそれが建礼門院とはわからないほどにやつれ、深い黒染めの衣も、ボロボロになっていました。
あまりの変わりように、法皇も涙にむせびなさる。
そこに阿波の内侍の老尼が女院のもとに参り、花籠を女院から頂いた・・・と続きます。
さて、その大原寂光院には、建礼門院が日々経をあげられていたお地蔵様もそのまま遺されていたのですが、2000年(平成12年)5月9日の未明に放火に遭って全焼。いまは復元された本堂が建ち、焼け残って炭のようになったお地蔵様が展示されています。
焼け跡からプラスチックの容器の燃えかすと灯油が検出されたことから、京都府警は放火と断定しましたが、結局犯人逮捕に至らず、いまは公訴時効となりました。
滅多なことは言えませんが、当時、日本の文化遺産に、わざわざ外国からやってきて放火して本国に逃げ帰るという犯行が流行っていましたから、もしかするとこの事件も、そんな一連の犯行のひとつであったのかもしれません。
さて、琵琶法師の語る平家物語は、実に色彩が豊かで、まさにそれは総天然色フルカラーの世界。
その口演が、一話2時間くらいで、12話で完結です。
二時間分の話し言葉というのは、だいたい1万字ですから、法師の語る平家物語は、全部でだいたい12万字、つまり、いまならちょうど本一册分くらいの分量です。
それだけの文学作品が、なんと13世紀頃にはできあがっていたというのですから、これまた日本というのはすごい国です。
平家物語は、歌舞伎や講談で、義経千本桜、熊谷陣屋、敦盛最期など、各名場面が興行され、多くの人の喝采を浴びました。
日本は、ほんとうに古くて長い歴史と伝統と文化を持った国です。
私たちは、そんな日本の歴史伝統文化をご先祖から受け継いで生まれてきました。
私たちにとっての日本は、ご先祖からの預かりものなのです。
建礼門院・平徳子

画像出所=https://www.1059do.com/sa-5-122.html
(画像はクリックすると、お借りした当該画像の元ページに飛ぶようにしています。 画像は単なるイメージで本編とは関係のないものです。)
この記事は2021年9月のねずブロ記事のリニューアルです。