
「老農」という言葉があります。
他に、篤農、精農、農聖、農哲などの呼び方があります。
在来の農法を研究し、自らの体験を加えて高い農業技術を身につけて農村における農業指導をする人のことです。
老農という言葉が使われだしたのは明治にはいってからのことです。
江戸時代までは「農学者」とか「本草学」、あるいは「興産方産物掛」などと呼ばれていました。
沢庵和尚が広げた「たくあん」、高野山から広まった「高野豆腐」も有名ですが、いつの時代でも、誰だって美味しいものは大好きです。
あたりまえのことですが、食を大切にした我が国において、農業と農業指導の歴史はものすごく古いものです。
いま学者といえば、たいてい本の虫になっている人達のことをいいます。
このように「体を動かさないで頭だけを使うのが学者」というようになったのは、実は戦後のことです。
それ以前は、江戸時代もそうでしたし、明治大正昭和初期までずっとそうでしたけれど、基本的に学者というのは、体を使う人達でした。
知行合一が重視されたというだけでなく、
「机上の学問を、自ら進んで実社会に活かしてこそ学問」
というのが、学者の誇りとされていたのです。
ですからたとえば幕末の適々斎塾を開いていた緒方洪庵にしても、進んで長崎まで勉強に行っているし、塾を開いてからも、自ら種痘のために、大阪各地を回って一般の人達が疱瘡に罹らないよう、種痘の普及に努めました。
あるいはみなさまよくご存知の吉田松陰も、ただ松下村塾を開いて若者たちを教えていたのではなく、自ら率先して行動を起こしました。
農業指導に関しても、江戸時代には農業全書を著して日本農学の祖といわれた宮崎安貞、実践的農業の書を著した大蔵永常、あるいは農業指導者として活動した佐藤信淵などにしても現場に出るという活動を、ものすごく大切にしていました。
戦前戦中の日本の東大の国際政治の教授や、世界の民俗学の教授たちなど、世界中をまわって自分の足で各地を歩き、また地元住民と起居をともにして現地の様子をつぶさに把握し、それを本にまとめ、また生徒たちに教えていました。
だからこそ当時の東大は世界の名門大学のひとつとされていたし、世界中から留学生たちがやってきていたのです。
昨今の東大が、特に文系において、発展途上国の大学以下の評価しかされていないのは、まことに残念なことです。
しかしそれは当然のことでもあるのです。
戦後にGHQによる公職追放があって、江戸時代の昌平坂学問所以来の伝統的な行動派教授たちが追放され、その後釜に屁理屈ばかりを言って特高に捕まっていた共産主義者らが教授職に就きました。
結果、すでに世界中で壮大な実験の結果、多数の人命を犠牲にして国家が崩壊した共産主義をいまだに信仰していたり、国を愛さないことを正義と勘違いしていたり、あるいは机にかじりついて教授間の権力闘争だけに明け暮れるような人物が、いまだに最高学府の教授陣であり続けています。
そのような体たらくで、東大が世界の名門大学になどなり得ようはずもないのです。
だいたいまともな書籍を焚書して、アカ系の学者が捏造した本だけを世に残し、「本も論文も引用先が明らかでなければ信頼に値しない」などと、おかしな空論が言い出されるようになったのは戦後のことです。
それまでは、一流の学者は、自分で考え、自分で行動して得た一次情報を提供す人でした。
当然、引用先なんてありません。
必要に応じて引用先を明らかにすることはあっても、引用がなければ論に値しないなどというのは、頭のおかしなヘンタイの所業でしかないのです。
引用先が大事なら、引用先の文書を読めば良いのであってそのような論は論考の名に値しないというのが一般的な考え方でした。
そもそも論考というのは、事実と意見から成り立ちます。
医学分野など、理系学問でも引用先の明記は必須とされていますが、それは実際の手術の術式や、発見された新たな数理や実験結果の引用であって、意見の引用ではありません。
ところが昨今の我が国では、特に文系学問において、文献資料などに書かれた「意見」を引用しなければならないとしている。
これはまことにおかしな理屈です。
なぜなら文系学問というのは、本来答えのない学問だからです。
「老農」が、我が国において貴重な存在として尊重されたのは、「老農」は、西洋的、分析的な近代農学に対して、古典的経験的な農業技術を活用した人達であり、そこに実践があったからです。
そんな明治の「老農」のひとりに秋田県の石川理紀之助(いしかわりきのすけ)という人物がいました。
石川理紀之助は、弘化二(1845)年、いまの秋田市金足小泉の奈良家の三男として生まれました。
慶応元(1865)年、21歳のときに、秋田郡山田村(現昭和町豊川山田)の石川長十郎に婿養子に入ました。
ところが理紀之助が養子にはいった石川家は、旧家だけれど借金もぐれでとても苦しい生活でした。
理紀之助は「このままではいけない」と、近隣の農家の若者たちと語り合い、「山田村農業耕作会」を結成しました。
そして「豊かな村づくり」を合言葉に、それまでの個人の営みとしての農業を、農民を広く組織した集団的農業に改革に乗り出したのです。
理紀之助の取組みは、大成功を納め、彼自身も石川家の借金を数年で完済してしまっています。
「山田村にすごいやつがいる」という噂がひろまりました。
秋田県は理紀之助を秋田県庁の勧業課に招きました。職員にしたわけです。
理紀之助28歳、明治五(1872)年のことでした。
こういう試験や学歴、家柄や門閥にこだわらず、必要とあればどんどん民間から人材を登用するというのは、古くからの日本の伝統です。
じつはこの頃、秋田県農業では腐米(くされまい)問題に頭を痛めていました。
ただでさえ寒冷地で稲作が困難な地域です。
そこへ稲の病気が流行ったのです。
理紀之助は原因を追究し、収穫時の米の乾燥方法に新しい方法をあみだして、県の腐米改良指導に尽力し、功績をあげました。
さらに理紀之助は、寒冷地に適したおいしいお米の生産の普及を目指し、明治十一(1878)年には「種子交換会」を開催しました。
いまでも秋田で続いている「種苗交換会」のはじまりです。
理紀之助は、こうして行政の農業指導官としての実績をあげながらも、官という上からの指導の限界を痛感しました。
ほんらいなら、お百姓のみんなと、毎日一緒になってやらなければだめだと思うようになったのです。
彼は、行政官としての仕事とは別に、各地の老農を結集して自主的な農事研究団体として「暦観農話連」を結成しました。明治十三(1880)年、理紀之助35歳のときです。
このときの理紀之助の言葉があります。
========
何よりも得がたいものは信頼です。
信頼は、つつみかくさず教え合うことから生まれます。
進歩というのは、厚い信頼でできた巣の中で育つのです。
========
まさにその通りです。
最近ではなんでもマニュアルにしたり、法律を作ったり取り締まったりしさえすればなんとかなると考える人が増えていますが、規則や決まり、ルールやマニュアルが人を育てたり進歩を導くものではありません。
互いの厚い信頼関係こそが、人を育て進歩を育くみます。
なぜなら人は人との関係の中でしか成長しないからです。
人の成長がなければ、そこに進歩はない。あたりますぎるくらいあたりまえのことです。
「暦観農話連」には、結成早々に74名の老農たちが参加しました。
ここで大事なのは、早々に74名の「老農たち」が参加した、という点です。
老農と呼ばれる農業の達人、あるいは農業指導者が、明治初期にたくさんいた、ということです。
そしてそれは江戸時代にもたくさんいたし、もっといえば神話の時代から数多くの老農がたくさんいて、全国の農産物指導を担っていたのです。日本は古来、そういう国だったのです。
暦観農話連

その「暦観農話連」で理紀之助は、会合の都度近くのお寺や農家に泊まり、自炊しながら催しを支えました。
夜になれば時のたつのを忘れてみんなと話し込みました。
こうすることで理紀之助は、農業への熱い夢と情熱を、みんなと共有したのです。
「暦観農話連」による信頼の輪と固い絆は、こうしてだんだんに広がり、明治の末にはなんと499名の会員を擁する老農集団となっていました。
会員は秋田県にとどまらず、お隣の山形、宮城や、遠く埼玉からも仲間が集まっています。
さらに理紀之助は、明治15(1882)年から6年にわたって、二県八郡49カ町村の「適産調(てきさんしらべ)」を実施しました。
各地の土壌、面積、人口、戸数、生産物、自作農地と小作農地の収入、農作業、生活習慣などを総合的に調査し、調査結果とその地の農業の再建計画を作成したのです。
このときの理紀之助のレポートは、731冊に及ぶ膨大なものです。
適産調
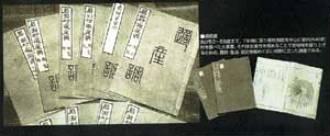
この調査のとき、理紀之助とその仲間たちは、つねに顔を覆う白布と、葬儀料、死亡届のための戸籍謄本を身につけていました。
旅先でいつ死んでもいいようにです。
自分が旅先の道中で死んだ時、旅先の人に迷惑をかけてしまう。
だからすこしでもその迷惑を減らせるようにとの配慮からです。
実はこうした習慣は、古くから続いている日本の習慣です。
江戸時代ですと、当時の通貨は「小判」ですが、旅をするときには、その小判を襟の中に縫い付けました。東海道中膝栗毛の弥次さん喜多さんも、襟には一両小判が縫い込んであったのです。
一両はいまでいったら、だいたい六万円くらいです。
明治十六(1883)年、三十九歳の時、理紀之助は役人の職を辞しました。
そして故郷の山田村の救済のためです。
実は明治十(1877)年ころから、米の値段が上がり出すのですが、五年後の明治十五(1882)年には、逆に米の値段が急落したのです。
これに冷害が重なりました。
どの農家も借金に悲鳴をあげますた。
至るところで食べれなくなる農民が増えたのです。
理紀之助の故郷の山田村もまた借金であえいでいました。
「この息も絶え絶えの農村を救うにはどうしたらよいのか」
これまで培った知識と技術をもとに農民に戻り田畑を耕し、山田村を建て直したいと、理紀之助は山田村に帰り、村人に次の提案をし「山田経済会」を発足させました。
一 質の良い肥料を作り、これまでの倍の量を田んぼに施し、米の収量を増やす。
二 収量が増えた分を借金の返済にあてる。
三 無駄遣いをやめ、暮らしに必要なものは「共同で」買う。
四 養蚕をとりいれ副業に精を出す。
五 仲間外れが出ないよう、助け合い、励まし合う。
困ったときに収穫高を増やしたり副業を振興したり無駄遣いやめようというのは、昨今の国政や、会社などでもよく言われることです。
けれど理紀之助は、さらにそこから一歩進めて、「暮らしに必要なものを共同で買う」ということを実施したのです。
実は、収入というのは、生産高と常に等しいものです。
生産し、働いた分が収入になるからです。
ところが価格が急落するというのは、生産量に対して、収入が減った状態を意味します。
収入が減ったからといって、生産量を減らしたのでは、ますます収入が減ります。
デフレのときに、リストラして生産量を減らせば、ますます収入が減るのです。
少し考えたら誰にでもわかるあたりまえのことですが、世の中というのは、デフレになったら生産量を減らす(=リストラ)したり、税を引き上げて、人々の減った収入からさらに収入を減らそうと考える人がいます。
頭のおかしな人としか言いようがありません。
これに対し、理紀之助が行ったことは、実に理にかなっています。
デフレで生産量に対して収入が減ったのだから、みんなでお金を出し合って、もっと生産量をあげ、収入を増やそうとしたのです。
理紀之助は「山田経済会」を発足すると、毎朝午前3時に、掛け板を打って村人を起こしました。
そして早朝からみんなで力を合わせて農作業を行ないました。
夜明け前の闇に、毎朝「コーン、コーン」という掛け板の音が響き渡る。村人が集まります。
そしてみんなで農作業をする。
山田村はこうして村人たちの努力と協力で、わずか五年で村の借金を完済してしまいます。
その当時に、理紀之助が詠んだ歌があります。
世にまだ生まれぬ人の耳にまで
響き届けよ 掛け板の音
吹雪の朝のことです。理紀之助がいつものように午前3時に打ち終えて、雪まみれになって家に入ると、妻が、「このような吹雪の朝に、掛け板を打っても誰にも聞こえないし、ましてやこの寒さでは、誰も起きて仕事をしようとはしないでしょう」と、言ったそうです。
理紀之助は、「そうかも知れないね。でも私は、この村の人々のためだけにやっているのではないのだよ。
ここから五百里離れたところの人々にも、また五百年後に生まれる人々にも聞こえるように打ってるんだ」
理紀之助の志が、単に目の前のことだけではなく、遠く未来を見据えたものであったことが、この一語にあらわれています。
毎朝3時に村民の起床を促した掛け板

明治三十四(1901)年、理紀之助56歳のとき、尊敬している前田正名(まえだまさな)から、九州の霧島山(きりしまやま)のふもとの開田事業の手伝いを頼まれました。
前田正名が五百町歩の新田を開いたから、来てくれないかというのです。
手紙にはこう書いてありました。
========
私は、この開かれた新田で、新しい農村をつくろうとしている。
そこで、あなたおよびあなたの同志数人に来てもらい、あなたたちの考える理想の村づくりをしてもらいたいと思う。
しかし、私は開田のために、もう資金がなくなってしまった。
なのであなた方に来てもらっても、日当も報酬も払えないし、往復の旅費も支払えない。
だから、費用は自前で、できれば一年ぐらい滞在して指導をしてもらいたい。
========
いやはやずいぶん無茶な話です。
農業指導に秋田から九州まで来てくれ。ただし、カネはない。交通費も日当も、給金も、ぜんぶ自前で、しかも仲間を連れてきてくれ、というのです。
理紀之助は、自分は行くにしても、仲間はついてきてくれるだろうかと悩みます。
そして正月早々、仲間に集まってもらってじっくりと話しました。
みんな快諾してくれました。
そしてそれぞれが家族や親類をまわって金を工面し、不在中のことについても話し合い、大変な無理をしながらも「先生と同行して勉強したい!」と申し込んできてくれたのです。
一行は、明治三十五(1902)年四月始めに、出発しました。
鹿児島まで汽車で行き、ここで一泊します。翌日から馬車に乗って北上し、宮崎県北諸県郡中霧島村(現在の北諸県郡山田町)の谷頭(たにかしら)の事務所に着いたのは、4月20日の夕方でした。
わらじを脱いで板の間に上がると、脚絆(きゃはん)(旅行時に歩きやすくするため足に巻く布)も解かずに、すぐに明日からの行動計画と自分たちの日課表を決めて、それを壁に張り付けました。
谷頭は、桜島が噴火したとき、難を逃れてきた人々が住み着いたところです。
一帯は霧島山の火山灰でできた台地で、樹木も十分に育たず竹林が茂っている。
畑からは芋(いも)しかとれない。
村には、すでにあきらめムードが漂っています。
理紀之助は翌朝から日程表に決められた通り、午前3時に起床の掛け板を打ち鳴らしました。
けれど誰も来ません。
そして朝7時頃になって、みんなそれぞれの自分の畑にバラバラに出かけて行きました。
理紀之助は村人を集め、農業振興のための方針を話そうとしました。
ところが理紀之助は、秋田弁です。谷頭の人たちは薩摩弁、まるで言葉が通じません。
筆談しようにも、村人たちは読み書きができない。
しかも、自分たちがどんなに貧しくても、そういうものなのだ、とあきらめきっています。
このとき、理紀之助は、秋田から一緒に来た仲間たちに次のように語りました。
=======
私たちは、まず指導しに来たのだという考えを捨てよう。
この村の一員となりきって行動するようにするのだ。
そしてこの村の欠点やここの人々の劣っていることを決して口にしないこと。
欠点を直そうと思ったら、自分たちの生活や行動で気付かせるようにしていくこと。
農業のことについて聞かれても、自分の知識や体験で断定的な話をしないようにすること。
=======
実は、ブータンでダショーの称号をもらった西岡京治も、台湾や朝鮮半島、満州で日本人が行ったやり方も、全部、これと同じです。
どこまでも謙虚に、そしてみんなを交えて、みんなの合意を形成する。
それが日本のやり方です。
理紀之助は、仲間たちと朝にわらじをつくり、それを庄内の店に売りに行ったら十銭儲かったとか、竹かごを売って十五銭儲かった、などと村人たちに話しました。
村人たちは、早朝に仕事をする習慣がなかったのだけれど、そんなに儲かるなら、じゃワシらもやってみようということになり、一人、二人と早朝に集う人が出てきました。
さらに理紀之助は、夜は子供たちのために夜学を開きました。
こうして理紀之助たちの指導が始まって二週間、村の中にほのかな希望が芽生え、明るく生き生きとした雰囲気が生まれてきます。
早起きする人も増えて、どこの村よりも多く貯金するようになってきたのです。
夜学の子供たちも、眼を輝かせて学問に励む。その様子は、外を歩く者が足を止めて見入るほどだったといいます。
こうして理紀之助が前田正名と約束した6ヵ月が過ぎたとき、いよいよ谷頭を去ろうとする頃には、村のお年寄りや若者、子供たちまで全員集まって、別れを惜しんでどこまでもついてきてくれました。
帰れといっても帰らない。
理紀之助は、別れを惜しむ村の人たちの純情に、涙を流さずにはいられなかったそうです。
理紀之助ら一行の、このときの心は、その後、全国の講演会で紹介され、日本の台湾や朝鮮半島、満洲での現地農業指導にそのまま活かされました。
台湾でも、満州でも、私たちの先人達は、まったくそのようにして現地の人々と一緒に開墾をしたのです。
その結果、台湾では米の生産高が30年で3倍以上、サトウキビの生産高は26倍、朝鮮半島ではわずか15年の間に農業生産高が2倍に増え、満洲の大豆の収穫高は14年で164倍に増えています。
人々に笑顔が戻る。みんなが労働の喜びを共有する。
そうして喜びをわかちあった現地の人々を漢奸狩りと称して、支那は虐殺の対象とした。人間の所業じゃありません。
ちなみに満洲(いまの支那東北省)の耕地面積は、日本の満洲統治時代に開墾した当時のまま増えていません。
その一方で、農業従事者の人口は約3倍に増えています。
食えようになったからではありません。ふたたび貧困が支配しているのです。
理紀之助は大正四(1915)年、70歳でその生涯を閉じました。
亡くなる前の最後の仕事は、秋田県仙北郡強首村の救済事業でした。
当時、理紀之助は、よく次のように語ったそうです。
「俺は農民だ。農民が農民を助けないで誰が助けると言うのだ。」
そう言って、老いる体にムチ打って、毎朝三時に掛け板を鳴らし続ける理紀之助のもとには、多くの若者たちが馳せ参じてくれたそうです。
「これら青年を見よ。わしらの意志をしっかり受け継いでくれている。これこそが世に残す財産だ」
理紀之助が残した最後の言葉です。
石川理紀之助の生涯を尋ねれば、決して豊かな暮らしをしていたわけではないし、どちらかといえば生涯富には恵まれず、貧乏な生活を送った人です。
けれど彼の生涯は、心根の豊かさを私たちに想起してくれます。
明治の気骨という言葉があります。
気骨の原点にあるのは「公に尽くす」ことです。
みんなのために尽くす人生。
人生は決して自分だけのものではないということを、理紀之助は私たちに教えてくれているような気がします。
※この記事は、2010年3月のねずブロ記事をリニューアルしたものです。



素晴らしいお話です。シェアさせてください。