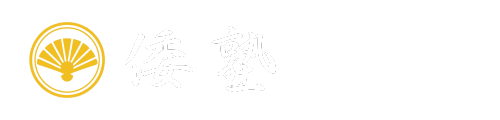かぐや姫は、なぜ月へ帰らなければならなかったのか。帝の想いも、兵の力も、深い愛情も、それを引き留めることはできませんでした。竹取物語の最終章は、「勝ち」でも「敗北」でもなく、人の文明が、自らの限界を知る瞬間を描いています。永遠を求めないこと。回収できないものがあると知ること。そして別れを引き受けること。かぐや姫の昇天は、日本文明がたどり着いた、ひとつの完成形を私たちに示しています。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
【現代語訳】かぐや姫の昇天(最終回)
このようにして、帝とかぐや姫は、互いに心を慰め合いながら過ごしていたが、三年ほどが経ちました。
春の初め頃から、かぐや姫は月が美しく出ているのを見ると、いつも以上に物思いに沈む様子を見せるようになりました。
ある人が「月を見るのはよくないことだ」とたしなめても、隙を見ては月を眺(なが)め、ひどく泣くのでした。
七月の満月の夜には、外に出て、ひときわ深く物思いに沈んでいる様子でした。
身近に仕えている人々がこの様子を竹取の翁(おきな)に伝えました。
「かぐや姫は以前から月を愛(め)でてはおられましたが、近頃は普通ではありません。深い悩みがあるに違いありません。どうかよくお尋ねください」
翁がかぐや姫に言いました。
「どうしてそんなに月を見て物思いに沈むのだ。こんなに良い世の中なのに」
かぐや姫が答えました。
「月を見ると、世の中がとても心細く、哀しく思われるのです。なぜ悲しまないでいられるでしょうか」
夜が更け、八月十五日の満月の夜になると、かぐや姫は人目もはばからず激しく泣きました。親たちは驚き、理由を問いただしました。かぐや姫が泣きながら語りました。
「以前から申し上げようと思っていましたが、心を惑わせてしまうと思い、黙っていました。けれど、もう隠しきれません。私はこの国の人ではなく、月の都の者なのです。昔の因縁によって、この世にしばらく留まっていただけなのです。今月十五日に、月の都から迎えが来ます。そうでなければ、すでに帰っていなければならない身なのです」
翁は驚き嘆き、「竹の中から見つけ、育てた我が子を、誰に渡せるものか。決して許さぬ。私は死んでも離さぬ」と泣き叫びました。かぐや姫は言いました。
「月の都には本当の父母がいます。けれど、こちらで長く暮らし、あなた方に育てられたことは、何よりも大切でした。それでも、自分の意思では逆らえないのです」
このことを帝(みかど)がお知りになられ、深く嘆かれました。帝は二千人の兵を派遣され、家を厳重に守らせました。翁にも弓矢を持たせ、「天の者が来ても必ず射落とせ」と命じられました。
しかし、かぐや姫は言いました。
「どれほど守っても、月の都の人々とは戦えません。心そのものが奪われ、誰も戦う気を失うでしょう」
やがて夜半、家の周囲は昼よりも明るく輝き、空から雲に乗った天人たちが降りてきました。守る人々は恐怖に包まれ、弓を取る力さえ失いました。天人(あまびと)の王(きみ)が言いました。
「かぐや姫は罪を犯したため、しばらくこの穢れた地に留まっていた。しかし、その期限は終わった。返してもらう」
戸は自然に開き、かぐや姫は抱えられて外へ出ました。翁は泣き伏し、引き留めることができませんでした。
かぐや姫が最後に言いました。
今はとて 天のはごろも きるをりぞ 君をあはれと おもひいでぬる
(意味)こころならず去りますが、どうか月を見て、私を思い出してください」
文を書き残し、形見として衣を置きました。また、不死の薬と、帝への手紙を託しました。
天(あめ)の羽衣(はごろも)を着せられると、かぐや姫の悲しみは消え、月へと昇っていきました。
残された翁と嫗は深く嘆き、病に伏しました。
帝は手紙を読まれ、深く悲しまれて、不死の薬を飲むことを拒(こば)まれました。
あふことも 涙にうかぶ わが身には しなぬくすりも 何にかはせむ
(意味)会えぬ身に、不死など何の意味があろうか。
帝はその薬と手紙を、天に最も近い山――駿河の国の山の頂で焼かせました。
その山は後に「富士の山」と呼ばれ、煙はいまも空へ昇っているといいます。
竹取物語 終
【解説】【第九章 解説】かぐや姫の昇天――文明が最後に向き合う「別れ」という真理
1 最終章が語るもの
竹取物語の最終章は、これまで積み上げられてきたすべての文明批評を、「別れ」という一点に集約させています。
技術、金、武力、知、国家権力――
それらが次々に破綻する過程を経て、最後に残されたのは、
「どれほど大切な存在であっても、
永遠に留めることはできない」
という、避けることのできない真理が描かれています。
この章は、文明の勝利でも敗北でもありません。
人間の文明が、自分の限界を知る瞬間を描いています。
2 かぐや姫が「月を見て泣く」理由
かぐや姫は、月を見るたびに涙を流しました。それは、郷愁でしょうか。感傷でしょうか。
いいえ、違います。
月は「帰るべき場所」であり、同時に「別れの予兆」です。
つまり月を見るという行為は、この世界が仮の滞在地であることを、否応なく思い出させる行為なのです。
だから彼女は、月を見て哀しみます。
この世が嫌だからではなく、この世を愛してしまったからこそ、哀しいのです。
3 かぐや姫は「真実を隠していた」のではない
かぐや姫は、自分の出自を長く語りませんでした。けれどそれは、欺(あざむ)きではありません。
「知らされたら、知らされた人が耐えられないこともある」
その深い理解が、彼女の沈黙の理由です。
真実とは、正しさではなく、「重さを伴うもの」です。
この章では、
「真実を告げること」と
「人を思いやること」の緊張関係が描かれているのです。
4 人間の文明は、天の文明と戦えない
帝は二千人の兵を派遣し、家を守らせました。これは人間の文明が、できうる限りの備えです。
けれど月の都の人々が現れた瞬間、兵たちは戦意を失います。
ここで重要なことは、彼らが「力で負けたのではない」という点です。
恐怖でもありません。
心そのものが、「戦うことを拒否」してしまったのです。
ここで竹取物語は、
「戦えない相手が存在する」
という厳然たる事実を、きわめて冷静に描いています。
5 天の羽衣が意味するもの
かぐや姫は、天の羽衣を着た瞬間、この世への哀しみを失っています。
これは冷酷な描写ではありません。
むしろ逆で、人がこの世で抱える苦しみや愛着は、
「有限」という条件のもとで生まれるものだからです。
羽衣は、苦しみを奪うと同時に、この世への執着や記憶をも奪うのです。
このことが意味していることは、
天の世界は、人間的な意味での「幸せな世界」ではない、ということです。
「天の世界」は、人間が思い描くような、あたたかくて、満たされて、幸せを実感できる世界ではありません。
そこには、老いもなく、病もなく、争いもなく、悲しみもありません。
けれど同時に、迷いも、葛藤も、選ぶ苦しさも、そして――誰かを思って胸が痛むような感傷もない。
つまり天の世界は、「苦しみがない代わりに、深い感動もない世界」と、竹取物語は伝えています。
*
かぐや姫が地上で味わったのは、「別れの悲しさ」であり、老いていく親への「いとおしさ」であり、帝への「距離のある想い」です。
それらはすべて、人間であるからこそ生まれる感情です。
おもしろいことに竹取物語は、天の世界を「理想郷」とは描いていません。
むしろ、「完全であるがゆえに、人間的ではない世界」として描いているのです。
この視点に立つと、竹取物語の問いが読めてきます。
「不完全で、限りがあって、別れがある世界と、
完全だけれど、何も失わない代わりに、何も深く感じない世界。
あなたは、どちらを生きたいですか?」
竹取物語は、答えを押しつけず、ただ、そっと景色を差し出しています。
これが千年前の、日本文化のもたらす知恵です。
6 不死の薬を飲まなかった帝
帝は、不死の薬を受け取られましたが、それを飲みませんでした。
理由は、ただ一つです。
「会えない存在のために生き続けることに、意味を見出せなかった」からです。
ここで帝は、「生の長さ」より、「生の重み」を選ばれています。
これもまた日本文明が一貫して大切にしてきた価値観です。
永遠ではなく、中今。
不死よりも、共に生きた時間・・・・。
7 富士山に昇る煙の意味
不死の薬は、富士の山で焼かれました。その煙はいまも空へ昇っている、と物語は結びます。
ここで重要なのは、薬が「捨てられた」のではなく、煙となって「天に返された」という構図です。
人間の世界に置いておくべきではないものは、無理に所有しない。元ある場所へ返す。
これもまた、回収しない文明の姿です。
8 かぐや姫は、最後まで裁かない
最終章においても、かぐや姫は誰かを裁きません。
帝を責めず、翁を否定せず、人間の弱さを咎めもしません。
ただ、別れを受け入れています。
竹取物語が描く理(ことわり)は、
誰かを正す力ではなく、
抗えない流れを、そのまま示す力なのです。
9 竹取物語が描いた文明の完成形
この物語は、文明が強くなる話ではありません。
欲望を制御し、限界を知り、手放すことを覚え、別れを引き受ける。
そのすべてを経た先に、壊れない文明の輪郭が、ようやく浮かび上がるのです。
10 結び――別れを引き受ける文明へ
かぐや姫の昇天は、喪失の物語です。
けれど同時に、人が人であり続けるための条件を提示した物語でもあります。
永遠を持たないからこそ、人は、愛し、悩み、歌を詠み、物語を紡ぎます。
竹取物語は、そのことを千年以上前に、すでに見抜いています。
そして私たちは今、千年の時を経て、ようやくその地点に立っているのです。
【原文】
かやうにて、御心を互に慰め給ふほどに、三年ばかりありて、春の初より、かぐや姫月のおもしろう出でたるを見て、常よりも物思ひたるさまなり。ある人の「月の顔見るは忌むこと」ゝ制しけれども、ともすればひとまには月を見ていみじく泣き給ふ。七月(ふみづき)のもちの月にいで居て、切に物思へるけしきなり。近く使はるゝ人々、竹取の翁に告げていはく、「かぐや姫例も月をあはれがり給ひけれども、この頃となりてはたゞ事にも侍らざンめり。いみじく思し歎くことあるべし。よく\/見奉らせ給へ」といふを聞きて、かぐや姫にいふやう、「なでふ心ちすれば、かく物を思ひたるさまにて月を見給ふぞ。うましき世に」といふ。かぐや姫、「月を見れば世の中こゝろぼそくあはれに侍り。なでふ物をか歎き侍るべき」といふ。かぐや姫のある所に至りて見れば、なほ物思へるけしきなり。これを見て、「あが佛何事を思ひ給ふぞ。思すらんこと何事ぞ」といへば、「思ふこともなし。物なん心細く覚ゆる」といへば、翁、「月な見給ひそ。これを見給へば物思すけしきはあるぞ」といへば、「いかでか月を見ずにはあらん」とて、なほ月出づれば、いで居つゝ歎き思へり。夕暗(ゆふやみ)には物思はぬ氣色なり。月の程になりぬれば、猶(なほ)時々はうち歎(なげ)きなきなどす。是をつかふものども、「猶(なほ)物思(ものおもほ)すことあるべし」とさゝやけど、親を始めて何事とも知らず。八月(はつき)十五日(もち)ばかりの月にいで居て、かぐや姫いといたく泣き給ふ。人めも今はつゝみ給はず泣き給ふ。これを見て、親どもゝ「何事ぞ」と問ひさわぐ。かぐや姫なく\/いふ、「さき\/も申さんと思ひしかども、『かならず心惑はし給はんものぞ。』と思ひて、今まで過し侍りつるなり。『さのみやは』とてうち出で侍りぬるぞ。おのが身はこの國の人にもあらず、月の都の人なり。それを昔の契なりけるによりてなん、この世界にはまうで来りける。今は帰るべきになりにければ、この月の十五日に、かのもとの國より迎に人々まうでこんず。さらずまかりぬべければ、思し歎かんが悲しきことを、この春より思ひ歎き侍るなり」といひて、いみじく泣く。翁「こはなでふことをの給ふぞ。竹の中より見つけきこえたりしかど、菜種の大(おほき)さおはせしを、我丈たち並ぶまで養ひ奉りたる我子を、何人か迎へ聞えん。まさに許さんや」といひて、「我こそ死なめ」とて、泣きのゝしることいと堪へがたげなり。かぐや姫のいはく、「月の都の人にて父母(ちゝはゝ)あり。片時の間(ま)とてかの國よりまうでこしかども、かくこの國には数多の年を經ぬるになんありける。かの國の父母の事もおぼえず。こゝにはかく久しく遊び聞えてならひ奉れり。いみじからん心地もせず、悲しくのみなんある。されど己が心ならず罷りなんとする」といひて、諸共にいみじう泣く。つかはるゝ人々も年頃ならひて、立ち別れなんことを、心ばへなどあてやかに美しかりつることを見ならひて、恋しからんことの堪へがたく、湯水も飮まれず、同じ心に歎しがりけり。この事を帝きこしめして、竹取が家に御使つかはさせ給ふ。御使に竹取いで逢ひて、泣くこと限なし。この事を歎くに、髪も白く腰も屈り目もたゞれにけり。翁今年は五十許なりけれども、「物思には片時になん老(おい)になりにける」と見ゆ。御使仰事とて翁にいはく、「いと心苦しく物思ふなるは、誠にか」と仰せ給ふ。竹取なく\/申す、「このもちになん、月の都よりかぐや姫の迎にまうでくなる。たふとく問はせ給ふ。このもちには人々たまはりて、月の都の人まうで来ば捕へさせん」と申す。御使かへり参りて、翁のありさま申して、奏しつる事ども申すを聞し召しての給ふ、「一目見給ひし御心にだに忘れ給はぬに、明暮見馴れたるかぐや姫をやりてはいかゞ思ふべき」かの十五日(もちのひ)司々に仰せて、勅使には少将高野(たか)の大國といふ人をさして、六衞のつかさ合せて、二千人の人を竹取が家につかはす。 家に罷りて築地の上に千人、屋の上に千人、家の人々いと多かりけるに合はせて、あける隙もなく守らす。この守る人々も弓矢を帶して居り。母屋の内には女どもを番にすゑて守らす。嫗(おみな)塗籠(ぬりごめ)の内にかぐや姫を抱きて居り。翁も塗籠の戸をさして戸口に居り。翁のいはく、「かばかり守る所に、天(あめ)の人にもまけんや」といひて、屋の上に居(を)る人々に曰く、「つゆも物空にかけらばふと射殺し給へ」守る人々のいはく、「かばかりして守る所に、蝙蝠(かはほり)一つだにあらば、まづ射殺して外にさらさんと思ひ侍る」といふ。翁これを聞きて、たのもしがり居り。これを聞きてかぐや姫は、「鎖し籠めて守り戦ふべきしたくみをしたりとも、あの國の人をえ戦はぬなり。弓矢して射られじ。かくさしこめてありとも、かの國の人こば皆あきなんとす。相戦はんとすとも、かの國の人来なば、猛き心つかふ人よもあらじ」翁のいふやう、「御(おん)迎へにこん人をば、長き爪して眼をつかみつぶさん。さが髪をとりてかなぐり落さん。さが尻をかき出でて、こゝらのおほやけ人に見せて耻見せん」と腹だちをり。かぐや姫いはく、「聲高になの給ひそ。屋の上に居る人どもの聞くに、いとまさなし。いますかりつる志どもを、思ひも知らで罷りなんずることの口をしう侍りけり。『長き契のなかりければ、程なく罷りぬべきなンめり。』と思ふが悲しく侍るなり。親たちのかへりみをいさゝかだに仕う奉らで、罷らん道も安くもあるまじきに、月頃もいで居て、今年ばかりの暇を申しつれど、更に許されぬによりてなんかく思ひ歎き侍る。御心をのみ惑はして去りなんことの、悲しく堪へがたく侍るなり。かの都の人はいとけうらにて、老いもせずなん。思ふこともなく侍るなり。さる所へまからんずるもいみじくも侍らず。老い衰へ給へるさまを見奉らざらんこそ恋しからめ」といひて泣く。翁、「胸痛きことなしたまひそ。麗しき姿したる使にもさはらじ」とねたみをり。かゝる程に宵うちすぎて、子の時ばかりに、家のあたり晝のあかさにも過ぎて光りたり。望月のあかさを十合せたるばかりにて、ある人の毛の穴さへ見ゆるほどなり。大空より、人雲に乘りておりきて、地(つち)より五尺ばかりあがりたる程に立ち連ねたり。これを見て、内外(うちと)なる人の心ども、物におそはるゝやうにて、相戦はん心もなかりけり。辛うじて思ひ起して、弓矢をとりたてんとすれども、手に力もなくなりて、痿(なえ)屈(かゞ)まりたる中(うち)に、心さかしき者、ねんじて射んとすれども、外ざまへいきければ、あれも戦はで、心地たゞしれにしれて守りあへり。立てる人どもは、裝束(さうぞく)の清らなること物にも似ず。飛車(とぶくるま)一つ具したり。羅蓋さしたり。その中に王とおぼしき人、「家に造麿まうでこ」といふに、猛く思ひつる造麿も、物に酔ひたる心ちしてうつぶしに伏せり。いはく、「汝をさなき人、聊なる功徳を翁つくりけるによりて、汝が助にとて片時の程とて降しゝを、そこらの年頃そこらの金賜ひて、身をかへたるが如くなりにたり。かぐや姫は、罪をつくり給へりければ、かく賤しきおのれが許にしばしおはしつるなり。罪のかぎりはてぬれば、かく迎ふるを、翁は泣き歎く、あたはぬことなり。はや返し奉れ」といふ。翁答へて申す、「かぐや姫を養ひ奉ること二十年あまりになりぬ。片時との給ふに怪しくなり侍りぬ。また他処(ことどころ)にかぐや姫と申す人ぞおはしますらん」といふ。「こゝにおはするかぐや姫は、重き病をし給へばえ出でおはしますまじ」と申せば、その返事はなくて、屋の上に飛車をよせて、「いざかぐや姫、穢き所にいかでか久しくおはせん」といふ。立て籠めたる所の戸即たゞあきにあきぬ。格子どもゝ人はなくして開きぬ。嫗抱きて居たるかぐや姫外(と)にいでぬ。えとゞむまじければ、たゞさし仰ぎて泣きをり。 竹取心惑ひて泣き伏せる所に寄りて、かぐや姫いふ、「こゝにも心にもあらでかくまかるに、昇らんをだに見送り給へ」といへども、「何しに悲しきに見送り奉らん。我をばいかにせよとて、棄てゝは昇り給ふぞ。具して率ておはせね」と、泣きて伏せれば、御心惑ひぬ。「文を書きおきてまからん。恋しからんをり\/、とり出でて見給へ」とて、うち泣きて書くことばは、「この國に生れぬるとならば、歎かせ奉らぬ程まで侍るべきを、侍らで過ぎ別れぬること、返す\〃/本意なくこそ覚え侍れ。脱ぎおく衣(きぬ)をかたみと見給へ。月の出でたらん夜は見おこせ給へ。見すて奉りてまかる空よりもおちぬべき心ちす」と、かきおく。天人(あまびと)の中にもたせたる箱あり。天(あま)の羽衣入れり。又あるは不死の薬入れり。ひとりの天人いふ、「壺なる御(み)薬たてまつれ。きたなき所のもの食(きこ)しめしたれば、御心地あしからんものぞ」とて、持てよりたれば、聊甞め給ひて、少しかたみとて、脱ぎおく衣に包まんとすれば、ある天人つゝませず、御衣(みぞ)をとり出でてきせんとす。その時にかぐや姫「しばし待て」といひて、「衣着つる人は心ことになるなり。物一言いひおくべき事あり」といひて文かく。天人「おそし」と心もとながり給ふ。かぐや姫「物知らぬことなの給ひそ」とて、いみじく靜かにおほやけに御(み)文奉り給ふ。あわてぬさまなり。「かく数多の人をたまひて留めさせ給へど、許さぬ迎まうできて、とり率て罷りぬれば、口をしく悲しきこと、宮仕つかう奉らずなりぬるも、かくわづらはしき身にて侍れば、心得ずおぼしめしつらめども、心強く承らずなりにしこと、なめげなるものに思し召し止められぬるなん、心にとまり侍りぬる」とて、
今はとて 天のはごろも きるをりぞ 君をあはれと おもひいでぬる
とて、壺の薬そへて、頭中将を呼び寄せて奉らす。中将に天人とりて傳ふ。中将とりつれば、ふと天の羽衣うち着せ奉りつれば、翁をいとほし悲しと思しつる事も失せぬ。この衣着つる人は物思もなくなりにければ、車に乘りて百人許天人具して昇りぬ。その後翁・嫗、血の涙を流して惑へどかひなし。あの書きおきし文を讀みて聞かせけれど、「何せんにか命も惜しからん。誰が為にか何事もようもなし」とて、薬もくはず、やがておきもあがらず病みふせり。中将人々引具して帰り参りて、かぐや姫をえ戦ひ留めずなりぬる事をこま\〃/と奏す。薬の壺に御文そへて参らす。展げて御覽じて、いたく哀れがらせ給ひて、物もきこしめさず、御遊等(など)もなかりけり。大臣・上達部(かんだちめ)を召して、「何(いづ)れの山か天に近き」ととはせ給ふに、或人奏す、「駿河の國にある山なん、この都も近く天も近く侍る」と奏す。是をきかせ給ひて、
あふことも 涙にうかぶ わが身には しなぬくすりも 何にかはせむ
かの奉る不死の薬の壺に、御文具して御使に賜はす。勅使には調岩笠(つきのいはかさ)といふ人を召して、駿河の國にあンなる山の巓(いたゞき)にもて行くべきよし仰せ給ふ。峰にてすべきやう教へさせたもふ(*ママ)。御文・不死の薬の壺ならべて、火をつけてもやすべきよし仰せ給ふ。そのよし承りて、兵士(つはもの)どもあまた具して山へ登りけるよりなん、その山をふしの山とは名づけゝる。その煙いまだ雲の中へたち昇るとぞいひ傳へたる。
竹取物語 了