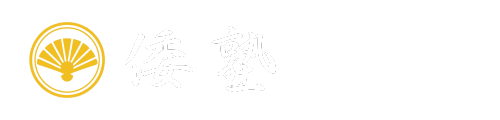火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)は、ただの不思議な毛皮の話ではありません。それは、「本物とは何か」を火の前に立たせて試す、きわめて厳しい文明の物語です。金で買われ、権威に包まれ、由緒と伝説で飾られた裘は、炎に入れられた瞬間、その正体を現します。試練をくぐっていないものは、どれほど立派に見えても、現実の前では燃え尽きる――。この章は、肩書・ブランド・物語が支配する現代社会に向けて、「本物は火を恐れない」と告げています。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
竹取物語・第五章(現代語訳)火鼠の裘(ひねずみのかわごろも)
右大臣・阿倍御主人(あべのみうし)は、たいへん財産が豊かで、大きな屋敷を持つ人物でした。
その年、日本にやって来ていた唐(中国)の商船の長・王卿(おうけい)のもとへ手紙を書き、
「火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)というものを買って送ってほしい」と頼みました。
そして家臣の中から特に信頼できる者を選び、小野房守(おののふさもり)という人を使者として派遣しました。
房守は唐の港に着き、王卿に金を渡しました。
王卿は手紙を読んで、こう返事を書きました。
「火鼠の裘というものは、我が国にもありません。
噂には聞いていますが、見たことがない品です。
もし本当にこの世にあるのなら、すでにこの国にも入ってきているはずです。
ただし、もし天竺(インド)あたりに偶然あるなら、裕福な家を訪ねて探してみましょう。
もし見つからなければ、この金は使者に返します。」
やがて唐の船が帰ってきました。
小野房守が帰国したと聞いた右大臣は、馬を走らせて迎えにやらせ、筑紫(九州)から七日で都に戻ってきました。
持ち帰った手紙にはこう書かれていました。
「火鼠の裘を、苦労して人を使って探し出しました。
今の世にも昔の世にも、めったにない品です。
昔、天竺の高僧がこの国へ持ち渡り、西の山寺にあると聞き、公の許可を得て、ようやく買い取りました。
代金は五十両です。船が帰るときに送金してください。
もし払えなければ、この裘は質に取ります。」
右大臣はこれを見て、
「金のことなど少しの問題だ。こんな貴重なものを手に入れられたのは、なんと嬉しいことだ」
と言って、唐の方角に向かって拝みました。
箱を開けると、美しい瑠璃で飾られた箱に入っており、中の裘は深い紺青色で、毛の先には金色の光がきらめいていました。まさに宝物と見え、火に焼けないこと以上に、その美しさが際立っていました。
右大臣は
「さすが、かぐや姫が望まれた品だ」
と言って、箱に入れたまま枝に掛け、立派に身支度を整え、歌を添えて持って行きました。
かぎりなき おもひに焼けぬ かはごろも
袂(たもと)かわきて 今日こそはきめ
(意味)限りない私の想いにも焼けないこの毛皮を身につけ、今日こそあなたの袖を乾かして、結ばれましょう。
門に着くと、竹取の翁がそれを取り次ぎ、かぐや姫に見せました。
かぐや姫は裘を見て言いました。
「見事な皮のようですが、本当に火鼠の皮かどうかは分かりませんね。」
翁は、
「とにかくお迎えしましょう。これほど珍しい裘です。疑わず本物と思ってください。」と言って、大臣を中へ招き入れました。翁の心では「今度こそこの縁がまとまる」と思っていました。
しかし、かぐや姫は翁に言いました。
「この裘は、火に焼いて燃えなければ本物でしょう。
世にないものなら、それでこそ本物ですから、
焼いて確かめましょう。」
翁ももっともだと思い、大臣に伝えました。
大臣は、
「唐でもめったにない品を苦労して手に入れたのです。
疑う必要などありません。
ですが、どうしてもというなら、焼いてみなさい。」と言いました。
そこで火に入れると、裘はめらめらと燃えてしまいました。
「やはりただの皮だったのだ」と人々は言いました。
右大臣は、顔色が青ざめ、かぐや姫は「ああ、うれしい」と言って喜びました。
かぐや姫は、右大臣の歌に返して、こう詠み、箱に入れて返しました。
なごりなく もゆと知りせば かは衣
おもひの外に おきて見ましを
(意味)跡形もなく燃えると知っていたなら、その衣は、思いの外に置いて見ていたでしょうに
右大臣は、そのまま帰って行きました。
人々は噂しました。
「阿倍大臣は火鼠の裘を持って、かぐや姫のもとに通っているらしい。」
「いや、火に入れたら燃えてしまって、姫には会えなかったそうだ。」
このことから、「とげのないものは、あえない(役に立たない)」という言葉が生まれたのです。
第五章(現代語訳)火鼠の裘(ひねずみのかわごろも)解説
1 火鼠の裘とは何か
かぐや姫が求めた「火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)」とは、火に焼いても燃えない毛皮です。
これは単なる不思議アイテムではありません。意味しているのは・・・
「本物は、現実にさらされても壊れない」ということです。
火は、試練を意味し、現実の危機を象徴します。
試練を受け、危機を乗り越える者だけが本物だという、これはきわめて厳しい文明の物差しです。
2 阿倍大臣(あべのおほおみ)がやったこと
これに対し、阿倍右大臣がしたことは、
「金を出し、商人を使い、伝聞で探し、権力で買い取る」という行動でした。
つまり、阿倍大臣は、自分の足で探していません。
ここが決定的で、これは車持皇子(くるまもちのみこ)とまったく同じ構造です。
| 皇子 | 大臣 |
|---|---|
| 技術で偽物を作る | 金で偽物を買う |
| 工匠を使う | 商人を使う |
| 物語で飾る | 伝聞で飾る |
結局どちらも、そこに「自分の霊(ひ)=火が入っていない」のです。
この発想は、西洋語ではまず出てこない、日本語独自の発想です。
3 なぜ「燃えた」のか
裘(かわごろも)は、きらびやかな宝石箱に入り、光り輝き、天竺の聖者の話が付いていました。
しかもこれを手に入れた方法は、なんと国家レベルの取引です。
つまり、外形的には、完全に「本物の顔」をしています。
でも、火に入れた瞬間、「燃えた」のです。
なぜか。そこに、命をかけた探求も、本人の試練も、現実との接触も、魂の賭けも、それらが、ひとつも入っていなかったからです。
つまりそれは、ただの「高級な物」でしかなかったのです。
なるほど、価値はあります。美しいし、高価です。
でも、魂が入っていないのです。火をくぐっていないのです。だから霊(ひ)が備わっていないのです。
だからダメだと竹取物語は書いています。
4 かぐや姫が見ていたもの
かぐや姫は、箱や皮の美しさも、値段も、伝説も見ていません。
見ていたのは、
「これは火に入る覚悟をくぐっているか?」という一点だけです。
だから、「焼いてみましょう」と言いました。
文明がどれだけ美辞麗句を並べても、最後に残るのは、
「それは現実を生き抜いたか?」
という問いだけだと、物語は語っているのです。
5 大臣が崩れた理由
大臣は「恋に負けた」のではありません。
「自分が空虚だったことが露呈した」から崩れています。
結局のところ、自分は何も探していないし、何も賭けていないし、何も生きていなかったことが、炎の前でバレたのです。
これは、現代で言えば、肩書き、カネ、権威、ブランドなどが、何の実体も持たないことがバレた瞬間です。
国や民族によっては、いたずらに肩書やカネや権威やブランドがものをいう国もあります。
そういった国の人は日本にやってきても、肩書やブランド等でものを言います。
もっといえば、肩書やブランド等で権威付けしようとしている人がいたら、まずはその本心を疑うべきということです。
私たち日本人は、現代社会での経験を通して、権威ある人の言うことが、いかに嘘っぱちなのかをすでに知っています。
6 とげなきものはあへなし
今回の章では、最後の言葉がすごいです。
とげなきものはあへなし
(とげのないもの=刺さらないものは、意味がない)
「あへなし」を「意味がない」と訳させていただきましたが、直訳すれば「会えない」です。
そして「会えない」は、関係が結ばれないことを意味します。
なぜか。「とげ」がないからです。
「とげ」とは、人の痛みであり、現実であり、試練であり、失敗であり、傷のことです。
物語で言えば「火をくぐった痕跡」です。
それがないものは、人と真に「会う」ことすらできないと書かれているのです。
この一文だけで、現代のSNS文明・ブランド文明・広告文明が、全部切られています。
7 この章が描いている未来像
この章では、文明が、カネや技術や流通やストーリー等で、どれだけ本物を装っても、火(現実)の前では必ずバレるということが語られています。
もっというなら、どんなに虚構で飾り立てても、事実の前には崩壊する、ということです。
そして「火をくぐっていない者ほど先に燃える」ということは、試練を受けていないものは、火(現実)の前で見事なまでに崩れ去る、ということです。
右大臣が燃えたのは、裘ではなく、彼自身の虚構であったのです。
その意味でこの物語は、「平安時代の恋話」ではありません。
AI・金融・ブランド・国家・宗教が氾濫する現代社会への警告書です。
だからかぐや姫は言っています。
「本物かどうかは、焼けばわかります。」
この一言で、文明のすべてが試されているのです。
【所感】
この物語が重要なのは、内容だけではありません。『竹取物語』が、平安中期のかな文字文学として成立しているという事実そのものが、決定的です。
かな文字は、当時の女性たちの言葉でした。つまりこの文明批評は、制度や権力の外側にいた女性たちの視線によって、語り継がれてきたものなのです。
彼女たちは、権威を論破しません。正義を叫びません。ただ、現実に即して、
「それは、本当に火をくぐっているのか?」
この一言で、金も、肩書も、由緒も、物語も、裁くためではなく、逃げ場のない現実として試しています。
だからこの物語は、千年経っても古びていないのです。
いやはや女性は怖い(笑)
【原文】火鼠の裘
右大臣阿倍御主人は財(たから)豐に家廣き人にぞおはしける。その年わたりける唐土船の王卿(わうけい)といふものゝ許に、文を書きて、「火鼠の裘といふなるもの買ひておこせよ。」とて、仕うまつる人の中に心たしかなるを選びて、小野房守といふ人をつけてつかはす。もていたりて、かの浦に居(を)る王卿に金をとらす。王卿文をひろげて見て、返事かく。「火鼠の裘我國になきものなり。おとには聞けどもいまだ見ぬものなり。世にあるものならば、この國にももてまうで來なまし。いと難きあきなひなり。しかれどももし天竺にたまさかにもて渡りなば、もし長者のあたりにとぶらひ求めんに、なきものならば、使に添へて金返し奉らん。」といへり。かの唐土船來けり。小野房守まうで來てまうのぼるといふことを聞きて、あゆみとうする馬をもちて走らせ迎へさせ給ふ時に、馬に乘りて、筑紫よりたゞ七日(なぬか)に上りまうできたり。文を見るにいはく、「火鼠の裘辛うじて、人を出して求めて奉る。今の世にも昔の世にも、この皮は容易(たやす)くなきものなりけり。昔かしこき天竺のひじり、この國にもて渡りて侍りける、西の山寺にありと聞き及びて、公に申して、辛うじて買ひとりて奉る。價の金少しと、國司使に申しゝかば、王卿が物加へて買ひたり。今金五十兩たまはるべし。船の歸らんにつけてたび送れ。もし金賜はぬものならば、裘の質かへしたべ。」といへることを見て、「何おほす。今金少しのことにこそあンなれ。必ず送るべき物にこそあンなれ。嬉しくしておこせたるかな。」とて、唐土の方に向ひて伏し拜み給ふ。この裘入れたる箱を見れば、種々のうるはしき瑠璃をいろへて作れり。裘を見れば紺青(こんじやう)の色なり。毛の末には金の光輝きたり。げに寳と見え、うるはしきこと比ぶべきものなし。火に燒けぬことよりも、清(けう)らなることならびなし。「むべかぐや姫のこのもしがり給ふにこそありけれ。」との給ひて、「あなかしこ。」とて、箱に入れ給ひて、物の枝につけて、御身の假粧(けさう)いといたくして、やがてとまりなんものぞとおぼして、歌よみ加へて持ちていましたり。その歌は、
かぎりなき おもひに焼けぬ かはごろも 袂(たもと)かわきて 今日こそはきめ
家の門(かど)にもて至りて立てり。竹取いで來てとり入れて、かぐや姫に見す。かぐや姫かの裘を見ていはく、「うるはしき皮なンめり。わきてまことの皮ならんとも知らず。」竹取答へていはく、「とまれかくまれまづ請じ入れ奉らん。世の中に見えぬ裘のさまなれば、是をまことゝ思ひ給ひね。人ないたくわびさせ給ひそ。」といひて、呼びすゑたてまつれり。かく呼びすゑて、「この度は必ずあはん。」と、嫗の心にも思ひをり。この翁は、かぐや姫のやもめなるを歎かしければ、「よき人にあはせん。」と思ひはかれども、切に「否。」といふことなれば、えしひぬはことわりなり。かぐや姫翁にいはく、「この裘は火に燒かんに、燒けずはこそ實ならめと思ひて、人のいふことにもまけめ。『世になきものなれば、それを實と疑なく思はん。』との給ひて、なほこれを燒きて見ん。」といふ。翁「それさもいはれたり。」といひて、大臣(おとゞ)に「かくなん申す。」といふ。大臣答へていはく、「この皮は唐土にもなかりけるを、辛うじて求め尋ね得たるなり。何(なに)の疑かあらん。さは申すとも、はや燒きて見給へ。」といへば、火の中にうちくべて燒かせ給ふに、めら\/と燒けぬ。「さればこそ異物の皮なりけり。」といふ。大臣これを見給ひて、御顔は草の葉の色して居給へり。かぐや姫は「あなうれし。」と喜びて居たり。かのよみ給へる歌のかへし、箱に入れてかへす。
なごりなく もゆと知りせば かは衣 おもひの外に おきて見ましを
とぞありける。されば歸りいましにけり。世の人々、「安倍大臣は火鼠の裘をもていまして、かぐや姫にすみ給ふとな。こゝにやいます。」など問ふ。或人のいはく、「裘は火にくべて燒きたりしかば、めら\/と燒けにしかば、かぐや姫逢ひ給はず。」といひければ、これを聞きてぞ、とげなきものをばあへなしとはいひける。