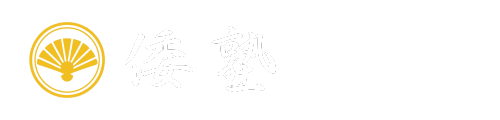竹取物語第八章「帝の懸想」は、物語の中で最も重い転換点です。これまで技術、金、武力、知略といった文明の力が次々と崩れてきました。ここでついに登場するのは、国家そのものを体現する帝(みかど)という御存在です。善政であり、正当な権力であり、節度ある国家最高権威であっても、それでもなお手に入れてはいけない領域がある。この章が描くのは、国家の敗北ではなく、国家が自ら踏みとどまる、きわめて成熟した文明の姿です。命令ではなく言葉で、強制ではなく距離で、所有ではなく往復によって関係を結ぶ。第八章は、「壊れない文明とは何か」という問いに、物語というかたちで答えていきます。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
【現代語訳】第八回 帝(みかど)の懸想(けそう)
さて、かぐや姫の姿かたちが世に比類なく美しいということを、帝がお聞きになり、内侍(ないし)である中臣(なかおみ)のふさ子にこうお命じになりました。
「多くの男たちの人生を無駄にして、誰にも会おうとしないというかぐや姫とは、いったいどれほどの女なのか。そなたが行って、実際に見てきなさい」
ふさ子は命を受けて出かけ、竹取の翁の家に到着すると、丁重に迎え入れられました。ふさ子が翁の妻(嫗・おみな)に言います。
「帝のご命令で、かぐや姫のご容貌がどれほどのものか、よく見て参れと仰せつかって参りました」
嫗は「それなら、そのように申し上げましょう」と言って奥へ入りました。
嫗がかぐや姫に
「さあ、帝の使いにお会いなさい」と言うと、かぐや姫は答えました。
「私は人に見せるほどの姿ではありません。どうしてお会いできましょう」
嫗が「なんということを。帝の御使いを粗略に扱うわけにはいきません」と言うと、かぐや姫はこう答えます。
「帝がお召しになることを、特別ありがたいとも思いません」
そう言って、どうしても姿を見せようとしませんでした。
幼い娘のようでもありましたが、非常に慎み深く、どこか距離を置いた物言いだったため、強く責めることもできませんでした。
嫗は内侍のもとへ戻り、「どうにもこの子は気難しく、対面はできそうにありません」と伝えます。すると内侍は言いました。
「必ず見て参れと仰せつかったのです。姿を拝見せずに、どうして帰れましょう。帝のご命令を、世に生きる者が無視するなどあってはなりません。どうか道理に外れたことをなさらないでください」
その言葉を聞いても、かぐや姫はなお応じません。
「帝の命に背くなら、いっそ殺してくださっても構いません」とまで言いました。
内侍は帰って、この一部始終を帝に奏上しました。帝はこれを聞いて、
「多くの人を死なせてきた心の持ち主なのだな」と一度は思いとどまりましたが、それでもなお心に引っかかるものがあり、「この女のたばかり(思わせぶり)に惑わされているのではないか」と思い、竹取の翁(おきな)を召(め)して仰(おっしゃ)られました。
「そなたのもとにいるかぐや姫を差し出せ。美しいと聞いて使いを何度も遣(つか)わしたが、ついに姿を見ることができなかった。このように拒(こば)み続けるのは、あまりにも失礼ではないか」
翁は恐れ入り、「この娘は宮仕えなど到底できない者で、私も困り果てております。しかし、いずれ改めて申し上げます」と答えます。帝は、
「なぜ翁の手元に置いて、私の思うままにしないのか。この娘を差し出せば、翁に官位や冠を与えよう」と仰いました。
翁は喜んで帰り、かぐや姫にこう語ります。
「帝はこのように仰っている。どうしても宮仕えはなさらぬか」
かぐや姫は答えます。
「私はもとより、そのような宮仕えをするつもりはありません。無理に仕えさせられるなら、消え失せてしまうでしょう。官位や冠をいただいて、死ぬようなものです」
翁は、「そんなことを言ってはいけない。お前のために官位を得るのだ。どうして宮仕えしてくれないのだ。死ぬなどということがあるものか」と言います。
しかし、かぐや姫は、「それは嘘ではありません。仕えさせてみれば、必ず死ぬと分かるでしょう。多くの人の誠実な志を無にしてきた私が、昨日今日の帝のお言葉に応じれば、世の噂が恥ずかしいでしょう」と言いました。
翁は、「天下(あめのした)のことがどうであれ、命が危ういことこそ重大です。やはり宮仕えできないと申し上げましょう」と帝に奏上しました。さらに「この娘は私の手で産んだ子ではなく、昔、山で見つけた子です。だから心も世の人とは違うのです」と付け加えました。
帝は、「翁の家は山の近くであったな。狩りのついでに見に行こう」と仰せになられます。
翁が「それはよいことです。突然おいでになってご覧ください」と奏上すると、帝は急に日を定め、狩りに出て、かぐや姫の家に入られました。
すると、あたり一面に光が満ち、清らかに座っている人がいました。
帝は「これがかぐや姫だろう」と思い、近づかれましたが、姫は逃げ込みます。帝が袖をつかまえると、姫は顔を隠しましたが、一度見たその姿は比類なく美しく、帝は、「このまま連れて行こう」と思われました。
しかし、かぐや姫は言いました。
「私がこの国に生まれた身であればお仕えできたでしょうが、ここに長く留まることはできません」
帝がなお連れて行こうとして御輿(みこし)を寄せると、かぐや姫はふっと影のように消えてしまいました。
帝は「やはり、ただの人ではなかったのだ」と思い、「それなら無理に連れては行かぬ。せめて元の姿に戻ってくれ。それを見て帰ろう」と仰いました。
かぐや姫は元の姿に戻りました。
帝はますます心惹かれましたが、無理に留めることはせず、後ろ髪を引かれる思いで帰られました。
帰り際、帝はかぐや姫に歌を詠みました。
かへるさの みゆき物うく おもほえて そむきてとまる かぐや姫ゆゑ
(意味)帰る道の行幸(みゆき)がつらく思えるのは、背を向けてとどまるかぐや姫のためである
かぐや姫は返歌しました。
葎(むぐら)はふ 下にもとしは 経(へ)ぬる身の なにかはたまの うてなをもみむ
(意味)荒れ草の生い茂る人里離れたこの身が、なぜ玉の御殿などを再び見るでしょうか
帝はこれを読んで、ますます名残惜しく思われましたが、夜を明かすわけにもいかず、都へ帰られました。
これ以後、帝は他の女性たちのもとへはほとんど通わず、ただかぐや姫のもとへ文を送り続けました。
かぐや姫も、無愛想ではない返事を交わし、草木や風景に寄せて歌を贈り合ったのです。
【第八章 解説】帝の懸想――権力ですら回収できない「天の理」
1 この章が決定的に重要な理由
ここまでの章では、
(1) 蓬莱の玉の枝・・技術の虚構
(2) 火鼠の裘・・・・金と流通の虚構
(3) 龍の首の玉・・・武力と支配の虚構
(4) 燕の子安貝・・・知と合理の虚構
が、順番に崩されてきました。
そして第八章で、登場するのが、国家そのものを体現する帝(みかど)のご存在です。
つまりこの章は、「個人の欲望」でも「権力者の横暴」でもなく、国家権力ですら回収できないものがあるという地点を描いています。
ものすごく例えは悪いですが、ものすごくわかりやすく言うと、ラスボス登場です。
2 帝は「暴君」ではない
ここで非常に大切なのは、帝(みかど)が横暴な支配者としては描かれていないことです。
強引に拉致せず、殺さず、命令を乱用せず、最後は「連れていかない」という判断を自ら下されています。
つまり帝は、きわめて節度ある統治者です。
それでも、かぐや姫は宮仕えを拒むのです。
ここで物語が主張していることは、
「善政であっても
正当な権力であっても、
回収してはいけない領域がある」
ということです。
3 かぐや姫が拒んでいるのは「帝」ではない
かぐや姫は、帝を侮辱していません。むしろ、帝の使いを粗略にしないよう気遣い、命令は恐れてないけれど、反抗も反発もせず、無礼でない程度の距離を取っています。
つまり、非常に日本的な拒絶をしています。
そして彼女が拒んでいるのは、宮仕えであり、権力に編入されることであり、制度の中に収まることです。
つまり、国家という枠組みそのものを拒んでいます。
4 「影になる」場面の意味
ひとつ不思議な描写がでてきます。帝がかぐや姫の手を取ろうとした瞬間、かぐや姫は影になるのです。
これは魔法的演出というより、象徴と読むべきところです。
なぜなら、
• 制度を掴(つか)もうとした瞬間
• 定義しようとした瞬間
• 所有しようとした瞬間に
消えてしまう存在が、かぐや姫=天の理だからです。
理(ことわり)は、説明しようとすると壊れ、掴もうとすると消えるのです。
5 帝は「負けていない」
ここも重要です。
帝は、無力化されていないし、断罪されていないし、滅ぼされてもいません。
そしてご自身で、「連れていかない」という判断を下されています。
これは敗北ではありません。
国家最高権威が、天の理の前に、自ら引き下がった瞬間です。
竹取物語は、国家が天の理に敗れる物語ではなく、
国家が、天の理の前で「踏みとどまる」物語、として描いているのです。
大切なことは、竹取物語が、
• 帝=敗者
• 権力=悪
などという単純化を、きっぱり避けているということです。
竹取物語の品格と、日本文明の成熟が、ここでちゃんと守られているのです。
6 歌の往復が示す「距離の文明」
帝とかぐや姫は、最後まで歌を交わし続けます。
これは非常に重要です。
• 命令ではなく、言葉
• 強制ではなく、往復
• 所有ではなく、距離
ここに、日本文明の理想形が示されているからです。
近づきすぎない
触れすぎない
それでも、想いは断ち切らない
7 なぜ「妻にしない」のか
帝は、かぐや姫を、妾(めかけ)にも、妻にもされていません。宮中に囲ってもいません。
ただ想い続けられます。
つまりこれは、恋愛譚ではありません。
「理は、制度化できない」
「愛しても、囲えないものがある」
という、日本文化の核心です。
8 この章が示す文明の到達点
これまでの七章が「壊れる文明」を描いてきたとすれば、第八章は、「壊さずに、手を引く文明」を描いています。
• 欲望を満たさなくてもよい
• 権力を使わなくてもよい
• 回収できないものがあると知る
ここに、文明の「成熟」が描かれています。
9 かぐや姫は、最後まで「裁かない」
この章でも、かぐや姫は、帝を否定せず、罰せず、正義を振りかざしていません。
ただ、応じなかっただけです。
竹取物語は、
「正しさで人を屈服させる文明」
ではなく、
「理に合わないものが、自然に手を引く文明」
を描いているのです。
10 まとめ
第八章「帝の懸想」は、国家権力、善政、正当性、愛のすべてを持ってしても、回収できない領域があるということを、きわめて美しく描いた章です。
そしてこの章で初めて、
「壊れない文明の姿」
が、うっすらと語られています。
第八章は、いよいよ、最終章へ向かう前の総決算なのです。
【原文】
さてかぐや姫かたち世に似ずめでたきことを、帝(みかど)聞(きこ)しめして、内侍(ないし)の中臣のふさ子にの給ふ、
「多くの人の身を徒(いたずら)になしてあはざンなるかぐや姫は、いかばかりの女ぞ」と、「罷(まか)りて見て参(まい)れ」との給ふ。
ふさ子承りてまかれり。竹取の家に畏まりて請じ入れてあへり。嫗(おみな)に内侍のたまふ、
「仰ごとに、かぐや姫の容(かたち)いうにおはすとなり。能(よ)く見て参るべきよしの給(たま)はせつるになん参りつる」といへば、「さらばかくと申し侍(はべ)らん」といひて入りぬ。
かぐや姫に、「はやかの御使(みつかひ)に対面し給へ」といへば、かぐや姫、「よき容(かたち)にもあらず。いかでか見(まみ)ゆべき」といへば、「うたてもの給ふかな。帝の御(み)使をばいかでか疎(おろそか)にせん」といへば、かぐや姫答ふるやう、「帝の召しての給はんことかしこしとも思はず」といひて、更に見ゆべくもあらず。うめる子のやうにはあれど、いと心恥しげに疎おろそかなるやうにいひければ、心のまゝにもえ責めず。嫗、内侍の許にかへり出でて、「口をしくこの幼き者はこはく侍るものにて、対面すまじき」と申す。内侍、「『必ず見奉りて参れ。』と、仰事ありつるものを、見奉らではいかでか帰り参らん。國王の仰事を、まさに世に住み給はん人の承り給はではありなんや。いはれぬことなし給ひそ」と、詞はづかしくいひければ、これを聞きて、ましてかぐや姫きくべくもあらず。「國王の仰事を背かばはや殺し給ひてよかし」といふ。この内侍帰り参りて、このよしを奏す。帝聞しめして、「多くの人を殺してける心ぞかし」との給ひて、止みにけれど、猶思しおはしまして、「この女(をうな)のたばかりにやまけん」と思しめして、竹取の翁を召して仰せたまふ、「汝が持て侍るかぐや姫を奉れ。顔容よしと聞しめして、御使をたびしかど、かひなく見えずなりにけり。かくたい\〃/しくやはならはすべき」と仰せらる。翁畏まりて御返事申すやう、「この女の童は、絶えて宮仕つかう奉(まつ)るべくもあらず侍るを、もてわづらひ侍り。さりとも罷りて仰せ給はん」と奏す。是を聞し召して仰せ給ふやう、「などか翁の手におほしたてたらんものを、心に任せざらん。この女めもし奉りたるものならば、翁に冠(かうぶり)をなどかたばせざらん」翁喜びて家に帰りて、かぐや姫にかたらふやう、「かくなん帝の仰せ給へる。なほやは仕う奉り給はぬ」といへば、かぐや姫答へて曰く、「もはらさやうの宮仕(つかう)奉まつらじと思ふを、強ひて仕う奉らせ給はゞ消え失せなん。御(み)司冠つかう奉りて死ぬばかりなり」翁いらふるやう、「なしたまひそ。官(つかさ)冠も、我子を見奉らでは何にかはせん。さはありともなどか宮仕をし給はざらん。死に給ふやうやはあるべき」といふ。「『なほそらごとか。』と、仕う奉らせて死なずやあると見給へ。数多(あまた)の人の志疎(おろか)ならざりしを、空しくなしてしこそあれ、昨日今日帝のの給はんことにつかん、人ぎきやさし」といへば、翁答へて曰く、「天の下の事はとありともかゝりとも、御おん命の危きこそ大なるさはりなれ。猶仕う奉るまじきことを参りて申さん」とて、参りて申すやう、「仰の事のかしこさに、かの童を参らせんとて仕う奉れば、『宮仕に出したてなば死ぬべし。』とまをす。造麿が手にうませたる子にてもあらず、昔山にて見つけたる。かゝれば心ばせも世の人に似ずぞ侍る」と奏せさす。 帝おほせ給はく、「造麿が家は山本近かンなり。御(み)狩の行幸(みゆき)し給はんやうにて見てんや」とのたまはす。造麿が申すやう、「いとよきことなり。何か心もなくて侍らんに、ふと行幸して御覽ぜられなん」と奏すれば、帝俄に日を定めて、御狩にいで給ひて、かぐや姫の家に入り給ひて見給ふに、光滿ちてけうらにて居たる人あり。「これならん」とおぼして、近くよらせ給ふに、逃げて入る、袖を捕へ給へば、おもてをふたぎて候へど、初よく御覽じつれば、類なくおぼえさせ給ひて、「許さじとす」とて率ておはしまさんとするに、かぐや姫答へて奏す、「おのが身はこの國に生れて侍らばこそ仕へ給はめ、いとゐておはし難くや侍らん」と奏す。帝「などかさあらん。猶率ておはしまさん」とて、御(おん)輿を寄せたまふに、このかぐや姫きと影になりぬ。「はかなく、口をし」とおぼして、「げにたゞ人にはあらざりけり」とおぼして、「さらば御供には率ていかじ。もとの御かたちとなり給ひね。それを見てだに帰りなん」と仰せらるれば、かぐや姫もとのかたちになりぬ。帝なほめでたく思し召さるゝことせきとめがたし。かく見せつる造麿を悦びたまふ。さて仕うまつる百官の人々に、あるじいかめしう仕う奉る。帝かぐや姫を留めて帰り給はんことを、飽かず口をしくおぼしけれど、たましひを留めたる心地してなん帰らせ給ひける。御(おん)輿に奉りて後に、かぐや姫に、
かへるさの みゆき物うく おもほえて そむきてとまる かぐや姫ゆゑ
御返事を、
葎(むぐら)はふ 下にもとしは 経(へ)ぬる身の なにかはたまの うてなをもみむ
これを帝御覽じて、いとゞ帰り給はんそらもなくおぼさる。御心は更に立ち帰るべくもおぼされざりけれど、さりとて夜を明し給ふべきにもあらねば、帰らせ給ひぬ。常に仕う奉る人を見給ふに、かぐや姫の傍(かたはら)に寄るべくだにあらざりけり。「こと人よりはけうらなり」とおぼしける人の、かれに思しあはすれば人にもあらず。かぐや姫のみ御心にかゝりて、たゞ一人過したまふ。よしなくて御方々にもわたり給はず、かぐや姫の御(おん)許にぞ御文を書きて通はさせ給ふ。御返事さすがに憎からず聞えかはし給ひて、おもしろき木草につけても、御歌を詠みてつかはす。