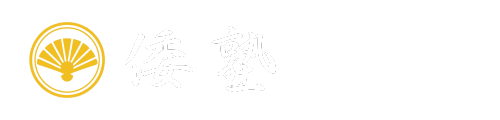「龍の首の玉」とは、願いを叶える宝ではありません。それは、人の力を超えた自然そのもの――理(ことわり)を象徴する存在です。大伴大納言は、権力と武力によって、それを奪おうとしました。その瞬間、世界は荒れ、嵐が起こり、命は危機に晒されます。しかし、力を捨て、祈りへと立ち返ったとき、嵐は静まりました。
この物語が語るのは、「努力すれば手に入るもの」と「最初から、取りに行ってはいけないもの」が、はっきりと分かれているという事実です。竹取物語・第六章は、力と支配の文明が、どこで、どのように破綻するのかを決定的に描いています。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
「竹取物語」第六回 龍の首の玉(現代語訳)
大伴御行(おおとものみゆき)の大納言は、家中にいる人々をすべて集めて、こう言いました。
「龍(たつ)の首に、五色に光る玉があるという。
その玉を取ってきた者には、どんな願いでも叶えてやろう。」
男たちはこの言葉を聞いて答えました。
「仰せはまことにありがたいことです。
しかし、その玉は容易に手に入るものではありません。
ましてや龍の首にある玉など、どうして取れるでしょうか。」
すると大納言は言いました。
「君の使いというものは、『命を捨てても主君の命令を果たそう』と思うべきだ。
この玉は、この国にない天竺や唐の宝ではない。
龍はこの国の海や山に現れるではないか。
なぜお前たちは、そんなに難しいことだと言うのだ。」
男たちは言いました。
「それでは、たとえ難しくとも、ご命令に従って探しに参りましょう。」
大納言は笑って言いました。
「それでこそ、君の使いと名乗れる。
主君の命令に、どうして背くことがあろうか。」
こうして彼らを、龍の首の玉を取りに出発させました。
大納言は、道中の食糧として、屋敷にある絹・綿・銭などをすべて与えました。そして、
「玉を取れなければ、決して家に帰ってくるな」と命じました。
男たちは表向きは命令を受け入れましたが、
「龍の玉など取れるはずがない」
「親や主君といえども、こんな無情な命令をするものか」
と陰で非難し合い、与えられた物を分け合うと、それぞれ自分の家に引きこもったり、好きな場所へ逃げてしまいました。
一方、大納言は、
「かぐや姫を妻に迎えるのだから、今までのような暮らしではならぬ」
と言って、豪華な邸宅を建てました。漆を塗り、蒔絵を施し、屋根には色とりどりの糸を染めて葺(ふ)かせ、室内には見事な綾織(あやおり)に絵を描いた屏風(びょうぶ)や壁掛けを飾りました。
以前の妻たちは去り、大納言は「必ずかぐや姫と結ばれる」と思い込んで、独りで日々を過ごしました。
しかし、使いに出した男たちは、年を越えても音沙汰がありません。
不安に耐えきれなくなった大納言は、ひそかに従者二人だけを連れて、難波のあたりへ出向き、船乗りたちに尋ねました。
「大伴大納言の家来が、船に乗って龍を殺し、
その首の玉を取ったという話を聞いたことはないか。」
船乗りたちは笑って答えました。
「そんな不思議なことをする船など聞いたことがありません。」
大納言はそれを信じず、
「私の弓の腕なら、龍がいれば射殺して玉を取ってみせる。
家来など待っていられぬ」と言って、自ら船に乗り、海を巡り始めました。
やがて筑紫の方の海へ出たとき、激しい風が吹き荒れ、空は暗くなり、波が船に打ちかかり、雷が落ちるように光り始めました。
大納言は恐れ惑って言いました。
「これほど恐ろしい目に遭ったことはない。
いったいどうなるのだ。」
船頭は答えました。
「これほどの嵐は、龍を殺そうとしたためでしょう。
神の怒りです。早く神にお祈りなさい。」
大納言はそれを聞き、「もっともだ」と言って、
「龍を殺そうなどと考えた自分の愚かさをお許しください。
これからは毛一本も傷つけることはいたしません」
と、何度も何度も祈りました。
すると次第に雷は収まり、風はなお強いものの、船は無事に進むようになりました。
数日後、船が着いた浜は、播磨の明石の浜でした。
大納言は衰弱しきって船底に伏せたままで、腹は大きく膨れ、両目はまるで李(すもも)を二つ付けたように腫(は)れていました。
それを見て、国司は思わず微笑みました。
やがて輿に乗せられて家に帰ったところへ、逃げていた家来たちが戻ってきて言いました。
「龍の玉が取れなかったので帰れませんでした。
しかし、その難しさをご存じなら、
罰はないだろうと思い、参りました。」
大納言は起き上がって言いました。
「よくぞ取らずに済んだ。
龍は雷神の類だったのだ。
もし玉を取ろうとすれば、多くの人が命を落としたであろう。
まして私自身も無事では済まなかったはずだ。」
そして、
「かぐや姫という者は、人を殺そうとした大盗人だ。
もうあの家の近くへは行かぬ。お前たちも近づくな」
と言って、残っていた財産を家来たちに分け与えました。
これを聞いた、離縁されていた元の妻は、腹を抱えて笑いました。
立派に建てた邸宅は、鳶や烏の巣となり、見る影もなく荒れていきました。
世の人々は噂しました。
「大伴の大納言は、龍の玉を取ったそうだ。」
「いや、龍の玉ではなく、目に李のような玉を二つ付けて帰ってきたのだ。」
このことから、「あなへがた(=とんでもない、あり得ない)」という言葉が生まれたのです。
【第六章 解説】龍の首の玉――力で真理を奪おうとする文明の末路
1 龍の首の玉とは何か
ここで語られる「龍の首の五色の玉」は、いわゆる願いを叶える宝珠ではありません。
それは、雷・嵐・海・風・生と死といった、人の力を超えた自然そのもの、すなわち「人智を超えた理(ことわり)」を象徴する存在です。
龍は倒す対象ではなく、本来、人が畏れ、祈り、距離を保つべき存在です。
つまり、かぐや姫が突きつけた課題は、「努力すれば届く試練」ではありません。
最初から、取りに行ってはいけないものに、どう向き合うか。
その姿勢そのものが問われていたのです。
2 大伴大納言の文明観
大伴大納言は、これまでの求婚者とは異なります。
偽物を作ることも、金で買うこともしません。
彼が選んだのは、権力であり、命令と忠誠の強制であり、自らの武力です。
そして、部下に向かって放った言葉は、
「命を捨てても、主君の命令を果たせ」。
大伴氏は、古代国家の軍事を担った家柄です。
この一言に、軍人としての彼の文明観――
自然や理は、人の力で制圧できる
という発想が、はっきりと表れています。
3 家来たちが「逃げた」理由
命令を受けた家来たちは、やがて散り散りになって逃げていきます。
これは、臆病だったからではありません。
彼らは、
龍は人の力で倒せる相手ではない、
これは忠誠の問題ではない、
命を捨てる価値のある使命ではない、
という現実を理解していたのです。
だから彼らは、表向きは従い、実際には離れ、
大納言を「つきなき(理不尽な)主」と評したのです。
ここで描かれているのは、
「無理な理念」が、人を「嘘と逃避」に追い込む構図です。
4 なぜ嵐に遭ったのか
大納言が自ら海に出た瞬間、世界は、闇、暴風、雷、大波で荒れ狂います。
これは偶然ではありません。龍とは自然そのもの、神意そのものだからです。
重要なことは、「龍と戦ったから嵐になった」のではない、という点です。
龍と戦おうとした心そのものが、理から外れていたのです。
そのズレに、世界が反応したと書かれています。
5 祈った瞬間、嵐が止んだ
象徴的なのはここです。
大納言が、力を捨て、武を捨て、支配を捨て、
祈りの存在へと変わった瞬間、嵐は収まりました。
竹取物語は、極めて明解に、
世界は、征服しようとすれば壊れる。
畏れに戻れば、元に戻る。
と語っています。
これは、日本的自然観そのものです。
6 「キツネと葡萄」との決定的な違い
イソップ寓話「キツネと葡萄(ぶどう)」では、
キツネが取れなかった葡萄を「酸っぱい」と言って諦めます。
しかし竹取物語では、
「取ろうとした」だけで、世界が壊れ、命が脅かされ、
心身ともに打ちのめされます。
そしてようやく、「取ってはいけなかった」と悟るのです。
これは「諦めろ」という教訓ではありません。
人には踏み込んではいけない領域があるという、文明への警告です。
7 目にできた「李(すもも)の玉」の意味
最後の結末は、あまりにも日本的です。
• 龍の玉 → 得られない
• 代わりに → 目に李のような腫れ
人の理(ことわり)を超えたものを欲した結果、
得たのは真理ではなく、滑稽さであったのです。
だから人々は笑いました。
これは断罪ではありません。
日本文化は、ここで裁かず、
笑って終わらせるのです。
8 この章が描いている本質
この章が語ることは、以下の4つです。
(1) 世界には、取りに行ってはいけないものがある
(2) 力で奪おうとすると、世界そのものが壊れる
(3) 引き下がれば、命は助かる
(4) それでも、人には笑われる
そして、「それでいい」と説きます。
生きて戻れたこと自体が、最大の学びだからです。
9 かぐや姫は、ここでも何もしていない
最後に重要な点です。
この章で、かぐや姫は一切、手を下していません。
試練を出し、構図を置いただけです。
壊れたのは、男の側の文明観でした。
竹取物語第六章は、
力と支配の文明が、どこで破綻するかを、
完全に描き切っています。
【補足】「理不尽な主君からは去る」という日本思想
なお、後世になりますが、江戸時代の日本に、
「君、君たらずんば自ら去るべし」と説いた思想家が現れます。
山鹿素行です。
主君であっても、理に反する命令に命を賭ける必要はない。
武士は蛮勇に走らず、正しく生きよ――。
これは近代思想ではありません。
千年前の竹取物語に、すでにその原型が描かれていたのです。
【原文】
大伴御行の大納言は、我家にありとある人を召し集めての給はく、
「龍(たつ)の首に五色の光ある玉あンなり。それをとり奉りたらん人には、願はんことをかなへん。」との給ふ。男をのこども仰の事を承りて申さく、
「仰のことはいとも尊(たふと)し。たゞしこの玉容易(たはやす)くえとらじを、况(いわん)や龍の首の玉はいかゞとらん。」と申しあへり。
大納言のたまふ、
「君の使といはんものは、『命を捨てゝも己(おの)が君の仰事(あほきこと)をばかなへん。』とこそ思ふべけれ。この國になき天竺唐土の物にもあらず、この國の海山より龍はおりのぼるものなり。いかに思ひてか汝等難(むつかし)きものと申すべき。」
男ども申すやう、
「さらばいかゞはせん。難きものなりとも、仰事(おほせごと)に従ひてもとめにまからん。」と申す。
大納言見笑ひて、
「汝等君の使と名を流しつ。君の仰事をばいかゞは背(そむ)くべき」との給ひて、龍の首の玉とりにとて出したて給ふ。
この人々の道の糧・食物に、殿のうちの絹・綿・錢などあるかぎりとり出でそへて遣はす。この人々ども、帰るまでいもひをして、
「我は居らん。この玉とり得では家に帰りくな。」との給はせけり。
「おの\/仰承りて罷りいでぬ。龍の首の玉とり得ずは帰りくな。」との給へば、いづちも\/足のむきたらんかたへいなんとす。かゝるすき事をし給ふことゝそしりあへり。賜はせたる物はおの\/分けつゝとり、或(ある)は己が家にこもりゐ、或はおのがゆかまほしき所へいぬ。
「親・君と申すとも、かくつきなきことを仰せ給ふこと。」と、ことゆかぬものゆゑ、大納言を謗りあひたり。
「かぐや姫すゑんには、例のやうには見にくし。」との給ひて、麗しき屋をつくり給ひて、漆を塗り、蒔繪をし、いろへしたまひて、屋の上には糸を染めていろ\/に葺かせて、内々のしつらひには、いふべくもあらぬ綾織物に繪を書きて、間ごとにはりたり。もとの妻どもは去りて、
「かぐや姫を必ずあはん」とまうけして、獨明し暮したまふ。遣しゝ人は夜晝待ち給ふに、年越ゆるまで音もせず、心もとながりて、いと忍びて、たゞ舍人二人召繼としてやつれ給ひて、難波の邊(ほとり)におはしまして、問ひ給ふことは、
「大伴大納言の人や、船に乘りて龍殺して、そが首の玉とれるとや聞く」と問はするに、船人答へていはく、
「怪しきことかな。」と笑ひて、「さるわざする船もなし。」と答ふるに、「をぢなきことする船人にもあるかな。え知らでかくいふ。」とおぼして、「我弓の力は、龍あらばふと射殺して首の玉はとりてん。遅く來るやつばらを待たじ。」との給ひて、船に乘りて、海ごとにありき給ふに、いと遠くて、筑紫の方の海に漕ぎいで給ひぬ。いかゞしけん、はやき風吹きて、世界くらがりて、船を吹きもてありく。いづれの方とも知らず、船を海中にまかり入りぬべくふき廻して、浪は船にうちかけつゝまき入れ、神は落ちかゝるやうに閃きかゝるに、大納言は惑ひて、
「まだかゝるわびしきめハ見ず。いかならんとするぞ。」との給ふ。
楫(かじ)取答へてまをす、「こゝら船に乘りてまかりありくに、まだかくわびしきめを見ず。御(み)船海の底に入らずは神落ちかゝりぬべし。もしさいはひに神の助けあらば、南海にふかれおはしぬべし。うたてある主(しう)の御(み)許に仕へ奉(まつ)には、りて、すゞろなる死(し)にをすべかンめるかな。」とて、楫取なく。大納言これを聞きての給はく、
「船に乘りては楫取の申すことをこそ高き山ともたのめ。などかくたのもしげなきことを申すぞ」と、あをへどをつきての給ふ。楫取答へてまをす、
「神ならねば何業をか仕(つかうま)つらん。風吹き浪はげしけれども、神さへいたゞきに落ちかゝるやうなるは、龍を殺さんと求め給ひさぶらへばかくあンなり。はやても龍の吹かするなり。はや神に祈り給へ。」といへば、
「よきことなり。」とて、「楫取の御(おん)神聞しめせ。をぢなく心幼く龍を殺さんと思ひけり。今より後は毛一筋をだに動し奉らじ」と、祝詞(よごと)をはなちて、立居なく\/呼ばひ給ふこと、千度(ちたび)ばかり申し給ふけにやあらん、やう\/神なりやみぬ。
少しあかりて、風はなほはやく吹く。 楫取のいはく、
「これは龍のしわざにこそありけれ。この吹く風はよき方の風なり。あしき方の風にはあらず。よき方に赴きて吹くなり」といへども、大納言は是を聞き入れ給はず。三四日(みかよか)ありて吹き返しよせたり。
濱を見れば、播磨の明石の濱なりけり。大納言「南海の濱に吹き寄せられたるにやあらん。」と思ひて、息つき伏し給へり。船にある男ども國に告げたれば、國の司まうで訪ふにも、えおきあがり給はで、船底にふし給へり。松原に御筵(みむろ)敷きておろし奉る。その時にぞ「南海にあらざりけり。」と思ひて、辛うじて起き上り給へるを見れば、風いとおもき人にて、腹いとふくれ、こなたかなたの目には、李を二つつけたるやうなり。これを見奉りてぞ、國の司もほゝゑみたる。國に仰せ給ひて、腰輿(たごし)作らせたまひて、によぶ\/になはれて家に入り給ひぬるを、いかで聞きけん、遣しゝ男ども参りて申すやう、
「龍の首の玉をえとらざりしかばなん、殿へもえ参らざりし。『玉のとり難かりしことを知り給へればなん、勘當あらじ。』とて参りつる。」と申す。大納言起き出でての給はく、
「汝等よくもて來ずなりぬ。龍は鳴神の類にてこそありけれ。それが玉をとらんとて、そこらの人々の害せられなんとしけり。まして龍を捕へたらましかば、またこともなく我は害せられなまし。よく捕へずなりにけり。かぐや姫てふ大盜人のやつが、人を殺さんとするなりけり。家のあたりだに今は通らじ。男どもゝなありきそ。」とて、家に少し殘りたりけるものどもは、龍の玉とらぬものどもにたびつ。これを聞きて、離れ給ひしもとのうへは、腹をきりて笑ひ給ふ。糸をふかせてつくりし屋は、鳶烏の巣に皆咋くひもていにけり。世界の人のいひけるは、
「大伴の大納言は、龍の玉やとりておはしたる。」
「いなさもあらず。御眼(おんまなこ)二つに李のやうなる玉をぞ添へていましたる。」といひければ、
「あなたへがた。」といひけるよりぞ、世にあはぬ事をば、あなたへがたとはいひ始めける。