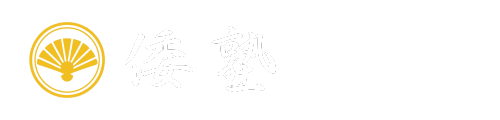仏の御石の鉢は、聖なる宝の物語ではありません。それは、「信仰が権威にすり替わる瞬間」を描いた、きわめて鋭い文明批評です。石作皇子が差し出したのは、遠い天竺の奇跡ではなく、人々の祈りを切り取った「偽物の聖性」でした。かぐや姫は、その鉢に光があるかどうかだけを見て、すべてを見抜きます。この章では、日本文明が大切にしてきた「本物は光る」という感覚を、千年前の物語で静かに語られています。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
竹取物語・第二章(現代語訳)仏の御石の鉢
石作皇子(いはさくのみこ)は、
「この姫を見ないでは、生きている心地がしない。
たとえ天竺(インド)にあるものでも、持って来られないだろうか」
と、あれこれ思い巡らしていました。
もともと策に長けた人物だったので、
「天竺に二つとない鉢を、何万里もの道を行って取ってくることなど、本当にできるだろうか」
と考え、かぐや姫のもとへ、
「今日、私は天竺へ、石の鉢を取りに旅立ちます」
と告げました。
そして三年ほどが過ぎたころ、大和国・十市郡(とをちのこおり)にある山寺で、賓頭盧(びんづる)という仏像の前に置かれていた、黒くすすけた鉢を手に入れました。
それを錦の袋に入れ、造花の枝につけて飾り、それらしく仕立てて、かぐや姫のもとへ持って来て見せたのです。
かぐや姫は不思議に思って鉢をのぞきました。
すると、中に一首の歌が入っていました。
海山の みちにこゝろを つくしは
てみいし鉢の なみだながれき
(意味)海と山の道に心を尽くしきって、ついにこの石の鉢を手に入れました。その苦労の涙が、いま流れています。
かぐや姫は、「では、この鉢は光っているのですか」と見ましたが、蛍ほどの光さえありません。
そこで、かぐや姫は返歌を詠みました。
おく露の ひかりをだにも やどさまし
小倉山にて なにもとめけむ
(意味)露のひとしずくほどの光さえ宿らない鉢を、小倉山まで来て、何を求めたのですか。
そう言って、その鉢を門の外に投げ捨てました。
それを見た石作皇子は、鉢を捨てたまま、なおも歌を返しました。
しら山に あへば光の うするかと
はちを棄てゝも たのまるゝかな
(意味)白い山に行けば光ると思ったのに、鉢を捨てられても、なお望みを捨てきれません。
しかし、かぐや姫はそれ以上、何の返事もしませんでした。
まったく耳にも入れなかったのです。
皇子は、言い訳ばかりして、みじめな気持ちで帰っていきました。
このことから、
「面目のないことは、恥を捨てることだ」
という言葉が生まれたのです。
【第三章 解説】仏の御石の鉢 ― 信仰が“権威”にすり替わる瞬間
1 石作皇子は「信仰」を選ばなかった
石作皇子は、こう考えました。
「天竺に二つとない鉢を、何万里も行って取れるものか」
つまり最初から、本物を取りに行く気がなかったということです。
彼が選んだのは、苦行でもなく、献身でもなく、信仰でもなく、「それらしく見えるものを作る」ことでした。
そして彼が盗んだものは、
「賓頭盧(びんづる)の前に置かれていた煤だらけの鉢」です。
賓頭盧とは「病を癒す仏」として、庶民の信仰を集めていた存在です。
つまり彼は、民衆の祈りの前に置かれた「信仰の器」を盗んだのです。
そうなると、これは単なる盗みではなくなります。
信仰の権威を切り取って、自分の恋と野心に転用した行為です。
2 「光っているはずの鉢」が光らない
かぐや姫が言った一言が、この章のすべてを暴きます。
「光やある。」
彼女は、「それは本当に仏の鉢なら、光るはずでしょう?」と問うたのです。
しかし「螢ばかりのひかりだになし」・・・蛍ほどの光さえない。
これは、本物の徳や信仰には、必ず「光」がある、という、日本的な霊性観の表現です。
どんなに形があっても、由緒があっても、伝説があっても、物語があっても、そこに「光(徳・誠・命の震え)」がないなら、それは、ただの「物」でしかないのです。
3 和歌が突き刺す文明批判
かぐや姫の返歌は、きわめて冷酷です。
「露のひとしずくほどの光さえ宿らない鉢を、
小倉山まで来て、何を求めたのですか」
これは恋の拒絶ではありません。文明への断罪です。
「そんな偽物の聖性で、私の魂を買えると思ったのですか?」と言っているのです。
4 それでも男は「物語」にすがる
石作皇子は、なおも歌を返します。
「鉢を捨てられても、なお望みを捨てきれません」
ここで彼がしているのは、現実を受け止めることではなく、自己正当化という物語です。
偽物と暴かれても、恥をかいても、それでも自分は「想っている」と言い張る。
これは、現代の政治家、宗教家、知識人が、スキャンダル後にやっていることと同じです。
さらにもっといえば、物語は、いくらでも捏造することができ、人を欺罔することができるということでもあります。
けれど、かぐや姫は、そのことを一刀両断に斬り捨てています。
下手に乗っかってはいけないのです。
一刀両断し、その先は、もはや相手にしてはいけないと述べられています。
5 「恥を捨てる」という言葉の誕生
最後の一文は、恐ろしい言葉です。
「面なき事をば、恥を捨つとはいひける」
これは、「面目を失っても、なお言い張る人間」を指す言葉です。
「恥を知らない」とは、「失敗したこと」ではありません。
失敗は誰にでもあるのです。
その「失敗を認めないこと」が、「恥を知らない」ことなのです。
6 この章の本当のテーマ
この章が描いているのは、「信仰が、権威にすり替わる瞬間」です。
本物の徳は、「光り、癒し、命を立ち上がらせる」のです。
けれど偽物の徳は、
• 物語だけがあり
• 権威だけがあり
• それが、支配と欲望に使われます。
石作皇子は、かぐや姫を得ようとして失敗したのではありません。
「神を装った権威」で、「人の魂を買おうとした」のです。
このことは、あたかも現代文明そのものの失敗が明言されているようなものです。
そしてこの章から、竹取物語ははっきり言い始めます。
本物は光る。
偽物は、どれだけ飾っても闇のままだと。
次の「蓬莱の玉の枝」では、今度は金と技術と虚構が暴かれていきます。
ここから、ますます鋭くなりますよ☆
【原文】仏の御石の鉢
「猶この女見では、世にあるまじき心ちのしければ、天竺にあるものも持てこぬものかは。」と、思ひめぐらして、石作皇子は心のしたくみある人にて、「天竺に二つとなき鉢を、百千萬里の程行きたりともいかでか取るべき。」と思ひて、かぐや姫の許には、「今日なん天竺へ石の鉢とりにまかる。」と聞かせて、三年ばかり經て、大和國十市郡とをちのこほりにある山寺に、賓頭盧びんづるの前なる鉢のひた黑に煤つきたるをとりて、錦の袋に入れて、作花の枝につけて、かぐや姫の家にもて來て見せければ、かぐや姫あやしがりて見るに、鉢の中に文あり。ひろげて見れば、
海山のみちにこゝろをつくしはてみいしの鉢のなみだながれき
かぐや姫、「光やある。」と見るに、螢ばかりのひかりだになし。
おく露のひかりをだにもやどさまし小倉山にてなにもとめけむ
とてかへしいだすを、鉢を門に棄てゝ、この歌のかへしをす。
しら山にあへば光のうするかとはちを棄てゝもたのまるゝかな
とよみて入れたり。かぐや姫返しもせずなりぬ。耳にも聞き入れざりければ、いひ煩ひて歸りぬ。かれ鉢を棄てゝまたいひけるよりぞ、面なき事をばはぢをすつとはいひける。