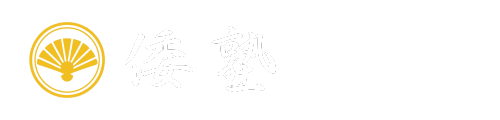「よばい」は、恋の始まりではありません。それは、欲望が共同体の境界を越え、世界が壊れ始める瞬間の名前です。竹取物語・第二章では、五人の権力者たちが、かぐや姫という“価値”を所有しようとしたとき、どのように関係の秩序が崩れていくのかが描かれます。この千年前の物語は、いまの社会で起きている「奪い合い」の原型そのものといえます。

「竹取物語」
第1章 生い立ち
第2章 よばひと五人の求婚者
第3章 仏の御石の鉢
第4章 蓬莱の玉の枝
第5章 火鼠(ひねずみ)の裘(かわごろも)
第6章 龍の首の玉
第7章 燕(つばめ)の子安貝
第8章 帝の懸想(けそう)
第9章 かぐや姫の昇天
竹取物語・第二章(現代語訳)
世の中の男たち、身分の高い者も低い者も、
「どうしてもこのかぐや姫を手に入れたい。ひと目でいいから見てみたい」と、その評判を聞いて心を奪われ、我を忘れてしまいました。
近所の垣根のそばに住む人でさえ、簡単には姿を見ることができないのに、夜もろくに眠らず、闇夜に外へ出ては穴を掘り、あちこちから覗き込んでは、ちらりとでも見ようと騒ぎ回ったのです。このころから、人々は夜に忍び寄ることを「よばい」と言うようになりました。
他人の家のものとも思わず、迷い狂う人々もいましたが、それで何か得られるわけでもありません。
家の人に何か話そうとしても取り合ってもらえず、屋敷のまわりを離れず、夜も昼も張りついている人がたくさんいました。愚かな人は「こんな無駄な通いはよくない」と思って、やがて来なくなりました。
しかし、それでもなお通い続けたのが、
世に「色好み」と名高い五人でした。
その名は、
石作皇子(いはさくのみこ)
車持皇子(くるまもちのみこ)
右大臣・阿倍御主人(うだいじん・あべのみうし)
大納言・大伴御行(だいなごん・おほとものみゆき)
中納言・石上麿呂(ちゅうなごん・いそがみのまろ)
この五人でした。
この人たちは、世の中で評判のよい女性がいると聞けば、必ず会ってみたいと思うような男たちでしたから、
かぐや姫の噂を聞いて、食事も喉を通らず、思いに沈みながら、その家の前を行き来して立ち尽くしていました。
しかし、どれほど通っても、少しの手応えもありません。
手紙を書いても返事はなく、恋の歌を書き送っても、返歌もありません。
「無駄なことだ」と思いながらも、寒い霜月(11月)・師走(12月)の凍える夜も、真夏の焼けつくような日差しの日も、彼らは通い続けました。
あるとき、五人は竹取の翁を呼び出して、
「どうか娘を私にください」と地に伏して頼み、手をすり合わせて願いました。
しかし翁は、
「自分の産んだ子ではないので、私の一存では決められないのです」と言って、ただ月日を過ごしました。
それでも五人は、家に帰っては思い悩み、祈祷をし、願掛けをし、何とか気持ちを断とうとしますが、どうしても忘れられません。
「いくらなんでも、最後には誰か一人くらいは選ばれるのではないか」と期待し、ますます熱心に通い続けました。
それを見て、翁はかぐや姫に言いました。
「おまえは仏の化身のような方だと言われているが、
これほど多くの人が長い年月、真心を尽くして通ってくるのだから、
その志も決して軽くはない。
どうか翁の言うことを聞いてくれないか。」
かぐや姫は答えました。
「どうしてお話を聞かないことがありましょう。
自分が変化の身だとも知らず、あなたを親と思ってきました。」
翁は喜んで言いました。
「私はもう七十を過ぎ、いつ死ぬかわからない。
この世では、男と女が結ばれて家が広がり、
人の世の道もそこから続いていく。
それなしで、どうして生きていけようか。」
かぐや姫は言いました。
「どうして、そんなことが必要なのでしょう。」
翁は言いました。
「たとえ変化の身であっても、あなたは女の身を持っている。
私が生きている間はこのままでもよいが、
この人たちの長年の思いを考えて、
一人一人と会って、その志を確かめてごらんなさい。」
かぐや姫は答えました。
「姿が立派でも、心の深さを知らずに結ばれたら、
後悔することになるでしょう。
どれほど立派な人であっても、
志が深くなければ、結ばれることはできません。」
翁は言いました。
「もっともだ。では、どのような志の人を選ぶつもりなのか。」
かぐや姫は言いました。
「とても難しいことではありません。
人の志は皆同じように見えても、実は違います。
五人にそれぞれ“ある物”を持ってきてもらい、
それを見て、もっとも志の深い人に仕えましょう。
そのようにお伝えください。」
翁は「それは良い」と承知しました。
夕方になると、いつものように五人が集まりました。
笛を吹き、歌を歌い、扇を鳴らして騒いでいるところへ、翁が出て言いました。
「長い年月、この粗末な家に通ってくださるそのご厚意、
まことにありがたいことです。
私の命も長くはありませんから、
皆さまもよくお考えください。」
五人は
「私たちの心の深さを知らずに言うのですか」と答えました。
翁は続けました。
「誰の志が勝っているかは、
これからお見せいただく“物”で決めましょう。
それでこそ、誰も恨みは残らぬでしょう。」
五人も「もっともだ」と同意しました。
そこで翁は中に入り、かぐや姫の言葉を伝えました。
かぐや姫は、
石作皇子には
「天竺にある仏の御石の鉢を取ってきてください」
車持皇子には
「東の海にある蓬莱山の、
銀を根とし、金を幹とし、玉を実とする木の枝を折ってきてください」
阿倍右大臣には
「唐土にある火鼠の皮衣を」
大伴大納言には
「龍の首にある五色に光る玉を」
石上中納言には
「燕の持つ子安貝を」
と、それぞれ命じました。
翁は
「どれもこの国にはない、あまりに難しいものだ」と言いましたが、
かぐや姫は
「何が難しいことがありましょう」と答えました。
翁はそれを五人に伝えると、五人は顔を見合わせて
「ずいぶん遠回しに拒まれたものだ」
と言いながら、しぶしぶ帰っていったのでした。
【第二章 解説】欲望が共同体を侵食していく瞬間(とき)
1 「よばい」の始まり
この章で最も重要な言葉が、ひっそり出てきます。
「さる時よりなん、よばひとはいひける」
夜に忍び込んで覗き見る行為を、ここで初めて「よばい」と呼ぶようになった、と書かれています。
ここは、単なる恋の始まりではありません。
「関係のルールが壊れた」ことを述べていると読むと、理解が深まります。
本来、我が国の男女関係は、
• 家と家
• 村と村
• 親と親
という共同体の同意の上で結ばれています。
このことは、現代でも結婚式のときに、「新郎・鈴木家、新婦・田中家」といったように、それぞれの個人名ではなく、名字で表記されるという慣習にも現れています。
こうした、共同体の同意を飛び越えて、個人の欲望が他人の家の境界を侵したものが、「よばい」です。
だから、「垣を越え、穴を掘り、闇の中から覗く」と表現されています。これは恋ではなく、侵犯です。
2 見るだけで満足できなくなる男たち
男たちはこう言いました。
「いかでこのかぐや姫を得てしがな、見てしがな」
「見たい」から始まり、すぐに「手に入れたい」に変わっていくのです。
ここに、人間の欲望の危うさがそのまま出ています。
しかも彼らは、
• 寝ない
• 食べない
• 寒さ暑さも気にしない
これらは恋の情熱というより、依存であり、執着です。
ここに理性はありません。
3 「色好みの五人」は文明の代表者
そして5人が残ります。
彼らはただの男ではありません。
「皇子・大臣・大納言・中納言」=いまで言えば“政治の中枢”です。
つまりここにあるのは、単に「男が女に恋をした話」ではなく、
「権力と富と地位を持った者たちが、
価値あるものを“所有”しようとした構図」であり、
国家の意思決定層そのものが欲望に呑み込まれる構図です。
あたりまえのことですが、覗く、追う、監視する・・・。
欲望が正義の顔をすると、社会は一気に息苦しくなります。
なぜなら、共同体の境界を越えた“覗き”は、やがて“管理”になるからです。
ここから竹取物語は、恋愛譚ではなく、権力と欲望の物語に変わっていくのです。
4 翁と姫の文明の違い
翁はこう言いました。
「男と女が結ばれてこそ、門も広くなる」
これは、関係を結び、家をつなぎ、社会を継ぐ、共同体としての論理です。
一方、かぐや姫はこう言います。
「姿がよくても、深い心を知らずに結ばれると後悔する」
ここに、文明の断絶があります。
• 翁の世界・・・・関係の文明
• 男たちの世界・・所有の文明
かぐや姫は、このどちらでもありません。
「魂の深さ」だけを基準にしようとするものです。
5 「志」を測るという恐ろしい提案
そこで、かぐや姫は言いました。
「五人に物を取って来させ、その志を見て決める」
ここで彼女は、わざと男たちの文明の土俵に乗っています。
「欲しいものを取ってくる」
「危険を冒してでも手に入れる」
これは、力・金・嘘・暴力・ごまかし等という、文明の技術が発動される場所です。
一般にはこの試練が、
「男たちをふるいにかける」ために行われたと解釈されがちですが、
実は、ここでかぐや姫は、「彼らの文明の正体を暴く罠」を仕掛けています。
6 この章が描いている本当のテーマ
第二章の本質は、
「価値あるものを、関係として迎えるか、所有物として奪うのか」
にあります。
翁は「預かる」文明。
男たちは「奪う」文明。
そして、かぐや姫はそのどちらにも回収されない、
「天の理(ことわり)」です。
7 現代とまったく同じ構図
この章は、現代の日本社会そのものです。
• 美しい自然
• 貴重な文化
• かけがえのない人
• 本来は共有されるべき価値
それらを、
「欲しい」
「手に入れたい」
「所有したい」
と囲い込み、奪い合っています。
そのとき必ず起こるのは、皆様もよくご存知の、
「侵入・監視・盗み・嘘・搾取」です。
これが「よばい」の正体です。
8 まとめ
第二章はこう言っています。
「欲望が共同体を越えた瞬間、世界は壊れ始める。」
かぐや姫はまだ何もしていません。
けれど男たちは、すでに壊れ始めています。
だからこの物語は恐ろしいのです。
なぜなら、破綻は、いつも恋のような「善意の顔」をしてやって来るからです。
次の章から、その「破綻」が一気に可視化されていきます。
欲望は次に「偽り」を生んで行きます。
ここからが、竹取物語の本番です。
【原文】
世界の男(をのこ)、貴なるも賤しきも、
「いかでこのかぐや姫を得てしがな、見てしがな。」と、音に聞きめでて惑(まど)ふ。
その傍(あたり)の垣にも家のとにも居をる人だに、容易たはやすく見るまじきものを、夜は安きいもねず、闇の夜に出でても穴を抉(くじ)り、こゝかしこより覗(のぞ)き垣間見惑ひあへり。
さる時よりなん「よばひ」とはいひける。人の物ともせぬ處(ところ)に惑ひありけども、何の効(しるし)あるべくも見えず。家の人どもに物をだに言はんとていひかくれども、ことゝもせず。傍(かたわら)を離れぬ公達(きみたち)、夜を明し日を暮す人多かり。愚なる人は、「益(やう)なき歩行ありきはよしなかりけり。」とて、来ずなりにけり。
その中に猶(なほ)いひけるは、色好(いろずき)といはるゝかぎり五人、思ひ止む時なく夜晝(よごと)来(きに)けり。
その名一人は石作皇子(いはさくのみこ)、一人は車持皇子(くらもちのみこ)、一人は右大臣阿倍御主人(うだいじんあべのみうし)、一人は大納言大伴御行(だいなごん おほとものみゆき)、一人は中納言石上麿呂(いそかみのまろ)、たゞこの人々なりけり。
世の中に多かる人をだに、少しもかたちよしと聞きては、見まほしうする人々なりければ、かぐや姫を見まほしうして、物も食はず思ひつゝ、かの家に行きてたたずみありきけれども、かひあるべくもあらず。文を書きてやれども、返事もせず、わび歌など書きて遣れども、かへしもせず。「かひなし。」と思へども、十一月(しもつき)十二月(しはす)のふりこほり、六月(みなつき)の照りはたゝくにもさはらず来けり。
この人々、或時は竹取を呼びいでて、「娘を我にたべ。」と伏し拝み、手を摩(す)りの給へど、「己(おの)がなさぬ子なれば、心にも従はずなんある。」といひて、月日を過す。かゝればこの人々、家に帰りて物を思ひ、祈祷(いのり)をし、願(ねがひ)をたて、思(おもひ)やめんとすれども止むべくもあらず。「さりとも遂に男合せざらんやは。」と思ひて、頼をかけたり。強(あながち)に志を見えありく。
これを見つけて、翁(おきな)かぐや姫にいふやう、
「我子の仏変化の人と申しながら、こゝら大さまで養ひ奉る志(こころざし)疎(おろか)ならず。翁(おきな)の申さんこと聞き給ひてんや。」といへば、かぐや姫、
「何事をか宣はん事を承らざらん。変化の者にて侍(はべ)りけん身とも知らず、親とこそ思ひ奉れ。」といへば、翁、「嬉しくも宣ふものかな。」といふ。「翁年七十(なゝそぢ)に餘りぬ。今日とも明日とも知らず。この世の人は、男は女にあふことをす。女は男に合ふことをす。その後なん門も広くなり侍る。いかでかさる事なくてはおはしまさん。」
かぐや姫のいはく、
「なでふさることかしはべらん。」といへば、
「変化の人といふとも、女の身もち給へり。翁のあらん限は、かうてもいますかりなんかし。この人々の年月を経(へ)て、かうのみいましつつ、宣(のたま)ふことを思ひ定めて、一人々々にあひ奉り給ひね。」といへば、かぐや姫いはく、
「よくもあらぬ容を、深き心も知らで、『あだ心つきなば、後悔しきこともあるべきを。』と思ふばかりなり。
世のかしこき人なりとも、深き志を知らでは、あひ難しとなん思ふ。」といふ。
翁いはく、
「思(おもひ)の如くものたまふかな。そも\/いかやうなる志あらん人にかあはんと思す。
かばかり志疎ならぬ人々にこそあンめれ。」
かぐや姫のいはく、
「何ばかりの深きをか見んといはん。いさゝかのことなり。人の志ひとしかンなり。
いかでか中に劣勝おとりまさりは知らん。『五人の中にゆかしき物見せ給へらんに、「御志勝りたり。」とて仕(つこ)うまつらん。』と、そのおはすらん人々に申まをし給へ。」といふ。
「よきことなり。」とうけつ。
日暮るゝほど、例の集りぬ。人々或は笛を吹き、或は歌をうたひ、或は唱歌をし、或はうそを吹き、扇をならしなどするに、翁出でていはく、
「辱くもきたなげなる所に、年月を經て物し給ふこと、極まりたるかしこまりを申す。翁の命今日明日とも知らぬを、かくのたまふ君達きみたちにも、よく思ひ定めて仕うまつれ。」と申せば、
「深き御心をしらでは」となん申す。さ申すも理なり。
「いづれ劣勝おはしまさねば、ゆかしきもの見せ給へらんに、御おん志のほどは見ゆべし。仕うまつらんことは、それになむ定むべき。」といふ。これ善きことなり。人の恨もあるまじ。」といへば、五人の人々も「よきことなり。」といへば、翁入りていふ。
かぐや姫、石作皇子には、「天竺に佛の御み石の鉢といふものあり。それをとりて給へ。」といふ。
車持皇子には、「東(ひむがし)の海に蓬莱といふ山あンなり。それに白銀を根とし、黄金を莖とし、白玉を實としてたてる木あり。それ一枝折りて給はらん。」といふ。
今一人には、「唐土にある、火鼠の裘(かはごろも)を給へ。」
大伴大納言には、「龍たつの首に五色に光る玉あり。それをとりて給へ。」
石上中納言には、「燕つばくらめのもたる子安貝一つとりて給へ。」といふ。
翁「難きことゞもにこそあンなれ。この國にある物にもあらず。かく難き事をばいかに申さん。」といふ。かぐや姫、「何か難からん。」といへば、翁、「とまれかくまれ申さん。」とて、出でて「かくなん、聞ゆるやうに見せ給へ。」といへば、皇子達上達部聞きて、「おいらかに、『あたりよりだになありきそ。』とやは宣はぬ。」といひて、うんじて皆歸りぬ。